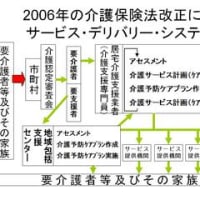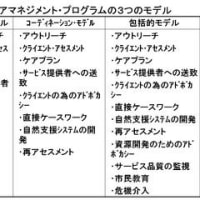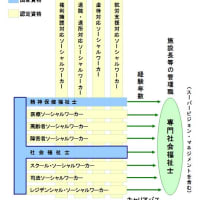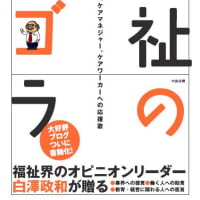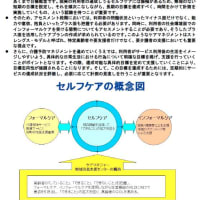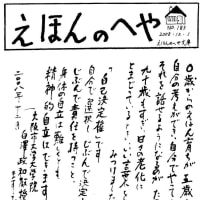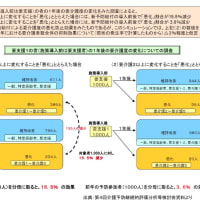先週の週末、娘夫婦と息子に、私と妻の還暦を祝っていただき、子どもたちと一泊の温泉旅行をしてきた。子どもたちには感謝で一杯である。
このような機会を得て、60歳という子どもに還る時期を迎え、今の時点での「老い」とは何かを考えた。これは、今からさらに老いていくるであろう、70歳での老い、80歳での老いとは異なるであろう。それゆえ、60歳という向老期での老いを考えることでもある。
私が学生に頃には、高齢者の生き方として、社会との交流をできる限りもった生活を続けていくことが幸福な老いをもたらすという活動理論(activity theory)と、徐々に社会から身を引き、関係を絶っていくことが高齢者にとっても望ましい姿であるとする離脱理論(disengagement theory)の論争があった。その後、継続理論(continuity theory)といった、中年期から高齢期に移行する際には、生活そのものや行動パターンの継続性を保ちつつ変化していくことが望ましいという考え方が示されてきた。
その後も、高齢期の生き方として、就労や社会への参加をすることは人生の目的をもっていきることができることで、高齢になっても様々な領域で活躍する高齢期を強調するプロダクティブ・エイジング(productive aging)がロバート.N.バトラー博士によって提唱されてきた。さらには、高齢期の心身の低下や喪失感に対処しながら、幸福な老いを追求するサクセスフル・エイジング(successful aging )が追求され、いかにして高齢者が質の高い生活を送るのかが問われている。
今の心境は、「継続理論」に近いものであるのかわからないが、2つの気持ちが交差する。一つは、これまでの人生に種をまいた木が育ち、果実を収穫できる「成熟期」という気分がある。もう一つは、徐々に自らの仕事を整理していく「離脱期」という気分がある。
今まで研究や教育してきたことが、実を結ぶ時期である。これの中心は、今までの研究成果をまとめるべき時期であり、刊行してきた論文をもとにして、著書にまとめることである。これについては、早晩していきたいと思っている。また、形になるかどうかは別にして、多くのことで果実が収穫できると感じることがある。例えば、些細なことであるが、25年以上前から大阪市社会福祉協議会の機関誌「大阪の社会福祉」に毎月書き続けてきた「福祉の用語」をぼちぼち誰かに代わってもらい、お役ご免になり、今まで書いてきた300以上の用語をどのように活用していこうかといったことを考えることである。
同時に、教育についても、ドクターの学位をできる限りだして、残っている大学院生の整理をしていくべき時期である。私の指導しているドクターの学生は20人ほどおり、定年を最終ゴールにして、それぞれの学生が学位を取得することで実を結んでいく成熟期といった気分になっている。今年度中に、少なくとも7名程度は学位が出せる水準まできていると思っている。
以上は「成熟期」ということを意識して整理したのであるが、逆の視点からみると、自らの仕事や社会的な役割を整理していることになり、「離脱期」という気持ちになる。例えば、研究にしても整理していくことで、教育にしてもある意味しかりである。その意味では、60歳と言うことで向老期としたが、この時期での気持ちは両者の心境が交差し、何か複雑である。
「離脱期」の心境は、ジャン=フランソワ・ミレーの有名な絵画「落穂拾い」を見た時に印象に近い。あの絵は、収穫期の刈り入れが終わった後の畑で、貧しい人々が落ち穂拾いをしているものである。あの絵にある何とも言えない哀愁が、「離脱期」の心境である。一方、天性のものであろうが、その年、その年で、全力を注ぐことで、いつも楽しい人生であることも事実である。今では、ブログも楽しい人生の一角を占めている。
このような機会を得て、60歳という子どもに還る時期を迎え、今の時点での「老い」とは何かを考えた。これは、今からさらに老いていくるであろう、70歳での老い、80歳での老いとは異なるであろう。それゆえ、60歳という向老期での老いを考えることでもある。
私が学生に頃には、高齢者の生き方として、社会との交流をできる限りもった生活を続けていくことが幸福な老いをもたらすという活動理論(activity theory)と、徐々に社会から身を引き、関係を絶っていくことが高齢者にとっても望ましい姿であるとする離脱理論(disengagement theory)の論争があった。その後、継続理論(continuity theory)といった、中年期から高齢期に移行する際には、生活そのものや行動パターンの継続性を保ちつつ変化していくことが望ましいという考え方が示されてきた。
その後も、高齢期の生き方として、就労や社会への参加をすることは人生の目的をもっていきることができることで、高齢になっても様々な領域で活躍する高齢期を強調するプロダクティブ・エイジング(productive aging)がロバート.N.バトラー博士によって提唱されてきた。さらには、高齢期の心身の低下や喪失感に対処しながら、幸福な老いを追求するサクセスフル・エイジング(successful aging )が追求され、いかにして高齢者が質の高い生活を送るのかが問われている。
今の心境は、「継続理論」に近いものであるのかわからないが、2つの気持ちが交差する。一つは、これまでの人生に種をまいた木が育ち、果実を収穫できる「成熟期」という気分がある。もう一つは、徐々に自らの仕事を整理していく「離脱期」という気分がある。
今まで研究や教育してきたことが、実を結ぶ時期である。これの中心は、今までの研究成果をまとめるべき時期であり、刊行してきた論文をもとにして、著書にまとめることである。これについては、早晩していきたいと思っている。また、形になるかどうかは別にして、多くのことで果実が収穫できると感じることがある。例えば、些細なことであるが、25年以上前から大阪市社会福祉協議会の機関誌「大阪の社会福祉」に毎月書き続けてきた「福祉の用語」をぼちぼち誰かに代わってもらい、お役ご免になり、今まで書いてきた300以上の用語をどのように活用していこうかといったことを考えることである。
同時に、教育についても、ドクターの学位をできる限りだして、残っている大学院生の整理をしていくべき時期である。私の指導しているドクターの学生は20人ほどおり、定年を最終ゴールにして、それぞれの学生が学位を取得することで実を結んでいく成熟期といった気分になっている。今年度中に、少なくとも7名程度は学位が出せる水準まできていると思っている。
以上は「成熟期」ということを意識して整理したのであるが、逆の視点からみると、自らの仕事や社会的な役割を整理していることになり、「離脱期」という気持ちになる。例えば、研究にしても整理していくことで、教育にしてもある意味しかりである。その意味では、60歳と言うことで向老期としたが、この時期での気持ちは両者の心境が交差し、何か複雑である。
「離脱期」の心境は、ジャン=フランソワ・ミレーの有名な絵画「落穂拾い」を見た時に印象に近い。あの絵は、収穫期の刈り入れが終わった後の畑で、貧しい人々が落ち穂拾いをしているものである。あの絵にある何とも言えない哀愁が、「離脱期」の心境である。一方、天性のものであろうが、その年、その年で、全力を注ぐことで、いつも楽しい人生であることも事実である。今では、ブログも楽しい人生の一角を占めている。