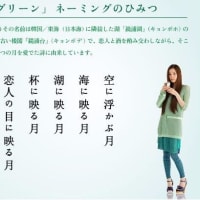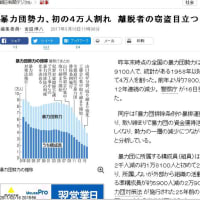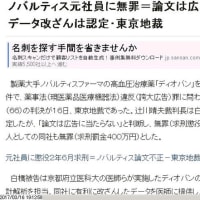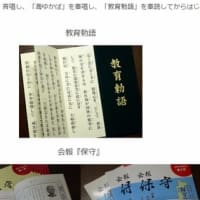故 鈴木万平氏(元三共株式会社(現第一三共株式会社)取締役社長・会長
ノスカール(rezulin)記事
【 リズリンは、日本の製薬メーカー三共が開発した薬で、米国では(日本と同時に)1997年3月から発売され、50万人の糖尿病患者に処方されてきた人気の高い薬だ。そして、その後重大な肝機能障害の副作用が報告され、これまでに61人が死亡している。】
三共製薬(現第一三共)と関係の深い大学と医者たち
役員名簿
役員名簿
理 事
*常勤/(50音順・平成21年6月現在)理事長 河村 秀穂 元 三共株式会社 代表取締役副社長
専務理事* 鬼丸 務 元 三共株式会社 執行役員
理 事 赤沼 安夫 財団法人 朝日生命成人病研究所 名誉所長
理 事 春日 雅人 国立国際医療センター 研究所長
理 事 門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授
(附属病院副病院長)
理 事 黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科 教授
(経営協議会委員)
理 事 佐藤 祐造 愛知学院大学心身科学部健康科学科 教授
理 事 七里 元亮 元 熊本大学 教授
理 事 庄田 隆 第一三共株式会社 代表取締役社長
理 事 豊田 隆謙 東北労災病院 名誉院長
理 事 中尾 一和 京都大学大学院医学研究科 臨床病態医科学 教授
理 事 松岡 健平 東京都済生会中央病院 顧問
東京都済生会渋谷診療所 相談役
理 事 松澤 佑次 財団法人 住友病院 院長
監 事
(50音順・平成21年6月現在)監 事 牧野 光宏 牧野公認会計士事務所 所長
監 事 横井 知雄 第一三共株式会社 執行役員
評議員名簿
(50音順・平成21年6月現在)評議員
(議長) 山下亀次郎 筑波記念病院 つくば糖尿病甲状腺センター センター長
評議員 荒木 栄一 熊本大学大学院 医学薬学研究部代謝内科 教授
評議員 磯貝 庄 藤沢御所見病院 名誉院長
評議員
(議長代行) 板倉 弘重 茨城キリスト教大学生活科学部 教授
評議員 伊藤 裕 慶応義塾大学医学部 内科学 教授
評議員 井上 圭三 帝京大学薬学部 薬学部長
評議員 蛯名 洋介 徳島大学 疾患酵素学研究センター 教授
評議員 岡 芳知 東北大学大学院 医学系研究科分子代謝病態学
糖尿病代謝科 教授
評議員 小田原雅人 東京医科大学 内科学第三講座 主任教授
評議員 菊池 方利 財団法人 朝日生命成人病研究所 所長
評議員 小林 正 富山大学大学院 医学薬学研究部 特別研究教授
評議員 齋藤 康 千葉大学 学長
評議員 重藤 學二 元 井上科学振興財団 常務理事
評議員 下村伊一郎 大阪大学大学院 医学系研究科内分泌・代謝内科学 教授
評議員 名和田 新 福岡県立大学 学長
選考委員名簿
(50音順・平成21年6月現在)選考委員長 春日 雅人 国立国際医療センター 研究所長
選考委員 河盛 隆造 順天堂大学大学院 教授
選考委員 齋藤 康 千葉大学 学長
選考委員 清野 裕 関西電力病院 院長
選考委員 山田 信博 筑波大学 学長
国内褒賞審査委員名簿
(50音順・平成21年6月現在)審査委員長 岩本 安彦 東京女子医科大学 糖尿病センター長・内科学第三講座 主任教授
審査委員 渥美 義仁 東京都済生会中央病院 副院長
審査委員 門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授
(附属病院副病院長)
審査委員 嶋森 好子 慶応義塾大学 看護医療学部 教授
審査委員 武田 倬 鳥取県立中央病院 院長
審査委員 花房 俊昭 大阪医科大学附属病院 病院長(大阪医科大学 教授)
審査委員 本田 佳子 女子栄養大学栄養学部 教授
国際褒賞審査委員名簿
(50音順・20年度〔第1回〕)審査委員長 春日 雅人 国立国際医療センター 研究所長
副審査委員長 門脇 孝 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授
(附属病院副病院長)
審査委員 柏木 厚典 滋賀医科大学附属病院 病院長
審査委員 清野 進 神戸大学大学院医学研究科 細胞分子医学分野 教授
審査委員 山本 博 金沢大学大学院医学系研究科 血管分子生物学 教授
簡単な論理構造である。
製薬会社が資金を提供して医者を海外へ留学させる。
医薬分業と言われながら根っこから高価な栄養を補給させる製薬会社と注入される医者との関係が成り立つと、ものの見事に癒着は行われる。
世界中から非難の的になったノスカール(rezulin)は多くの死者を出し販売中止になったが、それでも日本では投薬され続けた。しかも、重篤な肝機能障害があると知っていながら医者自らが処方箋を書き続けたのである。
上記の病院などで、なるほどしつこくノスカールが投与さえ続け、厚生労働省も後押ししていた理由はここにある。
製薬会社の支援のもとに留学するメンバー(将来薬害を製薬会社の立場から守り続ける医者たちのメンバーと考えてよい)
助成者 名簿
助成対象者(平成22年度)
海外留学助成
氏 名 所 属 留学先 研究課題
関谷 元博 東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 Harvard University,School of Public Health 栄養代謝病態を制御する新規小胞体ストレス関連因子の全ゲノムスクリーニング
渡邉 和寿 筑波大学大学院人間総合科学研究科 内分泌代謝・糖尿病内科 Columbia University 新規糖尿病感受性遺伝子の解析
田畑 光久 慶應義塾大学医学部内科 腎臓内分泌代謝科 Dana-Farber Cancer Institute 骨格筋におけるインスリン抵抗性の発症機序の解明と治療への応用
堀越 桃子 facebook momoko 東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism 2型糖尿病遺伝素因の解析
小島 洋児 京都大学大学院医学研究科 循環器内科 Children's Medical Research Institute 高効率のβ細胞再生を目指した膵発生の分子機構の解明
松本 仁 大阪大学大学院医学系研究科 消化器内科学 Washington University School of Medicine Microsomal TG transfer protein (MTTP) 小腸特異的欠損によるインスリン抵抗性改善機序の解明
外国人研究者招聘助成招聘外国人研究者
所属機関及び氏名 受入責任者
所属機関及び氏名 A.研究課題
B.招聘目的
Vanderbilt University Medical Center
Chairman of Molecular Physiology &Biophysics
Alan D. Cherrington 順天堂大学医学部内科学
准教授 綿田 裕孝 A 肝糖代謝
B 国際スポートロジー学会設立のための学術講演会の演者としての参加、及び準備委員会での討議
会議・シンポジウム助成会合名・開催日・場所 責任者所属機関及び氏名
第60回 日本体質医学会総会 熊本大学大学院医学薬学研究部 代謝内科学
教授 荒木 栄一
第25回 日本糖尿病・肥満動物学会年次学術集会 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科
教授 門脇 孝
第22回 日本糖尿病性腎症研究会 東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
教授 田嶼 尚子
米国実験生物学会連盟夏期リサーチカンファランス(AMPキナーゼ) 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科
教授 門脇 孝
第9回 日本・韓国糖尿病性腎症セミナー 金沢医科大学 内分泌代謝制御学
教授 古家 大祐
調査研究 II 助成調査研究 II 助成 調査研究タイトル
京都医療センター WHO糖尿病協力センター
WHO糖尿病協力センター長 河野 茂夫 アジア西太平洋地域途上国における糖尿病足病変の発症要因(生活習慣関連)の解明と予防のためのヘルスプロモーションの策定に関する研究
東京女子医科大学糖尿病センター
教授 内潟 安子 小児・思春期を含めた日本人若年発症2型糖尿病の合併症発症率の経年的全国調査
三共製薬(合併後第一三共に名前が変わった)は徹底的に患者を毒づけしようとした。
医者を籠絡する製薬会社、そして患者を殺すか半殺しの目に遭わせていながら平気なのである。
科学者というのは研究に従順な人間性のひとかけらも無いようなものが従事する。
核兵器製造もそうだが、原発も同じである。ひとえにそこには金儲け主義がある。
失敗百選
失敗百選
~糖尿病薬「リズリン」のリコール~ 【動機】
最近、失敗学とのかかわりの中で、医療関係者との交流が増えてきた。未だ、委員会に医療関係者が不在の中で、biomechanical 分野も包含する機械工学の立場から医療に関する詳述を1つ入れることにした。
【事例発生日付】2000年3月21日
【事例発生地】アメリカ合衆国
【事例発生場所】アメリカ合衆国を含め全世界に影響を及ぼした
【概要】
2000年、3月21日、米国食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)が2型糖尿病の処方薬として流通していたトログリタゾン(商品名リズリン、Rezulin)のリコールを製造社のWarner-Lambertに指示。それまでに同薬によると思われる死亡が63件に達していた。
【事象】
タイプ1は膵島が壊れた糖尿病、タイプ2は、肥満・過食などのため、体内のインスリン必要量が増えてインスリン 生産が間に合わない糖尿病。トログリタゾンはそのタイプ2特効薬として、1996年に製造社のワーナー・ランバート 社が、FDAに認可申請、ファーストトラック(Fast Track)と呼ばれる認可スピードアップ制度により、 1997年1月には認可が下りた。
FDA には早くもその年10月にトログリタゾンによる肝機能障害で2件の糖尿病患者の死亡報告を受け取った。 その後、製造社、医者、国立保険研究所(NIH: National Institute of Health)、FDA、市民団体などによって討議ややり取りが続けられ、数回にわたり、FDAは製造社にトログリタゾンの ラベル表示に注意書きを加えるように指示、その後、製造社が意図的にトログリタゾンの不利になるような臨床実験 データを隠していたとの内部告発もあり、2000年3月21日にFDAが製造社にトログリタゾンをリコールするよう指示。 それまでに FDAが受け取ったトログリタゾンによる疾病者数は90、うち、死亡者報告数は63名。
くわしい【経過】はこちらから
【情報源】
http://www.rezulin-side-effects.com/
http://www.rezulinnet.org/
しかし、実際は2000年以前から問題視されていたのである。
rezulinの経過
1996-6-11
国立保険研究所がRezulinの糖尿病臨床試験に1億5千万ドルの予算をつける。研究は政府ので糖尿病の権威Richard Eastman博士を長に行われた。同氏は、製造元のワーナー・ランバート社に、Rezulinの発売開始に関し、コンサルタントとして雇われていた。この研究の後、ワーナー・ランバート社はEastman博士が糖尿病に特効性がある旨、プレス発表。
1996-7-31
ワーナー・ランバート社がRezulinのファーストトラックでの認可をFDAに申請。
1996-10-9
FDAの科学者たちは、Rezulinが、動物実験で肝臓や心臓に障害をもたらす兆候に懸念を持った。最初にRezulin担当になったFDA医師は同薬の認可に否定的だったJohn Gueriguian博士。
1996-11-4
ワーナー・ランバート社が、言葉がわかりにくいという理由でGueriguian博士をRezulinの評価チームから外すことに成功。これにより、FDAの記録から同氏の意見も抹消される。
1996-12-11
ワーナー・ランバート社がRezulinをFDAの委員会に対して発表。同薬が心臓肥大や心機能の障害をもたらすことはないと証言。
1997-1
ファーストトラック認可システムにより、Rezulin が FDAの認可を受ける。通常は数年かかる新薬の認可が、今回は半年で終わった。肝臓に対する実際の試験は行われなかった。
1997-2-24
FDA は、ワーナー・ランバート社がプレス発表の中で「間違いで誤解を招く」表現を行ったと発表。同様の表現を使用したものも含めて、同発表を中止するよう伝えた。
1997-5-1
ワーナー・ランバート社の実験ではRezulinを使用すると placebo使用時に比べて肝機能障害を起こす可能性が3.6倍になると結果が出ているにもかかわらず、4色刷りの広告で、Rezulinによる副作用が placebo と同程度であると発表。Placebo は比較実験でよく使用される試薬。
1997-5-5
ワーナー・ランバート社の最高経営責任者が投資家に Rezulin が大ヒットして巨額の利益をもたらす可能性があると説明。
1997-9-30
FDAの糖尿病グループリーダー、Alexander Fleming博士が心臓、肝臓、腎臓に疾患がある患者が同薬によって悪い影響を受けないとは考えにくい、と発表。
1997-10-10
Rezulinに起因する肝臓の機能停止2例がFDAに報告される。
1997-11-3
FDAが、Rezulinのラベルに以下の表示を義務付ける。
・ Rezulinの治療を受ける際には最初の1,2ヶ月の間に肝臓酵素の試験を受け、最初の1年間は3ヶ月ごとに、その後も定期的に続けること。
・ Rezulinの服用による肝機能低下の症状として、吐き気、嘔吐、腹痛、疲労、食欲不振、尿の変色があり、このような症状が現れた人は肝臓試験を受けること。
・ Rezulinの服用者は肝臓障害が現れたら直ちに服用を中止すること。
・ 臨床試験の結果、Rezulin服用者のおよそ2%は服用をやめなければならない結果が出ている。
1997-11-12
FDAの糖尿病専門医Robert I.
Misbin博士がFDAの上層部に内部告発報告を提出。それによると、FDAの認可以前よりRezulinを使用していた, an FDA diabetes specialist that supported the Rezulin approval, sent an internal report to FDA supervisors stating that 21 patients treated with Rezulin prior to FDA approval had to discontinue the drug due to Rezulin liver injury, 13 patients had markers of Rezulin liver injury 10 to 30 times above normal which can threaten the lives of patients, and an estimated 2% or 12,350 of the 650,000 patients using Rezulin would experience some degree of liver injury.
12-1-97
England prohibits sales of Rezulin due to concerns about liver damage to patients in the U.S. The FDA announces a label change to require more frequent Rezulin liver testing. The new label recommends liver enzyme tests before starting Rezulin, monthly for the first six months of treatment, every other month for the next six months, and periodically thereafter.
5-17-98
A 55 tear old woman in good health dies of Rezulin liver failure while participating in the National Institutes of Health diabetes study. The panel of specialists hired by NIH concluded that her liver failure was probably due to the use of Rezulin diabetes drug.
6-4-98
The NIH study drops Rezulin due to the risk of liver damage in the remaining participants.
6-5-98
A press release by Warner-Lambert denies Rezulin killed the woman and instead claimed her death was the result of complications unrelated to the study or the diabetes medication. The FDA had then received 21 reports of Rezulin liver failures resulting in death and three Rezulin liver transplant patients.
7-27-98
The consumer group Public Citizen filed a petition for the immediate ban of Rezulin. At this point the FDA had received 26 reports of Rezulin liver failure deaths.
7-28-98
The FDA required another Rezulin label change to increase the frequency of liver testing. The recommendation then stated a Rezulin patient be tested before using Rezulin, monthly for the following 8 months and every two months for the rest of the year and periodically after that.
1-99
The FDA Commissioner orders a reevaluation of Rezulin after the series of articles by the Los Angeles Times investigated the "fast track" drug Rezulin tied to 33 Rezulin liver failure deaths.
3-26-99
After two months of FDA research the findings are present to an FDA advisory panel. The report found that an estimated 430 or more Rezulin patients have suffered a liver failure, Rezulin patients incur 1,200 times more risk of liver failure, one out of every 1,800 Rezulin patients can expect t suffer a liver failure, and liver function tests do not provide enough protection due to the rapid and unpredictable way Rezulin can affect the liver. In addition, Rezulin patients did not follow the recommended liver function tests after more than 4 months on the drug.
3-29-99
A Rezulin patient undergoing monthly monitoring in a Warner-Lambert clinical trial dies of liver failure.
6-16-99
The FDA requires the Rezulin label be changed for the fourth time now, increasing the frequency once again for liver tests. The new label recommended Rezulin patients get monthly liver monitoring for the first year on the diabetes drug.
12-15-99
The Los Angeles Times reports 21 Rezulin patients have died of liver failure since the March 26, 1999 report by Dr. Graham to the FDA Advisory Panel. Graham begins a new analysis of Rezulin despite his supervisors having no knowledge of his actions.
3-3-00
Dr. Graham sends an email to 14 FDA officials with the opinion that Rezulin is unsafe and should be stopped due to the liver failure problems occurring. Graham stated there was no existing data to support the idea that monitoring can prevent the Rezulin liver failures from occurring.
3-00
The FDA diabetes specialist who had analyzed the first cases of liver failure in October to November 1997 sends eight members of Congress internal FDA emails discussing Rezulin liver toxicity. Included in the email was the correspondence he had received from Dr. Janet B. McGill who had conducted early research on Rezulin for Warner-Lambert saying the company "deliberately omitted reports of liver toxicity and misrepresented serious adverse events experienced by Rezulin patients in their clinical studies." The FDA opens an internal-affairs investigation after Warner-Lambert complains about the leaks.
3-21-00
The FDA withdraws Rezulin from the U.S. market after finding the benefits of other diabetes drugs offer the same benefits Rezulin did without the same risks. Up to this point Warner-Lambert had grossed $2.1 billion in Rezulin sales. The FDA had reports of 63 Rezulin liver failure deaths.
8-16-00
The L.A. Times reports about the Federal prosecutors examining the FDA's quick approval method and the delayed withdrawal of Rezulin. It was reported that both the FDA and Warner-Lambert's actions were being examined.
Serious, life-threatening Rezulin side effects have been directly linked to the use of the diabetes drug. Warner-Lambert has been blamed in dozens of deaths from life failure and thousands of other liver damage cases from 1997-2000.
rezulinに関するページ 英語あり
厚生労働省発表資料
医薬品等安全性情報 145号(概要)
1.トログリタゾンによる肝障害
該当商品名: ノスカール錠(三共)
販売実績: 販売開始(本年3月)以後約60億円
トログリタゾンは、三共株式会社が開発した糖尿病治療薬であり、我が国では本年3月から販売されている。
本剤の肝臓に関する副作用については、治験段階ではGOTの上昇等が知られていたが、販売開始後、重篤な肝障害症例が13例(うち因果関係の否定できない死亡例3例)報告され、また、同時期の販売開始された米国でも肝障害が報告されていることから、投与前に肝機能を検査するとともに少なくとも1ヶ月に1回肝機能検査を行うなど「警告」欄の新設を含む使用上の注意の改訂を行い、あわせて緊急安全性情報を配布し、注意喚起を行った(12月1日)。
今般、症例を紹介し、警告の内容について解説を行い、情報の周知徹底を図る。
なお、本日(12月25日)に開催された中央薬事審議会副作用第一調査会において、さらに61例の重篤な肝障害症例(うち1例が因果関係の否定できない死亡例)の報告について確認した。(合計74例、うち4例が因果関係の否定できない死亡例)
2.血栓溶解剤ナサルプラーゼと脳出血該当商品名: トロンボリーゼ注1500(ミドリ十字)
トミーゼ注1500(吉富製薬)
年間推定出荷額: 両社あわせて約4億8千万円
ナサルプラーゼは、急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解を効能とした血栓溶解剤である。
急性心筋梗塞に対する血栓溶解療法での重篤な副作用として脳出血が知られており、冠動脈内投与製剤のナサルプラーゼについては、これまで使用上の注意において脳出血等の重篤な出血について注意喚起してきたところである。
本年6月承認された静注用のナサルプラーゼは、承認時までに脳出血が3例発現し、そのうち2例が死亡していることから、添付文書に警告欄を設け注意喚起することとされた。
これに伴い、すでに承認されている冠動脈内投与製剤のナサルプラーゼについても脳出血が2例報告(2例とも死亡)されていることから、新たに警告欄を設け、脳出血に関するなお一層の注意喚起を行うこととした。
今般、その内容について解説を行い、情報の周知徹底を図る。
問い合わせ先 厚生省医薬安全局安全対策課
担 当 山本、松田、小笠原 (内2748、2757)
電 話 (代)03-3503-1711
だから、科学研究者というのは見境もなく、研究のためには魂を売るのである。
なお、研究グループの教授の命令で投薬される薬は決まってくる。製薬会社は国内海外沢山あり、学会の研究発表を海外で行う場合は海外の製薬会社がホテル・旅費・航空券・おみやげ付きで招待するのである。
武田薬品のアクトスは副作用の強い経口投与薬として今では注意を喚起されている。
ただし、こちらは特許がきれるため後継の薬がすでに開発されているという。
そのため武田薬品はアメリカのファイザーと提携し、天津武田が中国ファイザーにアクトスの製造を一任する。
特許切れのアクトスは今後中国で製造されることになる。
詳しいアクトスの情報は、こちら。
武田薬品の共同開発先はこちら