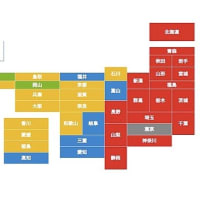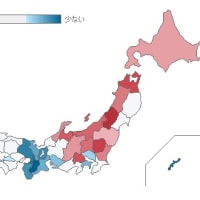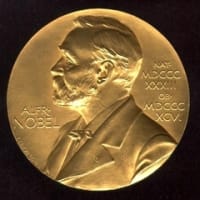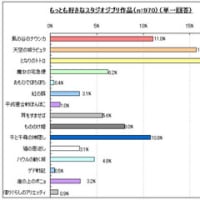古今の甲冑 名品をあれこれしてみました。
●源氏八領の鎧
・源頼義・義家のころより源氏に代々伝えられた八種の鎧。
・源太が産衣(げんたがうぶぎぬ)・薄金(うすかね)・楯無(たてなし)・膝丸(ひざまる)・八竜(はちりゅう)・沢瀉(おもだか)・ 月数(つきすう)・日数(ひかず)
*「源太が産衣」を除き、「七竜」を加える場合もある。
・六条判官源為義が、最期の合戦となった保元の乱の時に、代々相伝してきた鎧を一領ずつ五人の子どもに着せ、自分は薄金を着けたという。さらに源太が産衣と膝丸とは、源氏正嫡に代々伝わるものであるとして雑色の花澤に託し、(保元の乱で敵対することになった)下野守源義朝の許へと遣わしたという。
・別の書によると、保元の乱において源義朝は内四領(膝丸、八龍、沢瀉、源太が産衣)を受け継ぎ、自身は八龍を着用したという。また平治の乱においては、源義朝は膝丸、源義平は八龍、源朝長は沢瀉、源頼朝は源太が産衣を着用したという。
<源太が産衣(げんたがうぶきぬ)>
・源氏重代相伝の八領の鎧の一つ
八幡太郎義家は幼名を源太といい、二歳の時、院より召されて急ぎ鎧を威させ、袖にすえて見参に入れたことからその名がつけられた。胸板に天照大神、八幡神をあらわし、両袖に藤の花の咲きかかる様を威させている。平治の合戦では、源義朝の三男右兵衛佐頼朝が着用したが、合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<薄金(うすかね)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
緋威の鎧で、保元の合戦では、六条判官源為義が着用した。
<楯無(たてなし)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
黒糸威の鎧で、獅子の丸の裾金物が打ってあった。平治の合戦では、左馬頭源義朝が着用したが、合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<膝丸(ひざまる)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
牛千頭の膝の皮を取って威しているため、牛の精が宿っており、常に現じて主を嫌うという。保元の合戦の際、六条判官為義から、嫡子である敵方義朝に「源太が産衣」とともに贈られた。
<八竜(はちりゅう)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
八幡太郎義家が後三年合戦の折、八幡大菩薩の使者の神が八陣守護のために、金をもって八大竜王の形を打ち出し、所々に付けたためにその名がある。保元の合戦の折には下野守源義朝が、平治の合戦では義朝の長男悪源太義平が着用したが、義平が合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<沢瀉(おもだか)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
沢瀉威(沢瀉の葉のように長三角で底辺が食い込んだ形を2~5色の色変わりにあらわして威す威し方)の鎧。平治の合戦では、源義朝の次男中宮太夫進朝長が着用したが、合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<月数(つきすう)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
朽葉色の唐綾で威した鎧。保元の合戦では、源為義の四男、四郎左衛門頼賢が着用した。
<日数(ひかず)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
保元の合戦では、六条判官為義の子、五郎掃部助頼仲、賀茂六郎為宗、七郎為成、源九郎為仲のいずれかが着用したものと思われる。
<七竜(しちりゅう)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ(金刀本)
保元の合戦では、六条判官為義の子、五郎掃部助頼仲、賀茂六郎為宗、七郎為成、源九郎為仲のうちのいずれかが着用したものと思われる。 『保元物語』
●楯無(たてなし)の鎧
・源義光伝来の鎧とされる源氏八領のうちのひとつ。特に甲州武田家に伝わる大鎧で名高い。
・名前の由来は、その堅牢さの故に盾もいらぬほど、という理由から来たと言われる。
・保元物語や平治物語にその名が見られるが、平治の乱の際に源義朝が黒糸威の楯無を身に着けて戦った後、敗走中にそれを雪の中に脱ぎ捨てたとされている。
<武田家重代の鎧~楯無>
・『武田源氏一統系図』によれば、「楯無」と号された鎧は甲斐国守護家である甲斐源氏武田氏の家宝として、始祖と位置付けられる新羅三郎義光以来相伝されていると伝わり、御旗(みはた)と呼ばれる義光から受け継いだ日章旗と対になっている。
・戦国期には武田氏の親族衆や家臣団の間で神格化され、この鎧と旗に「御旗楯無も御照覧あれ(みはたたてなしも ごしょうらんあれ)」と誓い出陣した。
・菅田天神社(かんだてんじんしゃ 山梨県甲州市 旧塩山市上於曽)に伝わる小桜韋威鎧が楯無鎧であるとされており、現在も同神社に所蔵されている。御旗は甲州市塩山の雲峰寺に所蔵。
●避来矢(ひらいし)
・平安時代中期の武将藤原秀郷が百足退治の礼として龍宮の王からもらったという伝説のある大鎧の名称。「平石」とも記される。
・藤原氏子孫(下野国の佐野氏)に伝えられたが、江戸時代に浅草に保管してあったところ火災により焼失し、兜鉢、障子の板、壺板等の金属部分のみが残った。
・出流山千手院という寺院に保管された後、1869年(明治2年)に栃木県唐沢山神社に移され、大鎧初期の形式を現代に伝えている。(国の重要文化財)甲冑師明珍家の宗家第二十五代目当主明珍宗恭により復元された。
・寺院などに収められてからは、「おひらいし」「避来矢大権現」として崇拝の対象になっていた。また、秀郷の家には「室丸」という鎧も伝えられていたというが、これについては明らかではない。
<足利家重代の鎧~避来矢>
・足利忠綱(平安時代末期の武将 通称又太郎 下野の藤姓足利氏・足利俊綱の子~藤原秀郷の後裔 源姓足利氏とは異なる)が初陣の折 避来矢の鎧が石に変わったという伝説がある。
・敵の射かける弓矢のすべてが、まるで恐れおののいて逃げるかのように、その鎧を避けて飛び去るので、避来矢着用の者は、たとえ、どのような激戦の中にあろうとも、決して命を失うことはないと、代々言い伝えられてきており、足利家のみならず天下の秘宝ともいえる鎧であった。
●足利尊氏着用の鎧~御小袖(おんこそで)
●新田義貞着用の鎧~薄金(うすがね)
●平氏重代の鎧~唐皮の鎧(からかわのよろい)
・平氏に代々伝えられた鎧のひとつ。櫨匂威の鎧で黄色の蝶の裾金物が打ってあった。
・桓武天皇の甥の香円(もしくは伯父の慶円)が紫宸殿の前で真言の修法を行なった際、不動明王の七領の鎧の一つ「兵面」が天から降ってきたが、皮威で虎の毛がついていたので「唐皮(=中国から輸入された虎皮)」と名付けた。
・国家の守として内裏の御宝としたが、のちに平貞盛に下賜された。平治の合戦では佐衛門佐重盛が着用、その後嫡子の維盛に相伝した。
「重代の鎧唐皮といふ着背長(きせなが)をば、唐櫃(からびつ)にいれて」〈平家・五〉
「高望王の御孫、平将軍貞盛に下預被より以来、維盛迄は嫡々九代に伝はれり。今の唐皮と云は是なり」
*「不動明王の七領」とは、兵頭、兵体、兵足、兵腹、兵背、兵指、兵面を指すという。
●平氏重代の鎧~薄雲の鎧(うすぐものよろい)
・平氏に代々伝えられた鎧のひとつ。この鎧は、唐皮の鎧とともに平家重代の品とされる。源平争乱期を代表する華々しく豪壮な鎧である。
●敷妙(しきたえ)
・鞍馬寺の別当である東光房の阿闍梨が、左馬頭源義朝の末子牛若(のちの義経)に贈った腹巻。牛若は鞍馬での修行時よりこれを身につけ、鞍馬を出て奥州に下る際にも、直垂の下にこれを着こんでいた。『義経記』
●短甲(たんこう)
・弥生時代から古墳時代にかけて用いられた甲(鎧、よろい)の形式名のひとつ。木製・革製・鉄製のものがあり、原則として肩から腰の胴体を保護する。胴甲。主に古墳の副葬品として出土し、埴輪や石人にも見られる。
<出土例>
鉄製三角板革綴式短甲:長瀞西遺跡(群馬県高崎市)
横矧板皮綴短甲:狐山古墳(石川県加賀市)
竪矧板皮綴短甲:大丸山古墳(山梨県甲府市)
●挂甲(けいこう)
・古墳時代から奈良時代に用いられた鎧の形式のひとつ。
・鉄や革で出来た小さな板状の部品を縦横に紐で綴じ合わせて作成され、胴体の周囲を覆い前面や両脇で引き合わせて着用する。兜や肩鎧・膝鎧などのパーツが付属する。
・大陸の騎馬民族の鎧の影響が強く伺えるが、後にこの挂甲から日本風の大鎧・胴丸に変化していったと考えられている。同時期に用いられた鎧に短甲・綿襖甲がある。
●大鎧(おおよろい)
・日本の甲冑・鎧の形式のひとつ。馬上で弓を射る騎射戦が主流であった平安・鎌倉時代、それに対応すべく騎乗の上級武士が着用した。
・室町時代ごろには「式の鎧」「式正の鎧(しきしょうのよろい)」 江戸時代には「本式の鎧」と呼ばれた。あるいは胴丸や腹巻などと区別して、単に「鎧」ともいう。「着背長(きせなが)」ともいう。
・何によつてか一両の御着背長を重うはおぼしめし候ふべき〔出典: 平家 9〕
・大鎧の重量は、六貫から七貫(22~26キロ) 太刀を佩き弓をもって完全に武装した重量は十貫(37.5キロ)を超える。
<国宝・重文クラスの大鎧>
御物 逆沢濱威鎧 平安 法隆寺伝来 伝・聖徳太子玩具 高さ4寸7分
福島 都々古別神社 赤糸威鎧(残欠) 重文 平安
東京 武州御嶽神社 赤糸威鎧 国宝 平安後期 伝・畠山重忠奉納
東京 東京国立博物館 赤糸威鎧 重文 平安
栃木 唐沢山神社 大鎧 重文 平安 伝・避来矢の鎧
山梨 菅田天神社 小桜韋威鎧 兜・大袖付 国宝 平安後期 武田家伝来 伝・楯無の鎧
愛知 猿投神社 樫鳥威鎧 重文 平安
岡山 岡山県立博物館 赤韋威鎧 国宝 平安後期 備中赤木家に伝来
広島 厳島神社 小桜韋黄返威鎧 国宝 平安後期 伝・源為朝所用
広島 厳島神社 紺糸威鎧 国宝 平安後期 伝・平重盛奉納
島根 甘南備寺 黄櫨包威鎧 重文 平安
愛媛 大山祇神社 沢潟威鎧 国宝 伝・越智押領使好方奉納 日本最古の大鎧
愛媛 大山祇神社 紺糸威鎧 国宝 平安後期 河野通信所用
愛媛 大山祇神社 赤糸威鎧 大袖付 国宝 平安後期 伝・源義経奉納 <胴丸鎧>
個人蔵 赤韋威鎧 兜欠 重文 平安 伝・信濃赤木家伝来
青森 櫛引八幡宮 菊金物赤糸威鎧 国宝 鎌倉後期
東京 武州御嶽神社 紫裾濃威鎧 重文 鎌倉
東京 東京国立博物館 沢瀉威鎧 重文 鎌倉
東京 永青文庫 白糸妻取威鎧 袖欠 重文 鎌倉 伝・細川頼有所用
奈良 春日大社 逆沢濱威鎧 重文 鎌倉
奈良 春日大社 歌絵金物鎧 重文 鎌倉
奈良 春日大社 赤糸威鎧 兜、大袖付(梅鶯金物) 国宝 鎌倉後期
奈良 春日大社 赤糸威鎧 兜、大袖付(竹虎雀金物) 国宝 鎌倉後期
奈良 長谷寺 鷹羽威鎧 重文 鎌倉
広島 厳島神社 浅葱綾威鎧 国宝 鎌倉後期
島根 日御碕神社 白糸威鎧 国宝 鎌倉後期
山口 防府天満宮 紫韋威鎧 兜・袖・脇楯欠 重文 鎌倉
愛媛 大山祇神社 紫綾威鎧 兜欠 国宝 鎌倉前期
愛媛 大山祇神社 紫韋威鎧 重文 鎌倉
鹿児島 鶴嶺神社 赤糸威鎧 重文 鎌倉
青森 櫛引八幡宮 白糸威褄取鎧 国宝 南北朝 伝・南部信光奉納
青森 櫛引八幡宮 紫糸匂肩白鎧 重文 南北朝
奈良 春日大社 牡丹金物鎧 重文 南北朝
奈良 春日大社 龍胆金物鎧 重文 南北朝
京都 藤森神社 紫糸威鎧 重文 南北朝
京都 鞍馬寺 白糸妻取威鎧 南北朝
岡山 豊原北島神社 浅葱糸腰取威鎧 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 浅葱糸妻取威鎧 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 白糸妻取威鎧 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 萌葱綾腰取威鎧 重文 南北朝
大分 福岡市美術館 白綾威鎧 重文 南北朝
米国メトロポリタン美術館 白糸威褄取鎧 兜・袖欠 国宝級 南北朝 推定・足利尊氏所用
個人蔵 熏韋縅妻取威鎧 伝・飽浦信胤所用
奈良 長谷寺 赤糸威鎧 兜欠 重文 室町
奈良 長谷寺 白糸威鎧 重文 室町
広島 厳島神社 黒韋肩紅威鎧 重文 室町
広島 日吉神社 赤糸威鎧 重文 室町
島根 出雲大社 赤糸肩白威鎧 重文 室町
島根 日御崎神社 縹糸肩白威鎧 重文 室町
山口 防府天満宮 浅葱糸妻取威鎧 袖欠 重文 室町
山口 防府天満宮 浅葱糸威鎧 重文 室町
愛媛 大山祇神社 紅糸威鎧 重文 室町
鹿児島 鹿児島神宮 紺糸威鎧 重文 室町 伝・島津忠久所用
●胴丸(どうまる)
・日本の鎧の形式のひとつ。平安時代中期頃生じたもので、徒歩戦に適した鎧の形式である。
・右脇で開閉(引合わせ)する形式のものを指す。
・元は下級の徒歩武士が使用したものであり、下半身を防護する草摺(くさずり)が8枚に分かれ(大鎧の場合は4枚)、足が動かしやすく徒歩で動くのに都合の良い作りとなっている。
・その後の戦法の変化に伴い、胴丸はしだいに騎乗の上級武士にも用いられるようになり、デザイン的にも上級武士に相応しい華美なものへと発展していく。
・南北朝・室町期には、腹巻と共に鎧の主流となるが、安土桃山期には当世具足の登場により衰退・消滅する。
*現在「胴丸」と呼ばれている形式は、元々「腹巻」と呼ばれていたものであるが、室町時代後期~江戸時代初期頃までにその呼び方が取り違えられ現在に至る。
・大山祇神社には赤糸威の「胴丸鎧」と称する、大鎧と胴丸の折衷型のようなものが1領だけ残存している。
<国宝・重文の胴丸>
青森 櫛引八幡宮 白糸肩紅威胴丸 重文 室町
山形 致道博物館 色々威胴丸 重文 室町
東京 靖国神社 色々威胴丸 重文 室町
東京 東京国立博物館 黒韋肩白威胴丸 重文 室町
東京 東京国立博物館 色々威胴丸 重文 室町
東京 西光寺 金小札色々威胴丸 重文 室町
長野 北野美術館 紫裾濃威胴丸 重文 江戸
奈良 春日大社 伊予札黒韋威胴丸 国宝 南北朝
奈良 春日大社 黒韋威胴丸 重文 室町
大阪 壷井八幡宮 黒韋威胴丸 重文 室町
京都 建勲神社 紺糸威胴丸 重文 室町
京都 京都国立博物館 色々威胴丸 重文 室町
京都 高津古文化館 縹糸威胴丸 重文 室町
京都 高津古文化館 色々威胴丸 重文 室町
兵庫 湊川神社 白紅段威胴丸 重文 室町
岡山 林原美術館 縹糸威胴丸 重文 南北朝
広島 厳島神社 黒韋威胴丸 国宝 南北朝
島根 佐太神社 色々威胴丸 重文 室町
愛媛 大山祇神社 赤糸威鎧 大袖付 国宝 平安後期 伝・源義経奉納 <胴丸鎧>
愛媛 大山祇神社 伊予札紫韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 黒韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 牡丹金物黒韋威胴丸 重文 室町
愛媛 大山祇神社 伊予札熏韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 熏韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紫韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紫糸腰赤威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 黒韋肩腰白威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紅綾肩腰萌葱綾威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 色々威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 黒韋裾紫韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紺糸裾素懸威胴丸 重文 室町
愛媛 大山祇神社 熏韋包胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 熏韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 熏韋腰紫韋威胴丸 重文 南北朝
長崎 松浦史料博物館 色々威胴丸 重文 室町
鹿児島 鹿児島神宮 色々威胴丸 重文 室町
●腹巻(はらまき)
・日本の鎧の形式のひとつ。鎌倉時代に生じた簡易な鎧である「腹当」から進化したと考えられる。
・ 背中で開閉(引合わせ)する作りとなっている。
・大鎧に比べて腰部が細く身体に密着し草摺の間数が増えるなど、胴丸同様徒歩戦に適した動きやすい鎧で、元々は下級の徒歩武士が用いた。戦法の変化に伴い次第に騎乗の上級武士も着用するようになる。
・南北朝・室町期には胴丸と共に鎧の主流となるが、 安土桃山期には当世具足の登場により衰退する。
<国宝・重文の腹巻>
山形 上杉神社 色々威腹巻 重文 室町
東京 文化庁 色々威腹巻 重文 室町
東京 東京国立博物館 金小札糸緋威中白腹巻 重文 桃山
東京 東京国立博物館 色々威腹巻 重文 室町
奈良 石上神宮 片身変色々威腹巻 重文 室町
奈良 吉水神社 色々威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 洗韋威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 黒韋威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 黒韋肩白威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 黒韋包腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 色々威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 熏韋包肩白紅裾素懸威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 熏韋包腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 素懸浅葱糸威金腹巻 重文 室町
大阪 観心寺 黒韋肩紅威腹巻 重文 室町
京都 高津古文化館 黒韋威腹巻 重文 室町
兵庫 太山寺 紅糸中白威腹巻 重文 室町
兵庫 太山寺 素懸紺糸威腹巻 重文 室町
兵庫 湊川神社 赤白段威腰取腹巻 重文 室町
兵庫 炬口八幡宮 熏韋肩赤紅威腹巻 重文 室町
滋賀 兵主大社 白綾包腹巻 重文 室町
岡山 遍明院 黒韋肩白威腹巻 重文 室町
広島 金蓮寺 金白檀塗色々金腹巻 重文 室町
島根 佐太神社 色々威腹巻 重文 室町
島根 日御崎神社 色々威腹巻 重文 室町
山口 にしむら博物館 色々威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 洗韋威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 熏韋威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 色々威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 黒韋威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 色々裾素懸腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 素懸萌葱糸威金腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 素懸紫糸威金腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 色々威金腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 素懸茶糸威金腹巻 重文 室町
長崎 松浦史料博物館 素懸紅糸威腹巻 重文 室町<腹当>
大分 原八幡宮 金白檀小札浅葱糸威腹巻 重文 室町
●腹当(はらあて)
・日本の鎧の形式の一つ。腹巻や胴丸よりも簡易な鎧で、胸部と腹部を覆う胴鎧に小型の草摺を前と左右に三間垂らした形状で、着用者の胴体の前面及び側面のみ保護する構造となっている。(剣道の防具の「胴」と「垂」に類似)
・軽量で着脱は容易であるが、防御力は低い。腹当に背部まで防御する部分が付属し、腹巻に発展していったと考えられている。
・現在のところ実物は、平戸藩松浦氏伝来のものとして、素懸威の腹当(松浦史料博物館蔵)等が残されているが、多くが低級な消耗品であったため現存数は少ない。
●当世具足(とうせいぐそく)
・日本の甲冑の分類名称のひとつ。戦法の変化、武器の進歩、西洋甲冑の影響などのさまざまな要因により室町時代後期から安土桃山時代に生じた鎧の形式。単に具足とも。
・胴丸を改良する形で発展した。
・桶側胴、南蛮胴、仏胴、最上胴等その形式は多い。
<有名な当世具足>
黒漆塗五枚胴具足 (伊達政宗所用 仙台市博物館蔵) 金色の細い月形の前立 重文
銀伊予札白糸威胴丸具足(豊臣秀吉所用 伊達政宗拝領 仙台市博物館蔵)重文
三宝荒神形兜 具足共 (伝上杉謙信所用 仙台市博物館蔵)
南蛮胴具足 (徳川家康所用 日光東照宮蔵)
伊予札黒糸威胴丸具足(徳川家康所用 久能山東照宮蔵)
金溜塗二枚胴具足(徳川家康所用 久能山東照宮蔵)
畦目綴桶側胴具足 (細川忠興所用 永青文庫蔵)
金小札白絲素懸威胴丸具足 (前田利家所用 前田育徳会蔵)
片肌脱胴具足 (伝加藤清正所用 東京国立博物館蔵)
朱漆塗桶側胴具足 (井伊直政所用 彦根城博物館蔵)
黒絲威二枚胴具足 (本多忠勝所用 個人蔵)
金小札浅葱威二枚胴具足 付属兜 (直江兼続所用 上杉神社蔵 通称「愛」の兜)
熊毛植黒糸威具足 (徳川家康所用 徳川美術館蔵)水牛脇立熊毛植頭形兜
銀箔置白糸威具足 (松平忠吉所用 徳川美術館蔵)銀箔押越中頭形兜
●歯朶具足(しだぐそく)
・関ヶ原合戦前、徳川家康が霊夢により作らせた具足で「御無想形」あるいは「御霊夢形」とも称されている。大黒頭巾風の兜に歯朶(しだ)の葉形の前立がついているところから歯朶具足とも呼ばれた。家康は関ヶ原合戦に着用し、大坂の陣にも身近に置いて勝利を得た事で吉祥の鎧として尊ばれた。久能山東照宮博物館蔵 重要文化財
・家康が御霊夢を見て、岩井与左衛門にこの甲冑を作らせたとある。「御甲冑師岩井与左衛門由緒書」
・この事から、後のほとんどの徳川将軍も代々歯朶具足を、自分の甲冑として新調させた。全部で十九領のレプリカが存在する。
●金陀美具足(きんだびぐそく)
・永録3(1560)年5月、今川義元上洛に伴い、大高城(名古屋市緑区)への兵糧入れ際に、19歳の家康が着用していた甲冑。金箔張りの豪華さもさることながら、実用的な戦闘性能にも富んだ構造の名品。「大高城兵糧入れ具足」ともいう。久能山東照宮博物館蔵 重要文化財
●大山祇神社(おおやまずみじんじゃ)
・瀬戸内海の大三島に位置する神社 所在地は愛媛県今治市大三島町
・『国宝・重要文化財大全 5 工芸品I』(毎日新聞社刊、1998)によると、国宝・重要文化財指定の大鎧41件のうち11件、胴丸54件のうち27件、腹巻39件のうち14件が大山祇神社の所有である。以上を合計すると134件中52件(39パーセント)が大山祇神社の所有である。
参考にさせていただいたHP
http://209.85.175.132/search?q=cache:mCVSjjhUshUJ:gensounobuki.fc2web.com/t5/o3_gunki_na.html+%E5%94%90%E7%9A%AE%E3%80%80%E9%8E%A7&hl=ja&ct=clnk&cd=5&gl=jp
http://bugfix.s18.xrea.com/glossary/yogo.cgi
http://books.google.co.jp/books?id=ki99EtgfahoC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=%E4%B8%83%E7%AB%9C%E3%80%80%E9%8E%A7&source=bl&ots=EFHqz7S8Zq&sig=S9b7y1LmMW-idmAYNCfTON9PHyA&hl=ja&ei=qTSySbH7DtLEkAWCje2-BA&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result
http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/sengoku-armor.htm
ウィキペディア(Wikipedia)ほか
●源氏八領の鎧
・源頼義・義家のころより源氏に代々伝えられた八種の鎧。
・源太が産衣(げんたがうぶぎぬ)・薄金(うすかね)・楯無(たてなし)・膝丸(ひざまる)・八竜(はちりゅう)・沢瀉(おもだか)・ 月数(つきすう)・日数(ひかず)
*「源太が産衣」を除き、「七竜」を加える場合もある。
・六条判官源為義が、最期の合戦となった保元の乱の時に、代々相伝してきた鎧を一領ずつ五人の子どもに着せ、自分は薄金を着けたという。さらに源太が産衣と膝丸とは、源氏正嫡に代々伝わるものであるとして雑色の花澤に託し、(保元の乱で敵対することになった)下野守源義朝の許へと遣わしたという。
・別の書によると、保元の乱において源義朝は内四領(膝丸、八龍、沢瀉、源太が産衣)を受け継ぎ、自身は八龍を着用したという。また平治の乱においては、源義朝は膝丸、源義平は八龍、源朝長は沢瀉、源頼朝は源太が産衣を着用したという。
<源太が産衣(げんたがうぶきぬ)>
・源氏重代相伝の八領の鎧の一つ
八幡太郎義家は幼名を源太といい、二歳の時、院より召されて急ぎ鎧を威させ、袖にすえて見参に入れたことからその名がつけられた。胸板に天照大神、八幡神をあらわし、両袖に藤の花の咲きかかる様を威させている。平治の合戦では、源義朝の三男右兵衛佐頼朝が着用したが、合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<薄金(うすかね)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
緋威の鎧で、保元の合戦では、六条判官源為義が着用した。
<楯無(たてなし)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
黒糸威の鎧で、獅子の丸の裾金物が打ってあった。平治の合戦では、左馬頭源義朝が着用したが、合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<膝丸(ひざまる)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
牛千頭の膝の皮を取って威しているため、牛の精が宿っており、常に現じて主を嫌うという。保元の合戦の際、六条判官為義から、嫡子である敵方義朝に「源太が産衣」とともに贈られた。
<八竜(はちりゅう)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
八幡太郎義家が後三年合戦の折、八幡大菩薩の使者の神が八陣守護のために、金をもって八大竜王の形を打ち出し、所々に付けたためにその名がある。保元の合戦の折には下野守源義朝が、平治の合戦では義朝の長男悪源太義平が着用したが、義平が合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<沢瀉(おもだか)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
沢瀉威(沢瀉の葉のように長三角で底辺が食い込んだ形を2~5色の色変わりにあらわして威す威し方)の鎧。平治の合戦では、源義朝の次男中宮太夫進朝長が着用したが、合戦に負けて都落ちする際、雪の中に脱ぎ捨てた。
<月数(つきすう)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
朽葉色の唐綾で威した鎧。保元の合戦では、源為義の四男、四郎左衛門頼賢が着用した。
<日数(ひかず)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ
保元の合戦では、六条判官為義の子、五郎掃部助頼仲、賀茂六郎為宗、七郎為成、源九郎為仲のいずれかが着用したものと思われる。
<七竜(しちりゅう)>
・源氏重代の八領の鎧の一つ(金刀本)
保元の合戦では、六条判官為義の子、五郎掃部助頼仲、賀茂六郎為宗、七郎為成、源九郎為仲のうちのいずれかが着用したものと思われる。 『保元物語』
●楯無(たてなし)の鎧
・源義光伝来の鎧とされる源氏八領のうちのひとつ。特に甲州武田家に伝わる大鎧で名高い。
・名前の由来は、その堅牢さの故に盾もいらぬほど、という理由から来たと言われる。
・保元物語や平治物語にその名が見られるが、平治の乱の際に源義朝が黒糸威の楯無を身に着けて戦った後、敗走中にそれを雪の中に脱ぎ捨てたとされている。
<武田家重代の鎧~楯無>
・『武田源氏一統系図』によれば、「楯無」と号された鎧は甲斐国守護家である甲斐源氏武田氏の家宝として、始祖と位置付けられる新羅三郎義光以来相伝されていると伝わり、御旗(みはた)と呼ばれる義光から受け継いだ日章旗と対になっている。
・戦国期には武田氏の親族衆や家臣団の間で神格化され、この鎧と旗に「御旗楯無も御照覧あれ(みはたたてなしも ごしょうらんあれ)」と誓い出陣した。
・菅田天神社(かんだてんじんしゃ 山梨県甲州市 旧塩山市上於曽)に伝わる小桜韋威鎧が楯無鎧であるとされており、現在も同神社に所蔵されている。御旗は甲州市塩山の雲峰寺に所蔵。
●避来矢(ひらいし)
・平安時代中期の武将藤原秀郷が百足退治の礼として龍宮の王からもらったという伝説のある大鎧の名称。「平石」とも記される。
・藤原氏子孫(下野国の佐野氏)に伝えられたが、江戸時代に浅草に保管してあったところ火災により焼失し、兜鉢、障子の板、壺板等の金属部分のみが残った。
・出流山千手院という寺院に保管された後、1869年(明治2年)に栃木県唐沢山神社に移され、大鎧初期の形式を現代に伝えている。(国の重要文化財)甲冑師明珍家の宗家第二十五代目当主明珍宗恭により復元された。
・寺院などに収められてからは、「おひらいし」「避来矢大権現」として崇拝の対象になっていた。また、秀郷の家には「室丸」という鎧も伝えられていたというが、これについては明らかではない。
<足利家重代の鎧~避来矢>
・足利忠綱(平安時代末期の武将 通称又太郎 下野の藤姓足利氏・足利俊綱の子~藤原秀郷の後裔 源姓足利氏とは異なる)が初陣の折 避来矢の鎧が石に変わったという伝説がある。
・敵の射かける弓矢のすべてが、まるで恐れおののいて逃げるかのように、その鎧を避けて飛び去るので、避来矢着用の者は、たとえ、どのような激戦の中にあろうとも、決して命を失うことはないと、代々言い伝えられてきており、足利家のみならず天下の秘宝ともいえる鎧であった。
●足利尊氏着用の鎧~御小袖(おんこそで)
●新田義貞着用の鎧~薄金(うすがね)
●平氏重代の鎧~唐皮の鎧(からかわのよろい)
・平氏に代々伝えられた鎧のひとつ。櫨匂威の鎧で黄色の蝶の裾金物が打ってあった。
・桓武天皇の甥の香円(もしくは伯父の慶円)が紫宸殿の前で真言の修法を行なった際、不動明王の七領の鎧の一つ「兵面」が天から降ってきたが、皮威で虎の毛がついていたので「唐皮(=中国から輸入された虎皮)」と名付けた。
・国家の守として内裏の御宝としたが、のちに平貞盛に下賜された。平治の合戦では佐衛門佐重盛が着用、その後嫡子の維盛に相伝した。
「重代の鎧唐皮といふ着背長(きせなが)をば、唐櫃(からびつ)にいれて」〈平家・五〉
「高望王の御孫、平将軍貞盛に下預被より以来、維盛迄は嫡々九代に伝はれり。今の唐皮と云は是なり」
*「不動明王の七領」とは、兵頭、兵体、兵足、兵腹、兵背、兵指、兵面を指すという。
●平氏重代の鎧~薄雲の鎧(うすぐものよろい)
・平氏に代々伝えられた鎧のひとつ。この鎧は、唐皮の鎧とともに平家重代の品とされる。源平争乱期を代表する華々しく豪壮な鎧である。
●敷妙(しきたえ)
・鞍馬寺の別当である東光房の阿闍梨が、左馬頭源義朝の末子牛若(のちの義経)に贈った腹巻。牛若は鞍馬での修行時よりこれを身につけ、鞍馬を出て奥州に下る際にも、直垂の下にこれを着こんでいた。『義経記』
●短甲(たんこう)
・弥生時代から古墳時代にかけて用いられた甲(鎧、よろい)の形式名のひとつ。木製・革製・鉄製のものがあり、原則として肩から腰の胴体を保護する。胴甲。主に古墳の副葬品として出土し、埴輪や石人にも見られる。
<出土例>
鉄製三角板革綴式短甲:長瀞西遺跡(群馬県高崎市)
横矧板皮綴短甲:狐山古墳(石川県加賀市)
竪矧板皮綴短甲:大丸山古墳(山梨県甲府市)
●挂甲(けいこう)
・古墳時代から奈良時代に用いられた鎧の形式のひとつ。
・鉄や革で出来た小さな板状の部品を縦横に紐で綴じ合わせて作成され、胴体の周囲を覆い前面や両脇で引き合わせて着用する。兜や肩鎧・膝鎧などのパーツが付属する。
・大陸の騎馬民族の鎧の影響が強く伺えるが、後にこの挂甲から日本風の大鎧・胴丸に変化していったと考えられている。同時期に用いられた鎧に短甲・綿襖甲がある。
●大鎧(おおよろい)
・日本の甲冑・鎧の形式のひとつ。馬上で弓を射る騎射戦が主流であった平安・鎌倉時代、それに対応すべく騎乗の上級武士が着用した。
・室町時代ごろには「式の鎧」「式正の鎧(しきしょうのよろい)」 江戸時代には「本式の鎧」と呼ばれた。あるいは胴丸や腹巻などと区別して、単に「鎧」ともいう。「着背長(きせなが)」ともいう。
・何によつてか一両の御着背長を重うはおぼしめし候ふべき〔出典: 平家 9〕
・大鎧の重量は、六貫から七貫(22~26キロ) 太刀を佩き弓をもって完全に武装した重量は十貫(37.5キロ)を超える。
<国宝・重文クラスの大鎧>
御物 逆沢濱威鎧 平安 法隆寺伝来 伝・聖徳太子玩具 高さ4寸7分
福島 都々古別神社 赤糸威鎧(残欠) 重文 平安
東京 武州御嶽神社 赤糸威鎧 国宝 平安後期 伝・畠山重忠奉納
東京 東京国立博物館 赤糸威鎧 重文 平安
栃木 唐沢山神社 大鎧 重文 平安 伝・避来矢の鎧
山梨 菅田天神社 小桜韋威鎧 兜・大袖付 国宝 平安後期 武田家伝来 伝・楯無の鎧
愛知 猿投神社 樫鳥威鎧 重文 平安
岡山 岡山県立博物館 赤韋威鎧 国宝 平安後期 備中赤木家に伝来
広島 厳島神社 小桜韋黄返威鎧 国宝 平安後期 伝・源為朝所用
広島 厳島神社 紺糸威鎧 国宝 平安後期 伝・平重盛奉納
島根 甘南備寺 黄櫨包威鎧 重文 平安
愛媛 大山祇神社 沢潟威鎧 国宝 伝・越智押領使好方奉納 日本最古の大鎧
愛媛 大山祇神社 紺糸威鎧 国宝 平安後期 河野通信所用
愛媛 大山祇神社 赤糸威鎧 大袖付 国宝 平安後期 伝・源義経奉納 <胴丸鎧>
個人蔵 赤韋威鎧 兜欠 重文 平安 伝・信濃赤木家伝来
青森 櫛引八幡宮 菊金物赤糸威鎧 国宝 鎌倉後期
東京 武州御嶽神社 紫裾濃威鎧 重文 鎌倉
東京 東京国立博物館 沢瀉威鎧 重文 鎌倉
東京 永青文庫 白糸妻取威鎧 袖欠 重文 鎌倉 伝・細川頼有所用
奈良 春日大社 逆沢濱威鎧 重文 鎌倉
奈良 春日大社 歌絵金物鎧 重文 鎌倉
奈良 春日大社 赤糸威鎧 兜、大袖付(梅鶯金物) 国宝 鎌倉後期
奈良 春日大社 赤糸威鎧 兜、大袖付(竹虎雀金物) 国宝 鎌倉後期
奈良 長谷寺 鷹羽威鎧 重文 鎌倉
広島 厳島神社 浅葱綾威鎧 国宝 鎌倉後期
島根 日御碕神社 白糸威鎧 国宝 鎌倉後期
山口 防府天満宮 紫韋威鎧 兜・袖・脇楯欠 重文 鎌倉
愛媛 大山祇神社 紫綾威鎧 兜欠 国宝 鎌倉前期
愛媛 大山祇神社 紫韋威鎧 重文 鎌倉
鹿児島 鶴嶺神社 赤糸威鎧 重文 鎌倉
青森 櫛引八幡宮 白糸威褄取鎧 国宝 南北朝 伝・南部信光奉納
青森 櫛引八幡宮 紫糸匂肩白鎧 重文 南北朝
奈良 春日大社 牡丹金物鎧 重文 南北朝
奈良 春日大社 龍胆金物鎧 重文 南北朝
京都 藤森神社 紫糸威鎧 重文 南北朝
京都 鞍馬寺 白糸妻取威鎧 南北朝
岡山 豊原北島神社 浅葱糸腰取威鎧 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 浅葱糸妻取威鎧 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 白糸妻取威鎧 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 萌葱綾腰取威鎧 重文 南北朝
大分 福岡市美術館 白綾威鎧 重文 南北朝
米国メトロポリタン美術館 白糸威褄取鎧 兜・袖欠 国宝級 南北朝 推定・足利尊氏所用
個人蔵 熏韋縅妻取威鎧 伝・飽浦信胤所用
奈良 長谷寺 赤糸威鎧 兜欠 重文 室町
奈良 長谷寺 白糸威鎧 重文 室町
広島 厳島神社 黒韋肩紅威鎧 重文 室町
広島 日吉神社 赤糸威鎧 重文 室町
島根 出雲大社 赤糸肩白威鎧 重文 室町
島根 日御崎神社 縹糸肩白威鎧 重文 室町
山口 防府天満宮 浅葱糸妻取威鎧 袖欠 重文 室町
山口 防府天満宮 浅葱糸威鎧 重文 室町
愛媛 大山祇神社 紅糸威鎧 重文 室町
鹿児島 鹿児島神宮 紺糸威鎧 重文 室町 伝・島津忠久所用
●胴丸(どうまる)
・日本の鎧の形式のひとつ。平安時代中期頃生じたもので、徒歩戦に適した鎧の形式である。
・右脇で開閉(引合わせ)する形式のものを指す。
・元は下級の徒歩武士が使用したものであり、下半身を防護する草摺(くさずり)が8枚に分かれ(大鎧の場合は4枚)、足が動かしやすく徒歩で動くのに都合の良い作りとなっている。
・その後の戦法の変化に伴い、胴丸はしだいに騎乗の上級武士にも用いられるようになり、デザイン的にも上級武士に相応しい華美なものへと発展していく。
・南北朝・室町期には、腹巻と共に鎧の主流となるが、安土桃山期には当世具足の登場により衰退・消滅する。
*現在「胴丸」と呼ばれている形式は、元々「腹巻」と呼ばれていたものであるが、室町時代後期~江戸時代初期頃までにその呼び方が取り違えられ現在に至る。
・大山祇神社には赤糸威の「胴丸鎧」と称する、大鎧と胴丸の折衷型のようなものが1領だけ残存している。
<国宝・重文の胴丸>
青森 櫛引八幡宮 白糸肩紅威胴丸 重文 室町
山形 致道博物館 色々威胴丸 重文 室町
東京 靖国神社 色々威胴丸 重文 室町
東京 東京国立博物館 黒韋肩白威胴丸 重文 室町
東京 東京国立博物館 色々威胴丸 重文 室町
東京 西光寺 金小札色々威胴丸 重文 室町
長野 北野美術館 紫裾濃威胴丸 重文 江戸
奈良 春日大社 伊予札黒韋威胴丸 国宝 南北朝
奈良 春日大社 黒韋威胴丸 重文 室町
大阪 壷井八幡宮 黒韋威胴丸 重文 室町
京都 建勲神社 紺糸威胴丸 重文 室町
京都 京都国立博物館 色々威胴丸 重文 室町
京都 高津古文化館 縹糸威胴丸 重文 室町
京都 高津古文化館 色々威胴丸 重文 室町
兵庫 湊川神社 白紅段威胴丸 重文 室町
岡山 林原美術館 縹糸威胴丸 重文 南北朝
広島 厳島神社 黒韋威胴丸 国宝 南北朝
島根 佐太神社 色々威胴丸 重文 室町
愛媛 大山祇神社 赤糸威鎧 大袖付 国宝 平安後期 伝・源義経奉納 <胴丸鎧>
愛媛 大山祇神社 伊予札紫韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 黒韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 牡丹金物黒韋威胴丸 重文 室町
愛媛 大山祇神社 伊予札熏韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 熏韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紫韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紫糸腰赤威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 黒韋肩腰白威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紅綾肩腰萌葱綾威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 色々威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 黒韋裾紫韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 紺糸裾素懸威胴丸 重文 室町
愛媛 大山祇神社 熏韋包胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 熏韋威胴丸 重文 南北朝
愛媛 大山祇神社 熏韋腰紫韋威胴丸 重文 南北朝
長崎 松浦史料博物館 色々威胴丸 重文 室町
鹿児島 鹿児島神宮 色々威胴丸 重文 室町
●腹巻(はらまき)
・日本の鎧の形式のひとつ。鎌倉時代に生じた簡易な鎧である「腹当」から進化したと考えられる。
・ 背中で開閉(引合わせ)する作りとなっている。
・大鎧に比べて腰部が細く身体に密着し草摺の間数が増えるなど、胴丸同様徒歩戦に適した動きやすい鎧で、元々は下級の徒歩武士が用いた。戦法の変化に伴い次第に騎乗の上級武士も着用するようになる。
・南北朝・室町期には胴丸と共に鎧の主流となるが、 安土桃山期には当世具足の登場により衰退する。
<国宝・重文の腹巻>
山形 上杉神社 色々威腹巻 重文 室町
東京 文化庁 色々威腹巻 重文 室町
東京 東京国立博物館 金小札糸緋威中白腹巻 重文 桃山
東京 東京国立博物館 色々威腹巻 重文 室町
奈良 石上神宮 片身変色々威腹巻 重文 室町
奈良 吉水神社 色々威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 洗韋威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 黒韋威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 黒韋肩白威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 黒韋包腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 色々威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 熏韋包肩白紅裾素懸威腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 熏韋包腹巻 重文 室町
大阪 金剛寺 素懸浅葱糸威金腹巻 重文 室町
大阪 観心寺 黒韋肩紅威腹巻 重文 室町
京都 高津古文化館 黒韋威腹巻 重文 室町
兵庫 太山寺 紅糸中白威腹巻 重文 室町
兵庫 太山寺 素懸紺糸威腹巻 重文 室町
兵庫 湊川神社 赤白段威腰取腹巻 重文 室町
兵庫 炬口八幡宮 熏韋肩赤紅威腹巻 重文 室町
滋賀 兵主大社 白綾包腹巻 重文 室町
岡山 遍明院 黒韋肩白威腹巻 重文 室町
広島 金蓮寺 金白檀塗色々金腹巻 重文 室町
島根 佐太神社 色々威腹巻 重文 室町
島根 日御崎神社 色々威腹巻 重文 室町
山口 にしむら博物館 色々威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 洗韋威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 熏韋威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 色々威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 黒韋威腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 色々裾素懸腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 素懸萌葱糸威金腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 素懸紫糸威金腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 色々威金腹巻 重文 室町
愛媛 大山祇神社 素懸茶糸威金腹巻 重文 室町
長崎 松浦史料博物館 素懸紅糸威腹巻 重文 室町<腹当>
大分 原八幡宮 金白檀小札浅葱糸威腹巻 重文 室町
●腹当(はらあて)
・日本の鎧の形式の一つ。腹巻や胴丸よりも簡易な鎧で、胸部と腹部を覆う胴鎧に小型の草摺を前と左右に三間垂らした形状で、着用者の胴体の前面及び側面のみ保護する構造となっている。(剣道の防具の「胴」と「垂」に類似)
・軽量で着脱は容易であるが、防御力は低い。腹当に背部まで防御する部分が付属し、腹巻に発展していったと考えられている。
・現在のところ実物は、平戸藩松浦氏伝来のものとして、素懸威の腹当(松浦史料博物館蔵)等が残されているが、多くが低級な消耗品であったため現存数は少ない。
●当世具足(とうせいぐそく)
・日本の甲冑の分類名称のひとつ。戦法の変化、武器の進歩、西洋甲冑の影響などのさまざまな要因により室町時代後期から安土桃山時代に生じた鎧の形式。単に具足とも。
・胴丸を改良する形で発展した。
・桶側胴、南蛮胴、仏胴、最上胴等その形式は多い。
<有名な当世具足>
黒漆塗五枚胴具足 (伊達政宗所用 仙台市博物館蔵) 金色の細い月形の前立 重文
銀伊予札白糸威胴丸具足(豊臣秀吉所用 伊達政宗拝領 仙台市博物館蔵)重文
三宝荒神形兜 具足共 (伝上杉謙信所用 仙台市博物館蔵)
南蛮胴具足 (徳川家康所用 日光東照宮蔵)
伊予札黒糸威胴丸具足(徳川家康所用 久能山東照宮蔵)
金溜塗二枚胴具足(徳川家康所用 久能山東照宮蔵)
畦目綴桶側胴具足 (細川忠興所用 永青文庫蔵)
金小札白絲素懸威胴丸具足 (前田利家所用 前田育徳会蔵)
片肌脱胴具足 (伝加藤清正所用 東京国立博物館蔵)
朱漆塗桶側胴具足 (井伊直政所用 彦根城博物館蔵)
黒絲威二枚胴具足 (本多忠勝所用 個人蔵)
金小札浅葱威二枚胴具足 付属兜 (直江兼続所用 上杉神社蔵 通称「愛」の兜)
熊毛植黒糸威具足 (徳川家康所用 徳川美術館蔵)水牛脇立熊毛植頭形兜
銀箔置白糸威具足 (松平忠吉所用 徳川美術館蔵)銀箔押越中頭形兜
●歯朶具足(しだぐそく)
・関ヶ原合戦前、徳川家康が霊夢により作らせた具足で「御無想形」あるいは「御霊夢形」とも称されている。大黒頭巾風の兜に歯朶(しだ)の葉形の前立がついているところから歯朶具足とも呼ばれた。家康は関ヶ原合戦に着用し、大坂の陣にも身近に置いて勝利を得た事で吉祥の鎧として尊ばれた。久能山東照宮博物館蔵 重要文化財
・家康が御霊夢を見て、岩井与左衛門にこの甲冑を作らせたとある。「御甲冑師岩井与左衛門由緒書」
・この事から、後のほとんどの徳川将軍も代々歯朶具足を、自分の甲冑として新調させた。全部で十九領のレプリカが存在する。
●金陀美具足(きんだびぐそく)
・永録3(1560)年5月、今川義元上洛に伴い、大高城(名古屋市緑区)への兵糧入れ際に、19歳の家康が着用していた甲冑。金箔張りの豪華さもさることながら、実用的な戦闘性能にも富んだ構造の名品。「大高城兵糧入れ具足」ともいう。久能山東照宮博物館蔵 重要文化財
●大山祇神社(おおやまずみじんじゃ)
・瀬戸内海の大三島に位置する神社 所在地は愛媛県今治市大三島町
・『国宝・重要文化財大全 5 工芸品I』(毎日新聞社刊、1998)によると、国宝・重要文化財指定の大鎧41件のうち11件、胴丸54件のうち27件、腹巻39件のうち14件が大山祇神社の所有である。以上を合計すると134件中52件(39パーセント)が大山祇神社の所有である。
参考にさせていただいたHP
http://209.85.175.132/search?q=cache:mCVSjjhUshUJ:gensounobuki.fc2web.com/t5/o3_gunki_na.html+%E5%94%90%E7%9A%AE%E3%80%80%E9%8E%A7&hl=ja&ct=clnk&cd=5&gl=jp
http://bugfix.s18.xrea.com/glossary/yogo.cgi
http://books.google.co.jp/books?id=ki99EtgfahoC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=%E4%B8%83%E7%AB%9C%E3%80%80%E9%8E%A7&source=bl&ots=EFHqz7S8Zq&sig=S9b7y1LmMW-idmAYNCfTON9PHyA&hl=ja&ei=qTSySbH7DtLEkAWCje2-BA&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result
http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/sengoku-armor.htm
ウィキペディア(Wikipedia)ほか