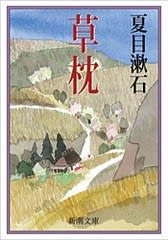
智に働けば角がたつ、情に棹させば流される―春の山路を登りつめた青年画家は、やがてとある温泉場で才気あふれる女、那美と出会う。俗塵を離れた山奥の桃源郷を舞台に、絢爛豊富な語彙と多彩な文章を駆使して絵画的感覚美の世界を描き、自然主義や西欧文学の現実主義への批判を込めて、その対極に位置する東洋趣味を高唱。
『吾輩は猫である』『坊っちゃん』とならぶ初期の代表作。
出版社:新潮社(新潮文庫)
『草枕』は十代のころに一度読んだことがあるが、はっきり言って何がおもしろいのか、さっぱりわからなかった。
率直に語るなら、つまらないとさえ感じたものである。
今回、十数年ぶりに『草枕』を読み返したのだが、思っていた以上におもしろかったので驚いている。
だがそのおもしろさは、楽しいという意味合いでのおもしろさとは少し違う。
どちらかと言うと、興味深い、といった方が適切なおもしろさなのだ。
楽しいと違う、と感じた点は、やはり筋書きがあってないようなものだからだろう。
「俳句的小説」という形容がされているみたいだが、言い得て妙である。
解説にもあったが、小説中で、主人公は、小説の筋なんかどうでもいい、ぱっと開いて漫然と読むのがおもしろい、って感じのことを書いている。
そのことからしても、作者は筋書きのことをそこまで意識してはいなかったのだろう。
この小説で問題になるのは、俳句のように、一瞬の情景を切り取ることにあるのだと思う。
画家を主人公に据えているため、そこら辺りの考えは徹底されている。
主人公は己の境地を離れ、情景だけをただ客観で見ることこそ、雅であると思っているらしい。自我というものにこだわり、主観的に見ることを、生々しく俗っぽいと考えているようにも見える。
あるいはそれは、俳句の用語を使うなら、「軽み」ってやつを追求しているのかもしれない。
そういう点、いかにも高等遊民的で偏屈な考え方なのだが、それを小説や人間社会への考え方にまで応用しようとする発想は実に鮮やかだ。
そんな高等遊民というインテリを主人公にしているだけあり、文中に出てくる学識はかなりのものがある。
たとえば文学に対する知識で言うなら、漢詩や俳句、英語の詩まで登場して博学だし、主人公がつくる俳句もいくつかはおもしろい。
また画家が主人公だけあり、絵に関する理論も興味深い。特に裸体画に関する考えなどはそういう視線もあるのだな、と気づかされて、刺激的だ。
それにミレイのオフェリヤのような絵を描くにはどうすればいいのか、考えているところも個人的には好きである。
衒学的な部分以外でも、主人公独自のおもしろい意見があり、いくつかは感心させられる。
「人のひる屁の勘定をして、それが人世だと思ってる」という文章が個人的には気に入っている。
そこからは主人公の偏屈さがうかがえるようで笑ってしまうのだが、同時に、押し付けがましい社会に対する反発心と批判を訴えているようで、なかなか勇ましい。
なかなかどこが良いかを伝えにくい作品ではあるが、上述のように主人公の視点や思考が目を引く作品である。
もちろんそれらを伝える文章のリズムが良い点は言うまでもない。
「智に働けば角がたつ」で有名な冒頭部はもちろん、どの文章もリズミカルで読んでいても心地よい。
『草枕』は漱石のベストではないだろう。だが一読忘れがたい作品である。
評価:★★★(満点は★★★★★)
そのほかの夏目漱石作品感想
『門』










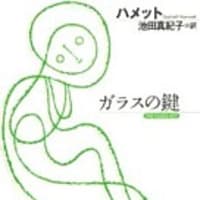

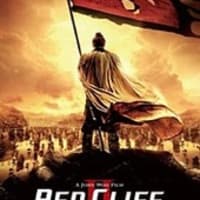
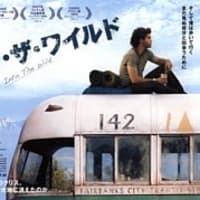
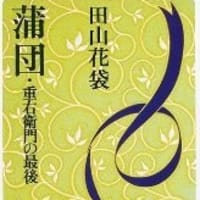
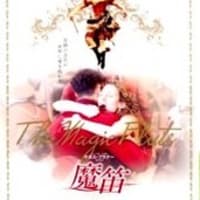
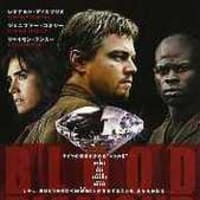
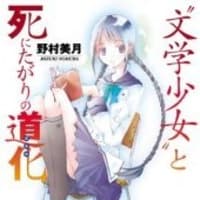
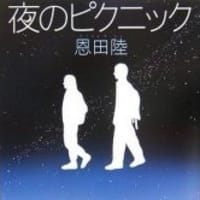









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます