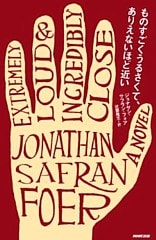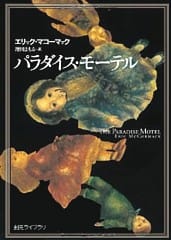平凡無垢な青年ハンス・カストルプははからずもスイス高原のサナトリウムで療養生活を送ることとなった。日常世界から隔離され,病気と死が支配するこの「魔の山」で、カストルプはそれぞれの時代精神や思想を体現する特異な人物たちに出会い、精神的成長を遂げてゆく。『ファウスト』と並んでドイツが世界に贈った人生の書。
関泰祐・望月市恵 訳
出版社:岩波書店(岩波文庫)
『八月の光』がおもしろかったので、同じように以前読んで挫折した本を読み返そうと、本書を手にしてみた。
で、今回再読して、なるほどむかしの僕が挫折したのも当然だったなと改めて感じた。
それは、訳が古く、内容が無駄に長く、幾分観念的だからだろう。
実際、読んでいる最中、内容が頭の中に入ってこないことも多かった。
そういう意味、『魔の山』は、精神的に余裕のあるときしか読めない本かもしれない。
そんな本書の印象を端的にまとめるならば、以下のようになる。
それは、『魔の山』は、教養小説の体裁を取りながら、そういった教養が実のところ、もろいものでしかないことを描いた作品である、ということだ。
解説を読む限り、誤読だろうが、僕はそう解釈したので、その論旨で進めていこう。
本書は、平凡な青年ハンス・カルストプが三週間の予定で、従兄がいるサナトリウムを訪れるところから始まる。しかし彼自身結核持ちであることが判明、そのサナトリウムに長期滞在することとなる。その過程でハンスは、恋をしたり、様々な人に触れたり、あらゆる思想を学んでいく。
サナトリウムというと、
『風立ちぬ』のイメージがあるので、静謐な雰囲気を想像するのだが、ここの人たちは概ね元気がいい。
セテムブリーニみたいに饒舌な人もいるし、シュテール夫人みたいに騒がしい人もいれば、ショーシャ夫人みたいにドアを大きな音を立てて閉める人もいて、個性的だ。
しかしその社会は、あくまでせまい。そして下界から隔絶していて、浮世離れしている。
前者で言うなら、ハンスがショーシャ夫人にほのかな恋心を抱くところも何となくそんな感じがする。
周りがハンスの恋心に気づき、どういう態度をとるか、見守るところなど、その印象は強い。
狭いサークルゆえに、互いの関心も狭いのだろう。
そして後者では、時間の観念がどんどん崩れていくところなどはそんな感じがするのだ。
実際停滞とも見えかねない、サナトリウムでの暮らしに、後年はハンスもどんどん無感覚になっていく。
下界との隔絶ゆえに、多くのことに関心をもてなくなっているのかもしれない。
そして、そんな浮世離れした世界観を象徴するのが、セテムブリーニとナフタの議論なのである。
前回読んだときも思ったけれど、彼らの議論は、抽象論に過ぎているし、古めかしい。
現代の人がいま読む意義ははっきり言って、僕には見出せなかった。
とは言え、その内容自体はおもしろい。
ざっくりとまとめるならば、二人の思想は以下のようになろう。
セテムブリーニは、理性を基盤に据えた理想主義。
ナフタは、宗教(ただし解説を読む限り、ここはイデオロギーと置き換えた方がいいようだ)を絶対視し、それを通すためなら、倫理をも無視していいと考える、禁欲的な原理主義。
そんなところだろうか。
ハンスが暮らしていたのは、ヨーアヒムに代表される、謹厳な価値観の世界だ。
しかしセテムブリーニとナフタの議論は、それとは対照的であり、ハンスはそういった世界の捕らえ方があることも学んでいく。
僕個人の好みで言うなら、セテムブリーニの思想の方に共感する。
しかし彼は、セテムブリーニの理想主義も、ナフタの原理主義のどちらにも、違和感があるらしい。
実際「雪」の章で、彼はどちらの思想にも与しないことを自らに確認している。
本当の答えはそういった考えの中間の位置にあることを、ハンスも気づいているのだ。
そういう点、思想に関しては、彼はひとつの結論に達したと言えるだろう。
しかし問題は、そういった思想がどれほどの強度を持つのかという点にある。
それを象徴するのはペーペルコルンだ。
彼は自分の思想をはっきりと語ることはほとんどない。
そのせいか、彼は馬鹿なのではないか、とセテムブリーニに言われたりもしている。
しかし、ペーペルコルンは、その人間的な雰囲気のために、周囲の評価を得ている。
僕個人は、ペーペルコルンはただのわがままな老人にしか見えなかったけど、ハンス的には、人物であるとのことらしい。
そしてそういった人間としての雰囲気のために、ペーペルコルンは、議論を重ね、思想を披露しているセテムブリーニたちよりも上だと見なされているのだ。
そういう風にみると、思想というものがとても弱々しいものに見えてならない。
どれほど強固な思想でも、カリスマティックな人物の登場で、思想はあっさり打ち破られる可能性もあるのだ。
思想は、雰囲気によって左右されかねない、ということだろう。そういう点は現代的だ。
そしてそれは時代の熱狂に飲み込まれていくラストにも通じることである。
そんな時代の熱狂は、ある意味では、死への熱狂ともいえるのかもしれない。
この作品では、サナトリウムという関係上、多くの人が死ぬ。
彼の親しい人間で言えば、ヨーアヒムなんかは典型だろう。
それ以外にもペーペルコルンやナフタは自ら死を選んだ。
ハンスは「雪」の章で、「死と病気とへの興味は、生への興味の一形態にほかならない」と述べている。
しかしだからと言って死に耽溺するではなく、「人間は善意と愛とを失なわないために、考えを死に従属させないようにしなくてはならない」とも考えている。
ハト派の僕としては、きわめてまっとうな意見だと思う。
しかしそんな考えを持っていても、第一次世界大戦に突入し、「ヒステリックな焔」に時代は熱狂することになる。
理想主義者のセテムブリーニすら、国家的な件については、マッチョな考えのとりこになる。
「抽象的なもの、純粋なもの、理念的なものは、同時にまた絶対的なものです、したがってまた、ほんとうにきびしいものです、そして、これこそ社会的生活よりもはるかに深刻に過激に、憎悪を、絶対的な妥協のない敵対関係を生じさせる可能性を宿しているのです」
そんなことをセテムブリーニは言っているけれど、時代もそれに巻き込まれる人々も、まさにそういう状態に追いやられてしまう。
最終的に物語は、ハンスが戦場に突入するところで終わる。
著者の意図はともかく、その中に、僕は理性的な行動と思想の限界を見る思いがした。
「死に従属させないように」あろうとしても、それを突きつめようとする理性は、とかくもろい。
しかし本書は、それでもヒューマニティある思想を希求する予感も感じられるのだ。
それが少し心に残ってならない。
長すぎる作品だとは思う。
しかしその長さに見合う長大な思考と思想を本書は展開していて忘れがたい。
まさに大作、そう呼ぶに足る一品であろう。
評価:★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのトーマス・マン作品感想
『トニオ・クレエゲル』(岩波文庫)
『トーニオ・クレーガー 他一篇』(河出文庫)
『トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す』(新潮文庫)