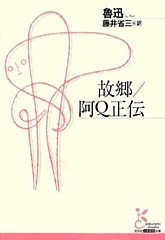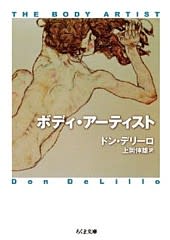ぼくは人生を愛している。これはいわば告白だ――陽気で生き生きとした普通の人たちに憧れる、孤独で瞑想的な少年だったトーニオは、過去と別れ、芸術家として名を成した。そして十三年ぶりに故郷を訪れるたびに出る……二十世紀文学の巨匠マンの自画像にして、不滅の青春小説。後期の代表的短編「マーリオと魔術師」を同時収録。
平野卿子 訳
出版社:河出書房新社(河出文庫)
僕が積極的に海外文学を読むようになったのは、赤川次郎『三毛猫ホームズの映画館』がきっかけだ。
その本の中で赤川次郎は、表紙がボロボロになるまで読み返した本として、岩波文庫の、つまりは実吉捷郎訳の『トニオ・クレエゲル』を挙げている。
実吉訳の『トニオ・クレエゲル』は人気が高い。
赤川次郎以外の有名どころでは、北杜夫や辻邦生が、実吉訳『トニオ』を好きな作品に挙げている。
そんな超メジャーな訳がある中で、新訳を出すのは勇気あることかもしれない。
だが本作は、新訳として世に問う価値のある、非常に丁寧な訳だと読んでいて感じた。
たとえば個人的に一番好きな、ラストのダンスパーティでのシーン。
岩波文庫の実吉訳は以下のようになっている。
「われは寝ねまし、されど汝は踊らでやまず。」この文句の語る憂鬱で北国的な、誠実で不器用な感覚の重苦しさを、彼は実によくしっている。眠るのだ……動くとか踊るとかいう義務なしに、甘くものうくそれ自身の中に安らっている感情――全くその感情にのみ生きられるようになりたい、とあこがれるのだ。――しかもそれでいて、踊らずにいられないのだ。敏活に自若として、芸術という難儀な難儀な、そして危険な白刃踊りを演ぜずにはいられないのだ――恋をしながら踊らずにいられぬという、その屈辱的な矛盾を、一度もすっかり忘れきることなしに……
ついでに、
新潮文庫の高橋義孝訳も挙げると、
「いねましものを、踊らむとや」。この詩の放散する感じの憂鬱で北方的な、切実で不器用な重苦しさ、これを彼は味わい尽くしていた。ねむり……行為したり踊ったりするという義務を負うことなく、心地よく気だるくそれ自身のうちに休らっている感情、そういう感情に従って素朴に完全に生きて行きたいと願う心が一方にありながら――しかも他方では手抜かりなく気を張りつめて芸術というじつに困難な危険このうえもない白刃の舞を舞いおおせねばならぬ――恋をしながら踊らねばならぬということのうちに含まれている屈辱的な矛盾をすっかり忘れてしまうことは絶対になく。……
そして本書、河出文庫の平野卿子訳は
「ぼくは眠りたい。なのに君は躍らずにはいられない」。この詩のもつ北国特有の憂鬱さ、誠実で不器用な重苦しさは、知りすぎるくらいよく知っている。眠るとは――何かをするとか踊るとかいった義務なしに、自分のなかにある甘くけだるい感情、ただそれだけを感じて生きたいと憧れること――それなのに、踊らなければならない。軽快に巧みに、芸術という名のこの上なく難しい危険な剣の舞を。しかも、愛しているのに踊らなければならないという屈辱的な矛盾を完全に忘れることはないのだ……
実吉訳は、これだけを引用してもわかりづらいかもしれないが、情感に訴えるような部分が強いように思う。
断定が目立つ文章には変な勢いがあって、その勢いは主人公が青年のこの作品にはマッチしているよう。
そしてその勢いこそ、『トニオ・クレエゲル』を魅力的なものにし、ファンを多くつくる一因になっているのだろう。
一方の高橋訳はいかにも硬く、理知的な印象を受け、どうにもとっつきにくい。つうか訳文がわかりにくい。
そして今回の平野訳は、とにかく文章の読みやすさに気を配っているように感じた。
上述の場面だと、一番文章の意味がすっきりするのは、平野訳だ。
それ以外でも、たとえば間接話法が使われている部分で、実吉訳が「トニオは」と訳しているところを、平野訳は「ぼくは」と訳しているところもある。
そういうポイントを見るに、平野訳の方が主人公に寄り添う感が強く、そのため主人公の繊細さがより一層伝わってくるように感じられる。
あとがきに書かれていた「再会」の件についても、平野訳だけが、そのシーンでトーニオはハンスたちと再会しているわけじゃないと、はっきりわかるよう訳している(読み返したら、実吉訳と高橋訳は誤訳?だった)。
それだけでもこの訳者の誠意が見えるようだ。
訳文比較するだけで、そういうことまで見えてくるっておもしろい。
好みはあるだろうけれど、いまの時代に『トニオ・クレーゲル』を初めて読むなら、平野訳がいいと僕は感じる。
文章に一番魅力があるのは実吉訳で、僕もその訳が好きだけど、言葉が古くなっているのは否めない。
訳は変わり、たぶんそれによって、受け手の印象も変わってくる。
そう考えると、海外文学も深いよな、とつくづくと思う次第だ。
内容にも触れる。
久しぶりに読み返したけれど、何度も読み返しても、この作品には新しい発見がある。
今回読み返して気づいたこと。それはトーニオが結構めんどくさい子だということだ。
トーニオは、文学をやっている自分にいくばくかの劣等意識があり、己の不甲斐なさに悩み、内気で、どちらかと言うとどんくさい。
そう書くと、謙虚っぽく思うが、どうも領事の息子である自分の出自にプライドがあることも伝わってくる。
そんな彼は、ハンスやインゲといった、ネアカで要領がよく、文学をまともに読まない、社交性豊かな人物に惹かれている。
これは踏み込んだ意見だが、彼がハンスやインゲに惹かれるのは、自分にないものを持ち合わせているからかもしれない、と僕は思う。
劣等感を抱えた彼は、好きでもない自分と似ているもの(たとえばマグダレーナのような)を好きにはなれないのだろう。彼が好むのは、自分が嫌っている己からかけ離れたような存在なのだ。
もちろん人間である以上、好きな相手を自分のテリトリーに引き寄せたいという気持ちはある。ハンスに『ドン・カルロス』を薦めるのはいい例だ。
だが自分を嫌うトーニオは、ハンスたちに自分の好きな文学に興味をもってほしくないと、矛盾したことを考えたりもする。彼らが好きだからこそ、彼らに自分の色に染まってほしくないのだ。
「幸せは愛されることじゃない」「幸せとは愛されること」と考えるトーニオにとって、あるいはそれは矛盾ないのかもしれないけれど。
やっぱり、トーニオ、めんどくさい子だ。
でもそんな風に、ハンスたちの世界(俗界)を愛する態度は、トーニオを根無し草的存在に追いやることとなる。
トーニオは芸術の世界に属していて、その世界にいることにプライドもあるらしい。
けれど、普通を愛する彼の態度は、芸術家たちから軽く見られ、「迷子になった普通の子」と言われてしまう。
どちらの世界にもしっかりと足をつけ、属することのできないトーニオは、「必然的に道に迷ってしまう人間」なのだろう。
「必然的に道に迷」う彼は、当然それゆえに悩むことだってある。
どこにも属することのできない彼は、ある程度の成功を収めても、進むべき方向に迷いもなくはない。
だけど、そんな風に、どの世界にも属することのできず、「必然的に道に迷ってしまう」自分自身を、トーニオは最後の最後になって、受け入れていれようと決意することとなる。
たぶん時代的に考えて、作者は、芸術か、生活かという問いを、この作品の中にこめているのだろう。
けれど、そんな小難しいテーマを掲げてみても、最終的に行き着くのは、トーニオという小さな人間のアイデンティティの問題なのだ。それゆえに、この作品には確かな普遍的要素をもつのである。
そして自身のアイデンティティと、いまの自分自身を受け入れようと決意するラストの展開には、三十過ぎになったいま読み返しても、十代のときのように感動し、深く胸が震えてしまう。
人それぞれ意見もあろうが、『トーニオ・クレーガー』は本当にすばらしい作品だ、と僕は思う。
僕の中では、いままで読んできた本の中でも五指に入るほどの傑作だと思う。
ついでに書くと、併録の『マーリオと魔術師』もおもしろい。
類型的で、ラストが教訓っぽく感じられる点が引っかかるけれど、魔術師というメタファーの使い方が興味深く、魔術師の雰囲気に乗せられていく観客たちの様子のちょっと不気味なところが印象的。
いろいろ考えさせられながら、読むことができる一品である。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのトーマス・マン作品感想
『トニオ・クレエゲル』(岩波文庫)
『トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す』(新潮文庫)