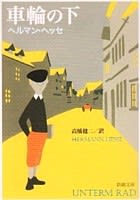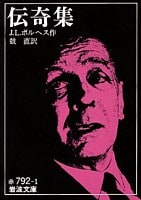鋭敏な頭脳をもつ貧しい大学生ラスコーリニコフは、一つの微細な罪悪は百の善行に償われるという理論のもとに、強欲非道な高利貸の老婆を殺害し、その財産を有効に転用しようと企てるが、偶然その場に来合せたその妹まで殺してしまう。この予期しなかった第二の殺人が、ラスコーリニコフの心に重くのしかかり、彼は罪の意識におびえるみじめな自分を発見しなければならなかった。
工藤精一郎 訳
出版社:新潮社(新潮文庫)
『罪と罰』はおもしろい作品である。
幾分まだるっこしいけれど、ポルフィーリイの追求の場面を始め、物語には緊迫感はあるし、そこで展開される思想性はおそろしく深い。
そしてエピローグで、ラスコーリニコフがソーニャのひざを抱きしめるシーンにはすなおに感動できる。
ドストエフスキーの代表作と呼ぶに足る一級の作品であった。
主人公のラスコーリニコフは、ひきこもり気味の学生である。
彼は人に対する飢えを持ちながらも、周囲の人間を見下す傾向にある人だ。
加えて、「虚栄心が強く、傲慢で、自尊心が強く、そして神を信じていない」男でもある。
そう書くと、一見冷血っぽく感じられるが、決して非道なやつではない。
子どものころ馬が虐待死されるのを見て心を痛めたこともあったし、マルメラードフの葬儀のときにはお金を恵んであげたりもした。ほかにも裁判の場面を読む限り、いくつかの慈善行為を行なっている。
そんな彼の慈善行為には、貧しさに対する怒りの意味合いもあるのかもしれない。
妹のドゥーニャがルージンという男と婚約したとき、愛する者のため、金のために、妹が身を投げ出したと勘付き、怒りに駆られている。
またマルメラードフの貧困生活を見たことも、その怒りに拍車をかけたのかもしれない。
彼にとって、生活とは、貧困であり、抜け出す対象であるようだ。
そしてその怒りもあり、ラスコーリニコフは金貸しの老婆という、貧困を生みだす象徴のような女を殺害するに至る。
彼がそのような犯罪に手を染めたのは、貧困に対する怒り以外としては、彼の普段からの持論も関係している。
彼は、人間は「《凡人》と《非凡人》に分けられる」と考えている人だ。
そして《非凡》な人間は、全人類の救いとなる思想の実行のためなら法律などを「ふみこえる権利がある」と考えている。
自尊心の強い彼は、自分を《非凡人》の側とみなしているらしい。
だから金貸しの老婆の殺害にも手を染めた。
だが彼は実際に殺害を行なったことで、病んでしまうこととなる。
幻覚だって見るし、破滅願望があるとしか思えない行動にも走っている。
それはどこからどう見ても、犯罪という事実に押しつぶされているとしか見えない。
つまり、彼は目的のためなら法を踏み越えても、平然としている《非凡》な人間の側ではなかったということだ。
そこでラスコーリニコフは苦悩するに至る。
だがここでおもしろいのは、その苦悩が「良心の呵責」によるものではない、ということだ。
そもそもラスコーリニコフは、目的のためなら「良心の声にしたがって血を許す」という考えを持っている人なのである。
良心の呵責など、彼は抱きようもない。
ではなぜ彼は、心を病むほどに苦悩しているのか。
それは、自分が《非凡》な人間ではない、「権力をもつ資格がない」という事実に「恥辱」を感じているからにほかならないのだ。
何たるプライド、と思うけれど、その事実に読んでいてぞくぞくしてしまった。
でもそんな恥辱を感じながらも、彼は生きていたい、と思うらしい。
それを彼は「卑劣」と感じているが、それが人間の真実だろう。
そんなラスコーリニコフを語る上で、特に対照関係にあるのは、スヴィドリガイロフとソーニャだと思う。
スヴィドリガイロフはラスコーリニコフに対し、「似た何かがある」と語っている。
それは世の中を斜に見ている点と、罪を犯しているという点にあると僕は感じる。
スヴィドリガイロフが見た幻覚から察するに、彼はむかし一人の少女を自殺に追いやっているらしい。
彼の慈善行為は、深層心理的には、その贖罪の意味もあるように感じなくはない。
それでも彼は自分の淫蕩という悪徳からは逃れられなかった。
たぶん彼は最後の幻覚に対する反応を見ても、良心の呵責を抱いていたように見える。
だが良心の呵責を抱いていても、淫蕩という悪徳からは逃れられず、ドゥーニャは得られず、彼に救いは訪れなかった。
では何が人に救いをもたらしうるのだろうか。
その答えこそ、ソーニャにあると思うのだ。
ソーニャは義母と血のつながらない弟妹のために、娼婦にまで身を落とした女だ。
それをラスコーリニコフは目的のために、自分の「生命を亡ぼした」とみなし、目的のため他人の命を奪った、自身の行動と重ね合わせている。
しかしソーニャはラスコーリニコフのように狂わず、罪に淫することもなかった。
その理由は信仰による面が大きいだろう。
ラザロの復活をめぐる両者の対応などはいい例だ。
あるいは信仰というよりも、何か大きなものの前にすなおにひざまずける気持ち、すなわち謙虚さと言い換えてもいいかもしれない。
それにソーニャは、頭でっかちに理性的なことばかり考えるのではなく、地に足のついた生活をしている点でもラスコーリニコフとは異なっていよう。
そんな彼女の在り方が、ラスコーリニコフに救いをもたらすこととなる。
しかしラスコーリニコフという人は恵まれた男だ。
ソーニャはもちろん、ラズミーヒンなんて熱い友人もいるし、母もドゥーニャもラスコーリニコフのことを愛し、心配をしてくれている。
刑事のポルフィーリイだって、ラスコーリニコフに自殺してもいいよ、と煽ってはいるが、罪の意識を持たせるためか「心理的に安定させ」ないよう逮捕しない。頭でっかちの彼を牽制し、「苦しみなさい」と諭している。
ルージンみたいなやつもいるけれど、いい人が多い。
そんなラスコーリニコフだが、周りの愛情に対し、「どうしてあの人たちはおれをこんなに愛してくれるんだろう、おれにはそんな価値はないのに」と感じている。
そう感じるラスコーリニコフの気持ちもわからなくはないが、そう感じることもまた、彼の頭でっかちっぷりを証明していると言える。
愛情は彼が思うような、理性的なものではないのだが、それにも気づかない。
彼はそういう意味、自分の思想に耽溺しているだけなのかもしれない。
そんな性格で、もともと傲岸なところもある人だからか、流刑地に行った後も、ラスコーリニコフは周囲との折り合いは悪かった。
しかしその土地で、生活を愛し生きている人に触れ続け、ありのままの人間の営みに触れていき、ソーニャの無心の愛に触れることで、彼の考えにゆらぎが生まれることとなる。
ラストのラスコーリニコフがソーニャのひざを抱きしめるシーンは感動的だ。
そこに至り、彼は、頭でっかちではない、まっとうな人間の生活を得たのだろう。
そしてそれをもたらしたのは、もちろん愛にほかならないのだ。
そしてそれが純粋に美しいゆえに、深く胸を打ってならない。
本書を初めて読んだのは大学生のとき。そのときも感動した記憶はあるが、再読した今回も心に響いた。以前読んだときよりも物語に深く入り込めた気もする。
『罪と罰』はそのように再読するたびに新しい発見を得られる。
『未成年』は未読だが、多分ドストエフスキーの五大長篇の中では一番とっつきやすいようにも思う。
ともあれ、傑作と呼ぶにふさわしい作品だ。
評価:★★★★★(満点は★★★★★)
そのほかのフョードル・ドストエフスキー作品感想
『悪霊』
『カラマーゾフの兄弟』
『虐げられた人びと』
『地下室の手記』
『白痴』