「ヴィバンガ(分別論)」は「分析の書物」の意味であり、十八の章がそれぞれ自己完結した論書となっている。ここで取り扱われているテーマは、集合体(蘊)、感覚基盤(処)、要素(界)、真理(諦)、縁による生起(縁行相)、気付きの基盤(念処)、正しい努力(正勤)、到達のための手段(神足)、悟りの因子(覚支)、八正道(道)、ジャーナ(禅定)、無限なもの(無量)、トレーニングのためのルール(学処)、分析的な知識(智)、知識の種類(小事)、マイナーな論点(数字による汚れ[=煩悩]の目録)、「理論の心臓」(dhammahadaya:法心)すなわち仏国土の心理宇宙的な地形学である。
分別論は、全てではないが、ほとんどの章が3つのサブセクションに別れている。すなわち、スッタの方法論にしたがった分析、アビダンマ自体の方法論にしたがった分析、およびその章の主題にマトリクスのカテゴリーを当てはめた質疑のセクションである。
「ダーツカター(界論)」は「要素に関する論説」という意味で、全部が教理問答の形式で書かれている。この論書は、全ての事象を集合体(蘊)、感覚基盤(処)、要素(界)に照らし合わせて、どれがどれに、どの程度まで含まれているか、含まれていないか、関連しているか分離しているかを論じている。
「プッガラバンニャッティ(人施設論)」は、「個人の概念」という意味で、アビダンマ・ピタカの一論書でありながら、アビダンマ自体というよりスッタの方法に近接している。これは、概念のタイプを大別するところから始まる。このことは、この論書の目的が、アビダンマの方法論を厳密に適用することで排除されてしまった概念世界を考慮に入れることであり、その意味で他の論書を補完するという意図のもとに作成されたことがうかがえる。この著作のほとんどは、様々なタイプの個人に形式的な定義を与えている。十の章から成り、最初は個人を一つのタイプで論じ、次に二つのタイプ、三つのタイプといったように論じ分けている。











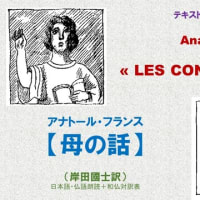
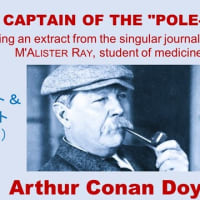
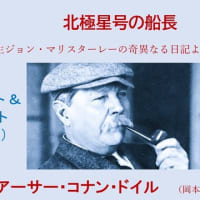
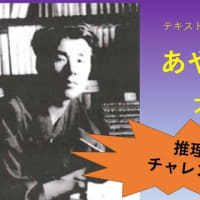
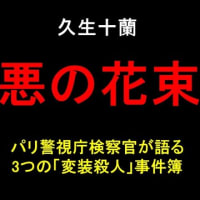
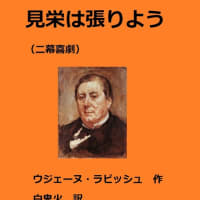
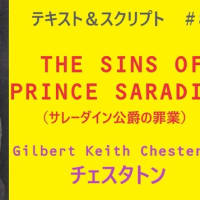
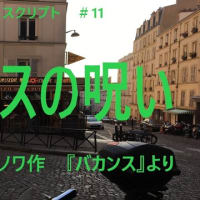





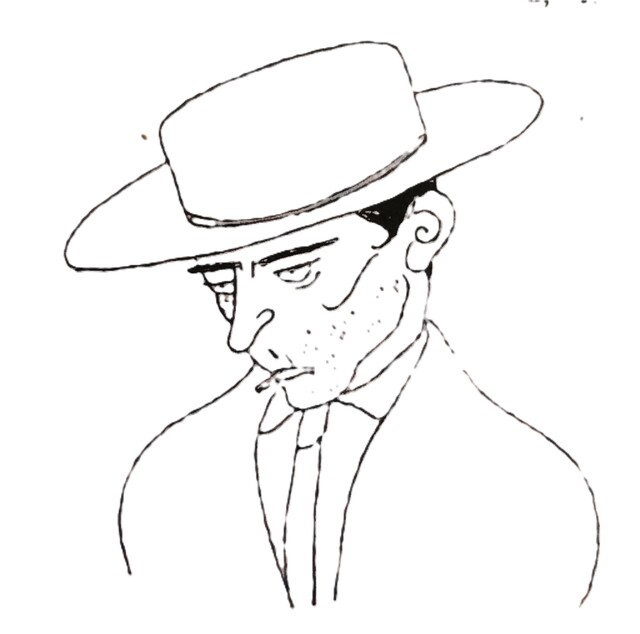

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます