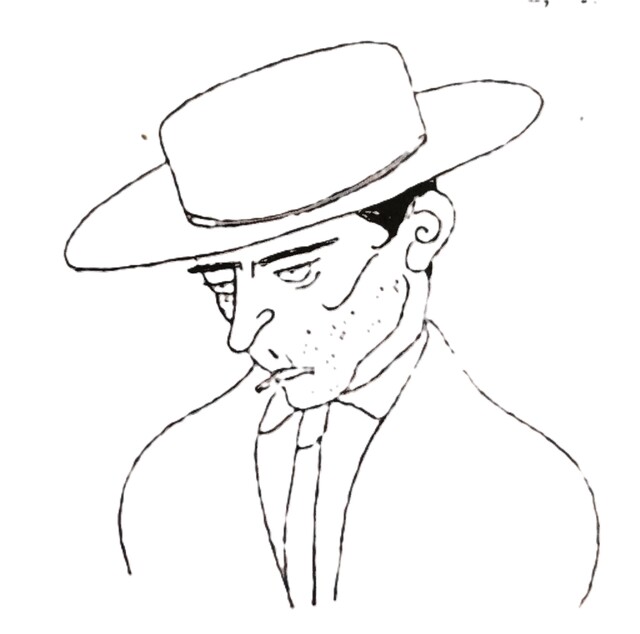おじさんは無言で歩き始めた。しばらくして、低い声で、独り言のように「馬鹿だったなあ」とつぶやいた。
「お嬢ちゃんは、組合運動って知っているかい?」
「クミアイ?」
「ああ、会社でね、弱い立場の人を助けるために、いろんなことをやるのさ」
「ふうん」
その時、久子は、おじさんの後ろではなく、横を歩いていた。
「おじさんはね、その組合運動をしている時に、会社の偉い人を殴ってしまったんだ」
「……」
「その人はね、その時の傷が原因で死んでしまった……「ひどいことをしてしまった、家族持ちの人だったのに……おじさんだって、最初から殴るつもりはなかったんだ。でも、結局は、人を傷つけて死なせてしまった……馬鹿だったんだね、未熟だった」
おじさんは、再び口をつぐんだ。
二人は、しばらく、沈黙のまま歩き続けた。
「そのバチが当たったんだ」
「バチが?」
「ああ。病気に罹ってしまったんだ。だんだん重くなってきて、もうどうしようもない」
「治らないの?」
「うん……」
おじさんは、立ち止まって、また汗をふいた。
「長い坂だなあ。でも、おじさんは嫌いじゃないんだ、こういう坂を上るのは。少しずつ頂上に近づいているんだからね、歩いているかぎり……」
おじさんは、坂の上を見ながら言った。「おじさんにも夢があった。家族一緒に暮らして、小さいけどゆっくりできる家を持って、遊んだり仕事をしたり……でも、もう駄目だな。おしまいだ」
少し歩くと、雑木林が切れて、空が一気に広くなった。片隅には雲が大きく立ち上がり、ちぎれ雲がときおり太陽を遮った。そのたびに、目の前の道路、土手、畑、遠くの竹林や点在する家々が明るく輝いたり、暗く沈んだりした。
それは、何か深い人生の秘密を暗示しているように見えた。
「きれいだねえ」おじさんは声を上げた。「実にきれいだ、なんてこともない風景だけど」
「お嬢ちゃんは、組合運動って知っているかい?」
「クミアイ?」
「ああ、会社でね、弱い立場の人を助けるために、いろんなことをやるのさ」
「ふうん」
その時、久子は、おじさんの後ろではなく、横を歩いていた。
「おじさんはね、その組合運動をしている時に、会社の偉い人を殴ってしまったんだ」
「……」
「その人はね、その時の傷が原因で死んでしまった……「ひどいことをしてしまった、家族持ちの人だったのに……おじさんだって、最初から殴るつもりはなかったんだ。でも、結局は、人を傷つけて死なせてしまった……馬鹿だったんだね、未熟だった」
おじさんは、再び口をつぐんだ。
二人は、しばらく、沈黙のまま歩き続けた。
「そのバチが当たったんだ」
「バチが?」
「ああ。病気に罹ってしまったんだ。だんだん重くなってきて、もうどうしようもない」
「治らないの?」
「うん……」
おじさんは、立ち止まって、また汗をふいた。
「長い坂だなあ。でも、おじさんは嫌いじゃないんだ、こういう坂を上るのは。少しずつ頂上に近づいているんだからね、歩いているかぎり……」
おじさんは、坂の上を見ながら言った。「おじさんにも夢があった。家族一緒に暮らして、小さいけどゆっくりできる家を持って、遊んだり仕事をしたり……でも、もう駄目だな。おしまいだ」
少し歩くと、雑木林が切れて、空が一気に広くなった。片隅には雲が大きく立ち上がり、ちぎれ雲がときおり太陽を遮った。そのたびに、目の前の道路、土手、畑、遠くの竹林や点在する家々が明るく輝いたり、暗く沈んだりした。
それは、何か深い人生の秘密を暗示しているように見えた。
「きれいだねえ」おじさんは声を上げた。「実にきれいだ、なんてこともない風景だけど」