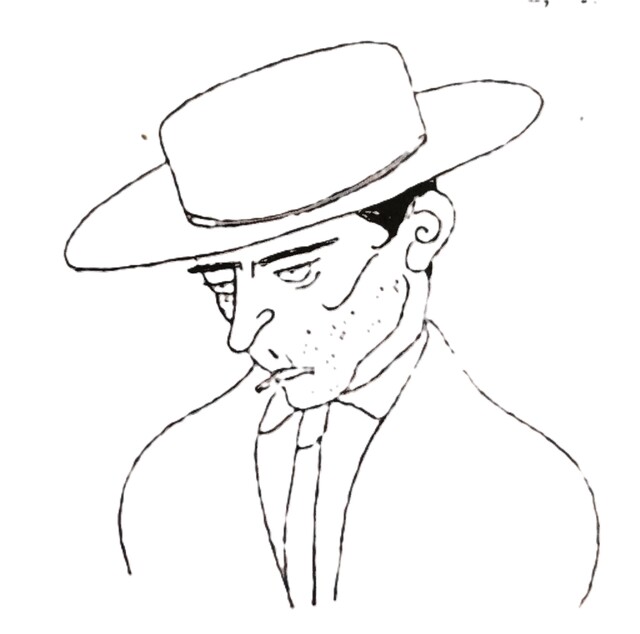施設から自宅マンションに戻った。リビングの壁に吊されているクラシック調の時計が十時を指していた。十二時までに、滝田氏にファイルを送らなければならないのだが、それは十分に間に合う。もう修正はしないのだから。
理恵はコーヒーを入れ、カップに注ぎ、パソコンの前に座ってスイッチを入れる。カーソルをファイルに置いてダブルクリック。開いたファイルを読んでいく。
思った通りだ。必要十分な英文がそこにある。
先日、あまりに凡庸でまったく使い物にならないと判断しうろたえたのと同じ文章だ。
しかし、現在の理恵は、その時とはまったく異なる評価をしている。
序論は、平易な単語と短いセンテンスで読みやすくし、専門用語を定義し、次第に複雑な論理展開に入っていく。しかし、そこでも読者が迷ったり飽き足りしないように、脚注を使って本文のパラグラフをうまく調節する。図表は地の文としっかり対比できるように配置されている。キャプションにも間違いはない。章分けも完璧だ。自然な流れの中で最後の結語と謝辞に到達する。
どこからどう見ても、プロが書いた英文である。堂々と発注者に渡せるだけの内容だ。
読み終わり、滝田に簡単なコメントを付して、添付メールで文書を送信した。
パソコンのスイッチを切り、立ち上がって窓を開ける。初夏の風が部屋の中で舞い上がる。
ああ、無事に『理恵』は卒業だ、これでやっと『理花』になれる……そう思った。
(了)
理恵はコーヒーを入れ、カップに注ぎ、パソコンの前に座ってスイッチを入れる。カーソルをファイルに置いてダブルクリック。開いたファイルを読んでいく。
思った通りだ。必要十分な英文がそこにある。
先日、あまりに凡庸でまったく使い物にならないと判断しうろたえたのと同じ文章だ。
しかし、現在の理恵は、その時とはまったく異なる評価をしている。
序論は、平易な単語と短いセンテンスで読みやすくし、専門用語を定義し、次第に複雑な論理展開に入っていく。しかし、そこでも読者が迷ったり飽き足りしないように、脚注を使って本文のパラグラフをうまく調節する。図表は地の文としっかり対比できるように配置されている。キャプションにも間違いはない。章分けも完璧だ。自然な流れの中で最後の結語と謝辞に到達する。
どこからどう見ても、プロが書いた英文である。堂々と発注者に渡せるだけの内容だ。
読み終わり、滝田に簡単なコメントを付して、添付メールで文書を送信した。
パソコンのスイッチを切り、立ち上がって窓を開ける。初夏の風が部屋の中で舞い上がる。
ああ、無事に『理恵』は卒業だ、これでやっと『理花』になれる……そう思った。
(了)