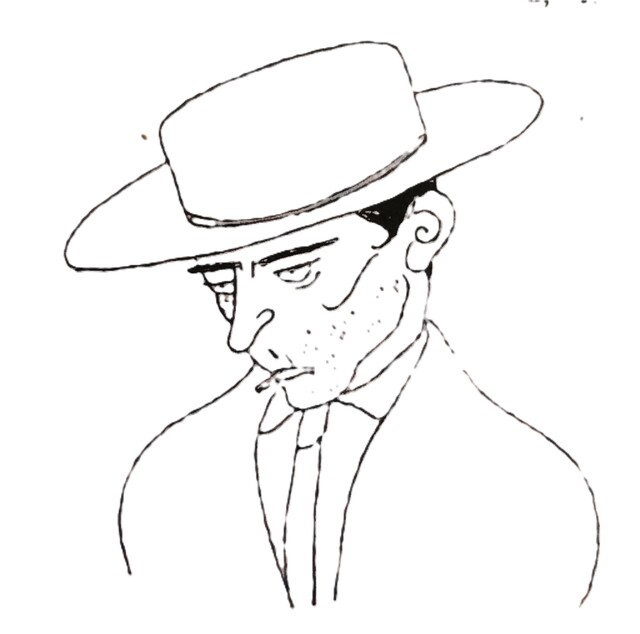「信仰と科学は、世界という同じように与えられた1つのことから出発しているのに、どうして全く対立する概念を持つに至ったのであろうか?」
存在する全てのものは、一方で「在る何か」であり、もう一方では「起きる何か」、すなわち、プロセスとして永遠に変化し続ける状態にある何かである。
何かが起きれば、そこには適切な原因がなければならない。これらの適切な原因が力を持つ。
全てのプロセス、すなわち世界イベントの振る舞い全体は、2つの大分類に入る。すなわち、活性化されないまま続いていくプロセスと、自ら自分を維持していく活性化されたプロセスである。後者は、たとえば炎などの燃焼プロセスや生物の栄養摂取プロセスである。
全ての非活性プロセスは、落下として解釈または読解できる。このタイプの例としては、落下する石がある。石は、落下を引き起こす内在的力を持って落下するのではない。それが落下するのは、最初にそれが持ち上げられ、石と地表との間にはテンションに差があるからである。したがって、この落下は、あらかじめ力が働いているという意味において、「前もって」力が存在していたのである。そうでなければ、石の位置と地表との間で差が生じることは決してなかったであろう。物理学は、石の落下を異なったやり方で解釈する。すなわち、落下運動の間、地球からの引力が働いているとする。これは、統一的な物理的世界理論のために提示された、純粋な作業仮説である。
機械的、化学的、熱的、電気的、磁気的またはその以外の同様の現象についても、例外なく、あらゆる物理的な出来事が落下する石とほとんど同じように解釈され理解される。高い場所からテンションの低い場所への落下と同じように、全てが受け取られる。どれもこれも、何らかの作用を働かせる力が前に存在していたという意味しか持っていない。それぞれのケースにおいて、我々は行為に関与せず、反応だけに関与しているというのが本当のところである。
いまここで現実に力が作用していないことの証拠は、テンションの差が調和されたとたんにプロセスが停止するという事実から理解できる。
このような反応の世界というのは、全ての科学の本来的領域である。
科学は、論証を与えることに熱心なので、感覚器官で感じ取れないものは存在しないという場合にのみ、その存在理由がある。現実に生命プロセスがあれば、そこには実際に力が存在していなければならない。しかし、力は、絶対に感覚器官では感受できない。感知可能なあらゆるものは、その適切な原因について、すなわち、それを存在させている力について必然的に疑問を抱く。不活性の再・現実プロセスでは、それ自体には力が作用しているわけではなく、したがって、力はリアルなものではなく、概念的な要請、単なる論理的前提でしかない。したがって、この再・現実世界の解釈においても、実際の力に関する疑問をあっさりと排除し、これを潜在性、テンションの差に置き換えてしまい、感知可能な領域の中にとどまるようにすることが常に可能となる。
テクニックに全面的に力を注いでいる科学、すなわち、前もって測定し計算すること以上のものは何も狙っていない科学にとって、このような立場は完全に許容可能なものである。なぜなら、前もって計算や測定が出来るのは、再・現実の手続きでしかありえないからである。これこれの星が天におけるこれこれの位置に来るだろうという場合、前もってきわめて正確にそれを計算することができる。しかし、来月私が親指を右か左かのどちらに回すかについては、それを前もって計算できるような科学やアカデミーは世界に存在しない。
科学が世界に対してとっている立場とは、感覚器官に感知できない全てのものを原則として拒絶し、必然的に再・現実世界だけに限定し、その中で世界イベントの振る舞いを機械的概念にするというものだ。