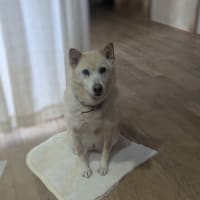※非常勤講師を勤めております前橋国際大学での授業内容を、問題のない部分のみ、ブログ上にアップすることに致しました(資料は大学のLMS上にアップしていますが、引用文など少し長めの文章を載せたものは、スマホの画面ではかなり読みにくいため。ブログ記事であればスマホ上でも何とか読めるだろうと思うので)。
すみません、今回も遅くなりました。
第7回をアップします。
はじめに
『御伽草子』については、バーバラ・ルーシュが
「中世小説においては、植物や獣、魚や昆虫にいたるまで、人間と自然との間に非常に親しい関係」「人間と人間以外の生き物がその種類を問わず共存し、お互い深く関わっていく」(「熊楠と御伽草子、そしてジェンダー」『国文学』1994年1月号)
と述べるように、人間と自然との親しい関係や、人間と人間以外の生物の共存が描かれることが指摘され、特に、菊の精と人間の姫君との恋物語である『かざしの姫君』については、「一人の女性の奥底に潜む寂しさをすばらしく描いたものであると同時に、その一方で植物もまた感情を持ち、我々と心を交い合える」(同)とも言われます。
『かざしの姫君』(梗概)
中納言の姫君は、植物、特に菊を愛する。姫君のもとに、「少将」と名乗る、二十余りくらいの美しい若者が現れ、関係を持つ。
ある日帝の「花揃え」があり、中納言は菊を差し出すよう御下命がある。
その夜姫君のもとを訪れた「少将」は別れの言葉を残し、鬢のあたりの毛を一ふさ紙に包んで姫君に渡すと、庭の籬の菊のあたりに消える。
翌朝中納言は菊を差し出し、褒められる。
姫君は、その夜も少将の訪れを待つが現れない。姫君が渡された鬢の毛を開くと、それは菊の花となっており、紙には歌が書かれていた。「少将」は実は菊の精であったことが分かる。
その後姫君は妊娠、美しい姫君を産むが、死んでしまう。生まれた姫君は美しく成長し、女御として入内し、皇子・皇女を産む。
さらに、メリッサ・マコーミックによって、
「表面上は、人が異界の者、あるいは人ならざる者に出会う物語(異類物)の単純な形態であるが、『菊の精物語』は、生殖と再生を通して、皇族のもつ超自然的な権威」(永井久美子訳「『菊の精物語』における花の擬人化と皇統の再生」国文学研究資料館編『アメリカに渡った物語絵―絵巻・屏風・絵本』ぺりかん社、2013年)
とも指摘されるように、菊が中世頃には天皇家の象徴となっていたことや、菊の精と人間の姫君との間の娘が、後に入内し皇子・皇女を産むことから、皇統の物語としても考察されます。
花である菊の精が、男性としてあらわれることからジェンダー論的な観点からも考察されます。菊の精が男性であることには、菊慈童(「中国の仙童。容姿が美しく、周の穆王(ぼくおう)に愛されたが、16歳の時、罪のため南陽郡県(れきけん)に流される。しかし菊を愛し、菊の露を飲んで不老不死になったという」『日本国語大辞典』)のイメージもあると思いますが、花のイメージとしては確かに重要でしょう。
絵などから「性教育の役割」(同)があったとも言われるのですが、これについては、
「少女は、園芸を通して新たな生命を育み、愛護することを学ぶことが可能だと考えられていた」(渡部周子「実践教育としての「園芸」:ケア役割の予行」『〈少女〉像の誕生:近代日本における「少女」規範の形成 』2007年、新泉社)
などと指摘される、近代における少女と花との結びつきも想起させます。
大枠としては「生殖と再生、皇族のもつ権威」という観点に首肯できるのですが、細かく見てゆくと、皇室に対する姫君の反抗心などを見て取ることもでき、それが最終的に皇室の権威の物語へと回収されてゆく構造として位置づけることができます。
そこで今回は、『かざしの姫君』について、菊の精が男性であることや、生殖の観点から見ていくことにしましょう。
『かざしの姫君』考察
中納言の姫君は、
春は花の下にて日を暮らし、秋は月の前にて夜を明かし、常には詩歌を詠じ、色\/の草花をもてあそび給ふ。中にも菊をばなべてならず愛し給ひて、(293頁)
【口語訳】(姫君は)春は桜の下で一日を過ごし、秋は月の前で夜を明かし、常に詩歌を詠み、色々な草花を賞玩しなさる。中にも菊の花を並々ならず愛されて、
とあるように、風流を愛する姫君でしたが、特に草花、その中でも菊を愛していました。そんな姫君のもとに、
年のほど二十余りなる男の、冠姿ほのかに、薄紫の狩衣に、鉄漿黒に薄化粧、太眉つくりて、いと花やかなるにほひの、やんごとなき風情(294頁)
【口語訳】齢の頃合いは二十歳余りくらいの男で、冠をかぶった姿がぼんやりとして、薄紫の狩衣に、鉄漿黒(鉄漿で歯を黒く染めた)に薄化粧、太い眉を眉墨でかいて、とてもはなやかな様子の、すぐれた有様
の貴公子が現れ、関係を持つことになります。
ここで菊の精は男性の姿をとっています。
菊の精は、人間と植物という観点からいえば他者ですが、庭の籬の菊であるという点からいえば、姫君にとっては身近なものであったといえます。したがって、「他者との交流」という面と同時に、生身の男性よりも庭の植物を愛するような、自分の手の届く庭の中に自閉してゆく姫の魂も見て取れるでしょう。
さてその頃、帝の花揃えが企画され、中納言も庭の菊を献上するよう言われます。
その頃、帝には、花揃へありとて、人\/を召さりければ、中納言殿も参り給ふ。帝、中納言をちかづけ給ひ、「世の常ならぬ菊の花揃へ奉れ」と綸言あらせ給へば、力なくして、中納言菊を奉らんとて、帰られけり。(297~298頁)
【口語訳】その頃、帝の御前で花揃え(花を集めて並べること)があるといって、人々をお呼びになったので、中納言殿も参上なさった。帝は中納言をちかづけなさって、「世の常ではないほどすばらしい菊の花をそろえて献上なさい」とお言葉がおありになったので、(拒絶する)力なくして、中納言は菊を献上しようとして、お帰りになった。
ここで少し注意しておきたいのが、帝のお前に献上される菊が、実は男性であることです。後宮に帝の妻として集められるのは女性ですから、ここでは性別が転倒していることになります。
その夜、姫君のもとを訪れた「少将」は、常よりもしおれた有様をしていました。
鬢の髪を切りて、下絵したる薄様におし包みて、「もしおぼしめし出でん時は、これをご覧ざせ給へ」とて、姫君に参らせて、また「胎内にもみどり子残し置けば、いかにもくよきに育ておきて、忘れ形見ともおぼしめせ」とて、泣く\/出で給へば、姫君も御簾のほとりまで忍び出でて見やり給へば、庭の籬のあたりへたゝずみ給ふかと思ひて、見え給はず。 (300頁)
【口語訳】鬢の髪を切って、下絵のある薄様(薄い鳥の子紙)におし包んで、「もし(私を)思い出しなさるときは、これをご覧になってください」と言って、姫君にお渡しして、また「(あなたの)胎内にも赤子を残し置いたので、どうにかどうにか良いように育てて、忘れ形見ともお思いになって下さい」と言って、泣く泣くお出になるので、姫君も御簾の側まで忍び出て見送りなさったところ、庭の籬のあたりに佇みなさったかと思うと、見えなさらなくなる。
ここで菊の精である少将は、「胎内にもみどり子残し置けば」と言っているように、生殖するわけですが、まるで意図的に妊娠させられるみたいで面白いセリフですね。
さてその翌日、菊は切られ、帝に献上されました。帝は大変喜び、この上なく賞美しました。
かくてその夜も明けぬれば、中納言は菊を君へぞ奉らせ給ひけり。君叡覧限りなし。(300頁)
【口語訳】こうしてその夜も明けてしまったので、中納言は菊を帝へ献上なさった。帝はご覧になって賞美なされることがこの上なかった。
姫君は夜になっても少将が訪れないため、嘆き悲しんで形見の品を開きます。そうすると鬢の毛であったと思ったものは菊の花になっており、紙には歌が書かれていました。
にほひをば君が袂に残し置きてあだにうつろふ菊の花かな
とありて、その黒髪と思ひしは、しぼめる菊の花なれば、いよ\/不思議におぼしめし、さては詠み置く言の葉までも、菊の精かとおぼえて、(絵)
その白菊の花園に立ち出で給ひて、のたまふやうは、(中略)。「御花揃へなかりせば、かゝるうきめはあらじ物を。とてもかくても長らへはつべき我が身ならねば」と、思ふもなか\/心苦し。(301頁)
【口語訳】香りをあなたの袂に残し置いて、空しく色あせる菊の花であることだなあ
とあって、その黒髪と思っていたものは、しぼんだ菊の花であったので、ますます不思議にお思いになり、それでは詠み置いた言の葉である歌までも、菊の精であるかのように思われて、その白菊の花園に立ち出でなさって、おっしゃることには、(中略)。「(帝の御前での)花揃えがなかったならば、このようなつらいことはなかったものを。なんにしても、(このまま)長らえ果てるべき私の身ではないから(早く死んでしまいたい)」と、思うのもかえって心が苦しい。
「少将」が菊の花の精であったことに気づいた姫君は、「帝の花揃えさえなかったら!」と悔しがります。ここには、花揃えをきっかけとした、帝への反抗心のようなものが見て取れるでしょう。
しかも姫君は菊の精によって妊娠し、そのために両親は彼女を入内させることをあきらめざるを得ません。
(父親の中納言殿)「たぐひなく浅ましきかな、内参りのことをこそ明け暮れ思ひしに、さてのみやまん本意なさよ」(305頁)
【口語訳】「この上なく驚きあきれることであるよ、入内させることを明け暮れ願っていたのに、このようにしてやめることの残念さよ」
結果的にではありますが、菊の花の精は、自らは帝に献上されましたが、姫君を妊娠させることで、姫君の入内を阻止したことになります。
月日が重なり、姫君は美しい姫君を出産します。
さるほどにやう\/月日も重なりて、姫君いよ\/御心弱く、頼み少なき御有様に見え給ふ。乳母を始めて女房たちあまた介錯申しければ、まことにいつくしく姫君いでき給ふ。中納言殿も北の御方も、かしづき給ふこと限りなし。されどもかざしの姫君は、今を限りと見えさせ給ふ。(305~306頁)
【口語訳】そうするうちに、だんだん月日が重なって、姫君はますます御心弱く、頼りないご様子にお見えになる。乳母を始め、女房たちがたくさんお世話し申し上げたので、本当に美しい姫君がお生まれになる。中納言殿も、北の方も、大切になさることはこの上ない。けれどもかざしの姫君は、今が最期(臨終)の様子でいらっしゃる。
ですが姫君自身は衰弱しきり、娘の姫君のことを頼む言葉を残しながら、「朝の露と消え」てしまいます(306頁)。
ここでは、常套表現ではありますが、姫君の命が「露」にたとえられています。姫君はまさに「露」のような存在であり、菊と露の取り合わせとして、この二人の恋が描かれているのです。
さて、娘の姫君は成長するにしたがって、かざしの姫君に似ていきます。
御齢の行くに従ひて、かざしの姫君に相似させ給へば、御いとほしみ給ひて、若き女房たちあまたつけ、かしづき給ふほどに、月日重なりて、七歳にて御袴着せ参らせ給ひけり。(307頁)
【口語訳】成長するにしたがって、かざしの姫君に瓜二つにおなりになるので、(両親は)可愛がりなさって、若い女房たちをたくさんつけ、大切になさる間に、月日は経って、七歳で御袴着(幼児から少年・少女になることを祝う儀式)をなさった。
どんどん美しくなる姫君のうわさを帝も聞きつけ、女御として入内させるようにという、勅が下ります。
さる程に、君きこしめされて、「女御に参らせよ」との勅によりて、女御にぞ定まり給ひける。(308頁)
【口語訳】そうしているうちに、帝は(姫君のうわさを)お聞きになって、「女御として参内させなさい」との勅命によって、女御に定まりなさった。
入内した姫君への寵愛は深く、皇子と皇女が生まれました。
さても帝は寵愛甚だしくこそ聞えけれ。いよく浅からず御心にもかなひ給へば、程なく若宮、姫宮打ち続きいでき給ひて、まことにめでたきことにぞ、人\/申しあへり。(308頁)
【口語訳】それにしても、帝の(姫君への)寵愛は甚だしくていらっしゃった。ますます深く、御心にもかなっていらっしゃったので、間もなく皇子・皇女が引き続いてお生まれになり、実にめでたいことであると、人々は申し上げあった。
菊の精とかざしの姫君との娘が、皇子・皇女を産んだという結末は、かざしの姫君の反抗心も垣間見えたこの物語が、最終的には王権に回収されたものと考えることができます。
まとめ
『かざしの姫君』では、菊の花の精が男性として描かれますが、『秋の夜長物語』と異なり、菊の花の精は生殖します。帝の花揃えに男性として描かれる菊の花が献上されることは、帝のもとに入内する女性たちと、性別が転倒しています。
一方で、ヒロインである姫君は、出産後はかなくなくなったことが、常套表現ではありますが、「露と消える」と表現されます。これは、姫君が菊にかかる露を象徴する存在であることを示すものでしょう。「菊の花の精」は、人間ではないという意味においては他者ですが、庭の籬の菊という意味では、身近な、自分の世界のなかにある存在でもあります。姫君は人間の男性と交わるよりも、自分の庭の植物を愛するような、自閉する魂を持っていたのです。また、菊の花の精の子を身ごもったことで、入内せず、菊の花の精が帝の花揃えのために死んでしまうと、「花揃えさえなければ!」と思う姫君は、帝や王権に対して反抗するかのようにも見えます。
しかしながらそのような反抗心は、菊の花の精と姫君の娘が入内し、皇子・皇女を産むことで、最終的には王権の物語へと回収されるのです。
*引用は、岩波新日本古典文学大系『室町物語集 上』による。
→第6回
→第8回
すみません、今回も遅くなりました。
第7回をアップします。
はじめに
『御伽草子』については、バーバラ・ルーシュが
「中世小説においては、植物や獣、魚や昆虫にいたるまで、人間と自然との間に非常に親しい関係」「人間と人間以外の生き物がその種類を問わず共存し、お互い深く関わっていく」(「熊楠と御伽草子、そしてジェンダー」『国文学』1994年1月号)
と述べるように、人間と自然との親しい関係や、人間と人間以外の生物の共存が描かれることが指摘され、特に、菊の精と人間の姫君との恋物語である『かざしの姫君』については、「一人の女性の奥底に潜む寂しさをすばらしく描いたものであると同時に、その一方で植物もまた感情を持ち、我々と心を交い合える」(同)とも言われます。
『かざしの姫君』(梗概)
中納言の姫君は、植物、特に菊を愛する。姫君のもとに、「少将」と名乗る、二十余りくらいの美しい若者が現れ、関係を持つ。
ある日帝の「花揃え」があり、中納言は菊を差し出すよう御下命がある。
その夜姫君のもとを訪れた「少将」は別れの言葉を残し、鬢のあたりの毛を一ふさ紙に包んで姫君に渡すと、庭の籬の菊のあたりに消える。
翌朝中納言は菊を差し出し、褒められる。
姫君は、その夜も少将の訪れを待つが現れない。姫君が渡された鬢の毛を開くと、それは菊の花となっており、紙には歌が書かれていた。「少将」は実は菊の精であったことが分かる。
その後姫君は妊娠、美しい姫君を産むが、死んでしまう。生まれた姫君は美しく成長し、女御として入内し、皇子・皇女を産む。
さらに、メリッサ・マコーミックによって、
「表面上は、人が異界の者、あるいは人ならざる者に出会う物語(異類物)の単純な形態であるが、『菊の精物語』は、生殖と再生を通して、皇族のもつ超自然的な権威」(永井久美子訳「『菊の精物語』における花の擬人化と皇統の再生」国文学研究資料館編『アメリカに渡った物語絵―絵巻・屏風・絵本』ぺりかん社、2013年)
とも指摘されるように、菊が中世頃には天皇家の象徴となっていたことや、菊の精と人間の姫君との間の娘が、後に入内し皇子・皇女を産むことから、皇統の物語としても考察されます。
花である菊の精が、男性としてあらわれることからジェンダー論的な観点からも考察されます。菊の精が男性であることには、菊慈童(「中国の仙童。容姿が美しく、周の穆王(ぼくおう)に愛されたが、16歳の時、罪のため南陽郡県(れきけん)に流される。しかし菊を愛し、菊の露を飲んで不老不死になったという」『日本国語大辞典』)のイメージもあると思いますが、花のイメージとしては確かに重要でしょう。
絵などから「性教育の役割」(同)があったとも言われるのですが、これについては、
「少女は、園芸を通して新たな生命を育み、愛護することを学ぶことが可能だと考えられていた」(渡部周子「実践教育としての「園芸」:ケア役割の予行」『〈少女〉像の誕生:近代日本における「少女」規範の形成 』2007年、新泉社)
などと指摘される、近代における少女と花との結びつきも想起させます。
大枠としては「生殖と再生、皇族のもつ権威」という観点に首肯できるのですが、細かく見てゆくと、皇室に対する姫君の反抗心などを見て取ることもでき、それが最終的に皇室の権威の物語へと回収されてゆく構造として位置づけることができます。
そこで今回は、『かざしの姫君』について、菊の精が男性であることや、生殖の観点から見ていくことにしましょう。
『かざしの姫君』考察
中納言の姫君は、
春は花の下にて日を暮らし、秋は月の前にて夜を明かし、常には詩歌を詠じ、色\/の草花をもてあそび給ふ。中にも菊をばなべてならず愛し給ひて、(293頁)
【口語訳】(姫君は)春は桜の下で一日を過ごし、秋は月の前で夜を明かし、常に詩歌を詠み、色々な草花を賞玩しなさる。中にも菊の花を並々ならず愛されて、
とあるように、風流を愛する姫君でしたが、特に草花、その中でも菊を愛していました。そんな姫君のもとに、
年のほど二十余りなる男の、冠姿ほのかに、薄紫の狩衣に、鉄漿黒に薄化粧、太眉つくりて、いと花やかなるにほひの、やんごとなき風情(294頁)
【口語訳】齢の頃合いは二十歳余りくらいの男で、冠をかぶった姿がぼんやりとして、薄紫の狩衣に、鉄漿黒(鉄漿で歯を黒く染めた)に薄化粧、太い眉を眉墨でかいて、とてもはなやかな様子の、すぐれた有様
の貴公子が現れ、関係を持つことになります。
ここで菊の精は男性の姿をとっています。
菊の精は、人間と植物という観点からいえば他者ですが、庭の籬の菊であるという点からいえば、姫君にとっては身近なものであったといえます。したがって、「他者との交流」という面と同時に、生身の男性よりも庭の植物を愛するような、自分の手の届く庭の中に自閉してゆく姫の魂も見て取れるでしょう。
さてその頃、帝の花揃えが企画され、中納言も庭の菊を献上するよう言われます。
その頃、帝には、花揃へありとて、人\/を召さりければ、中納言殿も参り給ふ。帝、中納言をちかづけ給ひ、「世の常ならぬ菊の花揃へ奉れ」と綸言あらせ給へば、力なくして、中納言菊を奉らんとて、帰られけり。(297~298頁)
【口語訳】その頃、帝の御前で花揃え(花を集めて並べること)があるといって、人々をお呼びになったので、中納言殿も参上なさった。帝は中納言をちかづけなさって、「世の常ではないほどすばらしい菊の花をそろえて献上なさい」とお言葉がおありになったので、(拒絶する)力なくして、中納言は菊を献上しようとして、お帰りになった。
ここで少し注意しておきたいのが、帝のお前に献上される菊が、実は男性であることです。後宮に帝の妻として集められるのは女性ですから、ここでは性別が転倒していることになります。
その夜、姫君のもとを訪れた「少将」は、常よりもしおれた有様をしていました。
鬢の髪を切りて、下絵したる薄様におし包みて、「もしおぼしめし出でん時は、これをご覧ざせ給へ」とて、姫君に参らせて、また「胎内にもみどり子残し置けば、いかにもくよきに育ておきて、忘れ形見ともおぼしめせ」とて、泣く\/出で給へば、姫君も御簾のほとりまで忍び出でて見やり給へば、庭の籬のあたりへたゝずみ給ふかと思ひて、見え給はず。 (300頁)
【口語訳】鬢の髪を切って、下絵のある薄様(薄い鳥の子紙)におし包んで、「もし(私を)思い出しなさるときは、これをご覧になってください」と言って、姫君にお渡しして、また「(あなたの)胎内にも赤子を残し置いたので、どうにかどうにか良いように育てて、忘れ形見ともお思いになって下さい」と言って、泣く泣くお出になるので、姫君も御簾の側まで忍び出て見送りなさったところ、庭の籬のあたりに佇みなさったかと思うと、見えなさらなくなる。
ここで菊の精である少将は、「胎内にもみどり子残し置けば」と言っているように、生殖するわけですが、まるで意図的に妊娠させられるみたいで面白いセリフですね。
さてその翌日、菊は切られ、帝に献上されました。帝は大変喜び、この上なく賞美しました。
かくてその夜も明けぬれば、中納言は菊を君へぞ奉らせ給ひけり。君叡覧限りなし。(300頁)
【口語訳】こうしてその夜も明けてしまったので、中納言は菊を帝へ献上なさった。帝はご覧になって賞美なされることがこの上なかった。
姫君は夜になっても少将が訪れないため、嘆き悲しんで形見の品を開きます。そうすると鬢の毛であったと思ったものは菊の花になっており、紙には歌が書かれていました。
にほひをば君が袂に残し置きてあだにうつろふ菊の花かな
とありて、その黒髪と思ひしは、しぼめる菊の花なれば、いよ\/不思議におぼしめし、さては詠み置く言の葉までも、菊の精かとおぼえて、(絵)
その白菊の花園に立ち出で給ひて、のたまふやうは、(中略)。「御花揃へなかりせば、かゝるうきめはあらじ物を。とてもかくても長らへはつべき我が身ならねば」と、思ふもなか\/心苦し。(301頁)
【口語訳】香りをあなたの袂に残し置いて、空しく色あせる菊の花であることだなあ
とあって、その黒髪と思っていたものは、しぼんだ菊の花であったので、ますます不思議にお思いになり、それでは詠み置いた言の葉である歌までも、菊の精であるかのように思われて、その白菊の花園に立ち出でなさって、おっしゃることには、(中略)。「(帝の御前での)花揃えがなかったならば、このようなつらいことはなかったものを。なんにしても、(このまま)長らえ果てるべき私の身ではないから(早く死んでしまいたい)」と、思うのもかえって心が苦しい。
「少将」が菊の花の精であったことに気づいた姫君は、「帝の花揃えさえなかったら!」と悔しがります。ここには、花揃えをきっかけとした、帝への反抗心のようなものが見て取れるでしょう。
しかも姫君は菊の精によって妊娠し、そのために両親は彼女を入内させることをあきらめざるを得ません。
(父親の中納言殿)「たぐひなく浅ましきかな、内参りのことをこそ明け暮れ思ひしに、さてのみやまん本意なさよ」(305頁)
【口語訳】「この上なく驚きあきれることであるよ、入内させることを明け暮れ願っていたのに、このようにしてやめることの残念さよ」
結果的にではありますが、菊の花の精は、自らは帝に献上されましたが、姫君を妊娠させることで、姫君の入内を阻止したことになります。
月日が重なり、姫君は美しい姫君を出産します。
さるほどにやう\/月日も重なりて、姫君いよ\/御心弱く、頼み少なき御有様に見え給ふ。乳母を始めて女房たちあまた介錯申しければ、まことにいつくしく姫君いでき給ふ。中納言殿も北の御方も、かしづき給ふこと限りなし。されどもかざしの姫君は、今を限りと見えさせ給ふ。(305~306頁)
【口語訳】そうするうちに、だんだん月日が重なって、姫君はますます御心弱く、頼りないご様子にお見えになる。乳母を始め、女房たちがたくさんお世話し申し上げたので、本当に美しい姫君がお生まれになる。中納言殿も、北の方も、大切になさることはこの上ない。けれどもかざしの姫君は、今が最期(臨終)の様子でいらっしゃる。
ですが姫君自身は衰弱しきり、娘の姫君のことを頼む言葉を残しながら、「朝の露と消え」てしまいます(306頁)。
ここでは、常套表現ではありますが、姫君の命が「露」にたとえられています。姫君はまさに「露」のような存在であり、菊と露の取り合わせとして、この二人の恋が描かれているのです。
さて、娘の姫君は成長するにしたがって、かざしの姫君に似ていきます。
御齢の行くに従ひて、かざしの姫君に相似させ給へば、御いとほしみ給ひて、若き女房たちあまたつけ、かしづき給ふほどに、月日重なりて、七歳にて御袴着せ参らせ給ひけり。(307頁)
【口語訳】成長するにしたがって、かざしの姫君に瓜二つにおなりになるので、(両親は)可愛がりなさって、若い女房たちをたくさんつけ、大切になさる間に、月日は経って、七歳で御袴着(幼児から少年・少女になることを祝う儀式)をなさった。
どんどん美しくなる姫君のうわさを帝も聞きつけ、女御として入内させるようにという、勅が下ります。
さる程に、君きこしめされて、「女御に参らせよ」との勅によりて、女御にぞ定まり給ひける。(308頁)
【口語訳】そうしているうちに、帝は(姫君のうわさを)お聞きになって、「女御として参内させなさい」との勅命によって、女御に定まりなさった。
入内した姫君への寵愛は深く、皇子と皇女が生まれました。
さても帝は寵愛甚だしくこそ聞えけれ。いよく浅からず御心にもかなひ給へば、程なく若宮、姫宮打ち続きいでき給ひて、まことにめでたきことにぞ、人\/申しあへり。(308頁)
【口語訳】それにしても、帝の(姫君への)寵愛は甚だしくていらっしゃった。ますます深く、御心にもかなっていらっしゃったので、間もなく皇子・皇女が引き続いてお生まれになり、実にめでたいことであると、人々は申し上げあった。
菊の精とかざしの姫君との娘が、皇子・皇女を産んだという結末は、かざしの姫君の反抗心も垣間見えたこの物語が、最終的には王権に回収されたものと考えることができます。
まとめ
『かざしの姫君』では、菊の花の精が男性として描かれますが、『秋の夜長物語』と異なり、菊の花の精は生殖します。帝の花揃えに男性として描かれる菊の花が献上されることは、帝のもとに入内する女性たちと、性別が転倒しています。
一方で、ヒロインである姫君は、出産後はかなくなくなったことが、常套表現ではありますが、「露と消える」と表現されます。これは、姫君が菊にかかる露を象徴する存在であることを示すものでしょう。「菊の花の精」は、人間ではないという意味においては他者ですが、庭の籬の菊という意味では、身近な、自分の世界のなかにある存在でもあります。姫君は人間の男性と交わるよりも、自分の庭の植物を愛するような、自閉する魂を持っていたのです。また、菊の花の精の子を身ごもったことで、入内せず、菊の花の精が帝の花揃えのために死んでしまうと、「花揃えさえなければ!」と思う姫君は、帝や王権に対して反抗するかのようにも見えます。
しかしながらそのような反抗心は、菊の花の精と姫君の娘が入内し、皇子・皇女を産むことで、最終的には王権の物語へと回収されるのです。
*引用は、岩波新日本古典文学大系『室町物語集 上』による。
→第6回
→第8回