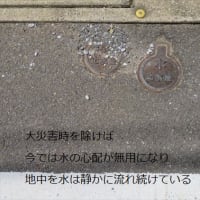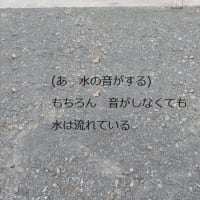最近のツイートや覚書など2023年11月 ②
2023/11/16
RT
産経ニュース@Sankei_news
「作戦司令室など発見」 ガザで病院突入のイスラエル軍
軍は15日、シーファ病院内のものだとする映像を公表した。監視カメラが設置された室内を報道官が歩いて案内し、発見されたとする自動小銃や手投げ弾、防弾ベストやラップトップ型パソコンなどを指し示す内容だった
画像では、なんでも発見できる。
現代の画像の有り様を「手品」と呼ばないとすれば、古風に言えば「神の手」によるものということになるだろうか。画像は、なんでも創造できる。「神の手」の舞台裏を知ることができるのは、現場に居合わせるか、想像力を行使すること。
2023/11/17
現代短歌bot@gendai_tanka
フォルテとは遠く離れてゆく友に「またね」と叫ぶくらいの強さ
千葉聡『そこにある光と傷と忘れもの』
何かを説明するのにこの歌のように表現することがある。そういう慣習に乗りながら人の別れの場面の切なさを描き出している。一首で独立の歌だとすれば、「遠く離/れてゆく友に/フォルテで/「またね」と叫ぶ/後ろ姿に」はどうかな。
なぜ「フォルテ」なのかなと思って調べたら、wikiにある大学の「校歌の作曲を担当している」とあった。音楽にも通じているのだろう。因みに、歌集『グラウンドを駆けるモーツァルト』には、「グラウンドにモーツァルトがいる 大地からもらったリズムで今走り出す」という歌がある。
2023/11/19
胎内(たいない)市って初めて出会った。由来にはいくつかあるそうだが、地形からの連想より、「アイヌ語の「テイ・ナイ」(清い川)、または「トイ・ナイ」(toy-nay 泥の川)を語源」の方かなと思った。万葉仮名以来、漢字は音の利用だけではなく意味の利用もあるからまぎらわしい。
2023/11/21
RT
白川静@sizukashirakawa
(レヴィ=ストロースが)調査をしているときに、そこの酋長に文字を見せて、文字の機能を説明したことがある。するとその酋長が、さっそく村人を呼んで、その知りたての文字を、きわめて権威的な方法で行使してみせたというのです。それはレヴィ=ストロースの目の前で起ったことです。
レヴィ・ストロースが「文字の機能を説明した」のは近代的な欧米的言語観によるものだろうが、酋長は「権威的な方法で行使してみせた」というのは、神との対話のようにして、あるいは神々(こうごう)しくということだろうか。というのは
白川 エジプトのヒエログリフでも、ピラミッドの中にしかありませんね。王さまの墳墓にしかない。・・・・・エジプトでも本来は、文字そのものは神との交通の手段であった。中国では祖先を祀(まつ)る時にも、祀る器物に文字を入れて祖先に告げる。そういう風なことを、殷代にはやっています。
吉本 最近、沖縄の学者さんが書いた方言札という表題の、要するに、その学者さんの文章を読むと、日本本土では、ただ言葉だけで言霊(ことだま)といっていたんだけれども、沖縄では、・・・中国の漢字が文字として入ってきたときに、文字どおり文字を書いた紙を祀って拝んだりしていたという。
本当に神様扱いにして、文字を奉って拝んだりしていたんだという研究が書いてあって、へーっと。
https://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/e821e2a6078d77ce41454cb31695cdcb
2023/11/23
RT
註(.イスラエル/エンジェル投資をしている人)
人質交換でイスラエル刑務所から解放されるパレスチナ人150人はテロリストです。イスラエル領土で犯罪を犯し司法に裁かれ判決を受けた犯罪者です。一方ガザに拉致されていて人質となり解放されると言われている50人は0才の赤ちゃんや80代の高齢者などです。
イスラエルの自衛する権利を批判し「中立」や「バランス」という美名を掲げる人々が本当にそう信じているならこの人質交換は全く中立でない。少なくとも「イスラエルの人質は50人じゃなく150人にすべきだ」という論理になるはずだが軽くスルーされる。
結局イデオロギーやポジショントークが先にあり便利できれいな「中立」や「バランス」を着ているだけだろう、という認識を僕は一定の勢力に対して持ってます。なので偽善ぽいんです。
2023年11月22日
この方でも、イスラエル人と結婚していた焼き物やっている女の人でも、現地とその地の人々と深い結びつきを持っていたら、例え一応圏外の日本人でもイスラエルの国際法を無視したいろんな負にも目をつぶりイスラエルびいきになるんだろうな。先の戦争中のこの地の人々もほとんどがそうだったろう。
戦争は人倫の死だからたとえ国際法があっても戦争の双方とも残虐が普通に行われる。そして、言葉を交わしている分には普通に見えても、双方の地の人々も心も 目もイッてしまう。世界も私たちも〈戦争〉から遠いと思っていたら、(戦争になったらきみはどうするの?)を迫られるような雰囲気を感じている。
現代短歌bot@gendai_tanka
目がさめるだけでうれしい 人間がつくったものでは空港がすき
雪舟えま『たんぽるぽる』
なんてことないような感情を表現された言葉が、歌として表現されている。逆に言えば、わたしたちの誰もが歌えるような言葉になっている。そして、そんな好き嫌いは誰にもある普遍的なものである。近代以前の昔では、例え文化上層の文学があっても、こんな万人の歌も存在し続けていたと思われる。
2023/11/24
現代短歌bot@gendai_tanka
3番線快速電車が通過します理解できない人は下がって
中澤系『uta 0001.txt』
まず、意味不明に突き当たる。普通なら、下の句は「白線の内側までお下がりください」となる。作品の言葉をこの世界の意志の表現と見るなら、この世界の動きになじめない者は近づくなという排斥の意志になる。一方、〈私〉(作者)の意志の表現と見るなら、この言葉の走行も歌の表現なんだ、それが分からない人は下がってくれ。この短い表現の一首だけではモチーフを決めかねる。わたしは、後者かなと思うけど。
2023/11/26
現代短歌bot@gendai_tanka
戦争が(どの戦争が?)終つたら紫陽花を見にゆくつもりです
荻原裕幸『あるまじろん』
註.「終つたら」は、「終ったら」の表記のミスではなく、戦前風の表記になっています。
表現している主要な場の次元とは別の次元からの言葉として、わたしも( )を時々使うけど、(どの戦争が?)はそのようなものとして表現されている。作中の〈私〉にとって〈戦争〉は自明のことを指しているのだろうが、戦争は大から小さな人間間のものまで無数にあり続けているよねという批評性が加えられている。
現代短歌bot@gendai_tanka
ぼくたちはこわれてしまったぼくたちはこわれてしまったぼくたちはこわ
中澤系『uta 0001.txt』
「ぼくたちはこわれてしまった」とずっと言い続けている「こわれてしまった」「ぼくたち」の状況が表現されているが、「ぼく」ではなく「ぼくたち」とは、小グループか社会全体の人々を指すのか?画像化してみれば、何気ない都市風景の中に空白感を抱えた人々が立っている。そうして、社会も人もこわれている。
2023/11/27
『大岡越前』の大岡忠相を演じるのが加藤剛の場合と東山紀之とでは、同じようなドラマの物語でも、何かちがう。また、『暴れん坊将軍』に登場する横内正演じる大岡忠相もいる。この間のジャニーズ問題で登場した東山紀之の言動で、大岡忠相を演じる東山紀之のイメージが揺らいだ。
例えば、結婚式などの司会業をやっている人が、舞台を下りるとまた別人のようになり得るように、それは当然のことだが、ふしぎな気分だ。
ファンとして追っかけやっている人は、相手の普通の生活人は捨象してまるごとドラマや歌を演じる人として見て感じ受けとめているのだろう。これって、卑弥呼の時代の人々で卑弥呼を崇拝する人々もそんなものだったんだろうか。近くは、それに政治性や宗教性が加味されたアベ信者や韓鶴子信者等がいる。
現代短歌bot@gendai_tanka
しろがねの洗眼蛇口を全開にして夏の空あらふ少年
光森裕樹『鈴を産むひばり』
言葉の選択は、イメージを左右する。「しろがね」とくると、「銀(しろがね)も金(くがね)も玉も何せむに・・・」を連想してしまう。こんな言い方は「少年」の世界と対応している。似た構成に「あかねさすGoogle Earthに一切の夜なき世界を巡りて飽かず」がある。枕詞の古さが新しい神話性を表出か。
「洗眼蛇口」って知らなかったけど、「洗眼蛇口って今はもうないんですよね。プールのあとに目を洗うための、二股で上に向かって水が出る蛇口があったんですよね。全開にしたらすごく高くまで水が上がって、子どもたちはそれを面白がってやる。」というのがあった。
2023/11/30
RT
日経サイエンス@NikkeiScience
「“新元素”を生む現代の錬金術」
複数の元素を原子レベルで混ぜると,もとの性質を失って“新元素”に生まれ変わる。
周期表の常識を超えた化学の新しい世界が見えてきた。
日経サイエンス2024年1月号【特集:ありえない物質を作る】
2023年11月30日
「異種の元素を原子レベルで均一に混ぜ合わせる」ということの具体的なイメージがよくわからないけど、人間は、遺伝子レベルで自然を操作できるのと同様に、原子レベルそのもので自然を操作できる自然認識の段階(深さ)に到っているということだろうか。
吉本さんは晩年に、対象(事象)の捉え方として、(水素と酸素を合わせると水ができる)、どれが水素に当たり、どれが酸素で、そういうこと(水)が起きたのかと考えると語っていたと記憶する。
そういう原子レベルそのものの操作・認識の段階に入ると、吉本さんが語った「水素+酸素→水」の化学反応(自然認識)ももちろん残るだろうけど、さらに新たな形の深まった自然認識の中に旧来のものは包括されていくような気がする。
RT
産経ニュース@Sankei_news
「作戦司令室など発見」 ガザで病院突入のイスラエル軍
軍は15日、シーファ病院内のものだとする映像を公表した。監視カメラが設置された室内を報道官が歩いて案内し、発見されたとする自動小銃や手投げ弾、防弾ベストやラップトップ型パソコンなどを指し示す内容だった
画像では、なんでも発見できる。
現代の画像の有り様を「手品」と呼ばないとすれば、古風に言えば「神の手」によるものということになるだろうか。画像は、なんでも創造できる。「神の手」の舞台裏を知ることができるのは、現場に居合わせるか、想像力を行使すること。
2023/11/17
現代短歌bot@gendai_tanka
フォルテとは遠く離れてゆく友に「またね」と叫ぶくらいの強さ
千葉聡『そこにある光と傷と忘れもの』
何かを説明するのにこの歌のように表現することがある。そういう慣習に乗りながら人の別れの場面の切なさを描き出している。一首で独立の歌だとすれば、「遠く離/れてゆく友に/フォルテで/「またね」と叫ぶ/後ろ姿に」はどうかな。
なぜ「フォルテ」なのかなと思って調べたら、wikiにある大学の「校歌の作曲を担当している」とあった。音楽にも通じているのだろう。因みに、歌集『グラウンドを駆けるモーツァルト』には、「グラウンドにモーツァルトがいる 大地からもらったリズムで今走り出す」という歌がある。
2023/11/19
胎内(たいない)市って初めて出会った。由来にはいくつかあるそうだが、地形からの連想より、「アイヌ語の「テイ・ナイ」(清い川)、または「トイ・ナイ」(toy-nay 泥の川)を語源」の方かなと思った。万葉仮名以来、漢字は音の利用だけではなく意味の利用もあるからまぎらわしい。
2023/11/21
RT
白川静@sizukashirakawa
(レヴィ=ストロースが)調査をしているときに、そこの酋長に文字を見せて、文字の機能を説明したことがある。するとその酋長が、さっそく村人を呼んで、その知りたての文字を、きわめて権威的な方法で行使してみせたというのです。それはレヴィ=ストロースの目の前で起ったことです。
レヴィ・ストロースが「文字の機能を説明した」のは近代的な欧米的言語観によるものだろうが、酋長は「権威的な方法で行使してみせた」というのは、神との対話のようにして、あるいは神々(こうごう)しくということだろうか。というのは
白川 エジプトのヒエログリフでも、ピラミッドの中にしかありませんね。王さまの墳墓にしかない。・・・・・エジプトでも本来は、文字そのものは神との交通の手段であった。中国では祖先を祀(まつ)る時にも、祀る器物に文字を入れて祖先に告げる。そういう風なことを、殷代にはやっています。
吉本 最近、沖縄の学者さんが書いた方言札という表題の、要するに、その学者さんの文章を読むと、日本本土では、ただ言葉だけで言霊(ことだま)といっていたんだけれども、沖縄では、・・・中国の漢字が文字として入ってきたときに、文字どおり文字を書いた紙を祀って拝んだりしていたという。
本当に神様扱いにして、文字を奉って拝んだりしていたんだという研究が書いてあって、へーっと。
https://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/e821e2a6078d77ce41454cb31695cdcb
2023/11/23
RT
註(.イスラエル/エンジェル投資をしている人)
人質交換でイスラエル刑務所から解放されるパレスチナ人150人はテロリストです。イスラエル領土で犯罪を犯し司法に裁かれ判決を受けた犯罪者です。一方ガザに拉致されていて人質となり解放されると言われている50人は0才の赤ちゃんや80代の高齢者などです。
イスラエルの自衛する権利を批判し「中立」や「バランス」という美名を掲げる人々が本当にそう信じているならこの人質交換は全く中立でない。少なくとも「イスラエルの人質は50人じゃなく150人にすべきだ」という論理になるはずだが軽くスルーされる。
結局イデオロギーやポジショントークが先にあり便利できれいな「中立」や「バランス」を着ているだけだろう、という認識を僕は一定の勢力に対して持ってます。なので偽善ぽいんです。
2023年11月22日
この方でも、イスラエル人と結婚していた焼き物やっている女の人でも、現地とその地の人々と深い結びつきを持っていたら、例え一応圏外の日本人でもイスラエルの国際法を無視したいろんな負にも目をつぶりイスラエルびいきになるんだろうな。先の戦争中のこの地の人々もほとんどがそうだったろう。
戦争は人倫の死だからたとえ国際法があっても戦争の双方とも残虐が普通に行われる。そして、言葉を交わしている分には普通に見えても、双方の地の人々も心も 目もイッてしまう。世界も私たちも〈戦争〉から遠いと思っていたら、(戦争になったらきみはどうするの?)を迫られるような雰囲気を感じている。
現代短歌bot@gendai_tanka
目がさめるだけでうれしい 人間がつくったものでは空港がすき
雪舟えま『たんぽるぽる』
なんてことないような感情を表現された言葉が、歌として表現されている。逆に言えば、わたしたちの誰もが歌えるような言葉になっている。そして、そんな好き嫌いは誰にもある普遍的なものである。近代以前の昔では、例え文化上層の文学があっても、こんな万人の歌も存在し続けていたと思われる。
2023/11/24
現代短歌bot@gendai_tanka
3番線快速電車が通過します理解できない人は下がって
中澤系『uta 0001.txt』
まず、意味不明に突き当たる。普通なら、下の句は「白線の内側までお下がりください」となる。作品の言葉をこの世界の意志の表現と見るなら、この世界の動きになじめない者は近づくなという排斥の意志になる。一方、〈私〉(作者)の意志の表現と見るなら、この言葉の走行も歌の表現なんだ、それが分からない人は下がってくれ。この短い表現の一首だけではモチーフを決めかねる。わたしは、後者かなと思うけど。
2023/11/26
現代短歌bot@gendai_tanka
戦争が(どの戦争が?)終つたら紫陽花を見にゆくつもりです
荻原裕幸『あるまじろん』
註.「終つたら」は、「終ったら」の表記のミスではなく、戦前風の表記になっています。
表現している主要な場の次元とは別の次元からの言葉として、わたしも( )を時々使うけど、(どの戦争が?)はそのようなものとして表現されている。作中の〈私〉にとって〈戦争〉は自明のことを指しているのだろうが、戦争は大から小さな人間間のものまで無数にあり続けているよねという批評性が加えられている。
現代短歌bot@gendai_tanka
ぼくたちはこわれてしまったぼくたちはこわれてしまったぼくたちはこわ
中澤系『uta 0001.txt』
「ぼくたちはこわれてしまった」とずっと言い続けている「こわれてしまった」「ぼくたち」の状況が表現されているが、「ぼく」ではなく「ぼくたち」とは、小グループか社会全体の人々を指すのか?画像化してみれば、何気ない都市風景の中に空白感を抱えた人々が立っている。そうして、社会も人もこわれている。
2023/11/27
『大岡越前』の大岡忠相を演じるのが加藤剛の場合と東山紀之とでは、同じようなドラマの物語でも、何かちがう。また、『暴れん坊将軍』に登場する横内正演じる大岡忠相もいる。この間のジャニーズ問題で登場した東山紀之の言動で、大岡忠相を演じる東山紀之のイメージが揺らいだ。
例えば、結婚式などの司会業をやっている人が、舞台を下りるとまた別人のようになり得るように、それは当然のことだが、ふしぎな気分だ。
ファンとして追っかけやっている人は、相手の普通の生活人は捨象してまるごとドラマや歌を演じる人として見て感じ受けとめているのだろう。これって、卑弥呼の時代の人々で卑弥呼を崇拝する人々もそんなものだったんだろうか。近くは、それに政治性や宗教性が加味されたアベ信者や韓鶴子信者等がいる。
現代短歌bot@gendai_tanka
しろがねの洗眼蛇口を全開にして夏の空あらふ少年
光森裕樹『鈴を産むひばり』
言葉の選択は、イメージを左右する。「しろがね」とくると、「銀(しろがね)も金(くがね)も玉も何せむに・・・」を連想してしまう。こんな言い方は「少年」の世界と対応している。似た構成に「あかねさすGoogle Earthに一切の夜なき世界を巡りて飽かず」がある。枕詞の古さが新しい神話性を表出か。
「洗眼蛇口」って知らなかったけど、「洗眼蛇口って今はもうないんですよね。プールのあとに目を洗うための、二股で上に向かって水が出る蛇口があったんですよね。全開にしたらすごく高くまで水が上がって、子どもたちはそれを面白がってやる。」というのがあった。
2023/11/30
RT
日経サイエンス@NikkeiScience
「“新元素”を生む現代の錬金術」
複数の元素を原子レベルで混ぜると,もとの性質を失って“新元素”に生まれ変わる。
周期表の常識を超えた化学の新しい世界が見えてきた。
日経サイエンス2024年1月号【特集:ありえない物質を作る】
2023年11月30日
「異種の元素を原子レベルで均一に混ぜ合わせる」ということの具体的なイメージがよくわからないけど、人間は、遺伝子レベルで自然を操作できるのと同様に、原子レベルそのもので自然を操作できる自然認識の段階(深さ)に到っているということだろうか。
吉本さんは晩年に、対象(事象)の捉え方として、(水素と酸素を合わせると水ができる)、どれが水素に当たり、どれが酸素で、そういうこと(水)が起きたのかと考えると語っていたと記憶する。
そういう原子レベルそのものの操作・認識の段階に入ると、吉本さんが語った「水素+酸素→水」の化学反応(自然認識)ももちろん残るだろうけど、さらに新たな形の深まった自然認識の中に旧来のものは包括されていくような気がする。