
今回は無知に関して、説いて下さっている。
無知こそ、無くしてしまわなければならない最も根源的なものといえるでしょうね。そのためにこそ、われわれ人間は生きているのかも知れない。
山口修源師は、「幻影としての現実」(星雲社)の中で、「要するに、明らかに、心によって宇宙というものは生じているのです。我々霊魂を持つすべての存在(動物まで含めたすべての霊のある生き物、即ち、一切有情)が、本当に百パーセント「空」を理解したならば、その瞬間に、この地球を含めた全宇宙は一瞬にして消え失せるのです。影も形もなくなってしまうという、信じがたい深奥の法則原理が存在するのです。」と述べられているが、確かに、そんな感じがするし、そんなエキサイティングな瞬間に立ち会ってみた気もします(笑い)。
それと、今回、「無知」に関連して、ダライラマ法王の講話も紹介させてもらいます。この講話は石浜裕美子さんによって翻訳されていますので、英文(ジェフリー・ホプキンス訳)と石浜先生の翻訳、両方を掲載させてもらいます。
This error, which Buddhism calls ignorance, gives rise to powerful reflexes of attachment and aversion that generally lead to suffering. As Etty Hillesum says so tersely: "That great obstacle is always the representation and never the reality." The world of ignorance and suffering - called samsara in Sanskrit -is not a fundamental condition of existence but a mental universe based on our mistaken conception of reality.
(24p)
【語句、文法】
give rise to:・・・・を引き起こす
reflex:思考(行動)様式
attachment:愛着
aversion:嫌悪
tersely:簡潔に
【日本語訳】この思い違いは、仏教では無知(無明)と呼んでいますが、一般的に苦しみへと導く、愛着や嫌悪という強力な思考様式を引き起こすのです。エッティ・ヒルエサムが非常に簡潔に述べています。「このような巨大な障害はいつも代表的なものですが、決して真実ではないのです。」
無知と苦しみの世界ーーサンスクリット語ではサムサーラと呼ばれていますがーーは存在の根本的な状態ではないのです。この無知と苦しみの世界は、私たちがリアリティーを誤って認識することによって形成されている精神的世界なのです。
以下は、ダライラマ法王が1984年の春、ロンドンで行われた講演の中の無知に関連した箇所です。この講演の内容は、「The Meaning of Life from a Buddhist Perspective」と題されて1992年に英語で出版され、日本でも1995年に「ダライラマの仏教入門」(光文社)と題されて、翻訳出版されています。
The twelve links of dependent-arising are symbolized by the twelve pictures around the outside. The first, at the top--an old person, blind and hobbling with a cane--symbolizes ignorance, the first link.. In this context, ignorance is obscuration with respect to the actual mode of being of phenomena.
十二支縁起が輪廻図の円周に描かれた十二の部分によって象徴されていることは前にもお話ししたとおりです。十二支縁起の最初の項目である無知は、六道輪廻図では天辺に描かれた、杖をついた目の見えない老人によって象徴されています。この文脈では無知は諸事物(諸法)の実相、すなわち、「すべてのものが空であること(空性)」に暗いことを意味しています。
One type of ignorance is the mere non-knowing of how things actually exist, a factor of mere obscuration.
無知のタイプの一つとして、ものが現実にはいかにして存在しているかということに対する無知、つまり、単純な無知、があります。
However, here in the twelve links of dependent-arising, ignorance is explained as a wrong consciousness that conceives the opposite of how things actually do exist.
しかし、ここ十二支縁起のなかでの無知は、ものごとをその真の様相とは反対のものとして認識する誤った意識と説明されています。
Ignorance is the chief of the afflictive emotions that we are seeking to abandan. Each afflictive emotion is of two types: innate and intellectually acquired. Intellectually acquired afflictive emotions are based on inadequate systems of tenets, such that the mind imputes or fosters new afflictive emotions through conceptuality. These are not afflictive emotions that all sentient beings have and cannot be the ones that are at the root of the ruination of beings.
無知は捨て去るべき煩悩のなかでも根本のものです。無知には「生来の無知」と「学問によって獲得された無知」の二種類があります。学問によって獲得された煩悩は、適切でない学問の体系に基付いています。その結果、心は誤った概念を通して新しい煩悩を生み出し、その煩悩を養ってしまいます。学問をするのは人間だけの行為ですから、この「学問によって獲得された無知」はすべての命あるものを破滅に向かわせる根本原因となるものでもありません。
As Nagarjuna says in his Seventy Stanzas on Emptiness:
ナーガールジュナの「空についての七十の詩」には以下のように述べられています。
That consciousness that conceives things
Which are produced in dependence upon
Causes and conditions
To ultimately exist
Was said by the Teacher to be ignorance.
From it the twelve links arise.
原因と条件によって生じたにすぎない事物を
真実に存在するものであると執着する意識は
仏陀によって無知と呼ばれている。
この無知から縁起の十二支が生じるのである。
This is a consciousness that innately misapprehends, or misconceives, phenomena as existing under their own power, as not dependent.
Because this consciousness has different types of objects, ignorance is divided into two types: one that conceives inherent existence upon observing persons and another type that conceives inherent existence upon observing other phenomena. These are called consciousnesses that conceive, respectively, a self of persons and a self of phenomena.
このように人には、事物を縁起によって生じたものではなく、それ自身の力によって成立しているものと誤解・誤認する意識ーー生来の無知ーーが備わっています。無知という意識はさまざまな種類のものを対象とするので、その対象の種類の違いによって、無知も二つのタイプに分けられます。
一方の無知は、「輪廻の主体」を実体的存在(我)であると構想するものであり、もう一方のタイプの無知は、事物(法)を実体的存在(我)であると構想するものです。これらはそれぞれ「輪廻の主体に実体性を認める意識」(人我執)、「事物に実体性を認める意識」(法我執)と呼ばれます。











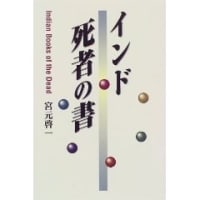
とても簡潔で解りやすい表現と、内容を持ったものなのですね。
>無知には「生来の無知」と「学問によって獲得された無知」の二種類があります。
私はこの文章を読んだ時に、ああそうか、と思ったんです。
つい先ほどまで、般若心経の「自己流の和訳」に取り組んでいたのですが、
数日かけて、そこでようやく得られた私なりの結論が、
この「学問によって獲得された無知」の無力化を説いた教えなんだ、ということでした。
もちろん、他の解釈が出来なくもないのですが、
要するに「解脱・悟り」に赴くのに「役に立ちそうな解釈」を考えていくと、
そのような結論に成らざるを得なかったのです。
私は、「生来の無知」を「外因(外界に対する倒錯した認識)」と名付けました。
それに対して「学問によって獲得された無知」は、
「内因(心の中に構築された誤ったイメージや、言葉によって仮構された概念など)」です。
私は、外因を滅して「慧解脱」を得たという自覚がありましたが、
今回、般若心経の内容について、色々と考察している最中に、
普段の日常生活の中で、とても面白い体験をいくつかしたのです。
それは、「識別が停止する」という経験でした。
その時に、「ああ、ありのままにモノを見つめる」というのは、こういう事なんだな。」と、
心の底から納得することが出来ました。
私はこれを「内因の消滅」、つまり「心解脱」の体験をしたのだと考えています。
そしてこれからは、「原始仏教」だけではなくて、
「大衆仏教(大乗とは呼びたくない)」にも目を向けてゆく必要性を感じ始めているところです。
>つい先ほどまで、般若心経の「自己流の和訳」に取り組んでいたのですが、
般若心経の和訳は最近もいろんな人が取り組んでいて、いろいろと出ていますね。
私も興味あるので、立ち読みするのですが、ども、イマイチだな、というのが正直な感想です(笑い)。
小室直樹さんなども、日本人の般若心経好きな傾向を皮肉って、解説している人自身も、読者も、本当の仏教を理解できていないのではないかと書いていますが、確かに、そんな気もしないでもありません。
>私は、「生来の無知」を「外因(外界に対する倒錯した認識)」と名付けました。
それに対して「学問によって獲得された無知」は、「内因(心の中に構築された誤ったイメージや、言葉によって仮構された概念など)」です。
なるほど。ダライラマの講話の内容を、こういうように説明してくれるとよく分かります。
>私は、外因を滅して「慧解脱」を得たという自覚がありましたが、
今回、般若心経の内容について、色々と考察している最中に、普段の日常生活の中で、とても面白い体験をいくつかしたのです。
それは、「識別が停止する」という経験でした。
その時に、「ああ、ありのままにモノを見つめる」というのは、こういう事なんだな。」と、
心の底から納得することが出来ました。
私はこれを「内因の消滅」、つまり「心解脱」の体験をしたのだと考えています。
こういう経験をした人でないと、この境地はどういうものだというのは分からないと思いますが、頭だけで分かっているような気になっても、それは本当の悟り、解脱ではないということですね。
和井さんのような境地は、自分の心の中にもはや煩悩的な思いは湧いてこないというようなものでしょうか。そういう体験をされたわけですね。なかなか普通の人にとっては、到達不可能のような境地だと思いますが、和井さんのブログで、いろいろその秘密を学んでいこうと思っています。
>この境地はどういうものだというのは分からないと思いますが、
いいえ、それは至って「シンプル」な体験でした。
例えば、バイクに乗って仕事場まで行く途中に、工事現場が出来ている。
こちらは時間が無いので急いでいるところ。
普通なら、何らかの「想い」が連動しますよね。
「ちぇっ、ついてないな」とか、「バイクだから、ギリギリ行けるだろう」とか、
とにかく、色々な想念が、次のステップを考える中で、連鎖されて出てくる。
それが、全くない。ただ、「工事中」なのを確認しただけで、
もう次のステップに(道順を変更する)スッと移行してしまっている。
だから、この意識状態では、目の前に何が起きても、平気なんですね。
つねに「平常心・不動心」をキープできるんです。完全に。
つまり、「何も認識できなくなる」わけではないんです。
そこには、「最もシンプルな認識(存在の有無)しか起きない」のです。
そこには、それに対する「肯定的な識別」も無く、
そしてまた、それに対する「否定的な識別」も無い。
目の前の変化の流れを「断片的」に捉えて、
あれやこれやと短絡的に、評価を下すような「心の働き」が一切無い状態。
「不生不滅、不垢不浄、不増不減。是故空中」
ふと、般若心経の、このワンフレーズが浮かんできました。
ああ、そうか。これが「識別の停止(無分別)」なんだな、
と、自分の中で納得できたわけです。
>煩悩的な思いは湧いてこないというようなものでしょうか。
充分に、自己コントロールが効く範囲内で、顕れては消えてゆく、と言う感じです。
ここが山の中とか、独居生活をしているのなら、もっと違うのでしょうけどね。
あと、他の人とのコミニュケーションを図る上で、わざと怒ったり、すねたり、
相手を突き放したり、ということは、たまにやりますけどね。
○ そこには、「最もシンプルな認識(現象の確認)しか起きない」のです
つねに「平常心・不動心」をキープできるんです。完全に。
つまり、「何も認識できなくなる」わけではないんです。
そこには、「最もシンプルな認識(存在の有無)しか起きない」のです。
そこには、それに対する「肯定的な識別」も無く、
そしてまた、それに対する「否定的な識別」も無い。
目の前の変化の流れを「断片的」に捉えて、
あれやこれやと短絡的に、評価を下すような「心の働き」が一切無い状態。
和井さんのこのような境地というのは、かなり、エゴの働きというのが無くなった状態なんでしょうね。この事象は自分にとって、損か得かという損得勘定がなくなった境地。これは普通の凡夫には絶対に不可能な境地。
事象、出来事を、ありのままに観る、というのでしょうか。
自分の心を客観視できる余裕ができているのでしょうね。
和井さんのコメントを読み、ああ、そうだ、何か、これと関連した本を読んだことがあるぞ、と、その本を探していたのですが、なかなか見つからず、かなりイライラした時を過ごしていたのです(苦笑)。まだまだ、目の前の出来事に左右される私です。悟りにはまだまだ遠い。
ようやく見つかりました。その本というのは、「なぜ人は破壊的感情を持つのか」という本です。これは和井さんも読まれたのではないかなと思います。
いろいろな専門家がダラムサラに集まって、なぜ人には破壊的感情が起きるのか、討論するという会議です。
その中で、クサラチッット師は、物事をありのままに観る最終段階として、
「認識が研ぎ澄まされt、感知したものと、それを分類して反応する心の接続回路を断ち切ることができるようになる。」
と述べておられるが、和井さん現在の境地というのは、まさに、この、自分にとって損か得かという評価してしまう心の接続回路を断ち切っている状態ではないかな、と思っています。
その「境地に達している(常住している)」わけではありません。
ただ、その状態を実体験できたというのは、かなりの収穫たな、と思っています。
>ようやく見つかりました。その本というのは、
>「なぜ人は破壊的感情を持つのか」という本です。
>これは和井さんも読まれたのではないかなと思います。
いえ、読んでないですね。
オウム事件以降、それほど多くの宗教関係の書物は読んでいないので…
その本、興味ありますね。今度図書館にでも行って探してみたいと思います。
識別と言うのは、世俗において「実在」を基盤とした人間社会の営みの中で成長した人間が、諸事物の諸関係を相互依存的に認識することだと私は考えています。
しかし、世俗において有効なそうした認識は、実は空であって絶対視できない、だから世俗で起こるさまざまな対立や、絶対視を根拠にした「それ以外」の排除のための戦争や殺戮などは迷妄なんだと、そんな風に私は考えます。
「境地」から戻って、世俗レベルで考えないと衆生を導くことはできないのではないか。私はそう考えます。