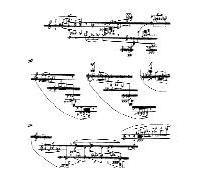道元が「仏性」巻を書いた動機は、大乗仏教において、仏性が重要な問題となり、中国の禅宗においても盛んに論じられるところとなっていたにもかかわらず、仏性についての正しい解釈が必ずしもなされていなかったという、当時の仏教界の状況において、真の仏教の立場から正しい仏性を説いておく必要があると考えたことによる。
ここでいう誤解というのは、仏性をバラモン教のアートマンのような究極の実体と考えてしまったり、まったくの無としてとらえてしまったりすることであり、そのどちらも超越的な観念として仏性をとらえていることで同様の誤解に陥っている。
それは仏教がバラモン教の実体論を否定し、無我を説いて出発しつつも、無常や無我といった、規定することのできないことを言語によって表現しなければならなかったことから超越的な実体としてとらえられてしまったり、無常なる存在を無常ならしめる、より高い次元の根本原理を想定せしめることとなってしまったりしたことにあると思われる。説一切有部が法の体系の基礎づけを縁起に求めず、「有」に求めたのは存在を可能にしているありかた(ものの本質)が超時間的に実在するとみたからであった。このような形而上学的実在論を否定したのがナーガールジュナであり、その否定の根拠として「空」や「縁起」を強調した。そうすることによって、実体論が陥る「常住」や「断滅」という、仏教では認められない欠陥を排した。つまり、法には実体がない(無自性)からこそ「不常不断」といえるのであり、一切の事物が相関関係をなして成立することができる(縁起)のであるとした。しかし、「空」を虚無としてとらえてしまう誤解を生むことにもなった。そこでナーガールジュナは「空見」の否定を言い、空を「有」とみることも「無」とみることもともに否定した。空というのは規定的な概念ではなく、従って有や無という規定的な概念でとらえることができないからである。空とは不変の実体として「ある」ものでもなければ、単なる否定でも「ない」ということでもない。つまり、実体論も虚無主義もともに否定しているのである。
有と無といった概念は互いに対立しているということにおいて相互に関係しあっているのであり、それぞれ独立して実在しているわけではない。この相関関係が成り立つためには一切の事物が絶対不変化の本質をそなえていてははならない。本質がない、すなわち無自性であればこそ事物が相互に関連し、また現象界の変化も成り立つのである。だからこそ無常のということも成り立つのである。無自性といい、無常といい、空といい、それらはすべて縁起から導き出され、基礎づけられていてそれゆえに同じ意味であると考えられている。
以上が大乗仏教における存在認識のありかたなのであるが、このことはつまり、仏教は現象界以外の何か超越的な絶対的存在を認めないということなのである。このような考え方は、存在論的な面においてだけでなく、実践面において特に重要な基盤となる。すべての事物がとどまることなく生滅変化しているからこそ実践が可能になるということができるだろう。すべての事物が固定化しており、絶対的で不変のものであるならば、一切のはたらきかけは無意味となるであろうからだ。例えばここで、仏と凡夫をそれぞれ実体として固定化されたものとして考えてみると、いくら修行をいくら修行を積んだところで凡夫と仏の間の深淵は埋めようがないということになってしまう。無常観、あるいは縁起説は、発心し修行すれば誰もがさとることができるということにおいてそのことの基礎となっているのである。そしてまた、そうであるがゆえに、さとるということも固定化されないのである。
仏教はこのように、存在論と実践とがともに無常や縁起によって基礎づけられており、そのことが理論と実践を直接に結びつけている。そしてこの無常や縁起はスタティックなものではなく、きわめてダイナミックなものである。
実体論と虚無主義を否定すること、そして存在論と実践の基礎に無常と縁起があること、以上が仏教の基本的な考え方といっていいと思われるが、以上のことは当然、道元によっても踏まえられている。これから道元の「仏性」巻を中心に論じていくことにするが、その際に問題とすることは。「有無」の問題である。道元は有と無をそれぞれいくつかの意味で使用している。もちろん恣意的な使用ではなく、コンテクストに応じてではあるが、おそらく、実体論と虚無主義としてとらえられてしまうことを極力回避しようとしたうえでのことと思われる。このような有と無の諸相・非相をみてみることにしたい。
ここでいう誤解というのは、仏性をバラモン教のアートマンのような究極の実体と考えてしまったり、まったくの無としてとらえてしまったりすることであり、そのどちらも超越的な観念として仏性をとらえていることで同様の誤解に陥っている。
それは仏教がバラモン教の実体論を否定し、無我を説いて出発しつつも、無常や無我といった、規定することのできないことを言語によって表現しなければならなかったことから超越的な実体としてとらえられてしまったり、無常なる存在を無常ならしめる、より高い次元の根本原理を想定せしめることとなってしまったりしたことにあると思われる。説一切有部が法の体系の基礎づけを縁起に求めず、「有」に求めたのは存在を可能にしているありかた(ものの本質)が超時間的に実在するとみたからであった。このような形而上学的実在論を否定したのがナーガールジュナであり、その否定の根拠として「空」や「縁起」を強調した。そうすることによって、実体論が陥る「常住」や「断滅」という、仏教では認められない欠陥を排した。つまり、法には実体がない(無自性)からこそ「不常不断」といえるのであり、一切の事物が相関関係をなして成立することができる(縁起)のであるとした。しかし、「空」を虚無としてとらえてしまう誤解を生むことにもなった。そこでナーガールジュナは「空見」の否定を言い、空を「有」とみることも「無」とみることもともに否定した。空というのは規定的な概念ではなく、従って有や無という規定的な概念でとらえることができないからである。空とは不変の実体として「ある」ものでもなければ、単なる否定でも「ない」ということでもない。つまり、実体論も虚無主義もともに否定しているのである。
有と無といった概念は互いに対立しているということにおいて相互に関係しあっているのであり、それぞれ独立して実在しているわけではない。この相関関係が成り立つためには一切の事物が絶対不変化の本質をそなえていてははならない。本質がない、すなわち無自性であればこそ事物が相互に関連し、また現象界の変化も成り立つのである。だからこそ無常のということも成り立つのである。無自性といい、無常といい、空といい、それらはすべて縁起から導き出され、基礎づけられていてそれゆえに同じ意味であると考えられている。
以上が大乗仏教における存在認識のありかたなのであるが、このことはつまり、仏教は現象界以外の何か超越的な絶対的存在を認めないということなのである。このような考え方は、存在論的な面においてだけでなく、実践面において特に重要な基盤となる。すべての事物がとどまることなく生滅変化しているからこそ実践が可能になるということができるだろう。すべての事物が固定化しており、絶対的で不変のものであるならば、一切のはたらきかけは無意味となるであろうからだ。例えばここで、仏と凡夫をそれぞれ実体として固定化されたものとして考えてみると、いくら修行をいくら修行を積んだところで凡夫と仏の間の深淵は埋めようがないということになってしまう。無常観、あるいは縁起説は、発心し修行すれば誰もがさとることができるということにおいてそのことの基礎となっているのである。そしてまた、そうであるがゆえに、さとるということも固定化されないのである。
仏教はこのように、存在論と実践とがともに無常や縁起によって基礎づけられており、そのことが理論と実践を直接に結びつけている。そしてこの無常や縁起はスタティックなものではなく、きわめてダイナミックなものである。
実体論と虚無主義を否定すること、そして存在論と実践の基礎に無常と縁起があること、以上が仏教の基本的な考え方といっていいと思われるが、以上のことは当然、道元によっても踏まえられている。これから道元の「仏性」巻を中心に論じていくことにするが、その際に問題とすることは。「有無」の問題である。道元は有と無をそれぞれいくつかの意味で使用している。もちろん恣意的な使用ではなく、コンテクストに応じてではあるが、おそらく、実体論と虚無主義としてとらえられてしまうことを極力回避しようとしたうえでのことと思われる。このような有と無の諸相・非相をみてみることにしたい。
















 シェーンベルクと出会ったカンディンスキーはその著書「芸術における精神的なもの」においてシェーンベルクについて言及し、シェーンベルクは1911年のカンディンスキーが主催した「青騎士展」に絵画を出展した。また1912年に刊行された「青騎士」にはシェーンベルクの論考「歌詞との関係」とシェーンベルク、ウェーベルン、ベルクそれぞれの歌曲の楽譜が掲載された。カンディンスキーは遠近法といった従来の技法にとらわれず、また具象的な外界の対象を描くことなく、いかに「内的必然性」から美や形態を生み出し得るかを模索し、色彩とフォルムだけの純粋絵画に到達した。シェーンベルクは調性を離れ、調性なしでいかに形式的な統一性を得られるかを模索し、十二音技法に到達した。シェーンベルクとカンディンスキーの出会いは絵画と音楽で同時並行的に起こった、新しく創造的な芸術運動の出会いであった。
シェーンベルクと出会ったカンディンスキーはその著書「芸術における精神的なもの」においてシェーンベルクについて言及し、シェーンベルクは1911年のカンディンスキーが主催した「青騎士展」に絵画を出展した。また1912年に刊行された「青騎士」にはシェーンベルクの論考「歌詞との関係」とシェーンベルク、ウェーベルン、ベルクそれぞれの歌曲の楽譜が掲載された。カンディンスキーは遠近法といった従来の技法にとらわれず、また具象的な外界の対象を描くことなく、いかに「内的必然性」から美や形態を生み出し得るかを模索し、色彩とフォルムだけの純粋絵画に到達した。シェーンベルクは調性を離れ、調性なしでいかに形式的な統一性を得られるかを模索し、十二音技法に到達した。シェーンベルクとカンディンスキーの出会いは絵画と音楽で同時並行的に起こった、新しく創造的な芸術運動の出会いであった。