 Berg WOZZECK
Berg WOZZECKAnja Silja(S)
Eberhard Waechter(B)
Christoph von Dohnanyi
Wiener Philharmoniker
アルバン・ベルク(1885-1935)はウィーンで生まれた。裕福で文化的な環境で育ち、幼少の頃から音楽や文学に親しんだ。ベルクは歌が好きな兄のために伴奏をし、妹とは古典派やロマン派の交響曲を一緒に演奏した。14歳の頃からは独学で作曲を始め、100を超えるほどの歌曲を作り、それらを兄妹で演奏しては楽しんだ。しかし、ベルクの少年時代は幸福なことばかりではなく、15歳で父親を亡くし、17歳のときにはベルク家で働いていた女中マリーを妊娠させ、18歳のときにはギムナジウムの卒業試験に失敗してしまった。これらの出来事は繊細で内向的であったベルクを追い詰めることとなり、彼は18歳のときに自殺を図った。
その翌年、1904年にシェーンベルクが出した生徒募集の新聞広告を見たベルクの兄がベルクの歌曲をシェーンベルクに見せたことがきっかけで、ベルクはシェーンベルクに師事することとなり、ベルクはシェーンベルクの下で6年間、対位法や和声などの音楽理論や作曲を学んだ。そこでウェーベルンと知り合い、また、ウィーンの文化人とも交流をするようになった。
1908年、ベルクは喘息を患った。23歳のことであり、その日が7月23日だったため、23という数字が自分の運命の数字だと思うようになる。このようなベルクの数字へのこだわりにはフロイトの精神分析学の誕生に影響を与えたといわれるヴィルヘルム・フリースの数秘学への関心があり、ベルクはこのフリースの数秘学を「観念的な音楽の哲学的な基盤」とする旨を記した手紙をシェーンベルクに宛てて書いたこともある(シェーンベルクも13という数字にこだわっていたことが知られていて、彼は7月13日の金曜日、それも翌日になる13分前に死去した)。
1911年にベルクはヘレーネ・ナホヴスキーと結婚した。この結婚はヘレーネの両親からの強い反対やベルクが敬愛し交流もあった詩人、ペーター・アルテンベルクもまたヘレーネとの結婚を望んでいたなど様々な障害があったが、それを押し切ってのことであった。ベルクの「弦楽四重奏曲」にはこれらのことが色濃く反映しているといわれている。
そして1914年、ベルクはビュヒナーの戯曲「ヴォイツェック」の上演を見たことで、この作品に基づいたオペラ「ヴォツェック」を作曲することを決意するが、1915年から1917年の間、第1次世界大戦のため兵役に就くことになり、作曲は戦後、1917年から1922年の間になされた。このオペラにはベルクの軍隊での経験が反映されている。ベルクは「ヴォツェック」について次のように言っている。
「良い音楽を作ろうという願望、即ちビュヒナーの不朽の戯曲の精神的な内容に、音楽的内容を与え、その詩的な言語を移しかえようという願望は別として、私がオペラを書こうと決心した時、私にとって演劇に属するものを演劇として与えることだけが気がかりであった。――作曲技法に関してさえも。言いかえれば、私にとって音楽を次のように構成していくことだけが気がかりであったのだ。つまり、戯曲に奉仕する義務を音楽が常に意識し――さらにその戯曲を舞台の上での現実性に置きかえていくのに必要な一切を、音楽だけから導き出すことができるように、そして、理想的な監督の本質的な責任をすべて作曲家がもつように――音楽を構成していくこと。しかもこれらすべてが、音楽のそれ以外の絶対的な(純粋に音楽的な)存在権を損なわず、音楽外的な何者によっても妨害されることのない、その独自の生命を損なうことのないように。」(ベルク「オペラの問題」)
オペラ「ヴォツェック」は1925年にエーリッヒ・クライバー(カルロス・クライバーの父)によってベルリン国立歌劇場で初演された。それ以降、ヨーロッパ各地の歌劇場で上演され成功をおさめ、このことによってベルクは国際的な名声を獲得した。そしてこの年、ハンナ・フックス=ロベッティンとの不倫関係が始まった。彼女との関係は「抒情組曲」に反映している。さらにこの年、十二音技法を用いたオペラとして、ヴェーデキントの戯曲に基づく「ルル」の作曲を開始した。このオペラは未完に終わったが、ツェルハにより補筆され、ブーレーズの指揮により1979年に初演された。ベルクは「ルル」の作曲を中断し、1929年にボードレールの詩に基づく演奏会用アリア「ワイン」と1935年にルイス・クラスナーから委嘱された「ヴァイオリン協奏曲」を作曲した。「ヴァイオリン協奏曲」は、アルマ・マーラーが二番目の夫であったグロピウスとの間にもうけた娘マノンの死を悼むレクイエムとして作曲された。ベルクにとってこれが遺作となり、ベルクはこの年、虫刺されが原因の敗血症によって死去した。
ベルクの音楽はブラームスやR.シュトラウス、マーラーといった後期ロマン派の影響から出発し、シェーンベルクと出会ってからは師にならい、無調や十二音技法を取り入れていった。
しかし、そのやり方はグールドが「一般大衆が聴いて即座にわかる唯一の十二音作曲家」と評したように、従来の調性を完全に排除してしまうのではなく、伝統的な音階や調性を十二音技法に結びつけるといったかたちでなされた。ベルクは伝統的な調性音楽とシェーンベルクが創始した新しい音楽様式との間に断絶があることを強調せず、むしろ自分の音楽が長調や短調を除けば「それ以外の真性かつ正当な音楽的な構成条件をすべて備えている」とし、「もしお望みなら私としては自分の音楽が優れた他のすべての音楽と同じように動機・主題・主要声部要するに旋律に基づくことを証明することもできるだろう」とさえ言っている。ベルクは十二音技法を汎調性的な原理に変えることによって、十二音音楽に調性を取り戻そうとし、そのために調性和声的な組み合わせが出てくるような形で原音列を作っている。こうしたベルクのやり方は音楽に自身の体験が色濃く反映されていることも含め、ロマン主義の感傷性をひきずった音楽として批判されることもあったが、1970年代以降、様々な角度からの研究が進み、今では多層的な構造を備えた音楽としてその独自性が明らかにされた。
→E.ロックスパイザー「絵画と音楽」(白水社)
→C.ダールハウス「ダールハウスの音楽美学」(音楽之友社)
→G.グールド「グールドのシェーンベルク」(筑摩書房)
→J-J.ナティエ「音楽記号学」(春秋社)










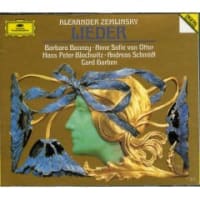
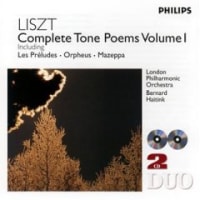
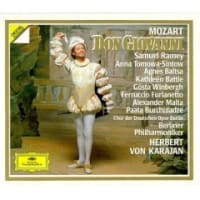
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます