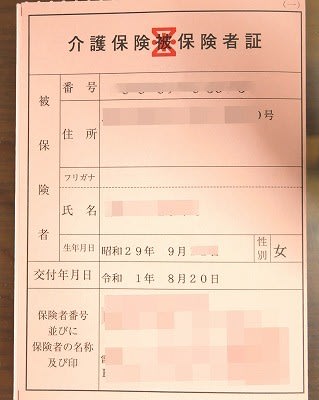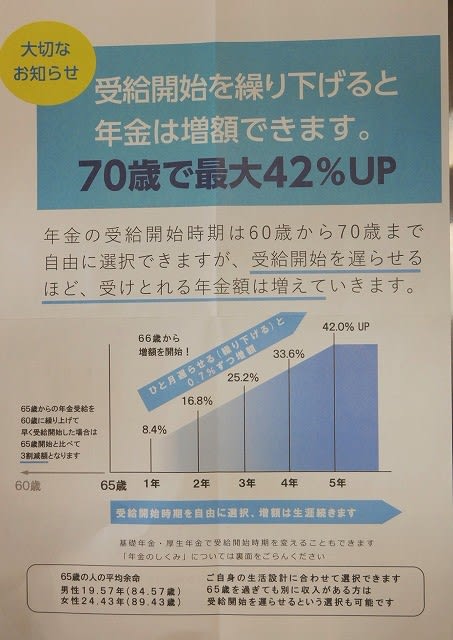台風19号の被害の甚大さには心が痛みます。
被災された方々、心よりお見舞い申し上げます。
今回の被害について、ハザードマップはかなり正確に予想していたとのこと。
そこで我が家周辺のハザードマップで見てみました。
私の居住している市の場合、ハザードマップは複数あって、地震、津波、高潮、洪水などです。
その内、津波と高潮は、私の家のある場所が内陸部ですので大丈夫ですが、近くの河川の堤防決壊による洪水被害が問題ありでした。
ハザードマップは色で浸水した時の水の高低を分けているのですが、家の周辺はざっと見たところ最大3~5m未満、水に浸かりそうでした。
もっと詳しく見る為にハザードマップを拡大してみました。
すると面白いことが分かりました。
私の家の前の道は3~5m未満、水に浸かりそうですが私の住んでいる家は最大1~3m未満、水に浸かりそうなのです。
どういうことかというと、私の家は1mほど地上げしているのです。
ハザードマップを詳しく見ると、地上げしている家と、していない家は色の区分が分かれているのです。
どういう方法でそこまで細かい地図を作れたのか不思議です。
私が子供だった頃、家の前の道が大雨で何度か川になったことがありました。
でも地上げしてあったおかげで家に被害はなかったのです。
近所でも地上げしていない家は当然浸水していました。
むろん市も下水道の整備に力を入れ、ここ何十年と家の前の道が川になることはなくなりました。
でも、今後やってくるかもしれない100年に一度くらいの大雨で、2キロほど離れた近くの河の堤防が決壊した場合、たぶん我が家も床上浸水くらいすることは覚悟しなければならないようです。
実は我が家の近辺は、50年くらい前まではあちこちに沼地が残されていたりして、元々湿地帯だったのです。
我が家が建っている周辺は、2000年くらい前は近くの河の河川敷だったことも分かっています。
その近くの河は明治初期まで暴れ川とか人喰い川(!!)と呼ばれていて、しょっちゅう氾濫しては甚大な被害を出していたのです。
我が家からほんの10m北にいくと少し地面が高くなっていて、その辺りは掘れば弥生時代の遺跡が出てきます。
2000年くらい前の昔の人は河の傍に住んでいたようです。
周辺には素戔嗚尊神社という名称の小さな神社がいくつもあるのですが、素戔嗚尊(スサノオノミコト)は暴風雨の神様で、台風被害を鎮めるための神社の建立だったようです。
(関西で素戔嗚尊神社という呼称の神社が多い場所は洪水被害が甚大だった同じような土地柄とのこと。)
とまあ歴史的にみても、近くの河の堤防が決壊したら被害は避けられそうにないです。
日本中どこでもそうでしょうが、災害は他人事ではないです。
近くの河、普段は水量もわずかなのですが。








何かあったら、この子達を避難所に連れて行かなくてはならないのですが、それも大変そう。
この夏までいたみーちゃんの居場所を占拠するハッピーです。


買ってあげた猫ちぐらの上が気に入ったラッキーです。


夜はハッピーは猫ちぐらの下の部分に入って寝ています。
報道はほとんどされていませんが、台風19号で亡くなった動物たちも多かったのではないでしょうか。
被災地に一日でも早く平穏な日常が戻ることをお祈りいたします。
被災された方々、心よりお見舞い申し上げます。
今回の被害について、ハザードマップはかなり正確に予想していたとのこと。
そこで我が家周辺のハザードマップで見てみました。
私の居住している市の場合、ハザードマップは複数あって、地震、津波、高潮、洪水などです。
その内、津波と高潮は、私の家のある場所が内陸部ですので大丈夫ですが、近くの河川の堤防決壊による洪水被害が問題ありでした。
ハザードマップは色で浸水した時の水の高低を分けているのですが、家の周辺はざっと見たところ最大3~5m未満、水に浸かりそうでした。
もっと詳しく見る為にハザードマップを拡大してみました。
すると面白いことが分かりました。
私の家の前の道は3~5m未満、水に浸かりそうですが私の住んでいる家は最大1~3m未満、水に浸かりそうなのです。
どういうことかというと、私の家は1mほど地上げしているのです。
ハザードマップを詳しく見ると、地上げしている家と、していない家は色の区分が分かれているのです。
どういう方法でそこまで細かい地図を作れたのか不思議です。
私が子供だった頃、家の前の道が大雨で何度か川になったことがありました。
でも地上げしてあったおかげで家に被害はなかったのです。
近所でも地上げしていない家は当然浸水していました。
むろん市も下水道の整備に力を入れ、ここ何十年と家の前の道が川になることはなくなりました。
でも、今後やってくるかもしれない100年に一度くらいの大雨で、2キロほど離れた近くの河の堤防が決壊した場合、たぶん我が家も床上浸水くらいすることは覚悟しなければならないようです。
実は我が家の近辺は、50年くらい前まではあちこちに沼地が残されていたりして、元々湿地帯だったのです。
我が家が建っている周辺は、2000年くらい前は近くの河の河川敷だったことも分かっています。
その近くの河は明治初期まで暴れ川とか人喰い川(!!)と呼ばれていて、しょっちゅう氾濫しては甚大な被害を出していたのです。
我が家からほんの10m北にいくと少し地面が高くなっていて、その辺りは掘れば弥生時代の遺跡が出てきます。
2000年くらい前の昔の人は河の傍に住んでいたようです。
周辺には素戔嗚尊神社という名称の小さな神社がいくつもあるのですが、素戔嗚尊(スサノオノミコト)は暴風雨の神様で、台風被害を鎮めるための神社の建立だったようです。
(関西で素戔嗚尊神社という呼称の神社が多い場所は洪水被害が甚大だった同じような土地柄とのこと。)
とまあ歴史的にみても、近くの河の堤防が決壊したら被害は避けられそうにないです。
日本中どこでもそうでしょうが、災害は他人事ではないです。
近くの河、普段は水量もわずかなのですが。








何かあったら、この子達を避難所に連れて行かなくてはならないのですが、それも大変そう。
この夏までいたみーちゃんの居場所を占拠するハッピーです。


買ってあげた猫ちぐらの上が気に入ったラッキーです。


夜はハッピーは猫ちぐらの下の部分に入って寝ています。
報道はほとんどされていませんが、台風19号で亡くなった動物たちも多かったのではないでしょうか。
被災地に一日でも早く平穏な日常が戻ることをお祈りいたします。