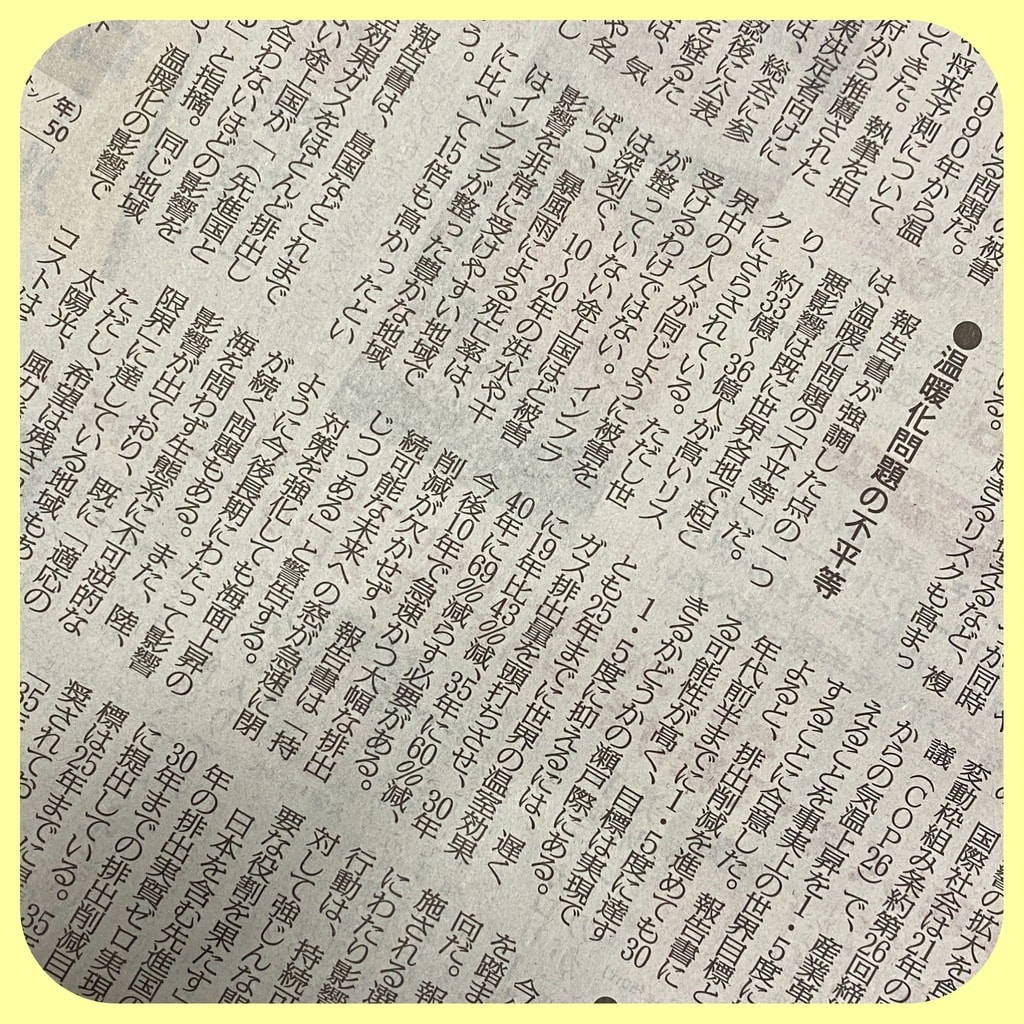大災害時代を迎え、耐震構造を施した高層ビルがそびえ立つようになりました。
高くそびえていて、人はその勇壮を見上げることもあります。
「ところが」です。
ふと気がつくのですが、高層ビルは下界のアリのような人間を見下ろしているだけで、人は見上げても「魂」を感じることが少ないのです。
それとは違い、自然は少しずつでもつねに生まれ変わっています。
あのときはなかったのに、今ではかすかな小川が流れるようになった。高く張っていた木の枝がなくなくなっている。・・・・・
だから、都会のビルとは違い、自然はいのちが通い毎年生まれ変わります。
そう感じながら、わたしは自分の生まれたふるさとで何十年も過ごしてきたのです。
ところが、高い山に登ったとき、そうでもなかったのかと思うようになりました。
自然さえもが、空から見れば結局は地上のことです。
動物もいつかは死にます。
木もいつかは朽ちるのです。
湖は干上がったり、埋まったります。
畑は放っておくとうっそうと茂る森になります。
もちろん、そびえるビルも永遠ではないのです。
じつは天体の月や太陽はその地球上の営みをすべて俯瞰しています。
持続可能な開発をして、環境と自然が共生する営みそのものは尊いことであり、否定されるべきことではけっしてありません。
しかしながら、私たちが下界で見ているものはいずれは滅びるのです。
対して、天体や宇宙は何億年も続く永遠というものでしょう。
現代社会はストレスフルな社会です。
人間関係が複雑化・高度化し、みんながけっこう傷つきやすくなっています。
また、人が日々の生活の中で出会う問題もすぐには解決しないようなことも多いのではないでしょうか。
解決しない不安や心配、悩みを抱えたままにしておくのは、ずっと重い荷物を背中にのせて歩いているようなものです。
一つの解決しにくい/解決できないことを考え続けたり、自分にとってイヤだったことを何度も思い出したりするのは、強いストレスを繰り返し受けているのと同じになります。
不安・心配や悩みを抱えすぎて限界に達しているのは、たとえばコップに水を注ぎ上の縁までいっぱいになっている状態にたとえることができます。うつ病などを患うことになります。
15人に一人は一生のうちでうつ病を経験すると考えられています。
少しでも揺らすと水がこぼれ出ます。これがいわゆる「バーン・アウト」になります。
ですから、水位を少しでも減らさなければなりません。つまり、不安や悩みから離れて、考えない時間をもつことが必要になります。
ところが、たいていの人は逆で、一つのことを考え続けたり、何度もイヤなことを思い出してしまうのです。
これではコップに水を注ぎ続けていることになります。
それではしんどいです。
人の心は、このようなコップのようなものですので、入ってくる水を減らし、入ってくる容量を空けておかなければなりません。
つまり、悩みや不安から距離をあけ、考えない時間をもつのはコップの水位を下げる効果があります。
水位が下がると、自分のことを客観視できることにもなります。
コップの水位を下げる方法とは、「もう限界だ」と感じたときに、好きなことにどっぷりとつかることでしょう。
テレビで好きな映画をどんどん見るとか、外界からの音を遮断するためヘッドフォンを付けて音楽をひたすら聴く、または単純作業でもいいので手を動かすようなことを黙々と続けると効果があるようです。
好きなことや単純作業を続けると、そちらに意識が向き、悩みや不安を忘れ、離れている状態になれるのです。
このようにして、好きなことに没頭して心の空きを増やしておき、明日のわたしに不安・悩みを託していきます。
そうすると、何かの拍子にふと解決の方法が見つかったり、支援者が現れたり、悩みや不安が気にならなくなったりすることもあるのです。
我を忘れて夢中になれる活動や好きなことを大事にしていきたのです。
わたしは縁あって教職について40年ほどになりますが、学校教育にかかわる仕事全般をするのが役割です。
ただし、わたしにはそれ以外にやる仕事があります。
ご縁のある教職をめざす学生または現職教員に、一人でも多くの子ども、保護者・地域の人から信頼される教師になってほしいという願いがあります。
出会った人に「あなたのおかげで教員になれた、教師としての今のわたしがある」と言っていただけるなら、何にも代えがたいやりがいです。
実際にいい先生になっている人に共通しているのは、「何のために教師をしているのか」という動機や目的がはっきりしています。
つまり、使命感をちゃんと認識できているのです。
「なんとなく教師をやっています」のではなく、使命感を確立して実践を重ねている人にお会いすると、あらためて、自らの心が洗われます。
教師になったのはその人の「天分」です。人はそれぞれ、何かの活動をする力・才能・特徴(天分)をもっています。天分を持っているのに、それが発揮されないこともあります。自分でフタをしてしまっています。
それが解き放たれるのは、自分だけがよければいいとするのではなく、与えられた天分を生かしきり、子どものことを思う時ではないでしょうか。
教師という人と児童生徒という人が関わり合う中で、相手がしあわせになることが自分の喜びになります。
自分もそうでありたいし、そのような教師が増えていけばいいなと思います。そのお手伝いをしたいというのがわたしの思いであり、使命です。
新型コロナウイルス感染防止が、ようやく下火になってきました。
もちろんまだ楽観視できる状況ではありません。「アフターコロナ」といっていいのか、「ウイズコロナ」というべきか迷うところです。
ただ、その問題とは別に、学校教育関係でいえば新型コロナウイルス渦の影響で不登校の児童生徒が増えたことは明らかな事実です。
2021年度実施の文科省調査では、全国の小中学生のおよそ24万人が不登校で、これは過去最多でした。
コロナ渦による休校、分散登校などで自宅学習をすることになった一方で、学校へ通うことが重荷になった児童生徒が増えたことが理由でしょう。
それ以外にも、低学年の子は「得体の知れない」ウイルスに恐怖を感じたのかもしれません。
不登校になった子は、その後どうするかというと、学校に再登校できることもあります。
学校の別室への登校を経て学級に入るようになった子もいます。
学年がかわりクラス替えをして登校できるようになる場合もあります。
もちろんすべて教職員の支援があってのことですが。
学校が無理なら、自治体のひらく「適応指導教室」に通う子がいます。
フリースクールに通う子もいます。
進学は、不登校生にとって一つの契機になることもあります。
通信制高校・単位制高校へ進学して、自分のペースで学習を進める子もいます。
ただ、費用面の問題があります。通信制高校・単位制高校、フリースクールも入学金や授業料がかかり、保護者にとって経済的な負担は少なくありません。
また、中学校の途中でボランティアが運営する学校へ行ったとしても、中学の卒業資格がもらえないという課題があります。
いま、細々とですが公立の夜間中学校通う子も出てきています。
公立の夜間中学校は、現在、事情があり義務教育が受けられなかった人が通うという役割から、渡日してきた外国籍の生徒に教育をする役割にシフトしてきています。年齢層もさまざまな人が集います。
そのような夜間中学校がほとんどですが、全国的に見ると不登校特例校の制度を受けた夜間中学校もあります。
ここは公立であり、義務教育学校なので費用も大きくはかかりません。しかし、今はまだ全国に20校ほどしかないのです。
ニーズはあるので、市町村が設置できるように財政補助が求められます。