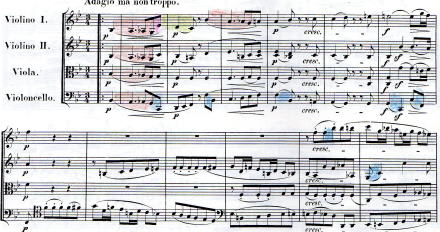10/15 私の音楽仲間 (624) ~ 私の室内楽仲間たち (597)
逆立ちで走るのだ
これまでの 『私の室内楽仲間たち』
関連記事 Beethoven の 四重奏曲 作品130
割り勘ドンブリ
不自由な輩め…
ドイツもこいつも…
最後の作品
酔いに任せて
知識も無しに作れるか!
お伴は忍者でござる
ふざけた曲さ
深刻めいた遊び
感じる殺気
逆立ちで走るのだ
[譜例]は、Beethoven の弦楽四重奏曲 変ロ長調
作品130 から、第Ⅵ楽章の最初の部分です。
一度ご覧いただいた、Vn.Ⅰのパート譜です。
関連記事 『最後の作品』

最終楽章は、舞曲調の気軽な足取りで、淀み
なく流れていきます。
「あの “いかめしい” 作曲家が最後に書いた
音楽とは思えない。」
そんな感想も、ときおり聞かれます。
[演奏例の音源]は、その少し先の部分。
しばらく行くと、次の[譜例]の箇所に差し掛かります。
(この[音源]では【17秒】の辺りです。)
まずチェロ、そして Viola が、前の音楽の、最後の
部分を繰り返す。 Vn.Ⅰも加わりますが、すぐ新しい
音楽が始まります。
↓

連続する3度の降下が特徴的ですね。
すると二段目の最後で、急に cresc. が現われる! 続いて
新しい音楽が、f の十六分音符で走り回ります。
この形、見覚えがありませんか? これまでも、以下の
記事で登場しています。
もうお解りですね。 正体は、第Ⅰ楽章の主部で
登場した “忍者” なのです。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

当初こそ、主題の “従者” 役に甘んじていました。
しかし他の楽章では、様々なテーマのモティーフと
して活躍することになる。
中には “逆立ち” までして、上下の向きが逆に
なっているものもあります。 今回もそうです。
この第Ⅵ楽章は、ロンド、あるいはロンドソナタ形式
ですから、色々なテーマが代わる代わる顔を出します。
ここでは、“忍者” が f で走り回る。 この主題全体
は、「単純な4音符モティーフだけで出来ている」…と
言ってもいいほどです。
さて、このテーマが現われる直前には、cresc. が
書かれていました。 なぜ?
おそらく、“場面の急転換” を強調するためでしょう。
「新しい音楽が突然 f で現われる」…演出も、それは
それで面白いのですが。
一昔前の Beethoven なら、cresc. は無しに、
いきなり f だけを書いたかもしれません。 でも
ここでは、音楽の流れはあくまでも自然です。
忍者を操る首領、頭目としての Beethoven。
その “眼” は、まだまだ健在なようです。
さて、先ほどの連続する3度の降下を見てみましょう。
役割としては、主題同士の繋ぎの部分にすぎないのですが。
↓

これに先立つ冒頭部分には、連続する3度の上昇が
ありましたね。 下の譜例のモティーフが “逆立ち” する
と、上の3度の降下になります。
↓ ↓

今回お読みいただいた、このような作業は、いわゆる
“アナリーゼ”。 楽曲の分析です。
その響きは、アカデミックで冷たい。
しかし貴方が演奏者の一員なら、それに止まってはいけない
でしょう。 問題は、「そこから何が得られるか?」…です。
机上の学問に終るのでは意味が無い。 いつも考えさせられ
る、難しい問題です。
今回も、それなりの収穫はありました。 でも、いつも
痛感することがある。 やり終えてみると、こんな作業が
すべて無駄に思えることが多いものです。
なぜなら、すべてが、いとも自然に行われているから。
大作曲家の手にかかると…。
大家は自然にして変幻自在。
凡人は策を弄して馬脚を露わす。