≪三島由紀夫と川端康成の『文章読本』≫
(2021年5月22日投稿)
今回のブログでは、三島由紀夫と川端康成の『文章読本』について紹介してみたい。
ひきつづき、名文とは何かについて、井上ひさしや中村明の著作をも参照しつつ、考えてみたい。
【三島由紀夫の『文章読本』はこちらから】


文章読本 (中公文庫)
【川端康成の『文章読本』はこちらから】


新文章読本
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
今まで“素人”向けの『文章読本』が多かったが、三島由紀夫は自ら“玄人”向けのそれを意図している。つまりレクトゥール(lecteurs、普通読者)から、リズール(liseurs、精読者)に導くために、『文章読本』を執筆した。
三島が大蔵省に勤務していた時、大臣の演説の草稿を、文学的に書いたところ、課長に下手だと言われ、事務官が改訂した。すると「感情や個性的なものから離れ、心の琴線に触れるような言葉は注意深く削除され、一定の地位にある人間が不特定多数の人々に話す独特の文体で綴られていた」「感心するほどの名文」ができあがっていたと回想している(三島由紀夫の『文章読本』中公文庫、1973年[1992年版]、8頁~10頁、および野口武彦の解説183頁参照のこと)。
三島は、文章の最高の目標を、格調と気品に置いていると明言している。そして、それらはあくまで古典的教養から生まれるものであり、古典時代の美と簡素は、いつの時代にも心をうつものであると信じていた。文体による現象の克服ということが文章の最後の理想であるかぎり、気品と格調はやはり文章の最後の理想となるであろうという(三島、1973年[1992年版]、154頁~155頁)。
そして、日本語の特質について次のように述べている。
「日本語の特質はものごとを指し示すよりも、ものごとの漂わす情緒や、事物のまわりに漂う雰囲気をとり出して見せるのに秀でています。そうして散文で綴られた日本の小説には、どこまでもこのような特質がつきまとって、どこかでその散文的特質をマイナスしつつ、しかも文体を豊かにしているのであります。」と述べている。
つまり、日本語の特質は、ものごとを指し示すよりも、情緒や雰囲気をとり出して見せるのに、秀でているというのである(三島、1973年[1992年版]、22頁および186頁)。
現代の日本人は、いまや七・五調の文章になじむことはできないが、それの持つ日本語独特のリズムは、われわれのどこかに巣くっている点を三島も指摘している。卑近な例でいえば、「注意一秒 怪我一生」「ハンドルは腕で握るな 心で握れ」といったキャッチフレーズ、標語や、「有楽町で逢いましょう」(歌・フランク永井、作詞・佐伯孝夫)といった歌のタイトルにも残っている(三島、1973年[1992年版]、22頁~23頁)。
日本文学の特質は、『源氏物語』などの平安朝文学に象徴されるように、女性的文学といってもよく、日本の根生(ねおい)の文学は、抽象概念の欠如からはじまったと三島由紀夫はみている。日本文学には、抽象概念の有効な作用である構成力、登場人物の精神的な形成に対する配慮が長らく見失われていたとし、男性的な世界、つまり男性独特の理知と論理と抽象概念との精神的世界は、長らく見捨てられてきたと三島はいう。
日本文学の風土は、古代から現代まで、男性的文学の要素が稀薄であり、抽象概念と構成力の男性的文学―対―感情と情念の女性的文学という対立は、そのまま散文と韻文との対決に置き換えられるとみる(三島、1973年[1992年版]、15頁、185頁)。
名文とは、明晰な文章であることを三島は力説している。鷗外は人に文章の秘伝を聞かれて、一に明晰、二に明晰、三に明晰と答えたといわれている。また、『赤と黒』や『恋愛論』で有名なスタンダールが『ナポレオン法典』を手本として文章を書き、稀有な明晰な文体を作ったといわれる。明晰な文章は、無味乾燥と紙一重であって、しかもそれとは反対のものである。
三島は鷗外の『寒山拾得』という小説を引用して、その文章が漢文的教養の上に成り立った、簡潔で清浄な文章で、名文であると賞賛している。とりわけ「水が来た」という一句に注目し、「現実を残酷なほど冷静に裁断して、よけいなものをぜんぶ剥ぎ取り、しかもいかにも効果的に見せないで、効果を強く出すという文章」は、鷗外独特のものであると解説している。鷗外のはなはだ節約された文体は「言葉を吝しむこと、金を吝しむがごとく」にして書かれた文体であるという(三島、1973年[1992年版]、41頁~47頁)。
川端康成と三島由紀夫は、作家としては師弟関係にあった。ただ、1969年、政治嫌いで、イデオロギー嫌いの川端が、「楯の会」一周年の式典祝辞を述べてほしいという依頼をにべもなく断ったのが原因で、二人の間に“しこり”ができ、それは1970年三島が割腹自殺するまで続いたようだ(それでも、三島の葬儀委員長は川端が引き受けた)。
作家の『文章読本』の中では、川端読本は一般に評判が悪い。ただ、川端読本の長所もある。美文と名文を区別した点は卓見であろう。
川端自ら、次のように述べている。
「美文と名文を区別することが、あるいはこの私の小論の使命かも知れぬ。美文は調子によって流れて、しかしその一字一句に自然と生命を忘れがちである。真の名文であれば、一字一句、魂あって生きるのではあるまいか」と(川端、1954年[1977年版]、18頁)。
この川端の業績を、中村明は『名文』において評価し、
「名文は一字一句に魂があって生きている(川端50)のに対し、美文のほうは調子に流れて内容が空疎になりやすい。」と、名文と美文の区別について、川端説を受け容れている(中村明『名文』ちくま学芸文庫、1993年、31頁)。
ところで、中村明は、「移りゆく名文像」と題して、名文はその定義の上で、“不易”という性格を持つはずであるが、具体的にどの文章を名文と考えるかという現実の判断のほうには時代の風、つまり時代時代の趣味、思想、感情によって変わるのはやむをえないとしている。名文か悪文を認定する規準は時代に影響されることは、たとえば森鷗外の『源氏物語』に対する評価にもよく表れている。
「人もあろうに明治の大文豪森鷗外が、事もあろうに日本文学を代表するとさえ見られているあの源氏物語をつかまえて悪文呼ばわりした」のである。通史的に見れば、名文評価には主観性とともにそこには時代的な流行性がのぞいている。
大文章と言われる源氏には、
①主語がめったに現れない
②地の文と会話文との区別がはっきりしない
③文が切れないという性格がある。
出来事の隈ぐままで描き、心の襞を語りつくす文章ではあるが、ともかく切れない文章である。文章は大きくゆったりとしたリズムで流れていき、その間に切れめが感じられないといわれる。
対句的表現を折り込んだ和漢混淆文体のやや調子の高い文章になじんだ者には、源氏流の文章は歯切れの悪い印象を与え、簡潔、明晰を志向する時代の好尚には合わない。この点で、鷗外の『源氏物語』への評価もうなづける点がないわけではない。というのは鷗外は文章を「明晰」の一点に賭けた作家であるから(中村、1993年、61頁~63頁)。
判りやすいという点は、名文の条件として最も人気のある項目である。能文の三要素として、「遒勁」「流暢」に先立って、「明晰」という点を第一にあげる。また、スマートな文章心得として「3Cの原則」があるといわれる。すなわち、clear(はっきりと)、correct(正しく)、concise(簡潔に)がそれである。このように「明晰さ」というものがいかに優先されてきたかがわかる(中村、1993年、38頁~39頁)。
【中村明『名文』ちくま学芸文庫はこちらから】

名文 (ちくま学芸文庫)
また、「簡潔に」という点では、川端読本も、「文章とは、感動の発する儘に、自己の思うことを素直に簡潔に解り易くのべたものを良しとする。古来文章の理範として「華を去り実に就く」といわれたのも、この所であろうか。文章の第一条件は、この簡潔、平明ということであり、如何なる美文も、若し人の理解を妨げたならば、卑俗な拙文にも劣るかもしれない。」と述べている。このように川端は文章の第一条件として、簡潔を挙げている(川端、1954年[1977年版]、17頁)。
川端康成という作家は、「餅のような肌」といった紋切り型の表現ではなく、さすがに「白い陶器に薄紅を刷(は)いたような」(『雪国』)といった秀逸な比喩を用いる作家だけのことはある。
また、商業文においても、簡潔さの重要性をよく説かれる。つまり、
「商業文で大切なのは、まず第一に正確さ、それに加えて「カメレオン」です」とよく強調される。カメレオンとは、カンケツ(簡潔)、メイリョウ(明瞭)、レイ(礼)にかなう、オンケン(穏健)の、四つの心得の頭音をつないだものを意味する(井上ひさし『自家製 文章読本』新潮文庫、1987年、64頁、67頁)。
【井上ひさし『自家製 文章読本』新潮文庫はこちらから】

自家製 文章読本 (新潮文庫)
ところで、谷崎・川端両大家は、志賀直哉の、彫琢、簡潔、達意、平明な文体を賞賛している。川端は、「その作者が全く浮かばぬほど、独立した完璧の文章である。文章の個性そのものに作者の刻印があるので、名文とは作者から独立したこのような文章をいうのであろう」と、志賀の『城の崎にて』を評言している(川端、1954年[1977年版]、40頁)。
また、谷崎は、「(『城の崎にて』の文章は)簡にして要を得てゐるのですから、此のくらゐ実用的な文章はありません」。また「小説に使ふ文章で、他の所謂実用に役立たない文章はなく、実用に使ふ文章で、小説に役立たないものはない」といっている(谷崎潤一郎『文章読本』中公文庫、1975年[1992年版]、24頁、26頁)。
ただ井上ひさしは、この両大家の、簡潔さや平明さへの賛辞的論法を推し進めていくと、「報知新聞」の芸能人窃盗事件の記事や、「日刊アルバイトニュース」の文も名文になってしまうと皮肉っている(井上、1987年、28頁~30頁)。
また中村明によれば、小林秀雄の文章を悪文とみなしていない。
「冷酷な抒情の閃く一行一行を書きすてた川端康成も、一文一文に過重の意味をこめて人をまどわせ、結局は心酔させてしまう小林秀雄も、それぞれに個性的な文章を綴りながら、一度も悪文視された例を知らない」という。
ただ、中村明の悪文の定義は特異である。悪文は個性の強い文章であり、あくの強い文章、つまりアク文だというのである。悪文は名文の対概念ではなく、本来の悪文は表層の性格をはっきり持った特殊な名文であると考え、名文と対極にあるのは、駄文であると理解している(中村、1993年、28頁~29頁)。
そして、三島由紀夫は、小林秀雄の批評を高く評価している。日本語における論理性の稀薄さと、批評の対象とすべき近代日本の浅薄さとのために、日本の評論家は批評の文章・文体を作ることがなかなかできなかったが、一人の天才、小林秀雄によって、それが樹立されたと三島はみている。
小林の文体の特徴は、近代の批評家で最も見事な評論の文章を書いたフランスのポール・ヴァレリーと同様に、論理的ありながらも、日本の伝統の感覚的思考の型を忘れずに固執したという強さにあるという(三島、1973年[1992年版]、86頁~87頁)。
三島は鷗外の文体を絶賛している。
「明治44年(1911年)、49歳の鷗外は、「妄想」や「心中」ののち、いよいよ名作「雁」を発表する。
「雁」を読み返すたびにいつも思ふことであるが、鷗外の文体ほど、日本のトリヴィアルな現実の断片から、世界思潮の大きな鳥瞰図まで、日本的な小道具から壮大な風景まで、自由自在に無差別にとり入れて、しかも少しもそこに文体の統一性を損ねないやうな文体といふものを、鷗外以後の小説家が持つたかといふことである。
適当な例ではないかもしれぬが、堀辰雄氏の文体は、ハイカラな軽井沢を描くことはできても、東京の雑沓を描くには適せず、谷崎潤一郎氏の文体は又、あれほどすべてを描きながら、抽象的思考には適しなかつた。どの作家も、鷗外ほど、日本の雑然たる近代そのものを芸術的に包摂する文体を持つた作家はなかつた。」(三島由紀夫「森鷗外」『文芸読本 森鷗外』河出書房新社所収、1976年、124頁)
堀辰雄の文体は、ハイカラな軽井沢の描写には向いているが、東京の雑沓を描くには不適で、谷崎潤一郎の文体は抽象的思考には適しなかったと三島は批評している。それに対して、鷗外の文体は、「近代そのものを芸術的に包摂する文体」で、「日本のトリヴィアルな現実の断片から、世界思潮の大きな鳥瞰図まで」「自由自在に無差別にとり入れ」たという。
三島は、「方言の文章について」という一文をしたためている。その中で、谷崎潤一郎の『細雪』がもし東京弁で書かれたところを想像すれば、方言というものが文学の中でどれだけ大きい力をもっているかがわかるという。そして『細雪』の翻訳がこのような方言の魅力を伝えなかったら、どれだけ効果を薄くするか想像にあまりあるとする。
谷崎は生粋の江戸っ子であるが、上方に移住してからこの方言の面白さに心を奪われ、関西弁の小説を書いた。『卍』はその関西弁で書かれた傑作である。この小説の構造は、あの独特な関西弁を除外しては考えられないが、谷崎はこの『卍』を書くにあたっては、大阪生まれの助手を使ったそうである。
そして三島自身は、その谷崎に比べて、「私の如きなまけ者は、『潮騒』という小説を書くときには、いったん全部標準語で会話を書き、それをモデルの島出身の人に、全部なおしてもらったのであります。」とその『文章読本』で記している(三島、1973年[1992年版]、177頁~178頁)。
谷崎にしても、三島にしても、一流の作家というものは、いかにその文体や会話に神経をつかっているかということが察せられるエビソードである。
「最後に、氏の「文章読本」は、日本の作文教育に携はる人たちにぜひ読んでもらひたい本であつて、谷崎氏が自分の好みに偏せず、古典から現代にいたる各種の文章の異なる魅力を、公平に客観的にみとめつつ、かつ自分の好みを円満に主張してゐる点で、日本の作文教育が陥りがちな偏向の、至上の妙薬になると思ふ。といふのは私自身、小学校の誤つた報告的リアリズム一辺倒の作文教育にいぢめられ、のち中学に入つて、この「文章読本」を読んで、はじめて文章の広野へ走り出したといふ何ともいへない喜びを味はつた経験があるからである。」(『文芸読本 谷崎潤一郎』河出書房新社、1977年[1981年版]、25頁)。
という。つまり、古典から現代にいたる各種の文章の異なる魅力を、公平に客観的にみとめつつ、かつ自分の好みを円満に主張している点を高く評価している。三島は、谷崎の『文章読本』を読んで、はじめて文章の広野へ走り出したという喜びを味わったと述懐している。
川端による各作家の文体批評は、的確で興味深い内容である。たとえば、宇野浩二、武者小路実篤、芥川龍之介、菊池寛、志賀直哉、久保田万太郎、里見弴の文章について、次のように論じている。
「たとえば宇野浩二氏の文章は「文語」の型を大胆に破って、一種の新しい「口語」を発見したという点でだけも永久に残るものであろう。武者小路氏の文章もまた同様である。
芥川竜之介氏や菊池寛氏は、漢語に頼ることの多かった文章家である。
漢語のあるものは、すでに言葉の生命が硬化して平明、新鮮、繊細、柔軟、具象、情感等を生命とする文芸創作の用語としては歓迎すべきものではないが、それに新しい秩序を与えたのは、芥川氏の功績であった。芥川氏は言葉の選び方が精厳で、その潔癖さでは泉鏡花氏と比肩されるであろう。
菊池寛氏は、力強く簡潔な文章を生み出した。文芸作品の文章に、普遍、通俗の重大要素を打ち込んだ功績は不滅ともいえようか。
志賀直哉氏の文章は、近代文章の模範とされている。志賀氏の文章を、理性の詩とすれば、情緒の詩は久保田万太郎氏の文章であろう。
里見弴氏は古い日本文章の文脈の上に、近代のリズムを加えて、生命を吹きこんだ。」
(川端康成『新文章読本』新潮文庫、1954年[1977年版]、57頁~58頁)。
そして、谷崎潤一郎と佐藤春夫の文章を、次のような比喩を用いて、理解している。
「谷崎潤一郎氏の文章が滔々たる大河とすれば、佐藤春夫氏の文章は水清らかな小川であ
る。両氏共に想像が豊かで連想が賑かで、視点の細かい文章を書くが、谷崎氏が稍々「説
明的」であるとすれば、佐藤氏は稍々「表現的」であるといえるかもしれない。表現的というのは、より多くの主観的というほどの意味である。つまり、文章の末節にまで作者の神経なり感情なりが息づいているのである。描く気持の裏に歌う気持が流れているのである。そしていわば作品が一元的なのである。作品の情操とか感懐とかいう一色の空気に、何もかもが包まれているのである。この点で佐藤氏の文章は室生犀星氏(前期の作品は除く)、永井荷風氏の文章に似ている」(川端、1954年[1977年版]、74頁)。
谷崎の文章が滔々たる大河で、「説明的」であるのに対して、佐藤の文章は水清らかな小川で、「表現的、主観的」で、室生犀星や永井荷風の文章に似ているという。
宇野浩二や武者小路実篤の文章は、一種新しい「口語」を発見したといい、芥川龍之介や菊池寛は、漢語に頼ることが多かった文章家であると捉え、芥川は言葉の選び方が精厳で、菊池は力強く簡潔な文章を生み出した。志賀直哉の文章は、近代文章の模範とされ、理性の詩と形容でき、それに対して久保田万太郎のそれは情緒の詩であった。また里見弴はその文章に近代のリズムを加えたという。
各作家の文章に対して、川端康成特有の“感覚的”理解が示されている。
(2021年5月22日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、三島由紀夫と川端康成の『文章読本』について紹介してみたい。
ひきつづき、名文とは何かについて、井上ひさしや中村明の著作をも参照しつつ、考えてみたい。
【三島由紀夫の『文章読本』はこちらから】

文章読本 (中公文庫)
【川端康成の『文章読本』はこちらから】

新文章読本
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・三島由紀夫の『文章読本』について
・明晰な文章について
・『文章読本』に関しての川端康成と三島由紀夫
・美文と名文の区別について
・三島による谷崎の『文章読本』評について
・川端康成の『新文章読本』について
三島由紀夫の『文章読本』について
今まで“素人”向けの『文章読本』が多かったが、三島由紀夫は自ら“玄人”向けのそれを意図している。つまりレクトゥール(lecteurs、普通読者)から、リズール(liseurs、精読者)に導くために、『文章読本』を執筆した。
三島が大蔵省に勤務していた時、大臣の演説の草稿を、文学的に書いたところ、課長に下手だと言われ、事務官が改訂した。すると「感情や個性的なものから離れ、心の琴線に触れるような言葉は注意深く削除され、一定の地位にある人間が不特定多数の人々に話す独特の文体で綴られていた」「感心するほどの名文」ができあがっていたと回想している(三島由紀夫の『文章読本』中公文庫、1973年[1992年版]、8頁~10頁、および野口武彦の解説183頁参照のこと)。
三島は、文章の最高の目標を、格調と気品に置いていると明言している。そして、それらはあくまで古典的教養から生まれるものであり、古典時代の美と簡素は、いつの時代にも心をうつものであると信じていた。文体による現象の克服ということが文章の最後の理想であるかぎり、気品と格調はやはり文章の最後の理想となるであろうという(三島、1973年[1992年版]、154頁~155頁)。
そして、日本語の特質について次のように述べている。
「日本語の特質はものごとを指し示すよりも、ものごとの漂わす情緒や、事物のまわりに漂う雰囲気をとり出して見せるのに秀でています。そうして散文で綴られた日本の小説には、どこまでもこのような特質がつきまとって、どこかでその散文的特質をマイナスしつつ、しかも文体を豊かにしているのであります。」と述べている。
つまり、日本語の特質は、ものごとを指し示すよりも、情緒や雰囲気をとり出して見せるのに、秀でているというのである(三島、1973年[1992年版]、22頁および186頁)。
現代の日本人は、いまや七・五調の文章になじむことはできないが、それの持つ日本語独特のリズムは、われわれのどこかに巣くっている点を三島も指摘している。卑近な例でいえば、「注意一秒 怪我一生」「ハンドルは腕で握るな 心で握れ」といったキャッチフレーズ、標語や、「有楽町で逢いましょう」(歌・フランク永井、作詞・佐伯孝夫)といった歌のタイトルにも残っている(三島、1973年[1992年版]、22頁~23頁)。
日本文学の特質は、『源氏物語』などの平安朝文学に象徴されるように、女性的文学といってもよく、日本の根生(ねおい)の文学は、抽象概念の欠如からはじまったと三島由紀夫はみている。日本文学には、抽象概念の有効な作用である構成力、登場人物の精神的な形成に対する配慮が長らく見失われていたとし、男性的な世界、つまり男性独特の理知と論理と抽象概念との精神的世界は、長らく見捨てられてきたと三島はいう。
日本文学の風土は、古代から現代まで、男性的文学の要素が稀薄であり、抽象概念と構成力の男性的文学―対―感情と情念の女性的文学という対立は、そのまま散文と韻文との対決に置き換えられるとみる(三島、1973年[1992年版]、15頁、185頁)。
明晰な文章について
名文とは、明晰な文章であることを三島は力説している。鷗外は人に文章の秘伝を聞かれて、一に明晰、二に明晰、三に明晰と答えたといわれている。また、『赤と黒』や『恋愛論』で有名なスタンダールが『ナポレオン法典』を手本として文章を書き、稀有な明晰な文体を作ったといわれる。明晰な文章は、無味乾燥と紙一重であって、しかもそれとは反対のものである。
三島は鷗外の『寒山拾得』という小説を引用して、その文章が漢文的教養の上に成り立った、簡潔で清浄な文章で、名文であると賞賛している。とりわけ「水が来た」という一句に注目し、「現実を残酷なほど冷静に裁断して、よけいなものをぜんぶ剥ぎ取り、しかもいかにも効果的に見せないで、効果を強く出すという文章」は、鷗外独特のものであると解説している。鷗外のはなはだ節約された文体は「言葉を吝しむこと、金を吝しむがごとく」にして書かれた文体であるという(三島、1973年[1992年版]、41頁~47頁)。
『文章読本』に関しての川端康成と三島由紀夫
川端康成と三島由紀夫は、作家としては師弟関係にあった。ただ、1969年、政治嫌いで、イデオロギー嫌いの川端が、「楯の会」一周年の式典祝辞を述べてほしいという依頼をにべもなく断ったのが原因で、二人の間に“しこり”ができ、それは1970年三島が割腹自殺するまで続いたようだ(それでも、三島の葬儀委員長は川端が引き受けた)。
美文と名文の区別について
作家の『文章読本』の中では、川端読本は一般に評判が悪い。ただ、川端読本の長所もある。美文と名文を区別した点は卓見であろう。
川端自ら、次のように述べている。
「美文と名文を区別することが、あるいはこの私の小論の使命かも知れぬ。美文は調子によって流れて、しかしその一字一句に自然と生命を忘れがちである。真の名文であれば、一字一句、魂あって生きるのではあるまいか」と(川端、1954年[1977年版]、18頁)。
この川端の業績を、中村明は『名文』において評価し、
「名文は一字一句に魂があって生きている(川端50)のに対し、美文のほうは調子に流れて内容が空疎になりやすい。」と、名文と美文の区別について、川端説を受け容れている(中村明『名文』ちくま学芸文庫、1993年、31頁)。
ところで、中村明は、「移りゆく名文像」と題して、名文はその定義の上で、“不易”という性格を持つはずであるが、具体的にどの文章を名文と考えるかという現実の判断のほうには時代の風、つまり時代時代の趣味、思想、感情によって変わるのはやむをえないとしている。名文か悪文を認定する規準は時代に影響されることは、たとえば森鷗外の『源氏物語』に対する評価にもよく表れている。
「人もあろうに明治の大文豪森鷗外が、事もあろうに日本文学を代表するとさえ見られているあの源氏物語をつかまえて悪文呼ばわりした」のである。通史的に見れば、名文評価には主観性とともにそこには時代的な流行性がのぞいている。
大文章と言われる源氏には、
①主語がめったに現れない
②地の文と会話文との区別がはっきりしない
③文が切れないという性格がある。
出来事の隈ぐままで描き、心の襞を語りつくす文章ではあるが、ともかく切れない文章である。文章は大きくゆったりとしたリズムで流れていき、その間に切れめが感じられないといわれる。
対句的表現を折り込んだ和漢混淆文体のやや調子の高い文章になじんだ者には、源氏流の文章は歯切れの悪い印象を与え、簡潔、明晰を志向する時代の好尚には合わない。この点で、鷗外の『源氏物語』への評価もうなづける点がないわけではない。というのは鷗外は文章を「明晰」の一点に賭けた作家であるから(中村、1993年、61頁~63頁)。
判りやすいという点は、名文の条件として最も人気のある項目である。能文の三要素として、「遒勁」「流暢」に先立って、「明晰」という点を第一にあげる。また、スマートな文章心得として「3Cの原則」があるといわれる。すなわち、clear(はっきりと)、correct(正しく)、concise(簡潔に)がそれである。このように「明晰さ」というものがいかに優先されてきたかがわかる(中村、1993年、38頁~39頁)。
【中村明『名文』ちくま学芸文庫はこちらから】

名文 (ちくま学芸文庫)
また、「簡潔に」という点では、川端読本も、「文章とは、感動の発する儘に、自己の思うことを素直に簡潔に解り易くのべたものを良しとする。古来文章の理範として「華を去り実に就く」といわれたのも、この所であろうか。文章の第一条件は、この簡潔、平明ということであり、如何なる美文も、若し人の理解を妨げたならば、卑俗な拙文にも劣るかもしれない。」と述べている。このように川端は文章の第一条件として、簡潔を挙げている(川端、1954年[1977年版]、17頁)。
川端康成という作家は、「餅のような肌」といった紋切り型の表現ではなく、さすがに「白い陶器に薄紅を刷(は)いたような」(『雪国』)といった秀逸な比喩を用いる作家だけのことはある。
また、商業文においても、簡潔さの重要性をよく説かれる。つまり、
「商業文で大切なのは、まず第一に正確さ、それに加えて「カメレオン」です」とよく強調される。カメレオンとは、カンケツ(簡潔)、メイリョウ(明瞭)、レイ(礼)にかなう、オンケン(穏健)の、四つの心得の頭音をつないだものを意味する(井上ひさし『自家製 文章読本』新潮文庫、1987年、64頁、67頁)。
【井上ひさし『自家製 文章読本』新潮文庫はこちらから】

自家製 文章読本 (新潮文庫)
ところで、谷崎・川端両大家は、志賀直哉の、彫琢、簡潔、達意、平明な文体を賞賛している。川端は、「その作者が全く浮かばぬほど、独立した完璧の文章である。文章の個性そのものに作者の刻印があるので、名文とは作者から独立したこのような文章をいうのであろう」と、志賀の『城の崎にて』を評言している(川端、1954年[1977年版]、40頁)。
また、谷崎は、「(『城の崎にて』の文章は)簡にして要を得てゐるのですから、此のくらゐ実用的な文章はありません」。また「小説に使ふ文章で、他の所謂実用に役立たない文章はなく、実用に使ふ文章で、小説に役立たないものはない」といっている(谷崎潤一郎『文章読本』中公文庫、1975年[1992年版]、24頁、26頁)。
ただ井上ひさしは、この両大家の、簡潔さや平明さへの賛辞的論法を推し進めていくと、「報知新聞」の芸能人窃盗事件の記事や、「日刊アルバイトニュース」の文も名文になってしまうと皮肉っている(井上、1987年、28頁~30頁)。
また中村明によれば、小林秀雄の文章を悪文とみなしていない。
「冷酷な抒情の閃く一行一行を書きすてた川端康成も、一文一文に過重の意味をこめて人をまどわせ、結局は心酔させてしまう小林秀雄も、それぞれに個性的な文章を綴りながら、一度も悪文視された例を知らない」という。
ただ、中村明の悪文の定義は特異である。悪文は個性の強い文章であり、あくの強い文章、つまりアク文だというのである。悪文は名文の対概念ではなく、本来の悪文は表層の性格をはっきり持った特殊な名文であると考え、名文と対極にあるのは、駄文であると理解している(中村、1993年、28頁~29頁)。
そして、三島由紀夫は、小林秀雄の批評を高く評価している。日本語における論理性の稀薄さと、批評の対象とすべき近代日本の浅薄さとのために、日本の評論家は批評の文章・文体を作ることがなかなかできなかったが、一人の天才、小林秀雄によって、それが樹立されたと三島はみている。
小林の文体の特徴は、近代の批評家で最も見事な評論の文章を書いたフランスのポール・ヴァレリーと同様に、論理的ありながらも、日本の伝統の感覚的思考の型を忘れずに固執したという強さにあるという(三島、1973年[1992年版]、86頁~87頁)。
三島は鷗外の文体を絶賛している。
「明治44年(1911年)、49歳の鷗外は、「妄想」や「心中」ののち、いよいよ名作「雁」を発表する。
「雁」を読み返すたびにいつも思ふことであるが、鷗外の文体ほど、日本のトリヴィアルな現実の断片から、世界思潮の大きな鳥瞰図まで、日本的な小道具から壮大な風景まで、自由自在に無差別にとり入れて、しかも少しもそこに文体の統一性を損ねないやうな文体といふものを、鷗外以後の小説家が持つたかといふことである。
適当な例ではないかもしれぬが、堀辰雄氏の文体は、ハイカラな軽井沢を描くことはできても、東京の雑沓を描くには適せず、谷崎潤一郎氏の文体は又、あれほどすべてを描きながら、抽象的思考には適しなかつた。どの作家も、鷗外ほど、日本の雑然たる近代そのものを芸術的に包摂する文体を持つた作家はなかつた。」(三島由紀夫「森鷗外」『文芸読本 森鷗外』河出書房新社所収、1976年、124頁)
堀辰雄の文体は、ハイカラな軽井沢の描写には向いているが、東京の雑沓を描くには不適で、谷崎潤一郎の文体は抽象的思考には適しなかったと三島は批評している。それに対して、鷗外の文体は、「近代そのものを芸術的に包摂する文体」で、「日本のトリヴィアルな現実の断片から、世界思潮の大きな鳥瞰図まで」「自由自在に無差別にとり入れ」たという。
三島は、「方言の文章について」という一文をしたためている。その中で、谷崎潤一郎の『細雪』がもし東京弁で書かれたところを想像すれば、方言というものが文学の中でどれだけ大きい力をもっているかがわかるという。そして『細雪』の翻訳がこのような方言の魅力を伝えなかったら、どれだけ効果を薄くするか想像にあまりあるとする。
谷崎は生粋の江戸っ子であるが、上方に移住してからこの方言の面白さに心を奪われ、関西弁の小説を書いた。『卍』はその関西弁で書かれた傑作である。この小説の構造は、あの独特な関西弁を除外しては考えられないが、谷崎はこの『卍』を書くにあたっては、大阪生まれの助手を使ったそうである。
そして三島自身は、その谷崎に比べて、「私の如きなまけ者は、『潮騒』という小説を書くときには、いったん全部標準語で会話を書き、それをモデルの島出身の人に、全部なおしてもらったのであります。」とその『文章読本』で記している(三島、1973年[1992年版]、177頁~178頁)。
谷崎にしても、三島にしても、一流の作家というものは、いかにその文体や会話に神経をつかっているかということが察せられるエビソードである。
三島による谷崎の『文章読本』評について
「最後に、氏の「文章読本」は、日本の作文教育に携はる人たちにぜひ読んでもらひたい本であつて、谷崎氏が自分の好みに偏せず、古典から現代にいたる各種の文章の異なる魅力を、公平に客観的にみとめつつ、かつ自分の好みを円満に主張してゐる点で、日本の作文教育が陥りがちな偏向の、至上の妙薬になると思ふ。といふのは私自身、小学校の誤つた報告的リアリズム一辺倒の作文教育にいぢめられ、のち中学に入つて、この「文章読本」を読んで、はじめて文章の広野へ走り出したといふ何ともいへない喜びを味はつた経験があるからである。」(『文芸読本 谷崎潤一郎』河出書房新社、1977年[1981年版]、25頁)。
という。つまり、古典から現代にいたる各種の文章の異なる魅力を、公平に客観的にみとめつつ、かつ自分の好みを円満に主張している点を高く評価している。三島は、谷崎の『文章読本』を読んで、はじめて文章の広野へ走り出したという喜びを味わったと述懐している。
川端康成の『新文章読本』について
川端による各作家の文体批評は、的確で興味深い内容である。たとえば、宇野浩二、武者小路実篤、芥川龍之介、菊池寛、志賀直哉、久保田万太郎、里見弴の文章について、次のように論じている。
「たとえば宇野浩二氏の文章は「文語」の型を大胆に破って、一種の新しい「口語」を発見したという点でだけも永久に残るものであろう。武者小路氏の文章もまた同様である。
芥川竜之介氏や菊池寛氏は、漢語に頼ることの多かった文章家である。
漢語のあるものは、すでに言葉の生命が硬化して平明、新鮮、繊細、柔軟、具象、情感等を生命とする文芸創作の用語としては歓迎すべきものではないが、それに新しい秩序を与えたのは、芥川氏の功績であった。芥川氏は言葉の選び方が精厳で、その潔癖さでは泉鏡花氏と比肩されるであろう。
菊池寛氏は、力強く簡潔な文章を生み出した。文芸作品の文章に、普遍、通俗の重大要素を打ち込んだ功績は不滅ともいえようか。
志賀直哉氏の文章は、近代文章の模範とされている。志賀氏の文章を、理性の詩とすれば、情緒の詩は久保田万太郎氏の文章であろう。
里見弴氏は古い日本文章の文脈の上に、近代のリズムを加えて、生命を吹きこんだ。」
(川端康成『新文章読本』新潮文庫、1954年[1977年版]、57頁~58頁)。
そして、谷崎潤一郎と佐藤春夫の文章を、次のような比喩を用いて、理解している。
「谷崎潤一郎氏の文章が滔々たる大河とすれば、佐藤春夫氏の文章は水清らかな小川であ
る。両氏共に想像が豊かで連想が賑かで、視点の細かい文章を書くが、谷崎氏が稍々「説
明的」であるとすれば、佐藤氏は稍々「表現的」であるといえるかもしれない。表現的というのは、より多くの主観的というほどの意味である。つまり、文章の末節にまで作者の神経なり感情なりが息づいているのである。描く気持の裏に歌う気持が流れているのである。そしていわば作品が一元的なのである。作品の情操とか感懐とかいう一色の空気に、何もかもが包まれているのである。この点で佐藤氏の文章は室生犀星氏(前期の作品は除く)、永井荷風氏の文章に似ている」(川端、1954年[1977年版]、74頁)。
谷崎の文章が滔々たる大河で、「説明的」であるのに対して、佐藤の文章は水清らかな小川で、「表現的、主観的」で、室生犀星や永井荷風の文章に似ているという。
宇野浩二や武者小路実篤の文章は、一種新しい「口語」を発見したといい、芥川龍之介や菊池寛は、漢語に頼ることが多かった文章家であると捉え、芥川は言葉の選び方が精厳で、菊池は力強く簡潔な文章を生み出した。志賀直哉の文章は、近代文章の模範とされ、理性の詩と形容でき、それに対して久保田万太郎のそれは情緒の詩であった。また里見弴はその文章に近代のリズムを加えたという。
各作家の文章に対して、川端康成特有の“感覚的”理解が示されている。












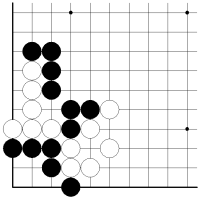







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます