《饗庭孝男の小林秀雄論 その2》
(2021年6月6日投稿)
今回のブログでは、饗庭孝男『小林秀雄とその時代』(小沢書店、1997年)において、論じられた日本古典論について解説しておきたい。
まず、「当麻」「平家物語」「徒然草」、そして「西行」および「実朝」といった小林秀雄の古典論について、饗庭孝男がどのように捉えていたのかを説明してゆく。
そして、小林秀雄の大著『本居宣長』と言語観について、饗庭がどのように理解しているのかについて、述べてみたい。
【饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店はこちらから】

小林秀雄とその時代
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
小林秀雄にとって開戦の翌年から、昭和18年にかけては、古典論を書くことに専念した期間であった。
「当麻」「無常といふ事」「平家物語」「徒然草」、そして「西行」が昭和17年に、「実朝」が翌年である。
その間、昭和17年の10月には、「近代の超克」(『文學界』)に出席している。この大座談会における小林の発言は、古典論と並行している時だけに多くの示唆をふくんでいると、饗庭はみている。
小林は、歴史は変化であり、進歩と見なす考えに懐疑を覚え、「何時も同じもの」があり、それを貫く人の書いた作品を「古典」とし、「美学」と呼び、現代にいても「古人の達したより以上のものは絶対にできんといふ謙遜な気持」をもつことを力説している。
ここに歴史から古典への移行が期せずしてかたられている趣きがある。
「当麻」は、形ある美しさへの直接経験にのみ認識の根拠を求めようとする思想から書かれたものである。古典論のはじめが、身体的行為としての能の表現についてのエッセイであることは、その意味で象徴的である。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、184頁~185頁)
沈黙のなかで戦争という歴史の劇を生きながら、小林は言いようのない「孤独」を感じていたはずである。
「徒然草」から「西行」「実朝」に至る評論を一貫して流れるものは、抗しがたい歴史(必然)の運命を前にした自意識の「孤独」が奏でる、あるパセティックな短調とでもいうべき、暗く低い旋律であったと、饗庭は捉えている。
兼好も西行も、実朝のいずれもが戦乱のなかで歴史(必然)に打ち砕かれる思想を「孤独」の裡に織っていた。そこに小林がおのれの姿を重ね、古典を現前させ、あるいは逆に古典のなかにおのれを織りこみ、いわば時をこえて生きつづける存在の「あかし」を願おうと考えたとする。
「当麻」は、そうした巨大な現実を前にし、それに拮抗しようとする小林の態度をものがたる古典論の「序奏」とでもいうべき作品であった。
この小さな「形」のなかに、「近代」日本にたいする自らをとおした総括的反省がこめられているとともに、歴史の闇のなかの「孤独」を「花」と化し、逆にそこに自らの「歴史」をイメージによって現象させようとした小林の意図が息づいているとみる。
「当麻」につづいて書かれた「平家物語」のとらえ方についても、「当麻」と同じく、イメージによる把握と「肉体の動きに則つて観念の動きを修正」しようとする小林の意図を看取できるようだ。
「言葉の故郷は肉体だ」とのべた思考が「当麻」と同じく、この「平家物語」をもつらぬいているという。
(こういう思考とは、かつて志賀直哉に小林が見た「自然」と「行為」の表現にたいする讃嘆の延長線上にあるものである。小林が志賀直哉論以来、歴史(自然)認識をへて対象のなかに、おのれの思考と共振するものをよみ、いかにそれをリアリティあるものとしているか否かが、そこでは問題であった。小林は『平家物語』に、いわば自らの思考と出会うもののみをイメージで表現した)
一方、『徒然草』に対しては、別の接近の仕方を行った。わずか2頁半のこのエッセイで小林が描いたものは、小林が批評行為の中心においた「見る」ことに徹した兼好の態度であった。
小林は「生死」と「自然」を見、それを表現するモラリスト的な形式の見事さと文体に感嘆した。「見る」行為と表現の形式と文体への関心こそ、このエッセイの本質であると、饗庭は理解している。
ところが、「西行」と「実朝」は、これまでの、対象にたいする独自な接近と、その切り口の提示が身上であった古典論と趣きをことにするようだ。そこには対象の全体を小林なりの視角からとらえようとする意図がある。
小林は西行を描くにあたって、「根は頑丈で執拗な」人間であると見た。小林が見ようとしたのは、「生得」の詩人であるばかりでなく、たとえば「世の中を反き果てぬといひおかんと思ひしるべき人はなくとも」という歌にみられる意志をつらぬこうとする勁い人間であった。
この視角から西行は「自ら進んで世に反いた者の世俗に対する嘲笑と内に湧き上る希望との渦巻く青春の歌」をうたう人として映じ、「女々しい感傷」をもたぬ「空前の内省家」となる。その苦い内省によって、そのまま放胆で自在な、しかも正確な歌をよむ詩人と、小林は考えた。
だから、小林はこう言い切る。
「天稟の倫理性と人生無常に関する沈痛な信念とを心中深く蔵して、凝滞を知らず、頽廃を知らず、俗にも僧にも囚はれぬ、自在で而も誤たぬ、一種の生活法の体得者だつたに違ひないと思ふ」
定家がいかにして歌を作るかという悩みをいだいていたのに対して、西行はいかにしておのれを知るか、という自問を持っていた詩人であると、小林は見る。西行にとって、「自然」とむかいあう、そのあらわな心の「孤独」を歌うことが唯一の生のあかしとなったという。
西行は「自然」にさらされた「孤独」をいだきながら、北面武士の俤をもち、勁い意志により、自意識の苦痛をもちながらも「行為」のひととして生きたとする。
この西行像は、「自然」をめぐり、ランボオから志賀直哉を経て、展開されてきた「わが心」(意識)を「行為」によってのりこえようとする反「近代」的な、あるべき人間像であると、饗庭は捉えている。
小林は西行の歌と「行為」のなかに「自然」にふれて放たれる勁い「孤独」の共鳴音(レゾナンス)をもった旋律をききとったであろう。つまり、小林の「西行」とは、「個」の懐疑の果てに「近代」の否定にたどりつき、その上で「自然」(歴史)の覚醒によってあらわにされた「わが心」の「孤独」を西行の行為と歌をとおして彫琢しようとした批評行為の所産にほかならないとする)
次に小林の「実朝」はどうか。
小林は昭和18年、『文學界』(2月号、5月号、6月号)に「実朝」を書いている。一方、太宰治は前年の10月ごろから書下しの小説『右大臣実朝』にとりくみ、小林と同じ昭和18年の9月にこれを出版している。両者の暗合は不思議である。
太宰は天稟をもった実朝を「神様」のように無垢で清澄きわまりない人間とし、そこにキリストの犠牲を重ね、「アカルサハ、ホロビの姿」という予感のなかに息づいていた破滅へのいそぎをあらわした。
しかし、小林の実朝は、「無垢」の天稟をもった詩人という点では共通していても、万葉の精神と出会う資質をもち、約束多い和歌の枠を自在にこえ、その詩魂に独創的な孤独を宿した詩人であると見る点でことなっていた。
太宰は「滅亡」のフィルターをとおし、小林は「孤独」をとおして、ともに時代のなかにおける自己証明のように実朝を描いたようだ。
小林が実朝に見たのは、歴史の暗闘のなかで不可避な「死」をかかえた「無垢」の詩人であった。この点、西行が旅のなかに生き、俗と僧との間に矛盾をかかえて生きながらも、何よりも「わが心」のありようを求めたのとはちがう。
12歳で征夷大将軍となり、右大臣となった28歳の惨死まで政治のなかに生きた実朝は、「愛惜」としての歴史の名に値いする人間である。そして歴史の必然にうちくだかれる悲劇の詩人である。
小林は「孤独」の独創性を実朝に感じた。
小林が「歴史について」や「歴史と文学」でのべてきた「愛惜」ともっとも呼ぶにふさわしい対象が、この実朝であったと見ることができる。
実朝は天与の詩才をいだきながら政治の渦中に生き、それなりに「物」が見えた人間である。この実朝を描く小林の筆致は、緊張し、高揚し、終末にむかって、あたかもおのれ自身をおいあげ、純化してゆくような美しさをたたえているといわれる。饗庭は、小林の古典論のなかで、もっとも見事な達成をここに見ている。
実朝は、小林にとって、「行為」の領域に運命的に生きながらも、すぐれた「天分」によってその運命をこえ、時の外に出て、しかも「伝統」のつねに「現前」する存在の典型に見えた。
小林は、史料を過信せず、感性的認識によって実朝の歌を、その「色や線や旋律」から、「夕暮」や「白波」あるいは「見え隠れする雪を乗せた島」からとらえたイメージをとおして、「詩魂」の内部に直接に推参しようとする。
小林は、「物」であの「形ある美」のリアリティを考えるに、観念や概念をこえて直接経験を重要視する人間であった。「大切な事は、真理に頼つて限定する事では」なく、「見る事が考へる事と同じになるまで、視力を純化する」(「私の人生観」)ことが、実朝の歌に対する感覚的把握の根底に働いていた。
「もの」にしたがい、その現前性をとらえ、「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」(「無常といふ事」)「伝統」の実体に迫る上で、おのずから遥かな日本の伝統的認識の仕方を小林は体現した。
この心性(メンタリティ)の個人的顕在こそ、小林の古典論を支えたものであると、饗庭は捉えている。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、187頁~195頁)
饗庭孝男は、『小林秀雄とその時代』(小沢書店、1997年)において、「第十章 「信」としての<知>――『本居宣長』」において、小林秀雄と『本居宣長』について、次のように述べている。
饗庭は、小林秀雄という批評家を次のように規定している。
「小林秀雄は、生涯にわたって「言語」とは何かを考えつづけてきた人間であった」(311頁)
そして小林の著作『本居宣長』について、次のように評している。
「『本居宣長』は、その意味でこうした「言語」を中心とし、それを「伝統」への「信」を前提としながら神話的共同体へと開いてみせた小林の批評の到達点であり、その集成とも呼んでいいものである」(312頁)
小林の『本居宣長』の主題は、「何よりも小林秀雄にとって重要であったのは、少くともこの『本居宣長』に関するかぎり、「言語」の発生のありようであった」(313頁)
宣長の「言語」についての論議は、賀茂真淵の『冠辞考』を問題にするあたりからはじまっているが、そこには2つの方向があったと饗庭は解説している。
①「ひたすら言語の表現力を信ずる歌人の純粋な喜び」という詩的言語への重視→歌人の「個」の表現
②「物のあはれに、たへぬところより、ほころび出る」、声や抑揚をもつ歌の原初性への重視→「言語」の身体性
①には、象徴主義の「言語」観の痕跡がある。②には、荻生徂徠の、音声を文字に優位させる、いわば現象学的な思考の反映があると饗庭はみる。
そして小林秀雄の『本居宣長』における「言語」論は、この2つが分ちがたくむすびついているとする。
また、饗庭は、小林の『本居宣長』に対する批判点として、次のようなことを述べている。
本居宣長の「物のあはれ」論から「古語」を明らかにすることで「道」をとく思考過程を、単に物語論と歌道、そして古語にかかわる「言語」論の水準で考える困難がここにあると饗庭は指摘している。
「古語」と「道」との関係をときほぐすために、宣長が生きた時代と彼の階級意識、そしてそこに息づく思想の交点を見ることが、小林秀雄にはさけてとおることのできない問題であったとする。
つまり、『古事記』が形成していた言語空間を、宣長の思想にそって想像力のなかで有機的な連関をとらえる手続が必要であったという。
宣長の「思想」が明確になるのも、時代と階級とのディアレクティック(弁証法)によってであると饗庭は批判している。
(そのことによって、逆に宣長の思い描いた『古事記』の宇宙が一層見えてきただろうとする)
宣長がどのように徂徠の「言語」観から「音声」と文字の関係を見て行ったかについて、いささかも小林は論争をしているわけではないと、饗庭は指摘している。
彼は稗田阿礼の「誦習(ヨミナライ)にむかい「言語」の「いきほひ」をのべるに至るのであるが、この過程にあらためて「凡ソ言語ノ道ハ、詩コレヲ尽ス」とし「言に物有る物」と「行ひに格有る事」とし「理」よりも「事実」を重んずるに至った徂徠の「言語」観を採用する。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、311頁~314頁)
小林秀雄は、生涯にわたって「言語」とは何かを考えつづけてきた人間であったと、饗庭は規定している。
小林の「言語」観は、象徴主義やヴァレリーの詩的言語をたてとし、伝達の機能よりも表現の意味作用を「個」と文学の自立性とにむすんだという。そして、それはマルクス主義と対峙した。その「言語」観は、「歴史」と「伝統」に出会うことによって、「言霊」の原初に遡行していった。
小林の批評の本質的な意味作用について、
〇「個」から「無私」へ
〇象徴主義の「言語」から共同体の「言霊」へ
と移っていった。
小林の『本居宣長』は、その意味で、こうした「言語」を中心とし、それを「伝統」への「信」を前提としながら、神話的共同体へと開いてみせた小林の批評の到達点であり、その集成であると、饗庭は理解している。
(饗庭孝男「「信」としての<知>」『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年所収、311頁~312頁)
小林の「言語」についての論議には、二つの方向があったといった。
その一つは、荻生徂徠の、音声を文字に優位させる、いわば現象学的な思考の反映があると饗庭はみている
(ジャック・デリダやフッサールの現象学における「言語」を解読しながらのべた「声(phoné フォネ)としての気息の精神性」(『声と現象』)に似た側面)
そして小林秀雄の『本居宣長』における「言語」論は、この二つが分ちがたくむすびついているとしたが、饗庭は、このことを時代の展望のなかにおきなおしている。
徂徠は、「言語」を漢字文化のなかで考えぬいたが、宣長は、漢意を排し、歌をとおして『古事記』のもつ口承的言語の原日本語的「言葉(パロール)」に移行した。
(ただ、宣長がどのようにして徂徠の「言語」観から「音声」と文字の関係を見て行ったかについて、小林は論証しているわけではないと、饗庭は断っている)
そして、饗庭は次のように記している。
「おそらくベルクソンを読み、そこにおける記号的認識にたいする深いベルクソンの懐疑と小林の「経験」主義にもとづく「物」への「無私」で直接的な感受の態度が、宣長の独自な「言語」観と共鳴しつつ、「見る」ことという態度とともに「古語を得る」宣長の内的経験の想像力的な復元にあって、その現象学的な接近を可能にしたにちがいない」
(饗庭孝男「「信」としての<知>」『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年所収、313頁~316頁)
言葉が力をもつとすれば何か、という自問を、小林は身体論的なレヴェルにつねに戻して考える習慣をもつようになっていた。それゆえ「言葉の故郷は肉体だ」(「オリムピア」)と小林が言うのも当然である。
小林は『本居宣長』のなかで、「古言」を得ることは「手答へのある『物』」であるとのべている。また、「言葉」について「私達の力量を超えた道具の『さだまり』」とする。
また、言葉を「たましひ」をもっている「生き物」と見る。「言語表現の本質を成すものは」「その人の持つて生れて来た心身の働きに、深く関はつてゐる」と考えている。
こうした認識のなかに、小林の「言語」観が一つのものとなってむすびついているといえる。
『本居宣長』における言語論の根は深い。
いいかえれば、小林は記号的な「言語」にたいする懐疑から、神話的言語へと遡行してきたと饗庭は捉えている。いわば≪自然≫に根ざし、存在と事物が認識の渇望によって呼び出される時、その根源の場でうかびあがる「言語」に小林は心惹かれてきたという。
多義的で重層しながら肉体を失わない原初の「言語」の意味作用(シニフィカシヨン)への関心が、小林をみちびいて本居宣長に至った。
「歴史」から「伝統」、そして古典の神話的言語空間へと、初期において得た西欧の象徴主義的な「言語観」は、日本の心性のなかでためされ、遡行の働きを得、小林の内部において「古語を得る」宣長の追体験への希求の道すじをたどって変容をとげた。
さて、小林は、こうした「言語」観を根底にもちながら、古典文学を題材とした次のような批評を書いた。「当麻」「無常といふ事」「徒然草」「西行」「実朝」等。
そして、日本近世の思想家たちのありかたに関心を集中させるようになる。
それは、パスカル、デカルト、ベルクソンといったフランスの思想家、ソクラテスやプラトンという古代の思想家にたいする関心と重なり、あるいはそれを契機として深められた。
小林のモラリスト的志向がたとえばモンテーニュをとおし、吉田兼好に「物が見え過ぎる眼」の「物狂しさ」と「死」への認識をよみとっていたのも、そうした糸口をつくっていたと、饗庭は推測している。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、292頁~293頁)
(2021年6月6日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、饗庭孝男『小林秀雄とその時代』(小沢書店、1997年)において、論じられた日本古典論について解説しておきたい。
まず、「当麻」「平家物語」「徒然草」、そして「西行」および「実朝」といった小林秀雄の古典論について、饗庭孝男がどのように捉えていたのかを説明してゆく。
そして、小林秀雄の大著『本居宣長』と言語観について、饗庭がどのように理解しているのかについて、述べてみたい。
【饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店はこちらから】

小林秀雄とその時代
饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年
本書の目次は次のようになっている。
【目次】
第一章 「故郷」喪失と「意識」のドラマ――「一ツの脳髄」
第二章 批評の誕生――ランボオとヴァレリー体験
第三章 拮抗する批評の精神――「様々なる意匠」と志賀直哉論
第四章 「思想」と実生活――「私小説論」の成立
第五章 意識の「地下室」を求めて――ドストエーフスキイ論考
第六章 歴史の闇の花――『無常といふ事』
第七章 「無垢」な魂の歌――『モオツアルト』
第八章 「精神」としての絵画――『ゴッホの手紙』と『近代絵画』
第九章 「経験」の深化――ベルクソン論としての「感想」
第十章 「信」としての<知>――『本居宣長』
あとがき
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・小林秀雄の古典論
・小林秀雄の古典論に対する饗庭孝男の理解
・「信」としての<知>――『本居宣長』
・小林秀雄の「言語」観と『本居宣長』
小林秀雄の古典論
小林秀雄にとって開戦の翌年から、昭和18年にかけては、古典論を書くことに専念した期間であった。
「当麻」「無常といふ事」「平家物語」「徒然草」、そして「西行」が昭和17年に、「実朝」が翌年である。
その間、昭和17年の10月には、「近代の超克」(『文學界』)に出席している。この大座談会における小林の発言は、古典論と並行している時だけに多くの示唆をふくんでいると、饗庭はみている。
小林は、歴史は変化であり、進歩と見なす考えに懐疑を覚え、「何時も同じもの」があり、それを貫く人の書いた作品を「古典」とし、「美学」と呼び、現代にいても「古人の達したより以上のものは絶対にできんといふ謙遜な気持」をもつことを力説している。
ここに歴史から古典への移行が期せずしてかたられている趣きがある。
「当麻」は、形ある美しさへの直接経験にのみ認識の根拠を求めようとする思想から書かれたものである。古典論のはじめが、身体的行為としての能の表現についてのエッセイであることは、その意味で象徴的である。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、184頁~185頁)
小林秀雄の古典論に対する饗庭孝男の理解
沈黙のなかで戦争という歴史の劇を生きながら、小林は言いようのない「孤独」を感じていたはずである。
「徒然草」から「西行」「実朝」に至る評論を一貫して流れるものは、抗しがたい歴史(必然)の運命を前にした自意識の「孤独」が奏でる、あるパセティックな短調とでもいうべき、暗く低い旋律であったと、饗庭は捉えている。
兼好も西行も、実朝のいずれもが戦乱のなかで歴史(必然)に打ち砕かれる思想を「孤独」の裡に織っていた。そこに小林がおのれの姿を重ね、古典を現前させ、あるいは逆に古典のなかにおのれを織りこみ、いわば時をこえて生きつづける存在の「あかし」を願おうと考えたとする。
「当麻」は、そうした巨大な現実を前にし、それに拮抗しようとする小林の態度をものがたる古典論の「序奏」とでもいうべき作品であった。
この小さな「形」のなかに、「近代」日本にたいする自らをとおした総括的反省がこめられているとともに、歴史の闇のなかの「孤独」を「花」と化し、逆にそこに自らの「歴史」をイメージによって現象させようとした小林の意図が息づいているとみる。
「当麻」につづいて書かれた「平家物語」のとらえ方についても、「当麻」と同じく、イメージによる把握と「肉体の動きに則つて観念の動きを修正」しようとする小林の意図を看取できるようだ。
「言葉の故郷は肉体だ」とのべた思考が「当麻」と同じく、この「平家物語」をもつらぬいているという。
(こういう思考とは、かつて志賀直哉に小林が見た「自然」と「行為」の表現にたいする讃嘆の延長線上にあるものである。小林が志賀直哉論以来、歴史(自然)認識をへて対象のなかに、おのれの思考と共振するものをよみ、いかにそれをリアリティあるものとしているか否かが、そこでは問題であった。小林は『平家物語』に、いわば自らの思考と出会うもののみをイメージで表現した)
一方、『徒然草』に対しては、別の接近の仕方を行った。わずか2頁半のこのエッセイで小林が描いたものは、小林が批評行為の中心においた「見る」ことに徹した兼好の態度であった。
小林は「生死」と「自然」を見、それを表現するモラリスト的な形式の見事さと文体に感嘆した。「見る」行為と表現の形式と文体への関心こそ、このエッセイの本質であると、饗庭は理解している。
ところが、「西行」と「実朝」は、これまでの、対象にたいする独自な接近と、その切り口の提示が身上であった古典論と趣きをことにするようだ。そこには対象の全体を小林なりの視角からとらえようとする意図がある。
小林は西行を描くにあたって、「根は頑丈で執拗な」人間であると見た。小林が見ようとしたのは、「生得」の詩人であるばかりでなく、たとえば「世の中を反き果てぬといひおかんと思ひしるべき人はなくとも」という歌にみられる意志をつらぬこうとする勁い人間であった。
この視角から西行は「自ら進んで世に反いた者の世俗に対する嘲笑と内に湧き上る希望との渦巻く青春の歌」をうたう人として映じ、「女々しい感傷」をもたぬ「空前の内省家」となる。その苦い内省によって、そのまま放胆で自在な、しかも正確な歌をよむ詩人と、小林は考えた。
だから、小林はこう言い切る。
「天稟の倫理性と人生無常に関する沈痛な信念とを心中深く蔵して、凝滞を知らず、頽廃を知らず、俗にも僧にも囚はれぬ、自在で而も誤たぬ、一種の生活法の体得者だつたに違ひないと思ふ」
定家がいかにして歌を作るかという悩みをいだいていたのに対して、西行はいかにしておのれを知るか、という自問を持っていた詩人であると、小林は見る。西行にとって、「自然」とむかいあう、そのあらわな心の「孤独」を歌うことが唯一の生のあかしとなったという。
西行は「自然」にさらされた「孤独」をいだきながら、北面武士の俤をもち、勁い意志により、自意識の苦痛をもちながらも「行為」のひととして生きたとする。
この西行像は、「自然」をめぐり、ランボオから志賀直哉を経て、展開されてきた「わが心」(意識)を「行為」によってのりこえようとする反「近代」的な、あるべき人間像であると、饗庭は捉えている。
小林は西行の歌と「行為」のなかに「自然」にふれて放たれる勁い「孤独」の共鳴音(レゾナンス)をもった旋律をききとったであろう。つまり、小林の「西行」とは、「個」の懐疑の果てに「近代」の否定にたどりつき、その上で「自然」(歴史)の覚醒によってあらわにされた「わが心」の「孤独」を西行の行為と歌をとおして彫琢しようとした批評行為の所産にほかならないとする)
次に小林の「実朝」はどうか。
小林は昭和18年、『文學界』(2月号、5月号、6月号)に「実朝」を書いている。一方、太宰治は前年の10月ごろから書下しの小説『右大臣実朝』にとりくみ、小林と同じ昭和18年の9月にこれを出版している。両者の暗合は不思議である。
太宰は天稟をもった実朝を「神様」のように無垢で清澄きわまりない人間とし、そこにキリストの犠牲を重ね、「アカルサハ、ホロビの姿」という予感のなかに息づいていた破滅へのいそぎをあらわした。
しかし、小林の実朝は、「無垢」の天稟をもった詩人という点では共通していても、万葉の精神と出会う資質をもち、約束多い和歌の枠を自在にこえ、その詩魂に独創的な孤独を宿した詩人であると見る点でことなっていた。
太宰は「滅亡」のフィルターをとおし、小林は「孤独」をとおして、ともに時代のなかにおける自己証明のように実朝を描いたようだ。
小林が実朝に見たのは、歴史の暗闘のなかで不可避な「死」をかかえた「無垢」の詩人であった。この点、西行が旅のなかに生き、俗と僧との間に矛盾をかかえて生きながらも、何よりも「わが心」のありようを求めたのとはちがう。
12歳で征夷大将軍となり、右大臣となった28歳の惨死まで政治のなかに生きた実朝は、「愛惜」としての歴史の名に値いする人間である。そして歴史の必然にうちくだかれる悲劇の詩人である。
小林は「孤独」の独創性を実朝に感じた。
小林が「歴史について」や「歴史と文学」でのべてきた「愛惜」ともっとも呼ぶにふさわしい対象が、この実朝であったと見ることができる。
実朝は天与の詩才をいだきながら政治の渦中に生き、それなりに「物」が見えた人間である。この実朝を描く小林の筆致は、緊張し、高揚し、終末にむかって、あたかもおのれ自身をおいあげ、純化してゆくような美しさをたたえているといわれる。饗庭は、小林の古典論のなかで、もっとも見事な達成をここに見ている。
実朝は、小林にとって、「行為」の領域に運命的に生きながらも、すぐれた「天分」によってその運命をこえ、時の外に出て、しかも「伝統」のつねに「現前」する存在の典型に見えた。
小林は、史料を過信せず、感性的認識によって実朝の歌を、その「色や線や旋律」から、「夕暮」や「白波」あるいは「見え隠れする雪を乗せた島」からとらえたイメージをとおして、「詩魂」の内部に直接に推参しようとする。
小林は、「物」であの「形ある美」のリアリティを考えるに、観念や概念をこえて直接経験を重要視する人間であった。「大切な事は、真理に頼つて限定する事では」なく、「見る事が考へる事と同じになるまで、視力を純化する」(「私の人生観」)ことが、実朝の歌に対する感覚的把握の根底に働いていた。
「もの」にしたがい、その現前性をとらえ、「解釈を拒絶して動じないものだけが美しい」(「無常といふ事」)「伝統」の実体に迫る上で、おのずから遥かな日本の伝統的認識の仕方を小林は体現した。
この心性(メンタリティ)の個人的顕在こそ、小林の古典論を支えたものであると、饗庭は捉えている。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、187頁~195頁)
「信」としての<知>――『本居宣長』
饗庭孝男は、『小林秀雄とその時代』(小沢書店、1997年)において、「第十章 「信」としての<知>――『本居宣長』」において、小林秀雄と『本居宣長』について、次のように述べている。
饗庭は、小林秀雄という批評家を次のように規定している。
「小林秀雄は、生涯にわたって「言語」とは何かを考えつづけてきた人間であった」(311頁)
そして小林の著作『本居宣長』について、次のように評している。
「『本居宣長』は、その意味でこうした「言語」を中心とし、それを「伝統」への「信」を前提としながら神話的共同体へと開いてみせた小林の批評の到達点であり、その集成とも呼んでいいものである」(312頁)
小林の『本居宣長』の主題は、「何よりも小林秀雄にとって重要であったのは、少くともこの『本居宣長』に関するかぎり、「言語」の発生のありようであった」(313頁)
宣長の「言語」についての論議は、賀茂真淵の『冠辞考』を問題にするあたりからはじまっているが、そこには2つの方向があったと饗庭は解説している。
①「ひたすら言語の表現力を信ずる歌人の純粋な喜び」という詩的言語への重視→歌人の「個」の表現
②「物のあはれに、たへぬところより、ほころび出る」、声や抑揚をもつ歌の原初性への重視→「言語」の身体性
①には、象徴主義の「言語」観の痕跡がある。②には、荻生徂徠の、音声を文字に優位させる、いわば現象学的な思考の反映があると饗庭はみる。
そして小林秀雄の『本居宣長』における「言語」論は、この2つが分ちがたくむすびついているとする。
また、饗庭は、小林の『本居宣長』に対する批判点として、次のようなことを述べている。
本居宣長の「物のあはれ」論から「古語」を明らかにすることで「道」をとく思考過程を、単に物語論と歌道、そして古語にかかわる「言語」論の水準で考える困難がここにあると饗庭は指摘している。
「古語」と「道」との関係をときほぐすために、宣長が生きた時代と彼の階級意識、そしてそこに息づく思想の交点を見ることが、小林秀雄にはさけてとおることのできない問題であったとする。
つまり、『古事記』が形成していた言語空間を、宣長の思想にそって想像力のなかで有機的な連関をとらえる手続が必要であったという。
宣長の「思想」が明確になるのも、時代と階級とのディアレクティック(弁証法)によってであると饗庭は批判している。
(そのことによって、逆に宣長の思い描いた『古事記』の宇宙が一層見えてきただろうとする)
宣長がどのように徂徠の「言語」観から「音声」と文字の関係を見て行ったかについて、いささかも小林は論争をしているわけではないと、饗庭は指摘している。
彼は稗田阿礼の「誦習(ヨミナライ)にむかい「言語」の「いきほひ」をのべるに至るのであるが、この過程にあらためて「凡ソ言語ノ道ハ、詩コレヲ尽ス」とし「言に物有る物」と「行ひに格有る事」とし「理」よりも「事実」を重んずるに至った徂徠の「言語」観を採用する。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、311頁~314頁)
小林秀雄の「言語」観と『本居宣長』
小林秀雄は、生涯にわたって「言語」とは何かを考えつづけてきた人間であったと、饗庭は規定している。
小林の「言語」観は、象徴主義やヴァレリーの詩的言語をたてとし、伝達の機能よりも表現の意味作用を「個」と文学の自立性とにむすんだという。そして、それはマルクス主義と対峙した。その「言語」観は、「歴史」と「伝統」に出会うことによって、「言霊」の原初に遡行していった。
小林の批評の本質的な意味作用について、
〇「個」から「無私」へ
〇象徴主義の「言語」から共同体の「言霊」へ
と移っていった。
小林の『本居宣長』は、その意味で、こうした「言語」を中心とし、それを「伝統」への「信」を前提としながら、神話的共同体へと開いてみせた小林の批評の到達点であり、その集成であると、饗庭は理解している。
(饗庭孝男「「信」としての<知>」『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年所収、311頁~312頁)
小林の「言語」についての論議には、二つの方向があったといった。
その一つは、荻生徂徠の、音声を文字に優位させる、いわば現象学的な思考の反映があると饗庭はみている
(ジャック・デリダやフッサールの現象学における「言語」を解読しながらのべた「声(phoné フォネ)としての気息の精神性」(『声と現象』)に似た側面)
そして小林秀雄の『本居宣長』における「言語」論は、この二つが分ちがたくむすびついているとしたが、饗庭は、このことを時代の展望のなかにおきなおしている。
徂徠は、「言語」を漢字文化のなかで考えぬいたが、宣長は、漢意を排し、歌をとおして『古事記』のもつ口承的言語の原日本語的「言葉(パロール)」に移行した。
(ただ、宣長がどのようにして徂徠の「言語」観から「音声」と文字の関係を見て行ったかについて、小林は論証しているわけではないと、饗庭は断っている)
そして、饗庭は次のように記している。
「おそらくベルクソンを読み、そこにおける記号的認識にたいする深いベルクソンの懐疑と小林の「経験」主義にもとづく「物」への「無私」で直接的な感受の態度が、宣長の独自な「言語」観と共鳴しつつ、「見る」ことという態度とともに「古語を得る」宣長の内的経験の想像力的な復元にあって、その現象学的な接近を可能にしたにちがいない」
(饗庭孝男「「信」としての<知>」『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年所収、313頁~316頁)
言葉が力をもつとすれば何か、という自問を、小林は身体論的なレヴェルにつねに戻して考える習慣をもつようになっていた。それゆえ「言葉の故郷は肉体だ」(「オリムピア」)と小林が言うのも当然である。
小林は『本居宣長』のなかで、「古言」を得ることは「手答へのある『物』」であるとのべている。また、「言葉」について「私達の力量を超えた道具の『さだまり』」とする。
また、言葉を「たましひ」をもっている「生き物」と見る。「言語表現の本質を成すものは」「その人の持つて生れて来た心身の働きに、深く関はつてゐる」と考えている。
こうした認識のなかに、小林の「言語」観が一つのものとなってむすびついているといえる。
『本居宣長』における言語論の根は深い。
いいかえれば、小林は記号的な「言語」にたいする懐疑から、神話的言語へと遡行してきたと饗庭は捉えている。いわば≪自然≫に根ざし、存在と事物が認識の渇望によって呼び出される時、その根源の場でうかびあがる「言語」に小林は心惹かれてきたという。
多義的で重層しながら肉体を失わない原初の「言語」の意味作用(シニフィカシヨン)への関心が、小林をみちびいて本居宣長に至った。
「歴史」から「伝統」、そして古典の神話的言語空間へと、初期において得た西欧の象徴主義的な「言語観」は、日本の心性のなかでためされ、遡行の働きを得、小林の内部において「古語を得る」宣長の追体験への希求の道すじをたどって変容をとげた。
さて、小林は、こうした「言語」観を根底にもちながら、古典文学を題材とした次のような批評を書いた。「当麻」「無常といふ事」「徒然草」「西行」「実朝」等。
そして、日本近世の思想家たちのありかたに関心を集中させるようになる。
それは、パスカル、デカルト、ベルクソンといったフランスの思想家、ソクラテスやプラトンという古代の思想家にたいする関心と重なり、あるいはそれを契機として深められた。
小林のモラリスト的志向がたとえばモンテーニュをとおし、吉田兼好に「物が見え過ぎる眼」の「物狂しさ」と「死」への認識をよみとっていたのも、そうした糸口をつくっていたと、饗庭は推測している。
(饗庭孝男『小林秀雄とその時代』小沢書店、1997年、292頁~293頁)












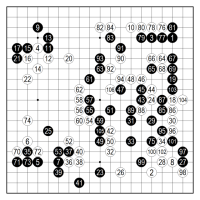
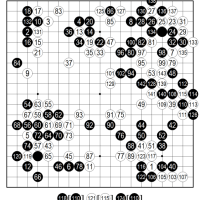
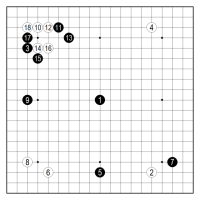
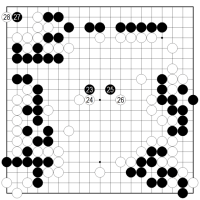
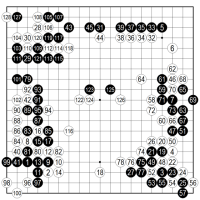
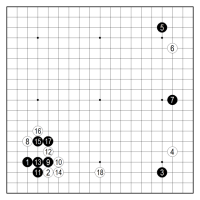
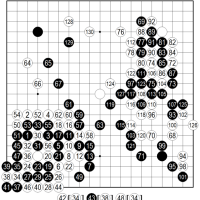
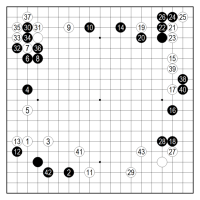
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます