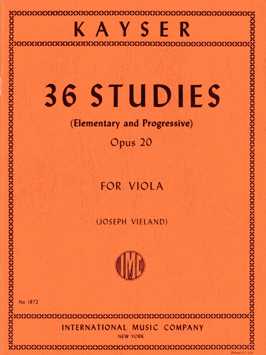フランツ・アントン・ホフマイスター(Franz.Anton.Hoffmeister 1754~1812)の12のヴィオラ エチュードを今日は上げます。ホフマイスターは、オーストリアの楽譜出版家及び作曲家です。
作曲家としては多作家で、出版事業も最初は上手くいっていたそうですが、元々事業家としては素人同然なのと作曲活動に力を注いでいたために会社は色々と苦労を重ねたそうです。
作品にはヴィオラ奏者にとってかけがいのないものがあります。ヴィオラ協奏曲がまず上げられます。そして、ヴィオラエチュードもそのうちの一つです。ヴィオラ奏者教育用としては、王道ではないですが私はとても好きな作品で以前よく練習していました。
各曲が、無伴奏の独立した作品のような感じがしてエチュード(練習曲)というイメ~ジを越えている気がします。特に第4番などはヴィオラ協奏曲 ニ長調の一部と全く同じ音楽の部分もあって、なかなか弾きがいのある曲です。
もし先に挙げた作品は、そこそこ演奏出来るけどもっと面白いエチュードないかな?と思っている方がいましたら、おすすめします。
作曲家としては多作家で、出版事業も最初は上手くいっていたそうですが、元々事業家としては素人同然なのと作曲活動に力を注いでいたために会社は色々と苦労を重ねたそうです。
作品にはヴィオラ奏者にとってかけがいのないものがあります。ヴィオラ協奏曲がまず上げられます。そして、ヴィオラエチュードもそのうちの一つです。ヴィオラ奏者教育用としては、王道ではないですが私はとても好きな作品で以前よく練習していました。
各曲が、無伴奏の独立した作品のような感じがしてエチュード(練習曲)というイメ~ジを越えている気がします。特に第4番などはヴィオラ協奏曲 ニ長調の一部と全く同じ音楽の部分もあって、なかなか弾きがいのある曲です。
もし先に挙げた作品は、そこそこ演奏出来るけどもっと面白いエチュードないかな?と思っている方がいましたら、おすすめします。