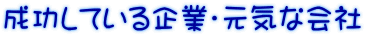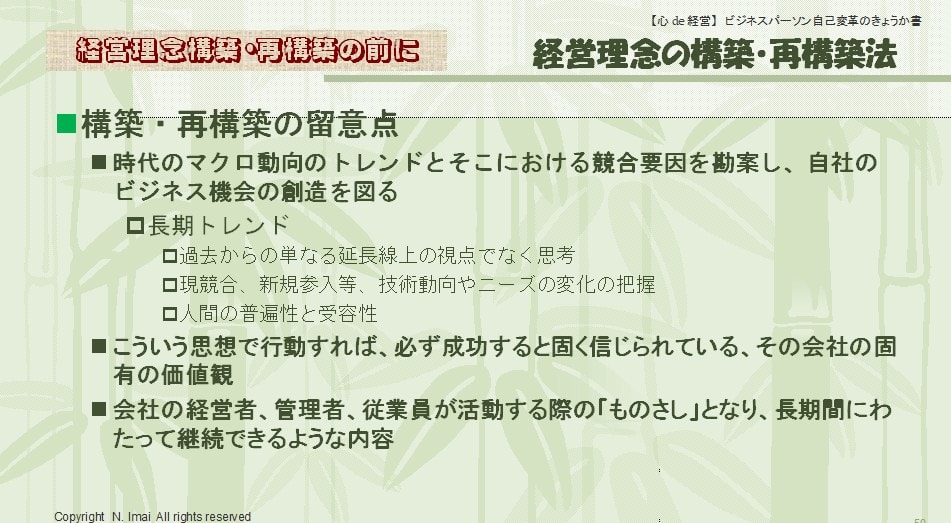【心 de 経営】『書話力』を高める 7108 書話ができる人の日常を参考にする

経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちあいたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。


*
「日本人は、議論に弱い」「日本人は、論理的な話し方ができない」などとしばしば言われます。かくいう私も、そう言われる人間のひとりです。
しかし、経営コンサルタントという仕事を半世紀も続けているうちに、それでは通じず、次第に、私なりの話し方やビジネスの仕方が、不充分ながら身についてきたように思えます。話すだけではなく、書くことにも共通する「表現力」というスキルがビジネスパーソンには不可欠です。「書く力」「話す力」をあわせて『書話の力』といい、表現力というスキルの一翼を担わせています。
この体験は、当ブログ「【小説】竹根好助の経営コンサルタント起業」としてもお届けしています。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

既述の通り、書話のできる人というのは、論理思考ができる人に多いです。論理思考が苦手な人でも、ロジカル・シンキングやロジカル・ライティングでトレーニングを積むことにより、書話力を各段に向上させることができます。
では、書話力が高い人は、平素、どの様な思考法や行動をしているのでしょうか。彼等から、コンピテンシーを盗み取ってみませんか。
*
①目的意識を常に持つ
書話力の高い人というのは、書話など自分の仕事だけではなく、日常生活でもPDCAが励行されています。
目的意識が強く、これから何かをしよう、何を書こう、話す準備をしようというようなときに、それは何のためにするのか、その結果、何を期待できるのか、誰のためにするのか等々、やるべきことの目的を常に意識しています。
*
②俯瞰的にものを見る
目的意識を持って行動するときに必要なことは、自分がすべきことの全体を意識することです。
そのために、書話力の高い人は、全体を俯瞰的に観るということが常態化しています。そして、自分がなそうとしている全体の中で、現状の立ち位置を常に意識しています。
自分の立ち位置が解りますと、次に何をすれば良いのか、それが、その後、どの様な影響を及ぼすだろうか、等々を予見できるようになります。予見できれば、失敗を避けることもできますし、次に何をすべきかも明確に読めます。
*
③相手のいうことに耳を傾ける
書話力の高い人は、相手のいうことを良く聞き、周囲をよく観察します。全体を俯瞰しながら、耳を傾けますので、相手の言っていること、言いたいことを理解できるのです。
彼等は、相手の言うことを傾聴する、高い傾聴力を持っています。しかし、それをはじめから持っている人は少ないでしょう。平素、目的意識を持ち、俯瞰的にものを観て、傾聴することを励行しています。
*
④謙虚な姿勢
書話力が高い人には、謙虚な人が多いです。謙虚さが傾聴する姿勢にも繋がります。
「自分は何でも知っている」というような姿勢では、周囲の人は、その人のために何かをしてあげようという気になりません。人の話を謙虚な姿勢で良く聞く人には、周囲の人が、その人のために何かをしてくれることが多いです。「情けは人のためならず」ということをよく理解できているのでしょう。
謙虚に自分を見られ、相手にも謙虚に接することにより、巡り廻って、形を変えて、自分にメリットのあることが返ってくるのです。
*
⑤クリティカルに物事をみる
小さい子供は、「なぜ?」「どうして?」という質問をしつこいくらいに投げかけてきます。大人よりも好奇心が強いのでしょうか。
ところが、私達はどうでしょう。
目の前にあることを、そのまま受け入れ、何の疑問も持たずに毎日を過ごしてしまっていませんか?
平素から、「Why so?」「So what?」という疑念を繰り返すことにより、新たな発見があります。
目の前のことに対して「本当にこれで良いのだろうか」「これは正しいことなのだろうか」「他に何かないのだろうか」というような疑問を持つことで思考力が高まり、それが書話力の向上に繋がります。