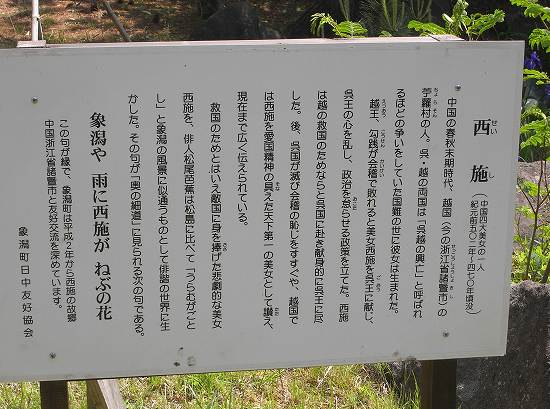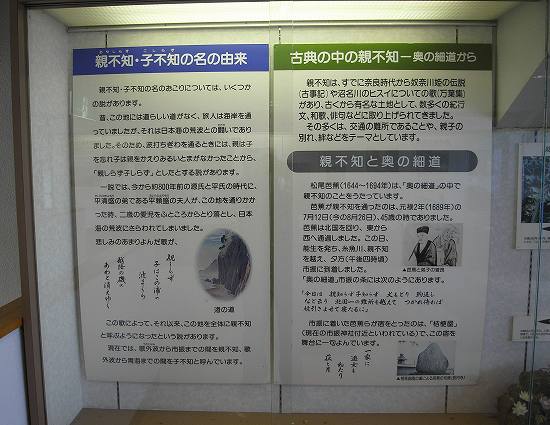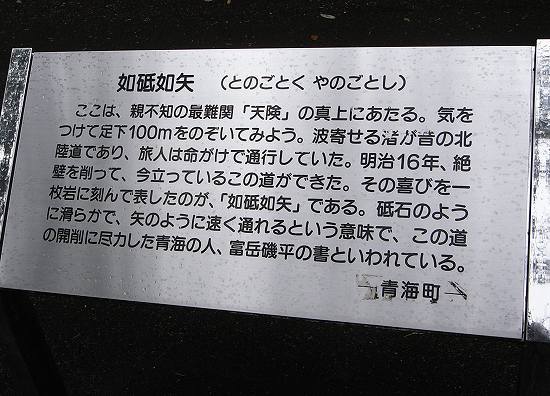6月12日(木) 晴 (秋田市・旅館「白鳥荘」連泊)
宿に連泊し、金沢以来の久しぶりの休養日。
本当は、秋田県立博物館に行き、菅江真澄の資料などを見たかったのだが、地図で調べてみると、県立博物館は宿からかなり遠く、むしろ翌日歩く行程の途中にあることがわかる。
8時、たっぷりの睡眠の後、遅い朝食をとる。
宿のオーナーは、秋田市は竿燈以外には特に見所はないと実に素っ気なかったが、天気も良いので、ともかく街に出てみることにする。
9時、宿を出る。
まず宿のすぐそばの千秋公園に行く。ここは藩主佐竹氏の居城であった久保田城址を公園にしたもの。久保田城は消失して今はなく、御隅櫓(おすみやぐら)と表門が名残をとどめるのみ。

若葉となった桜をはじめ、多数の木々に囲まれ、体全体が緑色に染まるくらいのさわやかな気分である。
久保田城御隅櫓を見学。



櫓も市制100年を記念して復元されたもので、物見や武器の貯蔵庫などの役割を持っていたとのこと。見学者は他にはおらず、一人でゆっくりと見せてもらう。内部には資料室と展望室があり、領主佐竹家の、常陸から当地への転封、歴代藩主の業績などの資料を興味深く見る。
「3階展望室」からの展望は、桜若葉にさえぎられて今一つだが、枝の隙間から鳥海山が見える。
公園内は、平日のせいか、まだほとんど人影を見かけず静かである。
中央に、第12代秋田藩主佐竹義堯(さたけよしたか)の像がある。像は、1915年(大正4年)に戊辰勤王記念銅像建設委員会によって建立されたが、太平洋戦争中に解体、1989年(平成元年)に復元された。
彼は最後の藩主で、戊辰戦争では、新政府方に属して戦った。つまり、奥羽越列藩同盟の会津藩・米沢藩の側から見れば「裏切り者」ということになる。もっとも、佐竹氏は、上記のごとく常陸から転封されてきたものでもあり、その思惑と行動などもっと調べてみないと軽々に評価を下すことは出来ない。

表門(一の門)を見る。

公園内には、若山牧水親子の歌碑もあり、
牧水の歌は、「鶸(ひわ)めじろ 山雀(やまがら)ひばりなきしきり さくらはいまだひらかざるなり」と刻まれている。


秋田市立中央図書館明徳館は、藩校「明徳館」にちなんだもので、菅江真澄の著作が多く収められている。
大手門の堀で睡蓮の写真を撮る。なぜか白い花はなく、ピンクの花がちょうど盛りである。

駅前郵便局で、この間に入手したパンフレットなどの諸資料を自宅に郵送。
駅前にジュンク堂があり、下関以来1ヵ月半ぶりに書店をのぞき、菅江真澄関連の書籍を眺める。
その後は、イトーヨーカ堂へ行き、地下で買い物と食事。玉丼パック、おにぎり2個。さらにダイソーで、定規、マーカー、接着剤。
午後は、「あきた文学資料館」へ行く。秋田県の文学史のパンフレットをいただき、

石川達三や石坂洋次郎など秋田出身や関連の作家などの写真や書籍などの展示を見る。

小林多喜二が秋田県大館の出身であったことを初めて知る。てっきり小樽の出だと思い込んでいた。小林多喜二や葉山嘉樹、徳永直などを読んだのは、全共闘運動が行きづまりつつあった頃のこと。

資料室で菅江真澄についての研究誌を見つけ、しばらく読む。
その後、再びイトーヨーカ堂へ行き、今後の食料などを調達。牛乳、食パン、クッキー、ピーナッツ、チョコレート、ポテトチップ、ココア、サラミ、レトルトカレー、コーヒーあめ、ガム2個。
帰路、千秋公園にてBさんと携帯電話で情報交換。彼は、今日は「道の駅いわき」に泊まる予定とのこと。
宿へ戻り、のんびり風呂に入って、買ってきたポテトチップをつまみに缶ビール。
翌日以降の計画の検討と経費の計算などをする。
宿の夕食は、オーナーの手作りで、おかずも和、洋、中とバラエティーに富んだもの。ボリュームたっぷりなり。
経費 3,413円 累計 239,819円
歩数 14,536歩 累計に加えず
距離 ?km 累計に加えず

(途中から当ブログにこられた方は、右バー「最新コメント」欄の「★はじまり★/ブログを始めました」をクリックして旅のはじめのページに飛び、最上段の「次の記事へ」から順に、日本縦断徒歩の旅をお楽しみください。--管理人より)
宿に連泊し、金沢以来の久しぶりの休養日。
本当は、秋田県立博物館に行き、菅江真澄の資料などを見たかったのだが、地図で調べてみると、県立博物館は宿からかなり遠く、むしろ翌日歩く行程の途中にあることがわかる。
8時、たっぷりの睡眠の後、遅い朝食をとる。
宿のオーナーは、秋田市は竿燈以外には特に見所はないと実に素っ気なかったが、天気も良いので、ともかく街に出てみることにする。
9時、宿を出る。
まず宿のすぐそばの千秋公園に行く。ここは藩主佐竹氏の居城であった久保田城址を公園にしたもの。久保田城は消失して今はなく、御隅櫓(おすみやぐら)と表門が名残をとどめるのみ。

若葉となった桜をはじめ、多数の木々に囲まれ、体全体が緑色に染まるくらいのさわやかな気分である。
久保田城御隅櫓を見学。



櫓も市制100年を記念して復元されたもので、物見や武器の貯蔵庫などの役割を持っていたとのこと。見学者は他にはおらず、一人でゆっくりと見せてもらう。内部には資料室と展望室があり、領主佐竹家の、常陸から当地への転封、歴代藩主の業績などの資料を興味深く見る。
「3階展望室」からの展望は、桜若葉にさえぎられて今一つだが、枝の隙間から鳥海山が見える。
公園内は、平日のせいか、まだほとんど人影を見かけず静かである。
中央に、第12代秋田藩主佐竹義堯(さたけよしたか)の像がある。像は、1915年(大正4年)に戊辰勤王記念銅像建設委員会によって建立されたが、太平洋戦争中に解体、1989年(平成元年)に復元された。
彼は最後の藩主で、戊辰戦争では、新政府方に属して戦った。つまり、奥羽越列藩同盟の会津藩・米沢藩の側から見れば「裏切り者」ということになる。もっとも、佐竹氏は、上記のごとく常陸から転封されてきたものでもあり、その思惑と行動などもっと調べてみないと軽々に評価を下すことは出来ない。

表門(一の門)を見る。

公園内には、若山牧水親子の歌碑もあり、
牧水の歌は、「鶸(ひわ)めじろ 山雀(やまがら)ひばりなきしきり さくらはいまだひらかざるなり」と刻まれている。


秋田市立中央図書館明徳館は、藩校「明徳館」にちなんだもので、菅江真澄の著作が多く収められている。
大手門の堀で睡蓮の写真を撮る。なぜか白い花はなく、ピンクの花がちょうど盛りである。

駅前郵便局で、この間に入手したパンフレットなどの諸資料を自宅に郵送。
駅前にジュンク堂があり、下関以来1ヵ月半ぶりに書店をのぞき、菅江真澄関連の書籍を眺める。
その後は、イトーヨーカ堂へ行き、地下で買い物と食事。玉丼パック、おにぎり2個。さらにダイソーで、定規、マーカー、接着剤。
午後は、「あきた文学資料館」へ行く。秋田県の文学史のパンフレットをいただき、

石川達三や石坂洋次郎など秋田出身や関連の作家などの写真や書籍などの展示を見る。

小林多喜二が秋田県大館の出身であったことを初めて知る。てっきり小樽の出だと思い込んでいた。小林多喜二や葉山嘉樹、徳永直などを読んだのは、全共闘運動が行きづまりつつあった頃のこと。

資料室で菅江真澄についての研究誌を見つけ、しばらく読む。
その後、再びイトーヨーカ堂へ行き、今後の食料などを調達。牛乳、食パン、クッキー、ピーナッツ、チョコレート、ポテトチップ、ココア、サラミ、レトルトカレー、コーヒーあめ、ガム2個。
帰路、千秋公園にてBさんと携帯電話で情報交換。彼は、今日は「道の駅いわき」に泊まる予定とのこと。
宿へ戻り、のんびり風呂に入って、買ってきたポテトチップをつまみに缶ビール。
翌日以降の計画の検討と経費の計算などをする。
宿の夕食は、オーナーの手作りで、おかずも和、洋、中とバラエティーに富んだもの。ボリュームたっぷりなり。
経費 3,413円 累計 239,819円
歩数 14,536歩 累計に加えず
距離 ?km 累計に加えず
(途中から当ブログにこられた方は、右バー「最新コメント」欄の「★はじまり★/ブログを始めました」をクリックして旅のはじめのページに飛び、最上段の「次の記事へ」から順に、日本縦断徒歩の旅をお楽しみください。--管理人より)