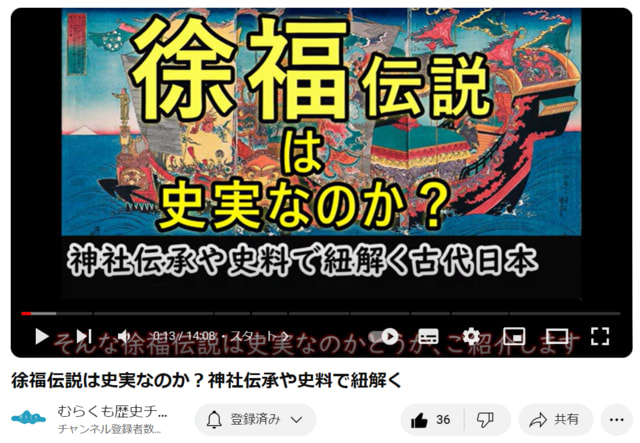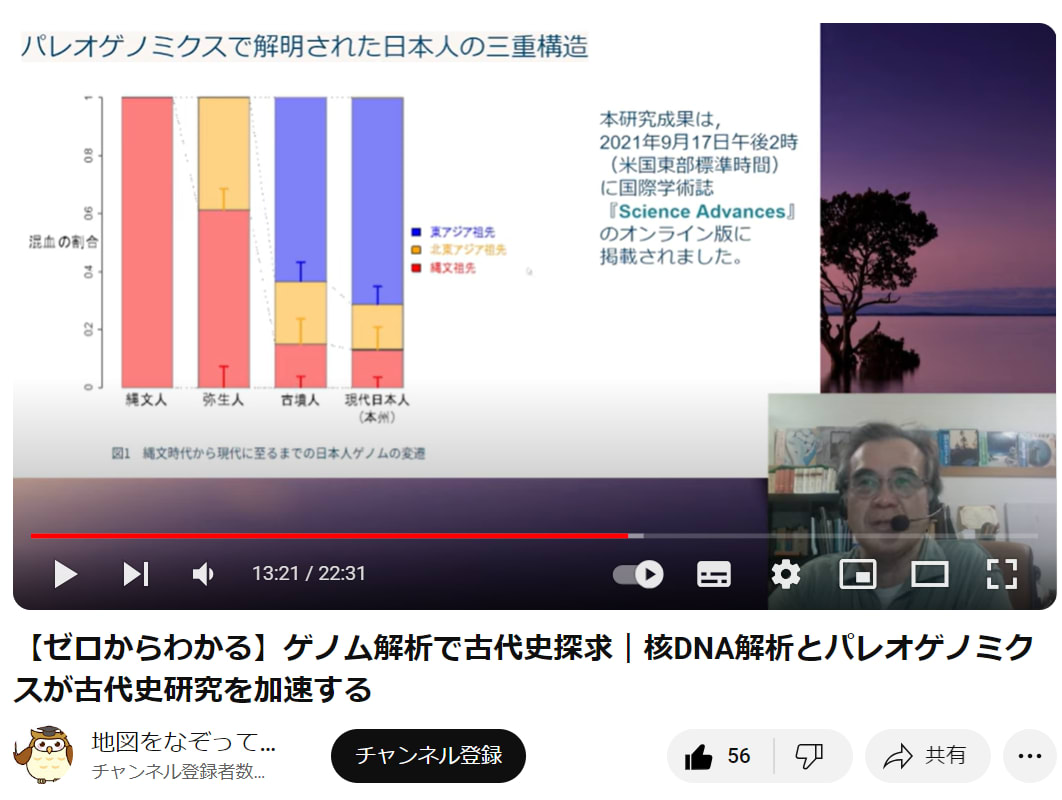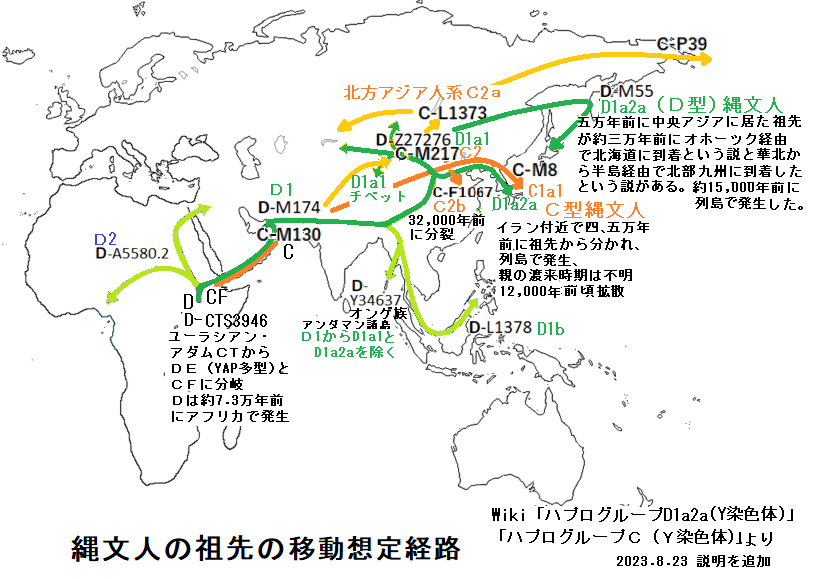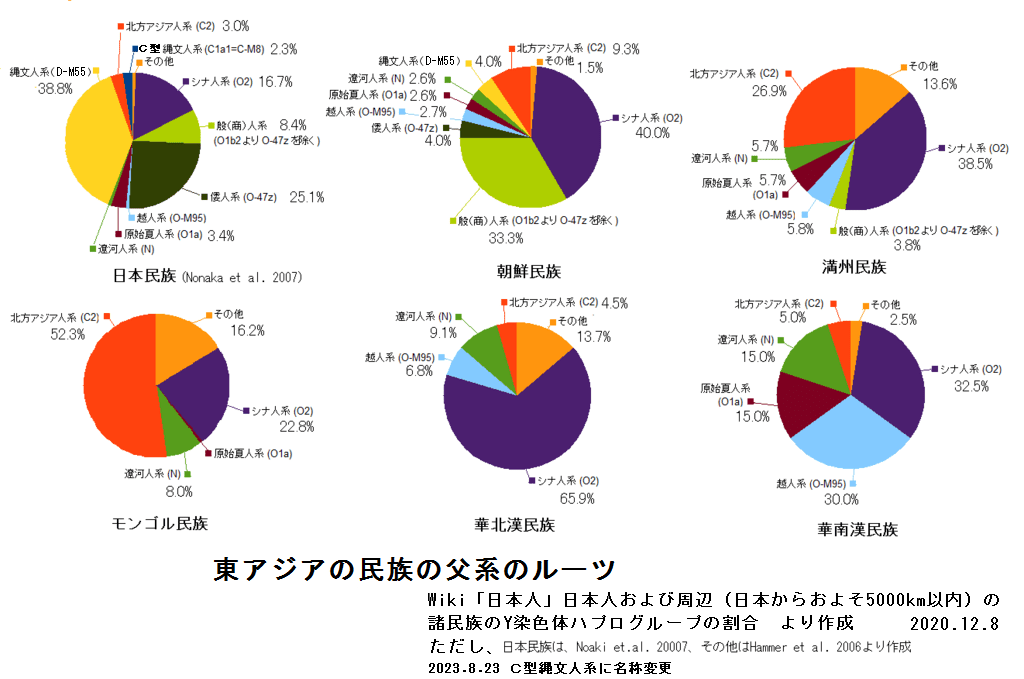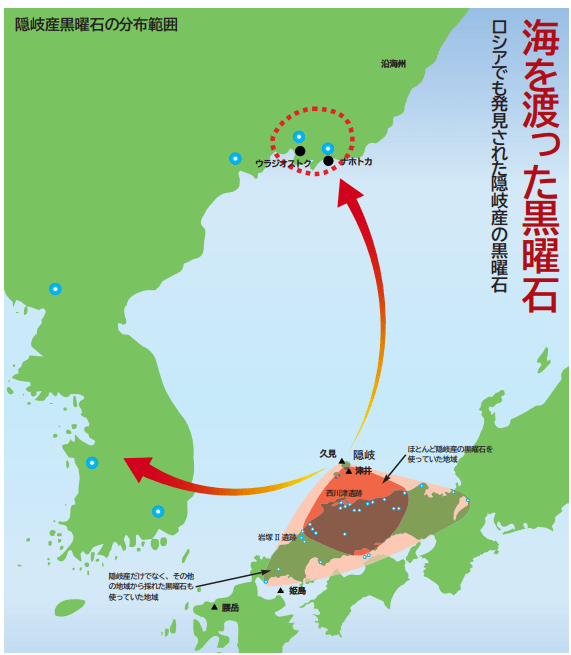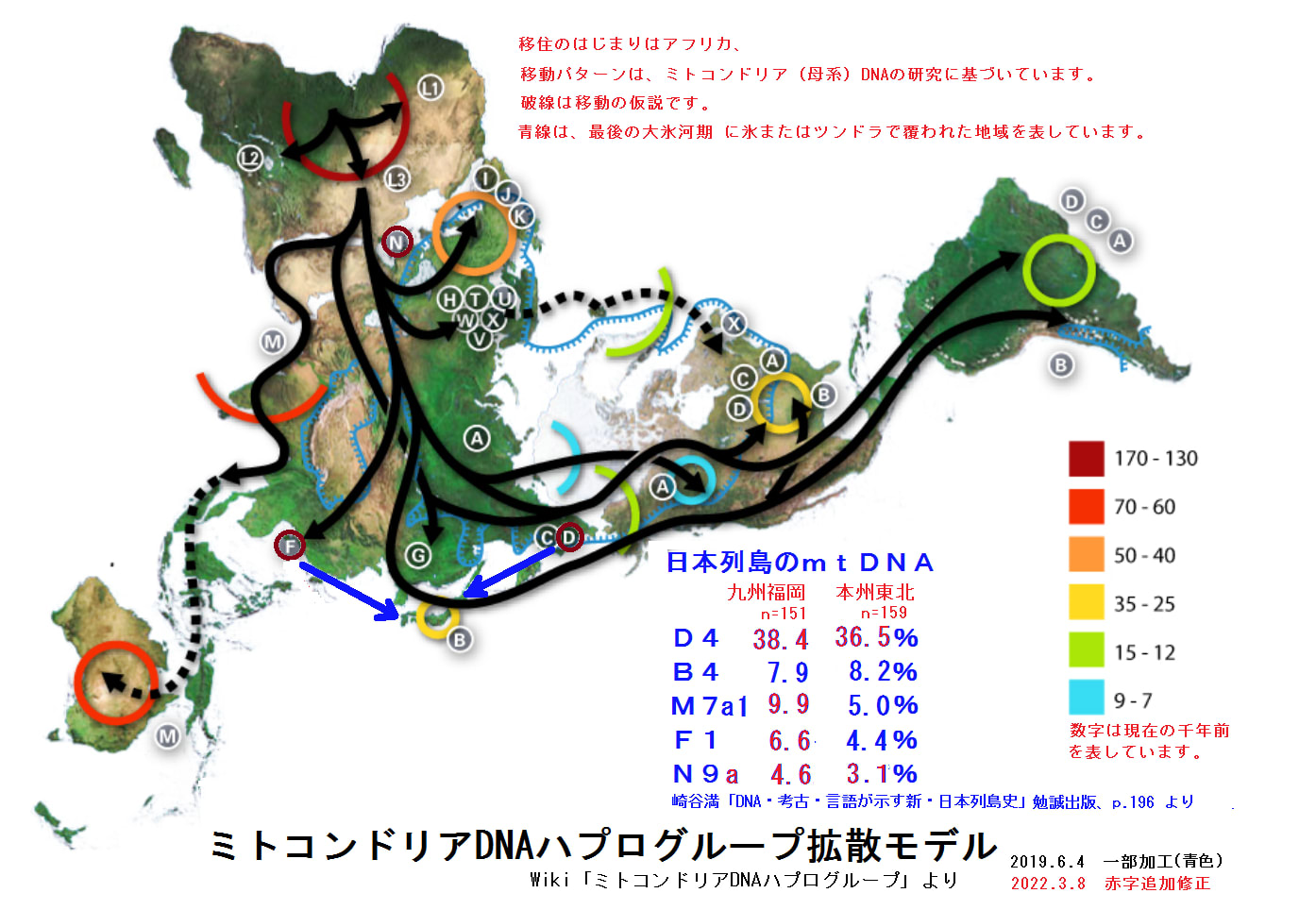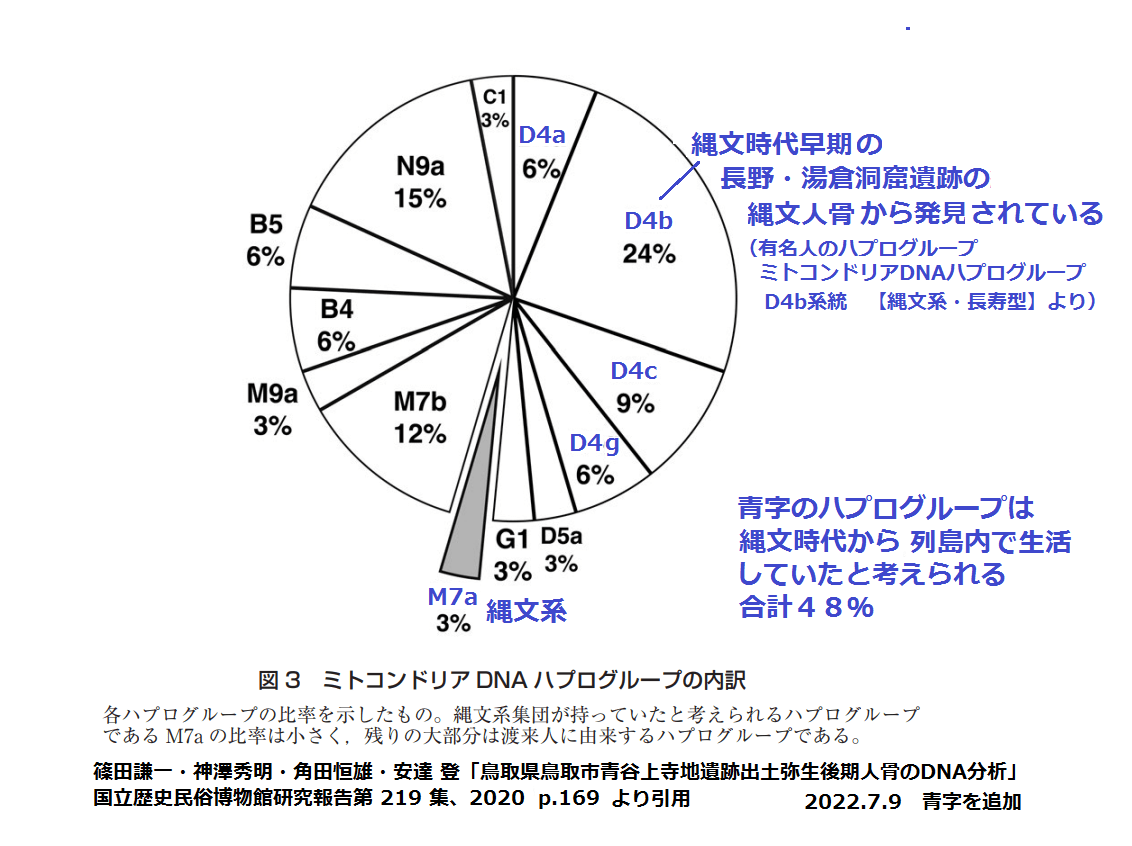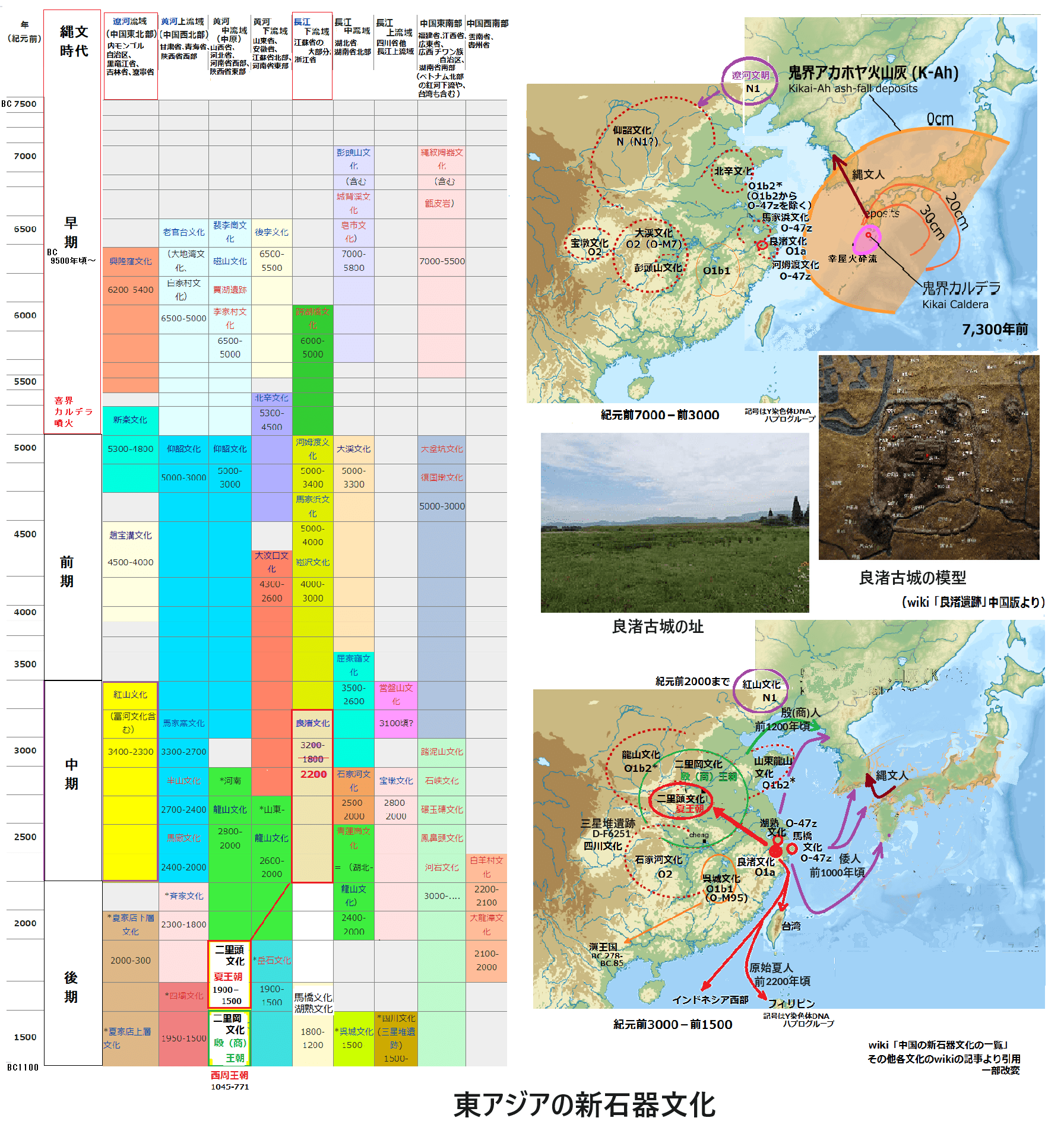いつも、ありがとうございます。
よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング

よい話題をありがとうございます。
纏向遺跡は卑弥呼が女王に共立された三世紀初頭に突然登場した祭祀・政治に特化した都市です。各地の首長クラスが集まって祈祷などを行っているのです。卑弥呼の倭国と対立する、下で説明する狗奴国(旧奴国)なのです。
纏向遺跡の外来土器に北部九州のものがありません。纏向が倭国ならば伊都国の一大率や部下などが纏向に頻繁に来ていないとおかしいんです。また、前方後円墳の重要な祭祀に北部九州の倭国の人々が参加していないのですから、倭国と対立する狗奴国とわかるのです。范曄後漢書倭伝にも「女王国より東へ渡海千里で狗奴国に至る」と明記されていますので、女王国は九州東部の周防灘に面する宇佐です。卑弥呼の巨大円墳「三柱山古墳」が見つかっています(詳細は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」参照)。
魏志倭人伝では狗奴国は女王国の南とありますが、政治的な事情で邪馬台国を呉の東方海上にあるとしたいので、嘘が書かれています。南九州に女王国と対立する大勢力など存在しません。邪馬台国への行程記事を帯方郡太守劉夏に書いて教えた人物は、107年に後漢安帝に朝貢した帥升(正しくは奴国宮廷楽師の師升、最後の奴国王スサノヲを殺して倭国を奪った)の孫の難升米だったのですよ(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?(@_@)」参照)。お邪魔しました^_-)-☆
【卑弥呼の死の直前の状況】

@KeCN
旧唐書には「倭国伝」と「日本国伝」があるので、邪馬台国と畿内大和王権は別の国(王朝)でしょうね。新唐書には日本国は倭国の別種なりとあります。白村江で大敗した倭国は衰退し、大和王権が倭国に取って代わって倭王として統一したのです。新唐書には、筑紫城にいた神武が大和を統治し天皇となったことなどが記載されているので、元々は倭と後の日本は同じ一族だと思います。
おっしゃるとおりです。新唐書にあるとおり「日本は古の倭の奴国」だったのです。つまり、元々、「王年代紀」にある初代王天御中主の子孫の歴代奴国王が支配していた倭国を別の勢力、つまり伊都国王師升(奴国宮廷楽師)に倭国が奪われたのですが、倭国大乱があり、卑弥呼が登場して、最終的に狗奴国(旧奴国)が倭国を取り戻してヤマト王権が成立したということなんですよ。詳しくは「刮目天の古代史」をご参照ください(;^ω^)
狗奴国が女王国の南だと魏志倭人伝にまんまと騙されました(*´Д`)
書かれたものにはウソがあるかも知れないので、疑わしいと思ったところは必ず、
事実(考古学や民俗学などの成果)で検証しないとダメだということですネ!
【関連記事】
ヤマト王権のルーツは吉備そして奴国だった(^_-)-☆
纏向遺跡の初期前方後円墳のルーツを調べるとやはり吉備にたどり着きます。楯築遺跡は双方中円墳という形式の古墳とされていますが、間違いなく前方後円墳のルーツです。それは特殊器台とその表面に描かれた弧帯文が証拠です(「弧帯文は龍蛇神(ナーガ)の文様だった!(^_-)-☆」参照)。

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆
10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)



卑弥呼と天照大御神が同一人物?(@_@)?
邪馬台国問題を解決するには3世紀の日本の建国の過程を解明しなければなりません。日本の最古の歴史書「古事記」「日本書紀」が天皇の歴史書だと多くの方は思っていますが、上の記事のとおり、思い込みなのです。藤原氏による勝者の歴史書だったのです。これに気付くと、事実、つまり考古学や民俗学のなどの成果から推理すると日本の古代史の真相が分かりますよ( ^)o(^ )
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
よい話題をありがとうございます。
纏向遺跡は卑弥呼が女王に共立された三世紀初頭に突然登場した祭祀・政治に特化した都市です。各地の首長クラスが集まって祈祷などを行っているのです。卑弥呼の倭国と対立する、下で説明する狗奴国(旧奴国)なのです。
纏向遺跡の外来土器に北部九州のものがありません。纏向が倭国ならば伊都国の一大率や部下などが纏向に頻繁に来ていないとおかしいんです。また、前方後円墳の重要な祭祀に北部九州の倭国の人々が参加していないのですから、倭国と対立する狗奴国とわかるのです。范曄後漢書倭伝にも「女王国より東へ渡海千里で狗奴国に至る」と明記されていますので、女王国は九州東部の周防灘に面する宇佐です。卑弥呼の巨大円墳「三柱山古墳」が見つかっています(詳細は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」参照)。
魏志倭人伝では狗奴国は女王国の南とありますが、政治的な事情で邪馬台国を呉の東方海上にあるとしたいので、嘘が書かれています。南九州に女王国と対立する大勢力など存在しません。邪馬台国への行程記事を帯方郡太守劉夏に書いて教えた人物は、107年に後漢安帝に朝貢した帥升(正しくは奴国宮廷楽師の師升、最後の奴国王スサノヲを殺して倭国を奪った)の孫の難升米だったのですよ(詳細は「伊都国の意味がヒントだった?(@_@)」参照)。お邪魔しました^_-)-☆
【卑弥呼の死の直前の状況】

@KeCN
旧唐書には「倭国伝」と「日本国伝」があるので、邪馬台国と畿内大和王権は別の国(王朝)でしょうね。新唐書には日本国は倭国の別種なりとあります。白村江で大敗した倭国は衰退し、大和王権が倭国に取って代わって倭王として統一したのです。新唐書には、筑紫城にいた神武が大和を統治し天皇となったことなどが記載されているので、元々は倭と後の日本は同じ一族だと思います。
おっしゃるとおりです。新唐書にあるとおり「日本は古の倭の奴国」だったのです。つまり、元々、「王年代紀」にある初代王天御中主の子孫の歴代奴国王が支配していた倭国を別の勢力、つまり伊都国王師升(奴国宮廷楽師)に倭国が奪われたのですが、倭国大乱があり、卑弥呼が登場して、最終的に狗奴国(旧奴国)が倭国を取り戻してヤマト王権が成立したということなんですよ。詳しくは「刮目天の古代史」をご参照ください(;^ω^)
狗奴国が女王国の南だと魏志倭人伝にまんまと騙されました(*´Д`)
書かれたものにはウソがあるかも知れないので、疑わしいと思ったところは必ず、
事実(考古学や民俗学などの成果)で検証しないとダメだということですネ!
【関連記事】
ヤマト王権のルーツは吉備そして奴国だった(^_-)-☆
纏向遺跡の初期前方後円墳のルーツを調べるとやはり吉備にたどり着きます。楯築遺跡は双方中円墳という形式の古墳とされていますが、間違いなく前方後円墳のルーツです。それは特殊器台とその表面に描かれた弧帯文が証拠です(「弧帯文は龍蛇神(ナーガ)の文様だった!(^_-)-☆」参照)。

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆
10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)



卑弥呼と天照大御神が同一人物?(@_@)?
邪馬台国問題を解決するには3世紀の日本の建国の過程を解明しなければなりません。日本の最古の歴史書「古事記」「日本書紀」が天皇の歴史書だと多くの方は思っていますが、上の記事のとおり、思い込みなのです。藤原氏による勝者の歴史書だったのです。これに気付くと、事実、つまり考古学や民俗学のなどの成果から推理すると日本の古代史の真相が分かりますよ( ^)o(^ )
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング