週刊ダイヤモンドの今週号「自動車100年目の大転換」特集。
大学生の関心ランキングの推移が面白い。
現在の4,50代と比較すると顕著なのだが、大学生の嗜好がとても多様化しているのだ。
ぱっとみただけでも、携帯音楽プレーヤー、携帯、PC、アニメ、ゲームといった新顔が
ランキング上位に名を連ねる。
一方、ランキング7位から17位へ急落しているのが自動車だ。
もうあちこちで言われていることだが、国内自動車市場の低迷は自動車自体に魅力が
なくなったのではなくて、多様化の結果にすぎない。
巨人やプロレス、ドラマの視聴率が下がったのも、というよりテレビ自体の視聴者数が
低下しているのも同じ理由だ。
素晴らしい。
みんなで巨人戦みて、トレンディドラマ(死語)に出てきたお店に並んで、ローン組んで
月に数回しか乗らない車買うような社会より、今のほうが全然楽しいから。
いくら補助金つけて買い替えを煽っても、この流れは止められない。
そしてもう一つ、このランキングからは重要な変化が読み取れる。
「語学・資格試験」と言う項目が、三世代の中で
もっとも高いのは、現在の大学生なのだ。
(書籍についても、2、30代よりは上位につけている)
いつも言っているように、大学のレジャーランド化は年功序列の副産物だ。
かばん持ち雑巾がけからスタートするのが明らかな社会において、それでも熱心に
高等教育に取り組もうとするのはごく一部の人間だけだから。
当然、日本型雇用の崩壊が進めば、以前の(というか当たり前の)健全なアカデミズムが
復活してくると思われる。
この図には、その兆候がすでにあらわれているように思う。
「最近の新人はバカだ」という意見はきわめて一面的である。
もちろん、依然としてレジャーランド脳の人も多いので、当分は二極化という形を
採ることになるのだろう。
21世紀のエリートがどちらから生まれるかは、言うまでもない。
ところで、20年以上勤められているような大学の先生に、一番勉強しなかった世代は
どの辺ですかと聞くと、なぜだか“団塊ジュニア”が上げられることが多い(笑)
言われてみると、そういう気がしないでもないが、なにか理由があるのだろうか。
大学生の関心ランキングの推移が面白い。
現在の4,50代と比較すると顕著なのだが、大学生の嗜好がとても多様化しているのだ。
ぱっとみただけでも、携帯音楽プレーヤー、携帯、PC、アニメ、ゲームといった新顔が
ランキング上位に名を連ねる。
一方、ランキング7位から17位へ急落しているのが自動車だ。
もうあちこちで言われていることだが、国内自動車市場の低迷は自動車自体に魅力が
なくなったのではなくて、多様化の結果にすぎない。
巨人やプロレス、ドラマの視聴率が下がったのも、というよりテレビ自体の視聴者数が
低下しているのも同じ理由だ。
素晴らしい。
みんなで巨人戦みて、トレンディドラマ(死語)に出てきたお店に並んで、ローン組んで
月に数回しか乗らない車買うような社会より、今のほうが全然楽しいから。
いくら補助金つけて買い替えを煽っても、この流れは止められない。
そしてもう一つ、このランキングからは重要な変化が読み取れる。
「語学・資格試験」と言う項目が、三世代の中で
もっとも高いのは、現在の大学生なのだ。
(書籍についても、2、30代よりは上位につけている)
いつも言っているように、大学のレジャーランド化は年功序列の副産物だ。
かばん持ち雑巾がけからスタートするのが明らかな社会において、それでも熱心に
高等教育に取り組もうとするのはごく一部の人間だけだから。
当然、日本型雇用の崩壊が進めば、以前の(というか当たり前の)健全なアカデミズムが
復活してくると思われる。
この図には、その兆候がすでにあらわれているように思う。
「最近の新人はバカだ」という意見はきわめて一面的である。
もちろん、依然としてレジャーランド脳の人も多いので、当分は二極化という形を
採ることになるのだろう。
21世紀のエリートがどちらから生まれるかは、言うまでもない。
ところで、20年以上勤められているような大学の先生に、一番勉強しなかった世代は
どの辺ですかと聞くと、なぜだか“団塊ジュニア”が上げられることが多い(笑)
言われてみると、そういう気がしないでもないが、なにか理由があるのだろうか。














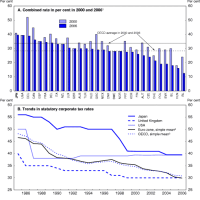





higutiさんと似た感じになりますが、自分は「仕事以外でのキャリア」と思っています。
「何とかの仕事を何年してきました。」
がキャリアになる(それ以外のことはキャリアになりにくい)現状というのは、なんとも年功序列だなあと勝手に思っています。
仕事以外で何をやってきたかを問われてもいいように、自分は仕事以外のキャリアを身に着けている最中です。
(自分はそれが資格でも学問でもボランティアでもいいと思っています)
マスコミの言説や世間一般が言う「普通」に惑わされることなく、自ら進んでいける勇気や芯の強さを持つことが第一条件だと思います。その上で、自分の考えるビジョンに向かって努力し各種の能力を高めたり追加してゆくのではないでしょうか。
ひとつのキーとしては、ある能力やスキルが必要だと思ったときに、自分にはできないと諦めたり、後でやればいいと先送りにするのではなく、その場その場で学び出来るかぎり身に着けてゆく、そういう姿勢が大事なのかなと。変化に対して柔軟であるというか。
IT化とグローバル化で、覚えること身に着けたいと思うことはますます増えてきていますが、好奇心をもって楽観的に取り組んでいれば意外と気づいたら身についていたりするのではないでしょうか。
今の20歳以下のような新世代はそういうところを当たり前のようにするようになる、とある講演会で聴いたことがあります。一転突破からマルチタスクへ。一人勝ちからコラボレーションへ。
生活の中での切り替えのスイッチがいくつも必要になるのでしょうね。
「これは変化に柔軟に対応できる人、つまり自分の能力を武器に、キャリアを形成していける人のことではないでしょうか。「士格」などがいい例だと思います。持っている人が限られているし、必要な職業のだから、状況に合わせて転職、独立も可能なはずです。」
日本のサラリーマンに「能力」など必要ない。必要なのは「忍耐」=「会社に魂を売り渡す決断」と言い換えてもいい。日本のサラリーマンが上位と下位を切り捨てた(=一定の品質枠に収まる)工業製品であることをみればそれがよく分かる。
「特になにも持っていない人でも、企業で実践を積み重ね、そこで一番になるくらいの実力をつけることができれば、自分のキャリアについて主導権を握れる機会が増えると思います。」
何も持ってない人が運良く正社員で企業に入れたとしたら、まず雑巾掛け&雑用から始まり、20代半ばででやっと仕事らしきものに参加させてもらい、30前でやっと狭い範囲を任せてもらって、気がついたら転職可能年齢が終わっている。
そもそも日本企業はガチンコの競争なんかさせないし、天と地ほどの差なんか付かないシステムになってる。
これが「日本は一度レールから外れたら戻れない」と言われる所以。一度企業社会に出たら、選択肢は下の2つのみ。
・システムにしがみつく
・ものすごく分の悪い一回勝負の「バクチ」に賭ける
それ以外で
・労働ビッグバンを起こし、何度でも挑戦できる社会に転換する。
今の日本は、実質「22才で勝負が着く社会」なんだよ。
>「21世紀型エリート」
これは変化に柔軟に対応できる人、つまり自分の能力を武器に、キャリアを形成していける人のことではないでしょうか。「士格」などがいい例だと思います。持っている人が限られているし、必要な職業のだから、状況に合わせて転職、独立も可能なはずです。
特になにも持っていない人でも、企業で実践を積み重ね、そこで一番になるくらいの実力をつけることができれば、自分のキャリアについて主導権を握れる機会が増えると思います。
私は現在、産近甲龍の中の一校に通っており、就職活動中の23歳です。1浪1留年でほとんど面接に進めず、進めたとしても絶対に今の年齢について聞かれ、落ちてしまいます。日本的雇用にも合わず、レールから外れキャリアを積める能力も、今はないです。大学生活をレジャーとして捉えてきたツケが今、一気に来ています。そしてこれからの自分を考えた結果、上記のような考えになりました。
また、上記のようなことを考えながら、キャリアを積むことが「21世紀型エリート」になる条件ではないでしょうか。
司法試験を目指して大学受験生の時より
勉強していると
やることがないので勉強している人も多いが、真剣にやっているのは少数派。昔から普通の就職するほうが多いです。ちなみに官僚内定者は90年代と比べて6割減。かわって外資志望者が増えた。
司法は受験者は増えているらしいが、これは合格者が増えたからでしょう。
>わたしは、大学に入るのは一部でいいから、中卒や高卒でも手に職を就けられて、本人が望むならば、いったん職を持ってからキャリアアップのために再び学べるような社会が最も公平だと思います。
まったく同感。行きたくもない人まで進学してブラブラして、それを養うために家計が負担しているのは社会にとって莫大な損失。行きたい人だけ、何歳からでも行ける方が合理的。一生懸命勉強するだろうし。
>「21世紀型のエリート」
一言では言えない。いろいろ読んでみて。
私もこれらに一票。
なにより一番勉強してないのって、「大学紛争」の頃な気がする。
>団塊ジュニアは競争が激しかったから、入学試験をクリアすると反動が来たんじゃないでしょうか。
あと大きいのは、あの世代だと大学に入れる人は、特に『一流大学』に入れる人は、受験戦争を勝ち抜いた今で言う「勝ち組」だけでした。それ以外の大半は大学に入ろうと思っても入れなかった。入った人は勝ち組になったのだから、一息ついてもおかしくはないでしょう。
実際にはその『勝ち組』でさえも、就職氷河期の中では「新卒で正社員になれなければ欠陥品」であることに気付くのは、そういう「欠陥品」が社会で生まれるまで待たなければならなかったのでしょう。そもそも91年頃までは、「内定取り消し」とか「新卒採用大幅減」とか「非正規雇用の自由化」なんてほとんど想定していなかったしね。
>「語学や資格試験などの勉強をすること」と「学問をすること」はぜんぜん違います。
そして『内定取り消し』や『受験戦争の勝ち組』でさえもまともに就職できない現状を見れば、その下の世代がそれに備えた「資格取得」(必ずしも学問とは限らない)していくのは当然のことでは?
>バブルの影響も大きいかもしれない。10代であの空気を嗅いでしまったことは後々まで尾を引いた気がする。
どこの誰の話か知りませんが、そういう人ばかりではないと思うなあ。あの世代だとバブルの頃は大半は受験戦争まっただ中で、受験勉強で忙しかったから。それこそ小学校受験が終われば中学受験。中学受験が終われば高校受験。高校受験が終われば大学受験と受験戦争をハシゴしてきた人なんて、気がついた頃にはバブルが終わっていましたよ。
確か、その下の世代・・・元2ちゃん管理人の、ひろゆき氏などの世代あたりでは、確か資格ブームが巻き起こっていたように思われます。会計士もその世代あたりから、合格者が1000人近くまで増え始めました。
城先生の↓の部分はとても共感できます。
>もちろん、依然としてレジャーランド脳の人も多いので、当分は二極化という形を採ることになるのだろう。
関関同立の一校に通ってますが、散々遊びまくって内定自体とれない人もいます。レジャーランドとして存分に大学生活を過ごした人々です。
気になったのは、
>21世紀のエリートがどちらから生まれるかは、言うまでもない。
という部分です。「21世紀型のエリート」これは何なんでしょうか?
近代社会は一人では生きることはできず、複雑な網の目の中に、各個人はいる。モット言うと我々は一つの社会の一部品としてしか、生存はできない。この感覚を持つ人は、少ないと私は思っている。モット言うと人は人口の中でしか生きることは不可能な存在で、その人口構造物がどのようなものかを知る必要があるかが、そのような関心は無い。
色々なもに対する見方、考え方を聞くと、見直さないでは無いだろうか。
引きこもりなど、昔なら座敷朗に入れて、食事を入れなければ治るものではないかと、私は思うが、意外とそれが分からないのが引きこもりかもしれない。
Yasさんのような意見は外国へ行った人からよく聞くが、Yasさん自身、日本的価値観を身につけるのも外国の価値観を身につけるのも同じくらい努力がいるとは考えていないでしょう。
そこが問題で、これから大変だよ。老婆心ながら言うが。
少し前にちょっとした会合があり、ソコで今の26歳から36歳くらいの人は親をうらんでいると話ス人があった。マサカと思った。何故なら我国は支那朝鮮と異なり、親が子供をかわいがる世界だから、子供が親に仕えるようにとは、教育の方向は無い。逆であるからである。
帰るとき電車の中でその話をしたら、その人が≪実を言うと私もです>というから愕いて、<何故>と聞くと、彼は<何が正しいか、正しく無いかとか之はしてはいけないとか、これがよいとか、そのようなことを全く教えてくれなかったから>というから、思わず<はあアン>と答えた。その後色々話したが、比ゆ的に言うと、学校の先生の言う事ばかり学んできたか、もしくはマスコミで流れる事をそのまま信じた人々ではないかと思った。
具体的にはできるけれどもしてはいけない。もしくはしないということを経験していないのでハとも思った。
皮肉に聞こえるかもしれないが勉強すれば東大へはいけるが、まあこんなところにしておくかという判断ができない人々とでも言うか。
>日本に帰る予定ですが、あくまでも自分に集中する。
之は簡単ではないよ。
それと価値観の転換という者は簡単ではない。死ぬか生きるかということになる。できたような価値観はその前に身についていないものに過ぎないと私は思っている。
その見本は身のまわりにいくらでもあるでしょう。
>「語学や資格試験などの勉強をすること」と「学問をすること」はぜんぜん違います。
私もそう思います。まじめに勉強するように
なったのは、資格取得のためとか就職のため
とかであって、アカデミズム発展のためという
人間は昔以上に少なくなっていると思いますよ。
まあ、早稲田や慶応ですら推薦やAOなんかで半数を占
めるようになり、就職時まで失敗する経験をしない人
間が増えすぎているから昭和的価値観が強い人の方が
多くなっているんじゃないでしょうか?
その点、就職氷河期世代は、受験と就職と挫折続きで
したからそれを乗り越えた人間は相当タフだと思いま
すよ。
ところが「将来の夢」というのはいまだに小中学校では書かせたりしています。なんか出発点から間違っている気がします。結局、脚光を浴びるような職につく人は一部分であって、まあそのようなことはわかりきっているのですが、小中学校の教師は、社会に出たり就活を経験したりしたわけではないので、現実的なキャリアについてでなく「夢」を聞いてしまうわけです。
それで、「夢はない」とか「野球選手になる」とか言っていた人たちが、大して勉強もせず、入っても意味のないような大学に入る。そこがレジャーランドではないでしょうか。
わたしは、大学に入るのは一部でいいから、中卒や高卒でも手に職を就けられて、本人が望むならば、いったん職を持ってからキャリアアップのために再び学べるような社会が最も公平だと思います。
高校入試、大学入試自体よりも、それしか社会の「階層」を決める通路がないというのを問題視すべきです。
大学に入る人をそのようにして絞れば、アカデミズムも、必要とされるような職業につく人がきちんとやっていくと思います。
司法試験を目指して大学受験生の時より
勉強しているという記事を読んだのですが
実際の所は城さん自身も含めてどうなのですか。
元東大総長の佐々木毅さんがまだ法学部長時代にも
テレビで法学部の学生は本当に勉強しているから
勉強しない大学生というのは私が教えている限り
感じないともテレビで言っているのも偶然見ました
団塊ジュニアは、ちょうど時代と価値観の転換期のハザマにはさまれてしまった。「良い大学良い会社」の価値観を半分信じながら、半分嘘だろうと思っていた。
引き篭もりが一番多いのも団塊ジュニアだそうですね。
僕自身アルコール依存症に陥り、新たな価値観を構築するために人生を費やしてきました。本当に本当に長い間苦しみました。
カナダに来て4年。日本人以外の友人がたくさんでき、欧米人の処世術を学び、宗教を研究し、日本的価値観からの脱却が34にしてようやく完了。
人生はこれからです。
日本に帰る予定ですが、あくまでも自分に集中する。
日本的常識は家畜養成のためのものですから、
真に受けてはいけませんね。
みなさん、昭和的日本を解体すべく頑張りましょう。
美紀といいます。
この度ブログを始めたので挨拶で
コメントさせて頂きました。
私のブログは競艇やギャンブルが主になっちゃうと
思いますが日常の事もいろいろ書いていくので
よかったらコメントください☆
起業を目指して様々な活動をしていた友人や私、国家試験の勉強を早くからしていた友人は独立したりベンチャーに転職したりしています。
一方、大学時代にバイトやったり女遊びしたりばかりしていた友人は大企業に就職した人も含め、結構会社にしがみついています。
意識の違いは大きいかもしれません。とはいえ、まだまだ後者の会社にしがみついている人が本当に多いですね。
そういえば「就職なんて、ハイって言ってれば決まるから」というのが、先輩からのアドバイスだった。
彼らは、生まれてから一度も好景気の実感を経験することなく過ごしてきていますから、もちろん趣味・娯楽が多様化していることも事実ですが、堅実なお金の使い方をしているのだと思います。
自動車は、維持費(大半が税金・保険)が掛かりすぎるんですよね…。大都市圏に住んでいる大学生や社会人の方は、公共交通機関とレンタ・カーで十分だと思います。
中堅大学では真面目に登校してきます。でも寝てます(笑)
ここまでで全国に100校程度。
残りの600校が問題ですね。分数の計算練習しないといけません。
復活してくると思われる。
これは違うんじゃないでしょうか。
「語学や資格試験などの勉強をすること」と「学問をすること」はぜんぜん違います。
むしろ語学や資格ばかりが重んじられて、大学で本来学ぶべきである「学問」はどんどん軽んじられるようになってきていると思います
ただ、一方ではそもそも大学の数自体が膨大に増えたことで、打ち込むに足る十分な対象そのものが希薄になってしまっている現状もあるのではないでしょうか。
こんなことでも「学」と言いうるのか、あるいはどういう「学」かよくわからないものが少なくないように思います。
昭和的価値観の中で育ってますからね。何がしたいのかを考えるより、いい大学入れって感じだったし。今の学生はちょっと前の世代を他山の石にできますけど。価値観の転換点にちょうどぶち当たっちゃたんですよね。幕末の士族みたいな。
ある時代を見たとき、見方にもいろいろあるが、風通しの良い時代は基本的に明るいと確か司馬遼太郎さんが仰っておられました(何の本かは失念)。そういう意味で明治初期は大変な時代だったのでしょうが、自分が国を創っていくんだという気概・希望が、国民にあったんじゃないかと思います。
翻って今を見ると、風通しがいいとは思えませんね。価値観は変えざるを得ず、しかし以前の構造まま生活しなければならないという矛盾の中にいるから、皆苦しいんでしょうね。
まずは価値観を変えないといけないのですが、自分自身大変苦しんでおります。
20年前だとバブルとその後だけですから、ちょっとスパンが足りないような感じもします。30年から40年くらいのスパンで見るともっと意義のある違いが見られるかも。(大学の教員は定年が遅い)
大学をレジャーランドと勘違いした。
といったような感じではないでしょうか?
どの辺ですかと聞くと、なぜだか“団塊ジュニア”が上げられることが多い(笑)
言われてみると、そういう気がしないでもないが、なにか理由があるのだろうか。
1.同世代人口200万超の受験戦争による疲弊と反動
2.中高時代に見ていたバブル大学生の生活を規範とし大金が必要なためバイト
3.98年の金融危機までは大学生には危機感がなかった
個体的資質によるのでしょうか?山口県出身者だからでしょうか?親が特異なのでしょうか?