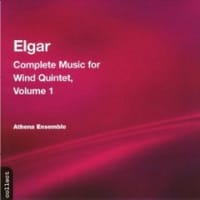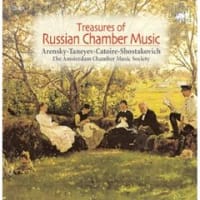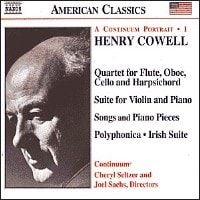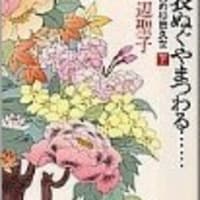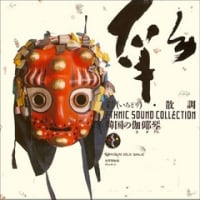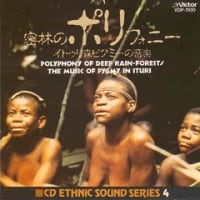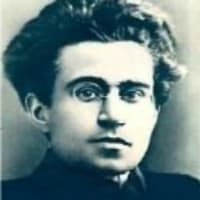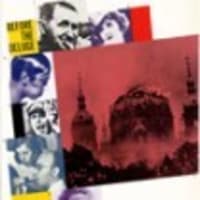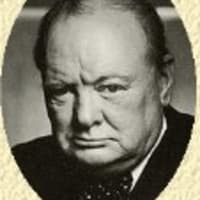昭和戦前期に、三田村鳶魚(みたむら・えんぎょ、1870 - 1952) という江戸文化や風俗の研究家が、当時流行っていた時代小説を、時代考証という観点から斬りまくった 『大衆文芸評判記』(1933) や『時代小説評判記』(1939) という文章を発表しました。
前者で槍玉に挙がったのは、直木三十五『南国太平記』、大仏次郎『赤穂浪士』、吉川英治『鳴門秘帖』、中里介山『大菩薩峠』などの時代小説10編、後者では、崎藤村『夜明け前』、吉川英治『宮本武蔵』、邦枝完二『女忠臣蔵』、菊池寛『有馬の猫騒動』、藤森成吉『渡辺崋山』など8編。
「当時の流行作家は、江戸のお目付役鳶魚を恐れると共に彼の著作を必読文献とした」とのことです。
まあ、それだけ時代小説を手掛けた作家には、「時代考証」という観念が乏しかったともいえる。
それ以降、多少なりとも鳶魚の苦言が役に立ったのか、講談と違わない程度の、さほどデタラメなものはなくなったように思えます(「大衆小説におけるライバル」での同人誌「実録文学」の記述などを参照)。
また、より広い観点からですと、歴史観と史料の取り扱いに関して、大岡昇平の『歴史小説論』などの著作も出てきています(大衆文学のみならず、歴史小説一般を読み/書くという意味で役に立つ)。
けれども、また最近の時代小説に目を通していると、鳶魚以前のレベルの作品が結構多いのね。
少なくとも、リアリズム小説という手法を採っている限り、「時代考証」という側面を無視することはできないと思うのですが……。
一例を挙げてみましょうか。
ターゲットは、谷恒生『新井白石――国家再建の鬼』(学陽書房)。
これらの店が、元禄時代からあったか、ということもありますが*、それよりも大きいのは、日本堤の様子。
広重の『名所江戸百景』「よし原日本堤」を見てもお分かりのように、よしず張りの小屋はあっても、とても「食べもの屋が軒を連らね」という具合ではない(まして、広重より100年以上前の元禄においてをや)。
どうも、この作家、現代の「土手通り」と誤解しているんじゃないかしらん。
その他、江戸城西の丸で、
まさか、お城に岡持を持った料亭の若い衆が出前してくれたんじゃないでしょうね。
あまり本質なことではない、とお思いでしょうか。
しかし「神は細部に宿り給う」。
ちょっとした部分に嘘っぽいところがあると、読者に全体の信頼性を疑わせることにもなりかねません。
やはり、三田村鳶魚翁に再度お出ましいただいた方が宜しいのではないでしょうか。
三田村鳶魚
『時代小説評判記』
中公文庫
定価:820 円 (税込)
ISBN4122035260
三田村鳶魚
『大衆文芸評判記』
中公文庫
定価:999 円 (税込)
ISBN4122035074
前者で槍玉に挙がったのは、直木三十五『南国太平記』、大仏次郎『赤穂浪士』、吉川英治『鳴門秘帖』、中里介山『大菩薩峠』などの時代小説10編、後者では、崎藤村『夜明け前』、吉川英治『宮本武蔵』、邦枝完二『女忠臣蔵』、菊池寛『有馬の猫騒動』、藤森成吉『渡辺崋山』など8編。
「当時の流行作家は、江戸のお目付役鳶魚を恐れると共に彼の著作を必読文献とした」とのことです。
まあ、それだけ時代小説を手掛けた作家には、「時代考証」という観念が乏しかったともいえる。
それ以降、多少なりとも鳶魚の苦言が役に立ったのか、講談と違わない程度の、さほどデタラメなものはなくなったように思えます(「大衆小説におけるライバル」での同人誌「実録文学」の記述などを参照)。
また、より広い観点からですと、歴史観と史料の取り扱いに関して、大岡昇平の『歴史小説論』などの著作も出てきています(大衆文学のみならず、歴史小説一般を読み/書くという意味で役に立つ)。
けれども、また最近の時代小説に目を通していると、鳶魚以前のレベルの作品が結構多いのね。
少なくとも、リアリズム小説という手法を採っている限り、「時代考証」という側面を無視することはできないと思うのですが……。
一例を挙げてみましょうか。
ターゲットは、谷恒生『新井白石――国家再建の鬼』(学陽書房)。
「(吉原の)大門前の日本堤には、けとばし屋、猪鍋屋、どじょう屋、鰻屋など精力のつきそうな食べもの屋が軒を連ね……」とあります。
これらの店が、元禄時代からあったか、ということもありますが*、それよりも大きいのは、日本堤の様子。
広重の『名所江戸百景』「よし原日本堤」を見てもお分かりのように、よしず張りの小屋はあっても、とても「食べもの屋が軒を連らね」という具合ではない(まして、広重より100年以上前の元禄においてをや)。
どうも、この作家、現代の「土手通り」と誤解しているんじゃないかしらん。
*鳶魚の『天麩羅と鰻の話』には、
「うなぎ蒲焼は天明のはじめ上野山下仏店にて大和屋といへるもの初めて売出す」(『世のすがた』、1833年・天保4年刊)
との史料が出ている。天明は18世紀後半だから、元禄とは100年近い差がある。
その他、江戸城西の丸で、
「ちかくの料亭『いちむら』からとりよせた仕出し弁当をひろげていた」なんて記述があります(この人、食い物の記述に妙なクセがある)。
まさか、お城に岡持を持った料亭の若い衆が出前してくれたんじゃないでしょうね。
あまり本質なことではない、とお思いでしょうか。
しかし「神は細部に宿り給う」。
ちょっとした部分に嘘っぽいところがあると、読者に全体の信頼性を疑わせることにもなりかねません。
やはり、三田村鳶魚翁に再度お出ましいただいた方が宜しいのではないでしょうか。
三田村鳶魚
『時代小説評判記』
中公文庫
定価:820 円 (税込)
ISBN4122035260
三田村鳶魚
『大衆文芸評判記』
中公文庫
定価:999 円 (税込)
ISBN4122035074