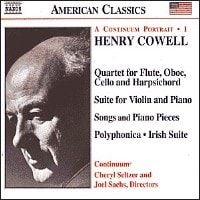全30編の東京町歩きなのだが、今出来の小洒落た町などが出てこないのが、いかにも種村調。
では、どのような町が出てくるかといえば、
上野、浅草、神楽坂などの有名どころは別にして、碑文谷、森ヶ崎、立石、大塚坂下町、というのだから、これはもう末枯れた風景が目に浮かぶようだ。
もうこうなると、懐古趣味ですらない。
しかも、そのような街々の現状や、著者の直接の記憶にダブって、例えば碑文谷の場合では、「蓮華往生」などという江戸時代の怪しげな宗教儀式が紹介される。
立石の章では、もっと古い「石」の正体。
街々には、地層のように、古くからの記憶が層をなして堆積している(それを「ゲニウス・ロキ」: Genius locii=genius 〔精霊〕of placeという)。
本書は、東京の各地の「ゲニウス・ロキ」を文章で呼び出す「マギ」、種村季弘の試みの一つであろう。
種村季弘
『江戸東京〈奇想〉徘徊記』
朝日新聞社
定価:1,680円 (税込)
ISBN978-4022578891
では、どのような町が出てくるかといえば、
「一種廃物のようななつかしい気分を感ずることが出来る」(田山花袋『東京近郊一日の行楽』)街々である。
上野、浅草、神楽坂などの有名どころは別にして、碑文谷、森ヶ崎、立石、大塚坂下町、というのだから、これはもう末枯れた風景が目に浮かぶようだ。
もうこうなると、懐古趣味ですらない。
しかも、そのような街々の現状や、著者の直接の記憶にダブって、例えば碑文谷の場合では、「蓮華往生」などという江戸時代の怪しげな宗教儀式が紹介される。
「信者に即身成仏を願うものがあるとしよう。まず希望者を募ったうえで、その人に経帷子(かたびら)を着せ、唐金(からかね)の八葉(はちよう)の蓮華の台にすわらせて葉を閉じる。坊主どもが蓮華台を囲んで木魚や鉦(かね)をジャンジャンたたき、耳を聾(ろう)せんばかりに読経の声を上げる。と、そのすきに蓮華台の下にもぐりこんだ黒衣の男が、犠牲者の肛門を槍先(焼け火箸とも)でエイヤッとばかりに刺しつらぬくのである。
ギャ、ギャッーと断末魔の叫びもものすごく、と思いきや、読経の合唱にかき消されて叫び声は周囲を取り巻く信者たちの耳には届かない。やがて蓮華の葉がおもむろに開くと、往生した信者がうっとりと安らかな死に顔を浮かべているという寸法。」
立石の章では、もっと古い「石」の正体。
「武蔵野研究でも知られた考古学者の鳥居龍蔵博士は、アイヌの建てた古代のメンヒル(巨石遺蹟)という説を提唱している。半村良の『葛飾物語』もこれを踏襲してストーン・ヘンジ説だ。もっとも、これはかならずしもそうと決まったわけでなく、現在はあまたある説の一つとされている(『葛飾の歴史と史跡・名所・文化財』葛飾区教育委員会)。
なにしろ奇怪である。石が生きて伸び成長するのだ。しかし石が生きているあるいは成長する、という考え方は、なにも立石の石、あるいは日本の石だけ(『君が代』の「さざれ石の巌となりて」は石が成長することを意味する)の特性ではない。古代ヨーロッパでも、石は生きて成長すると考えられた。しかしキリスト教が到来すると同時に石は成長をやめた。おそらく万物が生きているというアニミズム的世界観が一神教によって淘汰されたからだろう。」
街々には、地層のように、古くからの記憶が層をなして堆積している(それを「ゲニウス・ロキ」: Genius locii=genius 〔精霊〕of placeという)。
本書は、東京の各地の「ゲニウス・ロキ」を文章で呼び出す「マギ」、種村季弘の試みの一つであろう。
種村季弘
『江戸東京〈奇想〉徘徊記』
朝日新聞社
定価:1,680円 (税込)
ISBN978-4022578891