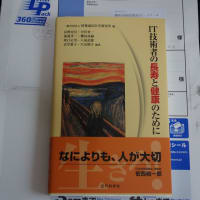入口から眺める戦前まで製糸工場の母屋であった現在の我が家。製糸工場はこの右と裏にあったが現在は痕跡も無くなった。戦時中は木製飛行機の部品工場、戦後はその機械をいかして父の経営する家具工場であった。
この玄関から眺めると前庭の雰囲気がこうなる。この写真では左は工場であったが、現在はDITの店になっている。正面には二台駐車できるスロープがある。

その向こうは旧国道であったが裏にバイパスができてご近所の往来の道となっている。その道路の向こうの光景は逆光で見難いが田んぼが広がる。休耕田になっていた。その昔は向こうに見える家並みのあたりを鉄道が走っていた。山鹿温泉鉄道、この写真の左奥に来民駅があった。毎朝鹿本高校に通学するお兄さんお姉さんで道が一杯になったものである。この鉄道は数回の台風によるトンネルの崩落で潰れた。末期には全国でも珍しいレールバスも運行していた。小学校の頃隣の山鹿まで5円だったと思う。もちろん、植木で国鉄に乗り入れて熊本まで運行していた。今これが残っていて電車にでもなっていれば世界が違うのだろうと思う。

この光景を眺める場所で我が家を見ると長い生け垣が敷地を囲んで居る雰囲気が分る。中は家屋はほんの少しで、小さな庭とその外には畑が広がり、栗、梅、柿などの果樹が植えられている。畑もイチゴ、ナス、キュウリ、など野菜類の他にガジュツなども姉夫婦が栽培している。そのための堆肥の造り方を今回お聞きした。

母屋から見る小さな庭。内部にも小さな垣根があり向こうの果樹園と区切りになっている。

この小さな池には金魚がいるようだが、サギが獲りに来るらしくネットが張ってあった。向こうの松の木の下には子供の頃不動岩で取って来た岩松が生きているようだ。この小さな池のカエルが夜ともなると大合唱でうるさいこと。
同じ場所から離れを望む。小学生の頃祖母といっしょに寝た部屋がある。

果樹園の様子。左は畑。色んなものが造られている。その昔はサツマイモ、サトイモ、トウキビ、ゴマ、陸稲、なども良くできたところ。

玄関の横の垣根の入口からはこんな雰囲気。草取りが辛いという姉に勧めて屋根材を敷いてある。横浜の我が家でも同じようなことをして楽をしている。

Facebookに玄関の写真を載せたら反響が大きく、中がどうなってるのかという興味もあるそうなのでちらりとご紹介してみた。な~~~んだ、かもしれない(笑) この屋敷内の畑は昔は反対側にもう倍ほどあって製糸工場の女工さんに給食をだすための野菜を作っていたのだと聞いた。野菜の中には大正時代としては珍しいイチゴやアスパラガスもあり、イチゴは今も生き残って毎年小さいが美味しい実を付ける。姉は大正イチゴと呼んでいるそうな。蕗、ミツバや芥子菜も残っていて自生している。
悩ましいのは、次の世代でこの田舎に住む人はいなさそうなことである。家屋の部分は長男として相続して姉夫婦に住んで頂いてもう長い。