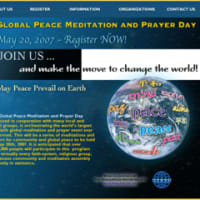「依存症の独り言」は
《a.徳川侍従長のが勇退日は昭和63(1988)年4月末日。(会見の有無は確認できず)》
としていますが、その他の「捏造派」は、4月28日の「Pressの会見」とは、徳川氏と記者との会見であり、その場に居合わせていた富田長官がその内容をメモしたものだと主張しています。そのような事実は確認できるでしょうか。
1988年(昭和63年)4月の出来事を時間順に書いてみましょう。
********************
4月12日:徳川侍従長退任。記者会見。
4月22日:奥野国土庁長官、靖国神社参拝批判を批判。
4月25日:昭和天皇記者会見。
4月29日:天皇誕生日。記者会見の内容が新聞各紙に発表。
********************
徳川侍従長が引退し、記者会見をしたのは4月12日であって、4月28日ではありません。毎日新聞には次のような記事があります。
********************
勇退の徳川侍従長が会見、昭和史のエピソードなどを語る
1988.04.12 東京夕刊 9頁 社会 写図有 (全1,556字)
宮中の生き字引、尾張徳川家の血筋、学者肌、頑固--。様々な人物評を贈られた徳川義寛侍従長が半世紀を超える侍従生活に終止符を打つ。侍従に就任したのは2・26事件の年の昭和十一年十一月。戦前、戦後の激動の中で、天皇、皇后両陛下の素顔に接し、皇室を支えてきた。次の侍従長は生っ粋の行政官。天皇の側近も大きく様変りする。
十二日午前の記者会見で徳川さんは「いつも陛下のおそばで教えていただいているうちに五十年がたってしまった」と退官に当たっての感想を語った。さらに「乾徳(けんとく)をつねに仰ぎてひたぶるに 仕へまつりぬこの五十年(いそとせ)を」と、今朝の心境を託した歌を披露した(乾徳とは天皇の徳の意味)。六十年十月、侍従長に就いた際「微風のような仕事をしたい」と述べたが、陛下の手術という“嵐”を無事乗り越え、皇居の新緑を渡る春風に送られて、昭和史のステージを去る。
********************
http://d.hatena.ne.jp/rna/20060724/p2
記者会見の内容は富田メモが語るものとはまったく違います。富田メモは、徳川侍従長の「プレス会見」のメモではありえません。つまり、「4月28日に徳川侍従長の記者会見が行なわれた」という情報こそが「捏造」であったわけです。
※ちなみに、「依存症の独り言」の
《イ.この日(4月28日)に昭和天皇陛下の会見は報道されていない。翌29日の天皇誕生日での会見は記録に残っている。
ロ.記者が天皇陛下に対してこのような質問をするとは思えない。又、質問する機会もない。》
というのは、誤った前提から出ている命題です。
・イについて言えば、昭和63年の天皇の会見は4月25日であり、29日はそれが新聞発表された日。28日には会見が行なわれなかったことは自明です。
・ロについて言えば、こんなことを天皇に質問した記者は一人もいないことは自明ですが、同時に、徳川侍従長に質問した記者もいなかったことは、上記、毎日新聞の記事を読めばわかります。これは、「Pressの会見」という表題を、「プレスの会見をメモしたもの」と短絡的に解釈したことから生じた間違った推論です。
「徳川侍従長説」は完全にその根拠を失いました。
さて、富田メモの次のパラグラフの分析に移りましょう。
********************
② 戦争の感想を問われ
嫌な気持を表現したが
それは後で云いたい
そして戦後国民が努力して
平和の確立につとめてくれた
ことを云いたかった
"嫌だ"と云ったのは 奥野国土庁長
の靖国発言中国への言及にひっかけて
云った積りである
********************
昭和天皇は昭和62年4月29日に「吐瀉」しましたが、その後徐々に体調が悪化し、ついに9月22日にガン摘出の手術を受けました。手術は成功し、昭和63年新年の一般参賀にもお立ち台に出られるほど元気を回復なさいました。そのように回復なされたので、昭和63年4月25日の記者会見が実現したのです。
記者会見の内容は――
・最近のご体調
・手術について
・皇后さまのご体調
・生物学のご研究について
・徳川侍従長の勇退について
・先の大戦について
・沖縄訪問について
です。
しかし、その後、徐々に体調が悪化し、9月19日に大量の吐血をなさい、念願の沖縄訪問をはたさず、昭和64年1月7日に崩御なされました。
4月25日の「先の大戦」のテーマについてのやりとりをここに引用しましょう。
********************
幹事記者 今年は陛下が即位式をされてから六十年目に当たります。この間、いちばん大きな出来事は先の大戦だったと思います。陛下は大戦について、これまでにも、お考えを示されていますが、今、改めて大戦についてお考えをお聞かせください。
陛下 えー、前のことですが、なおつけ加えておきたいことは、侍従長の年齢のためにこのたび辞めることになりまして私は非常に残念に思っています。
今の質問に対しては、何と言っても、大戦のことが一番厭な思い出であります。戦後国民が相協力して平和のために努めてくれたことをうれしく思っています。どうか今後共そのことを国民が良く忘れずに平和を守ってくれることを期待しています。
朝比奈記者 陛下、先の大戦のことでございますが、昭和の初めから自分の国が戦争に突き進んでしまったわけですが、その時々に陛下は大変にそのことにお心を痛められたと聞いておりますが、今戦後四十数年を経て、日本が戦争に進んでしまった最大の原因は何だったというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
陛下 えー、そのことは、えー、思想の、人物の批判とかそういうものが、えー、加わりますから、今ここで述べることは避けたいと思っています。
********************
http://d.hatena.ne.jp/lovelovedog/20060724/kaiken
ここでのポイントは「大戦のことが一番いやな思い出であります」というお言葉です。
以下の朝日新聞7月20日夕刊の記事をお読み下さい。(インターネットにアップされたのは7月21日)
********************
昭和天皇の靖国神社参拝が途絶えたのは、A級戦犯合祀(ごうし)に不快感を抱いたからだった。富田朝彦元宮内庁長官のメモは、天皇の戦争への苦い思いを浮き彫りにした。
公開された富田朝彦・元宮内庁長官の手帳と日記
A級戦犯合祀に不快感を抱いている――。その思いは、複数の元側近らから聞いていた。
「陛下は合祀を聞くと即座に『今後は参拝しない』との意向を示された」
「陛下がお怒りになったため参拝が無くなった。合祀を決断した人は大ばか者」
なかでも徳川義寛元侍従長の証言は詳細で具体的だった。
14名のA級戦犯を含む合祀者名簿を持参した神社側に対して、宮内庁は、軍人でもなく、刑死や獄死でもなく病死だった松岡洋右元外相が含まれていることを例にとって疑問を呈した。だが、合祀に踏み切った。
87年の8月15日。天皇は靖国神社についてこんな歌を詠んだ。
この年の この日にもまた 靖国の みやしろのことに うれひはふかし
徳川氏によると、この歌には、元歌があった。それは、靖国に祭られた「祭神」への憂いを詠んだものだったという。
「ただ、そのまま出すといろいろ支障があるので、合祀がおかしいとも、それでごたつくのがおかしいとも、どちらともとれるようなものにしていただいた」
側近が天皇から聞き取った『独白録』の中で、昭和天皇は日独伊三国同盟を推進した松岡洋右外相については「……別人の様に非常な独逸びいきになつた、恐らくは『ヒトラー』に買収でもされたのではないかと思はれる」とまで述べていた。
昭和天皇の「不快」の一因が、特に国を対米開戦に導いた松岡外相の合祀だったことがうかがえる。A級戦犯の14人は66年に合祀対象に加えられたが、当時の筑波藤麿宮司は保留していた。
筑波氏は山階宮菊麿王の三男。歴史の研究家としても知られた。しかし、78年に筑波氏の死去後、松平永芳宮司が就任すると、まもなく合祀に踏み切った。
松平元宮司は松平慶民元宮内大臣の長男で、元海軍少佐。父の慶民氏は、東京裁判対策や『独白録』の聞き取りなどに当たり、天皇退位論が高まった時も「退位すべきではない」と進言した有力な側近だった。
メモには、昭和天皇は慶民氏について「平和に強い考があった」と評価する一方で、永芳氏について「親の心子知らず」と評しているのにはこうした背景がある。
メモは、天皇が闘病中の88年、最後の誕生日会見直後の天皇とのやりとりだった。昭和天皇は「何といっても大戦のことが一番いやな思い出」と答えた。本来は「つらい思い出」と答える予定だった。天皇も戦争の第三者ではないからだ。
その頃、別の側近はこんなことを語っていた。 「政治家から先の大戦を正当化する趣旨の発言があると、陛下は苦々しい様子で、英米の外交官の名を挙げて『外国人ですら、私の気持ちをわかってくれているのに』と嘆いておられた」
A級戦犯合祀は、自らのこうした戦争の「つらい思い出」と平和への「強い考え」を理解していない、との天皇の憤りを呼んだことをメモは裏付けている。
「(昭和天皇の)御(み)心を心として」と、即位の礼で誓った現天皇陛下も、即位後は一度も靖国神社には参拝していない。
********************
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200607200618.html
これは、日経新聞朝刊のスクープのあとを追って朝日新聞が7月20日夕刊に書いた記事です。この記事が出た頃には、インターネットではまだ富田メモの他の部分は解読されていませんでした。
この記事で、朝日新聞は、
「メモは、天皇が闘病中の88年、最後の誕生日会見直後の天皇とのやりとりだった。昭和天皇は「何といっても大戦のことが一番いやな思い出」と答えた。本来は「つらい思い出」と答える予定だった。天皇も戦争の第三者ではないからだ。」
と書いています。朝日新聞は、「つらい思い出」を「一番いやな思い出」に言い換えた理由について、「天皇も戦争の第三者ではないからだ」という表面的な解釈を下しています。
※このような「言い換え」について新聞社が承知しているということは、記者会見の場で(あるいはその前に)天皇の発言についての何らかの「メモ」が配布されていることを示唆しています。「配布メモ」があとから配られたものであれば、そのメモは会見の場での実際の発言に即していたものになり、「言い換え」については知りようがありません。したがって、昨日のエントリーの「それともあとでメモを渡した」という部分は削除して、「それとも前もってメモを渡しておいた」に訂正いたします。
ところが、その後インターネットで明らかになった富田メモでは、「戦争の感想を問われ 嫌な気持を表現したが それは後で云いたい」「"嫌だ"と云ったのは 奥野国土庁長 の靖国発言中国への言及にひっかけて 云った積りである」とあります。
このようなことを言いうる人物は、昭和天皇をおいてほかにはありません。「言い換え」は天皇が行なったものであり、その真意は天皇だけが語りうるものです。もし徳川侍従長や別の第三者がこんなことを言ったとすれば、天皇の心をあたかも自分のことのように解説するとんでもない「不敬」にあたります。
つまり富田メモのこの部分は、昭和天皇が最初は「大戦はつらい思い出」と答える予定だったのを、実際の会見の場では、「大戦は一番いやな思い出」と言い換えたこと、そしてその理由は、「奥野国土庁長の靖国発言中国」にあると昭和天皇ご自身が富田長官に解説しているものと解釈することが最も自然です。
※記者会見の場でメモが配布されているとすれば、富田長官は当然それを入手できる立場にありますので、4月25日の記者会見をわざわざ手帳にメモすることはなかったでしょう。メモするとしたら、それは事前に作成されていた配布メモと異なった天皇の発言だけに違いありません。しかし、そういうことはほとんどないはずですから、「違い」についてはメモする必要すらなく、記憶だけでも十分です。そして、そういう記憶をもとに、「陛下、記者会見では「一番いやな思い出」とおっしゃいましたが・・・・」というように質問したことも考えられます。
なぜ昭和天皇が奥野国土庁長官の「言及にひっかけて云った」のかといえば、4月25日の記者会見の3日前の4月22日に、奥野氏が物議を醸した発言をしたからです。
※配布メモは、天皇陛下ご自身と宮内庁や側近たちの、長い時間をかけての綿密な検討をもって作成されるはずです。陛下の一言は非常な重みがありますので、片言隻句も検討されているはずです。したがって、4月22日にはすでに記者会見で配るメモは作成ずみで、ひょっとすると、すでに新聞社側に手渡されていたのかもしれません。いずれにせよ、4月22日の段階では、配布メモはもはや変更不可能であったのです。したがって、天皇陛下は自分のお気持ち、奥野氏の発言に対する反応を、会見の場での「言い換え」として表明するしかなかったのです。
《a.徳川侍従長のが勇退日は昭和63(1988)年4月末日。(会見の有無は確認できず)》
としていますが、その他の「捏造派」は、4月28日の「Pressの会見」とは、徳川氏と記者との会見であり、その場に居合わせていた富田長官がその内容をメモしたものだと主張しています。そのような事実は確認できるでしょうか。
1988年(昭和63年)4月の出来事を時間順に書いてみましょう。
********************
4月12日:徳川侍従長退任。記者会見。
4月22日:奥野国土庁長官、靖国神社参拝批判を批判。
4月25日:昭和天皇記者会見。
4月29日:天皇誕生日。記者会見の内容が新聞各紙に発表。
********************
徳川侍従長が引退し、記者会見をしたのは4月12日であって、4月28日ではありません。毎日新聞には次のような記事があります。
********************
勇退の徳川侍従長が会見、昭和史のエピソードなどを語る
1988.04.12 東京夕刊 9頁 社会 写図有 (全1,556字)
宮中の生き字引、尾張徳川家の血筋、学者肌、頑固--。様々な人物評を贈られた徳川義寛侍従長が半世紀を超える侍従生活に終止符を打つ。侍従に就任したのは2・26事件の年の昭和十一年十一月。戦前、戦後の激動の中で、天皇、皇后両陛下の素顔に接し、皇室を支えてきた。次の侍従長は生っ粋の行政官。天皇の側近も大きく様変りする。
十二日午前の記者会見で徳川さんは「いつも陛下のおそばで教えていただいているうちに五十年がたってしまった」と退官に当たっての感想を語った。さらに「乾徳(けんとく)をつねに仰ぎてひたぶるに 仕へまつりぬこの五十年(いそとせ)を」と、今朝の心境を託した歌を披露した(乾徳とは天皇の徳の意味)。六十年十月、侍従長に就いた際「微風のような仕事をしたい」と述べたが、陛下の手術という“嵐”を無事乗り越え、皇居の新緑を渡る春風に送られて、昭和史のステージを去る。
********************
http://d.hatena.ne.jp/rna/20060724/p2
記者会見の内容は富田メモが語るものとはまったく違います。富田メモは、徳川侍従長の「プレス会見」のメモではありえません。つまり、「4月28日に徳川侍従長の記者会見が行なわれた」という情報こそが「捏造」であったわけです。
※ちなみに、「依存症の独り言」の
《イ.この日(4月28日)に昭和天皇陛下の会見は報道されていない。翌29日の天皇誕生日での会見は記録に残っている。
ロ.記者が天皇陛下に対してこのような質問をするとは思えない。又、質問する機会もない。》
というのは、誤った前提から出ている命題です。
・イについて言えば、昭和63年の天皇の会見は4月25日であり、29日はそれが新聞発表された日。28日には会見が行なわれなかったことは自明です。
・ロについて言えば、こんなことを天皇に質問した記者は一人もいないことは自明ですが、同時に、徳川侍従長に質問した記者もいなかったことは、上記、毎日新聞の記事を読めばわかります。これは、「Pressの会見」という表題を、「プレスの会見をメモしたもの」と短絡的に解釈したことから生じた間違った推論です。
「徳川侍従長説」は完全にその根拠を失いました。
さて、富田メモの次のパラグラフの分析に移りましょう。
********************
② 戦争の感想を問われ
嫌な気持を表現したが
それは後で云いたい
そして戦後国民が努力して
平和の確立につとめてくれた
ことを云いたかった
"嫌だ"と云ったのは 奥野国土庁長
の靖国発言中国への言及にひっかけて
云った積りである
********************
昭和天皇は昭和62年4月29日に「吐瀉」しましたが、その後徐々に体調が悪化し、ついに9月22日にガン摘出の手術を受けました。手術は成功し、昭和63年新年の一般参賀にもお立ち台に出られるほど元気を回復なさいました。そのように回復なされたので、昭和63年4月25日の記者会見が実現したのです。
記者会見の内容は――
・最近のご体調
・手術について
・皇后さまのご体調
・生物学のご研究について
・徳川侍従長の勇退について
・先の大戦について
・沖縄訪問について
です。
しかし、その後、徐々に体調が悪化し、9月19日に大量の吐血をなさい、念願の沖縄訪問をはたさず、昭和64年1月7日に崩御なされました。
4月25日の「先の大戦」のテーマについてのやりとりをここに引用しましょう。
********************
幹事記者 今年は陛下が即位式をされてから六十年目に当たります。この間、いちばん大きな出来事は先の大戦だったと思います。陛下は大戦について、これまでにも、お考えを示されていますが、今、改めて大戦についてお考えをお聞かせください。
陛下 えー、前のことですが、なおつけ加えておきたいことは、侍従長の年齢のためにこのたび辞めることになりまして私は非常に残念に思っています。
今の質問に対しては、何と言っても、大戦のことが一番厭な思い出であります。戦後国民が相協力して平和のために努めてくれたことをうれしく思っています。どうか今後共そのことを国民が良く忘れずに平和を守ってくれることを期待しています。
朝比奈記者 陛下、先の大戦のことでございますが、昭和の初めから自分の国が戦争に突き進んでしまったわけですが、その時々に陛下は大変にそのことにお心を痛められたと聞いておりますが、今戦後四十数年を経て、日本が戦争に進んでしまった最大の原因は何だったというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
陛下 えー、そのことは、えー、思想の、人物の批判とかそういうものが、えー、加わりますから、今ここで述べることは避けたいと思っています。
********************
http://d.hatena.ne.jp/lovelovedog/20060724/kaiken
ここでのポイントは「大戦のことが一番いやな思い出であります」というお言葉です。
以下の朝日新聞7月20日夕刊の記事をお読み下さい。(インターネットにアップされたのは7月21日)
********************
昭和天皇の靖国神社参拝が途絶えたのは、A級戦犯合祀(ごうし)に不快感を抱いたからだった。富田朝彦元宮内庁長官のメモは、天皇の戦争への苦い思いを浮き彫りにした。
公開された富田朝彦・元宮内庁長官の手帳と日記
A級戦犯合祀に不快感を抱いている――。その思いは、複数の元側近らから聞いていた。
「陛下は合祀を聞くと即座に『今後は参拝しない』との意向を示された」
「陛下がお怒りになったため参拝が無くなった。合祀を決断した人は大ばか者」
なかでも徳川義寛元侍従長の証言は詳細で具体的だった。
14名のA級戦犯を含む合祀者名簿を持参した神社側に対して、宮内庁は、軍人でもなく、刑死や獄死でもなく病死だった松岡洋右元外相が含まれていることを例にとって疑問を呈した。だが、合祀に踏み切った。
87年の8月15日。天皇は靖国神社についてこんな歌を詠んだ。
この年の この日にもまた 靖国の みやしろのことに うれひはふかし
徳川氏によると、この歌には、元歌があった。それは、靖国に祭られた「祭神」への憂いを詠んだものだったという。
「ただ、そのまま出すといろいろ支障があるので、合祀がおかしいとも、それでごたつくのがおかしいとも、どちらともとれるようなものにしていただいた」
側近が天皇から聞き取った『独白録』の中で、昭和天皇は日独伊三国同盟を推進した松岡洋右外相については「……別人の様に非常な独逸びいきになつた、恐らくは『ヒトラー』に買収でもされたのではないかと思はれる」とまで述べていた。
昭和天皇の「不快」の一因が、特に国を対米開戦に導いた松岡外相の合祀だったことがうかがえる。A級戦犯の14人は66年に合祀対象に加えられたが、当時の筑波藤麿宮司は保留していた。
筑波氏は山階宮菊麿王の三男。歴史の研究家としても知られた。しかし、78年に筑波氏の死去後、松平永芳宮司が就任すると、まもなく合祀に踏み切った。
松平元宮司は松平慶民元宮内大臣の長男で、元海軍少佐。父の慶民氏は、東京裁判対策や『独白録』の聞き取りなどに当たり、天皇退位論が高まった時も「退位すべきではない」と進言した有力な側近だった。
メモには、昭和天皇は慶民氏について「平和に強い考があった」と評価する一方で、永芳氏について「親の心子知らず」と評しているのにはこうした背景がある。
メモは、天皇が闘病中の88年、最後の誕生日会見直後の天皇とのやりとりだった。昭和天皇は「何といっても大戦のことが一番いやな思い出」と答えた。本来は「つらい思い出」と答える予定だった。天皇も戦争の第三者ではないからだ。
その頃、別の側近はこんなことを語っていた。 「政治家から先の大戦を正当化する趣旨の発言があると、陛下は苦々しい様子で、英米の外交官の名を挙げて『外国人ですら、私の気持ちをわかってくれているのに』と嘆いておられた」
A級戦犯合祀は、自らのこうした戦争の「つらい思い出」と平和への「強い考え」を理解していない、との天皇の憤りを呼んだことをメモは裏付けている。
「(昭和天皇の)御(み)心を心として」と、即位の礼で誓った現天皇陛下も、即位後は一度も靖国神社には参拝していない。
********************
http://www.asahi.com/national/update/0721/TKY200607200618.html
これは、日経新聞朝刊のスクープのあとを追って朝日新聞が7月20日夕刊に書いた記事です。この記事が出た頃には、インターネットではまだ富田メモの他の部分は解読されていませんでした。
この記事で、朝日新聞は、
「メモは、天皇が闘病中の88年、最後の誕生日会見直後の天皇とのやりとりだった。昭和天皇は「何といっても大戦のことが一番いやな思い出」と答えた。本来は「つらい思い出」と答える予定だった。天皇も戦争の第三者ではないからだ。」
と書いています。朝日新聞は、「つらい思い出」を「一番いやな思い出」に言い換えた理由について、「天皇も戦争の第三者ではないからだ」という表面的な解釈を下しています。
※このような「言い換え」について新聞社が承知しているということは、記者会見の場で(あるいはその前に)天皇の発言についての何らかの「メモ」が配布されていることを示唆しています。「配布メモ」があとから配られたものであれば、そのメモは会見の場での実際の発言に即していたものになり、「言い換え」については知りようがありません。したがって、昨日のエントリーの「それともあとでメモを渡した」という部分は削除して、「それとも前もってメモを渡しておいた」に訂正いたします。
ところが、その後インターネットで明らかになった富田メモでは、「戦争の感想を問われ 嫌な気持を表現したが それは後で云いたい」「"嫌だ"と云ったのは 奥野国土庁長 の靖国発言中国への言及にひっかけて 云った積りである」とあります。
このようなことを言いうる人物は、昭和天皇をおいてほかにはありません。「言い換え」は天皇が行なったものであり、その真意は天皇だけが語りうるものです。もし徳川侍従長や別の第三者がこんなことを言ったとすれば、天皇の心をあたかも自分のことのように解説するとんでもない「不敬」にあたります。
つまり富田メモのこの部分は、昭和天皇が最初は「大戦はつらい思い出」と答える予定だったのを、実際の会見の場では、「大戦は一番いやな思い出」と言い換えたこと、そしてその理由は、「奥野国土庁長の靖国発言中国」にあると昭和天皇ご自身が富田長官に解説しているものと解釈することが最も自然です。
※記者会見の場でメモが配布されているとすれば、富田長官は当然それを入手できる立場にありますので、4月25日の記者会見をわざわざ手帳にメモすることはなかったでしょう。メモするとしたら、それは事前に作成されていた配布メモと異なった天皇の発言だけに違いありません。しかし、そういうことはほとんどないはずですから、「違い」についてはメモする必要すらなく、記憶だけでも十分です。そして、そういう記憶をもとに、「陛下、記者会見では「一番いやな思い出」とおっしゃいましたが・・・・」というように質問したことも考えられます。
なぜ昭和天皇が奥野国土庁長官の「言及にひっかけて云った」のかといえば、4月25日の記者会見の3日前の4月22日に、奥野氏が物議を醸した発言をしたからです。
※配布メモは、天皇陛下ご自身と宮内庁や側近たちの、長い時間をかけての綿密な検討をもって作成されるはずです。陛下の一言は非常な重みがありますので、片言隻句も検討されているはずです。したがって、4月22日にはすでに記者会見で配るメモは作成ずみで、ひょっとすると、すでに新聞社側に手渡されていたのかもしれません。いずれにせよ、4月22日の段階では、配布メモはもはや変更不可能であったのです。したがって、天皇陛下は自分のお気持ち、奥野氏の発言に対する反応を、会見の場での「言い換え」として表明するしかなかったのです。