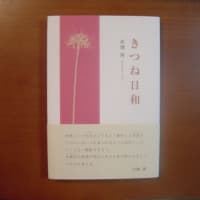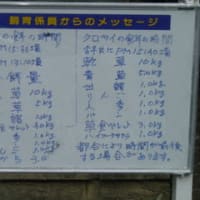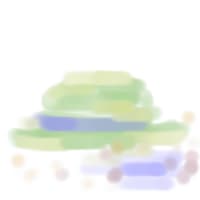『楽園』は藤原龍一郎さんの第八歌集。
平成十八年七月二十五日、角川書店発行(角川短歌叢書)。定価2571円(税別)。
・明日は夏至 永久に帰れぬあの夏のヨットの真赤 なしくずしの死
これは歌集冒頭の一連「イエスタデイ」の2首目におかれた歌。
「明日は」と未来を予感しつつも、藤原さんが追うのは「永久に帰れぬあの夏」である。
藤原さんは、たしかにあったはずなのに、今となってはもはや取り戻すこともできない歳月を、
ふたたび会うことも出来ない人々を、戻ってくるはずのない時代を、
くり返しくり返しその作品に歌い上げる。
それはなぜなのか。
そこに歌人としての藤原龍一郎の存在理由があると言ってしまっては、あまりにも安易にすぎるだろうか。
しかし今年「短歌研究」に連載中の藤原作品には、朔太郎、キシガミ、乱歩・・・と、今となっては
もはや会うことも見ることもかなわない先人たちが登場する。
そしてその面影を或いは魂をひたすら作品上に追い求めようとしているように思えるのだ。
作品中には数年前に他界した春日井建も、今春亡くなったばかりの山中智恵子も出現した。
果たしてくり返しくり返し死者たちを歌うのはなぜか。
先人たちへの鎮魂ともリスペクトとも思えるこれらの作品を読むとき、
読者であるわたしは「もはや今日ここにはいない」彼らを、藤原さんと同じように
追っているようにも思えるし、
時には藤原さんのその熱意に圧倒されて、ただ茫然と立ち尽くしてしまうようにも思える。
一体ひとはなぜ歌(短歌)をうたうのか。
この歌集を読みながら、そのような根源的な問題を突きつけられているように感じた。
以下、この『楽園』より数首紹介しておこうと思う。
どうか直にこの『楽園』にふれて読んでほしいと願う作品ばかりだ。
・燃え尽きて白き灰への蕩尽はジョーのみならず のみならず今日
・汐留に高層ビルは群生し千年のちの廃墟を見せる
・子規の声聞こえてくるか湾岸に終りの秋の雲が流れる
・季寄せ入り電子辞書もて分け入るかかつて芭蕉も越えたる曠野
・荷風訳『珊瑚集』さえ慰謝なれば驟雨が夜半の湾岸を撃つ
・「さよなら、さよなら」鸚鵡が無邪気に繰り返しもう一度ヤスケンにサヨナラ
・クセのあるペン字のハガキくれしゆえ高瀬一誌はインクの匂い
・啄木をブルースにして口ずさみ何処へ脱出したきや 友よ!
・降る雨をすべて飲み込む巨大なる幻獣としてこの定型詩

平成十八年七月二十五日、角川書店発行(角川短歌叢書)。定価2571円(税別)。
・明日は夏至 永久に帰れぬあの夏のヨットの真赤 なしくずしの死
これは歌集冒頭の一連「イエスタデイ」の2首目におかれた歌。
「明日は」と未来を予感しつつも、藤原さんが追うのは「永久に帰れぬあの夏」である。
藤原さんは、たしかにあったはずなのに、今となってはもはや取り戻すこともできない歳月を、
ふたたび会うことも出来ない人々を、戻ってくるはずのない時代を、
くり返しくり返しその作品に歌い上げる。
それはなぜなのか。
そこに歌人としての藤原龍一郎の存在理由があると言ってしまっては、あまりにも安易にすぎるだろうか。
しかし今年「短歌研究」に連載中の藤原作品には、朔太郎、キシガミ、乱歩・・・と、今となっては
もはや会うことも見ることもかなわない先人たちが登場する。
そしてその面影を或いは魂をひたすら作品上に追い求めようとしているように思えるのだ。
作品中には数年前に他界した春日井建も、今春亡くなったばかりの山中智恵子も出現した。
果たしてくり返しくり返し死者たちを歌うのはなぜか。
先人たちへの鎮魂ともリスペクトとも思えるこれらの作品を読むとき、
読者であるわたしは「もはや今日ここにはいない」彼らを、藤原さんと同じように
追っているようにも思えるし、
時には藤原さんのその熱意に圧倒されて、ただ茫然と立ち尽くしてしまうようにも思える。
一体ひとはなぜ歌(短歌)をうたうのか。
この歌集を読みながら、そのような根源的な問題を突きつけられているように感じた。
以下、この『楽園』より数首紹介しておこうと思う。
どうか直にこの『楽園』にふれて読んでほしいと願う作品ばかりだ。
・燃え尽きて白き灰への蕩尽はジョーのみならず のみならず今日
・汐留に高層ビルは群生し千年のちの廃墟を見せる
・子規の声聞こえてくるか湾岸に終りの秋の雲が流れる
・季寄せ入り電子辞書もて分け入るかかつて芭蕉も越えたる曠野
・荷風訳『珊瑚集』さえ慰謝なれば驟雨が夜半の湾岸を撃つ
・「さよなら、さよなら」鸚鵡が無邪気に繰り返しもう一度ヤスケンにサヨナラ
・クセのあるペン字のハガキくれしゆえ高瀬一誌はインクの匂い
・啄木をブルースにして口ずさみ何処へ脱出したきや 友よ!
・降る雨をすべて飲み込む巨大なる幻獣としてこの定型詩