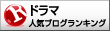なんてことだ! 生まれて初めて、自分のケータイ番号を記したメモを、女の子に渡してしまった!
マチダさん(仮称)はたぶん30歳前後だから「女の子」と呼ぶのは失礼かも知れないけど、今年の誕生日でついに還暦を迎えてしまう僕から見れば完璧に女の子だ。実際はいないけど、もし僕に子供がいたなら、我が子よりも若い娘をナンパしたことになる!
老人ホームで二年前から介護職員をしている僕と、同じ施設の新入り看護師であるマチダさんは、それぞれ退勤時間までノンストップで動き回る多忙さで、顔を合わせる機会も少ないし、そんな中で同僚たちにバレないようメモを渡すチャンスは、滅多にない。
でも、早く渡したかった。どうしても渡したかった。僕は、自分を変えたい。前向きな人間になりたい。そうしないと、残りの人生が虚しいものに、きっとなると思うから。フラれてもいい。「キモい」と思われてもいい。とにかく自分から積極的に動くことにこそ意味がある。

僕はチビだしメガネだし、ここ数年で前髪がどんどん寂しくなっているけど、清潔感にはすごく気をつけてる。なにせ周りにいる同僚にしろ入居者さんにしろ、大半が女性なのだ。今さら「モテたい」なんていう野望はなく、ただ嫌われたくない一心。この職場で女性に嫌われたら、きっと居られなくなる。
でも、今回はちょっと違う。結果的に嫌われることになっても、マチダさんには何が何でも好意を伝えたい。もう二度と、若い頃みたいな過ちは冒したくない!

20代の頃、僕はちょっと可愛い顔だった。自主制作の映画で、監督とか主演とかしてたお陰もあり、女の子に好意を示されることも、少しはあった。
なのに僕がファーストキスを経験したのは、あと数か月で30代に突入するというタイミングだった。それも、酔っぱらうと誰彼かまわずチュウしちゃう「キス魔」の女の子に奪われた形で。
それくらい、僕は女性に対して臆病だった。今も臆病だけど、20代までは異常に恐れていたと思う。そのせいで、僕は女の子と交際できる絶好のチャンスを、何度も逃してきた。

たとえば、映像制作の専門学校に通ってた頃。僕が監督する映画のスタッフになった、僕よりチビでチャーミングなクミちゃん(仮称)が、ほかのスタッフに「この中にいる男でカレシにするなら誰?」という愚かな質問をされたとき、迷わず僕を指差してくれたのだ。
「ええっ、なんで!?」
「う〜ん……お父さんみたいだから」
「ああ、そういうことね」
その愚かなスタッフと同じように僕も思った。異性としての好意とは違うんだと。
だがしかし! 夏休みが終わりに近づいた頃、クミちゃんから電話がかかってきた。諸事情あって、専門学校を辞めるという報告だった。
「えっ、そうなん? 辞めて欲しくないなあ」
「え……なんで?」
「なんでって……クミは面白いし、いないと寂しくなるやん」
「ああ、そういうことか」
明らかに、ガッカリした言い方だった。えっ、なにか違った返事を期待してくれたの!?って、すぐに気づいたけど、もう撤回のしようが無い。僕も彼女が好きだったのに、二度とないチャンスを逃したのだ。
それと似たような過ちを、僕は何度も冒してきた。もし、僕が勇気を奮っていれば、少なくともデートには漕ぎ着けただろう。
自信がなかった。仮にデートしたとて、なにを話せばよいやら分からない。あっ、そう言えば、こんなこともあった。いま思い出した!

同じく専門学校時代に、初めて参加した「合コン」とやらで、1ダースの数はいたであろう男女の中、ただ1組だけマッチングに成功したのが、なんと僕だった。
そのときはデートに漕ぎ着けたのに、やっぱり何を話してよいやら分からず、なぜか僕は長年の親友であるカラマツ(仮)との絆がいかに深いかを懸命になって語り、当然のようにフラれてしまった。
あとで知ったことだけど、合コン相手のメンバーたちに、僕はホモだと思われたらしい。違う! むしろ僕は男という生きものが大嫌いで、女の子がめちゃくちゃ好きなのに! むっつりスケベなのに! ど変態なのに!

結局、初めてのカノジョになってくれたのは、酔った勢いで僕の唇に吸いついた「キス魔」の子だった。その後も何度か恋愛をしたけど、相手は僕の臆病という壁を平気で突き破る、勢いを持った子ばかり。つまり百戦錬磨で、そんな子がビクビクしっぱなしの僕に満足するワケもなく、どれも長くは続かなかった。
そもそも、僕は壁を突き破ってくれた子らを受け入れただけで、本当に相手を愛してたかどうか、正直そこにも自信がない。だから続くワケも無いのだ。
僕に恋愛は向いてない。まして結婚なんかしたいとも思わない。けれどホモじゃないことだけは強く主張したい。女性が大好きなのに自分で壁を破れないから、ど変態なのだ。

そんな僕に、なぜか顔を合わせるたび声をかけてくれるのが、同じ老人ホームで働く新入りナースのマチダさんだ。声がけどころか、嬉しそうに手を振ってくれたりもする。なぜ?
1週間ほど前、その理由が分かった。自分で言うことじゃないけど僕は人あたりが良く、特に女性に対しては優しい。他人様の生命を預かる厳しい職場にいると、僕みたいな同僚は彼女にとって有難い存在なのだ。
「だって、なにを尋ねても優しく答えてくれるから、いてくれないと困ります」
ああ、そういうことか。たとえば何十人といる入居者さんの名前とか、そう簡単に憶えられるワケがないのに「まだ憶えられないの?」って、言葉にせずとも答えるときの表情や、声のトーンで伝えてくる先輩は少なくないだろう。
一旦はそれで納得したけれど、一昨日、職員用の食堂で僕がポツンとひとりで昼ごはんを食べていたら、たまたまマチダさんもひとりで食事にやって来て、「ここ、いいですか?」と、わざわざ真正面の席に着くもんだから驚いた!
けど、なぜか僕は緊張しなかった。マチダさんが僕を毛嫌いしていないことは既に知ってるし、怖い先輩に質問できない彼女の気の弱さに、僕はたぶん自分と同じ匂いを感じているのだ。
それにこのとき、僕にはとっておきの話題があって、親友との絆を延々と語る必要がなかった。その話題とは、昨年から自分の体力と気力が急降下し、1日中ノンストップで動き続けるハードワークに限界を感じ、上司にワガママを言ってフルタイムの勤務を半日に減らしてもらったこと。
「えええ〜っ!?」
マチダさんは、僕より小さな躰をのけ反らせ、本当に残念そうなリアクションをしてみせた。
まあ、その気持ちは解る。なにせ僕自身、いつも味方になってくれた先輩職員を二人、退職という形で失ったばかりなのだ。思い返せば、二人が辞めると知ったときは僕も身をのけ反らせた。それくらいショックだった。解るよマチダさん。ごめん!
さて……ここで話が終わっていれば、自分のケータイ番号を記したメモを彼女に渡そうなんて、僕は発想もしなかったと思う。問題は、この後だ。

ちょっと前の公休日に、歯医者さんへ治療を受けに出かけたとき、駐車場からたった50メートルほど歩いただけでゼエゼエ言ってる自分に愕然とした僕は、即座に人間ドックを受けることを決め、大病院に電話して予約を入れた。かかりつけ医の紹介状は要らなかった。
それをマチダさんに話すと、彼女はこう言ったのだ。
「私も、いざとなったとき、そこ行きます。こんど連絡先教えてください!」
もちろんお安い御用だけど……令和の時代、そんなのインターネットで検索すれば「秒で片づく」こと。あれ? これってもしかして……まさか?
男とは、妄想する生きものだ。それが無ければ求愛する勇気が湧かず、子孫繁栄につながらない。だから生まれたときから遺伝子に組み込まれてるに違いない。
それは闘争心と表裏一体で、平和な時代が続くと失われていくのかも? 還暦近くまで人に暴力を振るった経験がない僕には、妄想力も足りなかったような気がする。無くはなかったけど、平和主義がそれを抑えて来たのだ。
なのに今回は、妄想が止まらない。つまり、彼女は誘いを待っているんじゃないのか? あわよくば、とっても久しぶりに、僕は女体を抱けるのかも知れない!と。
若い頃は、そこで「いや、勘違いだったらどうしよう」とブレーキをかけてしまい、せっかくのチャンスを自分で潰していた。そんなことの繰り返しだった。悔しくて悔しくて仕方がない。今回を逃したらもう、そんなチャンスは二度と巡って来ないだろう。
僕より小さくて、丸いメガネが似合ってて、ポニーテールっぽく結んだ髪がまた可愛くて、いつも一生懸命な彼女は、もしかしたらずっと待ちわびた運命の……とまでは思わないけど、心の底から、う〜ん寝てみたい!と思う。

昨日、人間ドックの連絡先を書いたメモに「もし、職場では言えないグチとか話したくなったら、気軽に電話ください」というメッセージと自分のケータイ番号を添えて、僕はマチダさんに手渡した。勤務中の数少ないチャンスを、ほんの一瞬のチャンスを、僕は逃さなかった!
彼女は頬が真っ赤だったけど、それは直前までお風呂場で入居者さんの看護をしていたから。それを自分のせいだと思い込むほどの妄想力が男には必要だと、つくづく思う。
あまりに忙しすぎて、彼女は4つに折り畳まれたメモをその場では開いていない。たぶん勤務が終わってから、ロッカールームか、マイカーか自宅で開いて、見てたいへん驚くに違いない。僕がそんな大それたことを、図々しいことをシレッとする人間だとは、誰も思っていないだろう。僕自身がいちばん驚いてることだし。
そこまでの光景は目に浮かぶけど、直後に彼女がどんなリアクションをするのか、まったく想像がつかない。身をのけ反らせて「わあ、嬉しい! さっそく電話しよう!」って言うに決まってると思えるだけの妄想力が、やっぱり僕には無い。「うわっ、きもっ!」と言われ、今後は職場で顔を合わせても無視される……という極めて現実的な予想が、どうしても上回る。
ああ、怖い! 怖いけど、番号を教えなきゃ電話はかかって来ないし、実のところ、かかって来なくてもいいのだ。
この僕が、生まれて初めて積極的に、女の子にアプローチをかけたという事実。そこに最大の意味がある。もう後悔したくないし、むしろ残りの人生はドキドキ、ハラハラと楽しみたい。安全運転をやめ、ギアをトップに入れるのだ!
帰宅後はケータイを手放さず、まさにドキドキ、ハラハラと就寝までの時間を過ごしたけれど、着信音はピクリとも聴こえず、僕はガッカリしながらホッとした。

そして今日、僕は出勤し、まず食堂で昼ご飯を食べた。その後でタイムカードをセンサーにかざし、自分が働く部署につながる階段へと向かう。すると!
その階段を、女子職員が急いで駆け下りて来た。うわっ、いきなりマチダさんだ! おい、ちょ、待てよ! 心の準備が全然できてない!
彼女はまだ、私の存在に気づいていない。でも急ぎ足だから、1秒も経たず鉢合わせになるだろう。やっぱり怖い! 無視されるのが怖い! 使用済み紙オムツを見るような眼をされるのが怖い! 僕はなんてことをしちまったんだ!
そしてどうやら、マチダさんの視界に、うすら禿げた僕の姿が入った。
(つづく)
☆☆☆☆☆☆☆
以上、練習がてら、いま実際に経験していることを小説風に書いてみました。最後の1行までちゃんと読んで貰えたらまずまず成功、早く第二章が読みたい!とまで思って貰えたら大成功じゃないかと思ってます。
もちろん文学にはまったく程遠く、もっともっと推敲を重ねて、謎を小出しにしたり、情景描写や比喩表現を入れたりしないとダメなのは分かってます。
けど、これを1日で、夢中になって書けたことが何よりの成果。それだけの執筆意欲があれば、少なくとも中篇ぐらいの小説はきっと書けるでしょう。
もし、今回みたいなのも小説として成立するなら、ネタはいくらでも、誰にだってありますよね。人生そのものがネタの宝庫!
私にはたぶん、空想世界をゼロから築き上げるような才能は無いけど、実際に起きたことを面白おかしく文章にする才能なら、少しはある。
例えばこのブログで書いた、中学時代に親友Hと看護学校の女子寮を覗きに行った話とか、舞台『サロメ』の観劇記をヘロデ王になりきって書いた記事とかは、自分で読み返しても笑えます。そういうパロディー的な才能だけはある。
圧倒的に足りてないのはやっぱり、文学的な表現力。こればっかりは学んでいくしかない。
今日、たまたまラジオで、太田裕美さんが唄われた世紀の名曲『木綿のハンカチーフ』を聴いて、また泣いたんだけど、あれは歌詞で描かれたストーリーだけじゃなく、「都会の絵の具に染まらないで帰って」とか、「木枯らしのビル街、からだに気をつけてね」などの比喩表情がめちゃくちゃ効いてますよね。
たった1行で主人公の想いと情景が読み取れるし聴き取れる。もちろん素晴らしいメロディー(歌詞に反して明るい!)との相乗効果もあるにせよ。
まあ、そのレベルまで意識しちゃうと書けなくなるだろうから、とにかく書きたいことを好きなように書いて、あとから直していくというやり方しかありません。プロの作家さんだってそこは同じでしょう。
とりあえず、要望があろうと無かろうと、マチダさん(仮称)にまつわる話だけは、小説風に書いて行こうと思ってます。どうか、第二章であっさり終わる(つまり即フラれる)ような結果にならないよう応援して下さい!