航空自衛隊小松基地所属のF15戦闘機墜落事故で殉職した操縦員2名(1佐・1尉)が帰還したが、殉職した隊員に心からの哀悼を捧げる。
事故は、1月31日の夕刻、基地離陸直後に基地の西北西5㎞に墜落したものであるが、操縦員はブルーインパルスにも選抜されるほどの技量であったことから突発的な故障であろうとされている。
遺体捜索には海自と海保の艦艇・航空機が当たったとされるが、海自兵力の詳細は明らかでないもののネット上の写真等を見るとヘリ空母型護衛艦「ひゅうが」と潜水艦救難母艦「ちよだ」であるよう思える。
今回の事故では、墜落地点がほぼ特定されていることから、捜索には直ちに「ちよだ」の深海潜水員を投入したことで早期の機体発見と遺体収容ができたものと思うが、自分が経験した一時代前の航空機救難について書いてみたい。
昭和50年代中頃、海自ヘリコプターが美保関北方で墜落し、搭乗員の一部は脱出・救助されたものの正副操縦士は機体とともに行方不明となった。
自分が乗っていた掃海艇は半月に及ぶ「むつ湾掃海特別訓練」を終えて舞鶴帰投中であり、墜落の一報と機体捜索参加の命令は能登半島沖で受けた。舞鶴入港後に燃料や糧食を緊急補給して、直ちに墜落海面に急行したが海域到着はヘリ墜落から4日後であった。海域到着後に機雷探知機による機体発見に努めたが、乗り組んでいた掃海艇の機雷探知機は旧式で物体の識別能力も低く、加えて現場海域の水深は150mと探知能力の限界に近かった。位置極限の方法は「クラスター法」といって墜落予想地点を含む海域を規則的に走行して、探知機が「何かある」と複数回反応した箇所を候補地点(クラスター)とする前時代的なものであった。5日程の努力の結果複数個所のクラスターを作成したものの識別は不可能であったが、漸くに呉・横須賀基地から最新鋭掃海艇が到着して識別した結果、墜落ヘリコプタの位置を示す浮標を設標できたのは、墜落から半月以上も経っていた。
遺体の引き上げについても、当時の海自には深海潜水の技術・装備がなかったので、民間船「ネリウス」のダイバーが2名の頭部を収容し得たのは、墜落から2か月近くも経過していた。
今回の事故と往時の事故の事後対応を比べると隔世の感に打たれる。
今回の報道では、30年近いF15戦闘機の安全性と事故原因に関するものが殆どであるが、今回の救難・救助活動における装備や技術の向上にも目を向けて欲しいと願うところでる。なぜならば、これらの進化は、何時かは国民の不測の事態に対しても有効に機能することが期待できるからである。











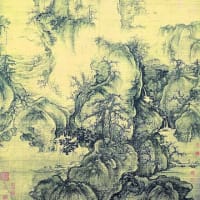








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます