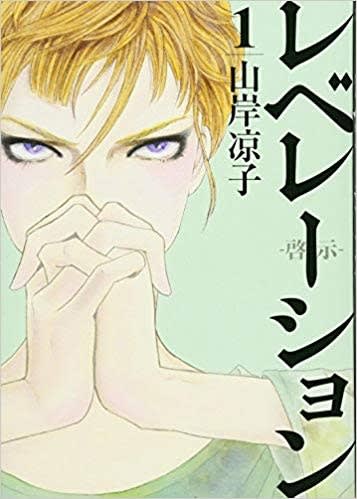


進行形で読んでいるマンガのひとつ、と言っても単行本になってからの話なので今現在お話がどうなっているのかは知らないので、3巻までの内容として書いていきます。
以下、内容に触れますのでご注意を。
宗教に関連した歴史もの長編ということですぐに「日出処の天子」と重ね合わせて読む人も多いと思うけど、はっきりと同じ意識で描かれている作品でありますね。
「日出処の天子」の感想で書いたように厩戸皇子は山岸凉子氏が抱えている疑問を“女と見まごう美しい男性”という形で表した作品だった。
作者は男主人公の口を借りて「私たちが組めば世界を変えられる。それでも、お前(男である毛人)は子供を産める女を選ぶのか?」と問いかける。世界を変えてしまうほどの能力より「異性と交わって子供を作ること」こそが「自然の摂理」だという毛人の答えに厩戸皇子は絶望する。
世界は男たちの力で作られ動かされている。その中で女たちは利用されていく。それが世界の仕組みだ。その仕組みから逃れることはできない。でもそれで本当にいいのか?と作者は怒りを込めて描いたのだった。
本作「レベレーション」でも実は問いかけは同じだ。というより山岸凉子という作家は一貫して同じ疑問を作品の中で訴え続けているのである。
「日出処の天子」で女と見まごうほどとはいえ男である厩戸皇子を借りて表現したことを今度は女性であるジャネット=ジャンヌ・ダルクによって語ろうとしているのだ。
ジャンヌ・ダルクと言えば「女だてらにフランス軍を率いてイギリス軍を蹴散らし、オルレアンを取りもどした」「髪を短く切り男装をしたことで異端者とみなされた」「神の啓示を受けて自分を神の使者と考えたちょっと頭のおかしな女」などというような
イメージがすぐに湧くだろう。
山岸凉子氏はそのようなジャンヌ・ダルクへの批評はは男性社会で活躍する女性が常に言われ続けてきた言葉と同じではないかと語る。
美しく善良な姉カトリーヌが嫁ぎ先で受けたそしりと暴力。石女=子供の産めない女め、夫からの絶え間ない暴力DVに耐え続けなけらばならないのが女だ。
女は父親が選ぶ男としか結婚できないのか。好きな男と寄り添うのは許されないのか。
ジャネット=ジャンヌ・ダルクは絶望の中で神の声を聞く。
「王を助けよ」と。
父親からは女のおまえに何ができる、とののしられ、信頼する司祭からも「現実から逃れたかったために神の声を聞いたのではないか」「女の身でなにができようか」と諭される。この時の司祭の言葉は非常に重要なものだ。「それでも人はその声に囚われてはいけないのだ」
神の声を聞いたものはと途轍もない力を持ってしまうのだろう。その力をコントロールできる者は少ない。まして女の身では自分をコントロールするだけではなく他者も操る能力を要する。それなしでは破滅へと行き急ぐ運命を免れないのだ。
そこがこの物語の要となる。
神の声を聞き、危うい戦争で勝利をものにする奇跡。
男であれば「英雄」として尊敬を得るはずだ。
だが、女であるというだけで、それは「異端者」であり「異常者」であり「頭のおかしな女」と謗られ、辱めを受け死刑となってしまったのだ。こんなことができるのは魔女に違いないと烙印を押され恐れられる。
ならば女はどう生きればいいのか。
男の中で戦わなければ、男に従って暴力を受けるしか生きる術はないというのに。
上手く世渡りをしてうまく男を扱えばいいのよ、という方法をジャネット=ジャンヌ・ダルクは拒絶した。拒絶したかった。それは許されないことなのか?と「レベレーション」で作者は問うている。
男社会の中で戦うことを(神の声を聞いて)選択したジャネット=ジャンヌ・ダルクは女の体であることに苦悩する。男たちの性的な嫌がらせ、セクシャル・ハラスメントは避けられない苦痛だ。
神の使命を負って戦ってる最中でも女は絶えずそのことを意識し男からのセクハラを退ける努力を払わないといけないのである。
ジャンヌ・ダルクが処女(ラ・ピュセル)である、ことが重要視される。処女(ラ・ピュセル)であるためにフランス軍の男たちは彼女に従ったのだろうか?アイドルは処女でなければその価値を失うということなのだろうか。
ジャネット=ジャンヌ・ダルクは穢れ泣き少女そして処女であるがために純粋に疑いもなく神を信じ男たちを従えて戦う。その危うさ。
急げ!急げ ラ・ピュセル!
と3巻は幕を閉じる。
ジャンヌの人生が向かうこの先の闇を私たちは見つめなければならない。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます