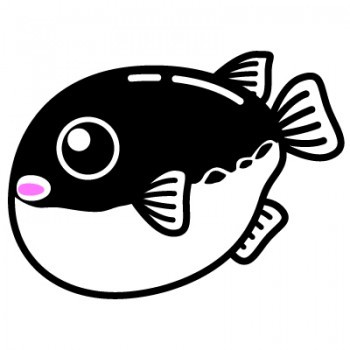1.まえがき
無限長電線に流れる電流という設定を使って、座標系を変換した時、磁界と誘導電界の等価性の
説明に使われている。このときは、両端が無いので問題ないが、有限長になると、ある種のパラ
ドックスが指摘されている。そこで有限長電線に流れる電流について考えてみる。
2. パラドックスの概要
まず、長さLの導線(正イオン)が静止した系をS系、速度uの電子に固定した座標系をS’ 系とす
る。この導線には、垂直に導線が接続されて、電流が流れている。このとき、つぎの疑問がある。
ここで、γ(u)=1/√(1-u²/c²) とする。
(1) S系でそれぞれ、長さLをもつ正イオンの導線部分はS'系では速度(-u)をもつため、L/γに
短縮し、速度uをもつ電子の部分はS系では短縮しており、S’ 系では停止するため、長さは
γLに伸長する。すると電子が導線からはみ出てしまう。これはおかしい。
(2) 正イオンと電子の線電荷密度をS系でq、-qとすると、S’ 系では、それぞれ γq、-q/γとな
る。すると、Lの部分の電荷は、<正イオン>=γqL/γ=qL、<電子の電荷>=(-q/γ)γL=-qL
となり、電荷は保存されている。しかし、もし電子が正イオンの範囲 L/γにあれば
<電子の電荷>=(-q/γ)L/γ=-qL/γ²となって、電荷が保存されない。
つぎに、これらのことを実際に計算してみる。
3. S’ 系の座標・長さの計算
図2のように、導体棒(正イオン)の両端A,BのS系の時刻 t=0 における座標 x=0,L はローレ
ンツ変換により、S’ 系で、それぞれ (x’,t’)=(0,0) および (x’,t’)=(γL,-γLu/c²) である。つま
り、B'端は x'=γL と伸長しているが、時刻は t'=-γLu/c²<0 であり、A端の時刻 t'=0 以前の
座標である。S'系では導体棒は -uで運動しているから、B'の座標は t'=0 には x'=
γL-u(γLu/c²)=L/γ のB''端の座標になり(A'端は x'=0 のA''端に移動する)、短縮している
ことには変わりない。つまり、2項の(1)は解釈が誤っており、パラドックスは無い。
導体棒の端で起きている現象のイメージは、S'系に停止した電子を -uで運動するB'端が吸い取っ
ていき、A'端では電子を供給している。
4.S’ 系の電荷保存の計算(1)
つぎに、電荷保存を考える場合、上のモデルは下側に電流が途切れているので理論的に不備であ
る。そこで図3のようなループ回路を考える。

まず、S系で静止しているAB、CD間の正イオンの電荷保存について考える。電荷の線密度をqと
すると、S系の電荷は2qLとなる。S’ 系での電荷は(正イオンのS系の速度はv=0だから i=qv=0)
ρ’=γ(q-ui/c²)=γq、長さは L/γになるので、ρ’L/γ=qL となって保存されている。
つぎに、電子の電荷保存を考えるが、S系では、正イオンと同じ(符号は逆)線電荷密度(-q)を
持つから、AB、CD間の全電荷は(-2qL)である。S’ 系での電荷密度は(S系で i=-qu だから)
ρ’=γ(-q-u(-qu)/c²)=-q/γ となるから、全電荷は
Q₁=(-q/γ)L/γ=-qL/(γ(u))²=-qL(1-u²/c²)・・・・・①
となり、保存されていない。
つぎに、CD間を考える。S系で電子は速度(-u)をもつ。この電荷は速度変換則により、S' 系で
速度
v=(-u-u)/(1-(u)u/c²)=-2u/(1+u²/c²) ・・・・②
をもつ。速度(-u)の電荷線密度 -qは静止座標で電荷線密度は ρ₀=-q/γ(u)である。この電荷の
S' 系での線密度 ρ' は、ρ₀が速度vの座標に移ったものだから ρ'=γ(v)ρ₀=( γ(v)/γ(u) )(-q)
である。
結局、C’ D’ 間の全電荷は
Q₂=ρ'L/γ(u)= -( γ(v)/γ²(u) )qL ・・・・・・・③
となる。ここで、②を使って
1/γ(v)²=1-v²/c²=1-(4u²/c²)/(1+u²/c²)²=(1-u²/c²)²/(1+u²/c²)²
=1/{γ⁴(u)(1+u²/c²)²}
つまり、γ(v)=γ²(u)(1+u²/c²) となる。これを③に代入すると Q₂=-qL(1+u²/c²) となる。
①からS' 系でのA’ B’ 、C’ D’ 間の全電荷は
Q₁+Q₂=2qL
となって、S'系でも回路全体として保存されている。そして、S'系では正負の電荷を考えると回
路の上側は+に下側は-に帯電する。
5.S’ 系の電荷保存の計算(2)
以上でS'系ても回路全体として、電荷保存することを示したが、上下の電線で電荷が偏っている。
これについて、少し考察する。簡単にするため、帯電していない(ρ=0)ループに電流 i だけが流
れているとする。
図4のようにS’ 系に静止した四角枠コーナB'の➃⑤の出入りの部分で(ρ=0, u・i=-ui, i(//)=0)
i’=γ(i-uρ)=γi , ρ’=γ(ρ+ui/c²)=γui/c²・・・・④
i’=i(⊥)=i , ρ’=γ(ρ-ui(//)/c²)=0・・・・・・・⑤
となる。

ここで、B'の部分での電流を考えると、➃で電流γiが流出し、⑤で i が流入するため、電流の
連続が満たされていないように見えるが、⑤の部分では電線の断面が1/γに短縮している。結
局、電流の差は
γi – i/γ=γi(1-1/γ²)=γi(u/c)²・・・・・⑥
となる。また、➃の部分の電荷密度は γui/c²>0 であるが、この部分は -u で移動して、単位
時間当たり (γui/c²)u の電荷が消失している。つまり、⑥のの電荷が流出していることと一
致して、電流連続ではなく、電荷保存則(div i=-∂ρ/∂t)が成立している。
以上