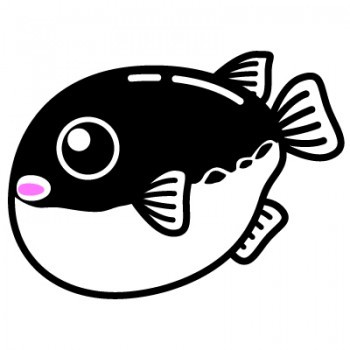1.まえがき
あるサイトに数列 {xn} が
x1≦x2≦x3≦・・・≦xn ・・・・①
を満たすとき
Σi,j=1~n |i-j| |xi -xj |=(n/2)Σi,j=1~n |xi -xj |・・②
を証明する問題があった。簡単そうに見えたが面倒だった。
与式の左辺と右辺を L,Rとする。この Lの各項を(i,j)の行列として
並べると対角線?の部分が0の対称行列
0, 1(x2-x1), 2(x3-x1), 3(x4-x1), 4(x5-x1),・・・・・・・, (n-1)(xn - x₁)
_,_______, 0 , 1(x3-x2), 2(x4-x2), 3(x₅-x2), ・・・, (n-2)(xn - x₂)
_,______ ,_______, 0 , 1(x₄-x3), 2(x₅-x3), ・・・, (n-3)(xn - x₃)
・・・・・・
_,_____ ,_____ ,_____ ,・・・・,_________, 0 , 1(xn - xn-1 )
_,_____ ,_____ ,_____ ,______ ,・・・・・・・,______, 0
となる。対角線より下側は同じなので省略。
2.準備1
|i-j|, |xi -xj | ともに、i,j を交換しても値は変わらず、i=j のとき、いずれも 0だから、
①により、i > j の和を2倍すればよい。つまり
L=2Σj=1~n-1 Σi=j+1~n (i-j) (xi -xj)
同様に
R=2Σj=1~n-1 Σi=j+1~n (xi -xj)
である。
これらは行ごとの和であるが、k=i-j として対角線ごとの和に変換すると
L=2Σk=1~n-1 Σm=1~n-k k(xm+k -xm)
=Σk=1~n-1 (2k) Σm=1~n-k (xm+k -xm)・・・③
R=2 Σj=1~n-1 Σm=1~n-k (xm+k -xm)・・・・④
となる。②は
L=(n/2)R・・・・・⑤
となり、これを証明すれば良い。
つまり、Lの和の順序して次のような並びを考える。Rも同様。
上から k=1,2,・・・,(n-1)に対応する。
2(x2-x1), 2(x3-x2), 2(x4-x3),・・・・・・・, 2(xn -xn-1)
__0__ , 4(x3-x1), 4(x4-x2), 2(x5-x3),・・・ , 4(xn -xn-2)
____0_________ , 6(x4-x1), 3(x5-x2),・・・ , 6(xn -xn-3)
・・・・
______0________________, 2(n-2)(xn-1 -x1), 2(n-2)(xn -x2)
________0_____________________________, 2(n-1)(xn -x1)
3.準備2
ここで、
Ak=Σm=1~n-k (xm+k -xm)・・・・⑥
とおくと③④は
L=Σk=1~n-1 (2k)Ak ・・・・⑦
R=2Σk=1~n-1 Ak ・・・・⑧
となる。
つぎに、この Ak ( A1 からk番目のもの )に対して、最後の An-1 から、逆方向に k番目
のものは⑥で k→ n-k として
An-k =Σm=1~k (xm+n-k -xm) であるが、Ak とAn-k の差を計算すると
Ak -An-k=( Σm=1~n-k xm+k -Σm=1~n-k xm )
- ( Σm=1~k xm+n-k - Σm=1~k xm )
(m+k, m+n-k → m のパラメータ変換をすると)
=( Σm=k+1~n xm - Σm=1~n-k xm )
- ( Σm=n-k+1~n xm - Σm=1~k xm )
=Σm=k+1~n-k xm - Σm=k+1~n-k xm
=0
ここで、n-k≧k および (n-k+1)≧k+1 を使った。つまり、
Ak=An-k ・・・・⑨
をえる。
4.証明
⑦の級数の k番目の項は (2k)Ak であり、(n-k)番目の項は 2(n-k)An-k であるが、
後者のうち、(n-2k)An-k を k番の項に移動して加える。すると⑨により k番目の項は
(2k)Ak +(n-2k)An-k=nAk となる。もとの(n-k)番の項は
nAn-k となる。つまり、⑦⑧から
L=n( Σk=1~n-1 Ak )=(n/2)R・・・⑩
となり、⑤が証明された。
ここで、nが偶数の時、k=1~(n-1) の真ん中のAk には、対となる項が存在しない。
しかし、n=2p とすると 真ん中の項は k=pとなり、2k=2p=n となり、対となる項を
加える必要も無く⑩が成立する。
以上
掲題の問題が電車内に日能研の広告として載っていた。 2010年 城西川越中学校 【算数】の問題
らしいが、証明の解説が理解できなかった。おもしろい問題なので考えてみた。
1.まず、任意の0以上の整数nは整数m,aを使って n=5m+a(m≧0,a=0,1,2,
3,4) と表わされる。
2.このとき、nが複数の5と7の和で表わされる場合を考える。
(1)a=0のとき
当然除外できる。
(2)a=1のとき
n=5(m-4)+20+a=5(m-4)+7・3 となるから、n≧20ならば「2」
は満たされる。
(3)a=2のとき
n=5(m-1)+5+a=5(m-1)+7 となるから、n≧5ならば「2」は満た
される。
(4)a=3のとき
n=5(m-5)+25+a=5(m-5)+7・4 となるから、n≧25ならば「2」
は満たされる。
(5)a=4のとき
n=5(m-2)+10+a=5(m-2)+7・2 となるから、n≧10ならば「2」
は満たされる。
3.まとめると、nが25以上なら、「2」項はみたされるから、命題が成り立つとすれば24以下
の数である。
まず、24=5・2+7・2となって除外できる。23が求める答えであることは4通りの計算
をすれば分かる。
追記(2011/3/20)
この問題は、3と5の場合で、第10回日本数学オリンピック予選(2000年)に載っていた。証明方法は
私には難しかった。