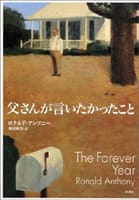大学4年のときに初めてニューヨークへ行った。
当時、雑誌「ニューヨーカー」に掲載されるような洒脱でエスプリの利いた短編を読んでいたので、
ろくに読めもしないのに街角のニューススタンドで「ニューヨーカー」を買い求めたりした。
茶色く変色したそのときの「ニューヨーカー」を見ると当時のことが懐かしく思い出される。
「ニューヨーカー」の作家の中でもとりわけアーウィン・ショウの短編が好きだったが、
ショウの多くの作品を翻訳していたのは「遠いアメリカ」で直木賞を受賞した常盤新平氏だった。
そしてこの常盤さんが、何かのエッセイで「若い人にもこの面白さをぜひ知って欲しい」と紹介していたのが「鬼平犯科帳」だった。
私と「鬼平」との出会いである。以来、細々と「鬼平」を読んできた。
空港の本屋で「今日は機内で読む本がないなあ」というようなときには決まって「鬼平」を買って入った。
季節の折々(冬が多かったような気がする)にふっと思い出したように読むのが「鬼平」だった。
そうやって10年以上の時間をかけて細々と「鬼平」読んできて、ようやく最終巻までたどり着いた。
私は熱心な池波正太郎ファンとは言えない。「鬼平」を除く他の池波作品は数えるほどしか読んでいないからだ。
ただただ、長谷川平蔵という主人公に敬服しその人物像に憧れて読み続けてきた。
熱心な池波ファンからは笑われるようなレベルでしかないが、それでも常盤さんの言った「面白さ」というのはよく分かったような気がする。
確か常盤さんは、あまり読書をしないような最近の若い人が読書の楽しさを発見する意味で「鬼平」は最適だ、
というような意味のことを仰っていたと記憶しているが、私もそう思う。
私にとってはアメリカ現代文学の紹介者と言ってよい常盤氏が時代小説を推奨するという、
ある種のギャップに興味を引かれて「鬼平」を読み始めたのだが
読書は苦手というような若い人にこそこういう本を読んで欲しいと思う。
最終巻は「女密偵女賊」、「ふたり五郎蔵」という二編のあと長編の「誘拐」が収められている。
私は前作を読んだときにお夏のその後がどうなるのかが描かれていないことに不満が残っていた。
魅力的なキャラクターを登場させておきながらこのまま終わるのはもったいないと思っていたが、
やはり池波正太郎はそのままでは終わらせなかった。
「女密偵女賊」でもお夏に触れて巧妙に伏線を張りながら、「誘拐」でこの妖艶なお夏をもう一度登場させた。
そして、さあここからどうなるのかとまさに興が乗ってきたその瞬間、忽然と絶筆してしまうのである。
妖しさをたたえたお夏は文字通り永遠にミステリアスな存在のまま残ってしまった。
しかし、長かった「鬼平」がこのような形で未完となったことは決して不満足ではない。
どこか、物語の続きを夢想させてくれるようなこの終わり方も「鬼平」らしくてよかったのかもしれない。
また、そのうちに忘れた頃にひょっと取り出して読むことがあるだろう。
「鬼平犯科帳」という作品に出会えたことは幸せな体験だったと思う。
当時、雑誌「ニューヨーカー」に掲載されるような洒脱でエスプリの利いた短編を読んでいたので、
ろくに読めもしないのに街角のニューススタンドで「ニューヨーカー」を買い求めたりした。
茶色く変色したそのときの「ニューヨーカー」を見ると当時のことが懐かしく思い出される。
「ニューヨーカー」の作家の中でもとりわけアーウィン・ショウの短編が好きだったが、
ショウの多くの作品を翻訳していたのは「遠いアメリカ」で直木賞を受賞した常盤新平氏だった。
そしてこの常盤さんが、何かのエッセイで「若い人にもこの面白さをぜひ知って欲しい」と紹介していたのが「鬼平犯科帳」だった。
私と「鬼平」との出会いである。以来、細々と「鬼平」を読んできた。
空港の本屋で「今日は機内で読む本がないなあ」というようなときには決まって「鬼平」を買って入った。
季節の折々(冬が多かったような気がする)にふっと思い出したように読むのが「鬼平」だった。
そうやって10年以上の時間をかけて細々と「鬼平」読んできて、ようやく最終巻までたどり着いた。
私は熱心な池波正太郎ファンとは言えない。「鬼平」を除く他の池波作品は数えるほどしか読んでいないからだ。
ただただ、長谷川平蔵という主人公に敬服しその人物像に憧れて読み続けてきた。
熱心な池波ファンからは笑われるようなレベルでしかないが、それでも常盤さんの言った「面白さ」というのはよく分かったような気がする。
確か常盤さんは、あまり読書をしないような最近の若い人が読書の楽しさを発見する意味で「鬼平」は最適だ、
というような意味のことを仰っていたと記憶しているが、私もそう思う。
私にとってはアメリカ現代文学の紹介者と言ってよい常盤氏が時代小説を推奨するという、
ある種のギャップに興味を引かれて「鬼平」を読み始めたのだが
読書は苦手というような若い人にこそこういう本を読んで欲しいと思う。
最終巻は「女密偵女賊」、「ふたり五郎蔵」という二編のあと長編の「誘拐」が収められている。
私は前作を読んだときにお夏のその後がどうなるのかが描かれていないことに不満が残っていた。
魅力的なキャラクターを登場させておきながらこのまま終わるのはもったいないと思っていたが、
やはり池波正太郎はそのままでは終わらせなかった。
「女密偵女賊」でもお夏に触れて巧妙に伏線を張りながら、「誘拐」でこの妖艶なお夏をもう一度登場させた。
そして、さあここからどうなるのかとまさに興が乗ってきたその瞬間、忽然と絶筆してしまうのである。
妖しさをたたえたお夏は文字通り永遠にミステリアスな存在のまま残ってしまった。
しかし、長かった「鬼平」がこのような形で未完となったことは決して不満足ではない。
どこか、物語の続きを夢想させてくれるようなこの終わり方も「鬼平」らしくてよかったのかもしれない。
また、そのうちに忘れた頃にひょっと取り出して読むことがあるだろう。
「鬼平犯科帳」という作品に出会えたことは幸せな体験だったと思う。