先週末は、東京都内の某所で、放射能の実験に立ち会った。ある物質を放射能で汚染された土壌に混ぜると、放射能が劇的に減少するのだという。一度、実験を見てほしいということで、自分もサーベイメータを持参して見せていただくことにした。
福島県内から採取された土を重量を測ってタッパの容器につめる。同じものを二つ用意し、まずは、サーベイメータで放射能を測定。次に一つのタッパのふたを開けて、ある物質を混ぜて、ふたをして、再び測定する。ほとんど変化はない。少なくとも劇的に放射能が減少するということはないようだ。結局、私がそこにいた3時間ほどの間には、有意な変化はなかった。
これまで測定したデータを見せてもらったところ、それは、土壌に件の物質を混ぜると、4~5日程度を半減期として放射能が劇的に減少しているグラフだった。この場では、何ともコメントしようがないのであるが、半減期を求めて、それが何回やっても同じなのか、それとも毎回ばらつくのか、まずはデータを解析してみては、とコメントした。また比較対象実験、つまり何も混ぜない試料の測定を常に同時に行って、測定装置の感度が変化していないか、試料の状態が変化していないかなどを、チェックしながら測定を繰り返してほしいと注文しておいた。
ガンマ線の測定というのは、科学的な測定の中で、ある意味ではもっとも簡単なものである。スイッチを入れれば、何か数値が出てくる。しかし、正確に測定するにはやはりさまざまなコツがあって、注意深くやらなければ、何を測っているか分からないことになる。
例えば、同じ放射能(放射性物質の濃度)の、同じ質量の土壌でも、容器の中にぎゅっとつめるか、すかすかにつめるか、水分が多いか、少ないか、ということで、測定値は変わってくる。
また、同じ試料を繰り返し測ると、測定値にばらつきがあることが分かる。そのばらつきは放射能が低い場合には顕著である(計数の統計誤差)。どの程度ばらつくのか、繰り返し測定して、その範囲を知っておかなければならない。そのばらつきの範囲よりも、充分に大きな変化しか、本当の変化とは認定できない。単なるばらつきを、真の変化と勘違いしてしまう危険性は高い。
放射性核種は固有の半減期を持ち、それは化学的な操作では変化しないというのは、原子核物理学の100年にわたる歴史の中で確立した物理法則である。もちろん、科学の歴史とは、従来の知見が覆されることによって進歩した歴史である。そうでないことが本当にあれば、ノーベル賞級の発見となるのであるが、やはり学問の100年の歴史に対しては、その重みに対する謙虚さも必要だと思う。安易に結論を出さず、実験が何か間違っていないか、まずは虚心に、徹底的に追求してほしい。
どうやって間違いさがしをするかというノウハウが、科学者の専門性と言ってもよい。博士課程でトレーニングされるのはそういうことである。徹底的に間違いさがしをしてもなお、説明できない現象を記述できた時、それを革命的な発見と呼ぶ。それは地味で地道な作業の繰り返しである。
それはともかく、私がやや気になったのは、私を呼んでくださったみなさんの、件の物質に対する思い入れの強さである。それは私には「執着」というべきレベルのように感じられた。一方で、土壌に含まれる放射性物質を、何が何でもやっつけてやる、というのもひとつの「執着」のように私には感じられる。「執着」は人のこころの余裕を奪い、冷静な判断力を鈍らせる。土壌の再生については、もうすこし、ゆったり、しっかり、腰をすえて取り組んでいきたいと思う。
















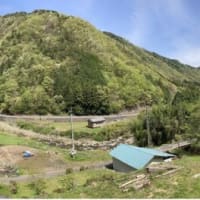


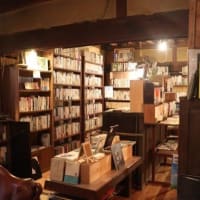






以下、未だ何も成し得てない半端者の眠れぬ夜の妄想なんですが…
千年先には、原生林が再生されているべきと思います。基本的に、人間の立ち入りは禁止され、棲み分けが守られ、クマや狼や猛禽類が生態系のバランスをとっているような…。里山よりも生産性が高い…。(明治神宮の杜は、実際、ほぼ人の管理を離れて生態系が維持されつつあると。)トキが帰化されつつあるように、狼なども復活できるはずです。また、日本を離れて、砂漠のような、著しく生産性の低くなってしまったエリアも、福岡さんの粘土団子などを用いれば、緑化の方向へ向かえるはずです。
また、バイオマスエネルギーの資材として、木質プラス、麻や茅のような生命力盛んな草を用いるのはどうでしょう?
日本において、瓦が普及する以前には、茅山が管理され、屋根の葺き替えを村落の持ち回りでやっていたとか。茅などから、植物性プラスチックが作れれば、建築資材としても活用できるかと。
食糧となるものからバイオエタノールを得るのは、やはり生産コストに見合わないですよね?
自然農だったら…里山の落ち葉も腐葉土に利用しなくて済むから、何かエネルギーに利用したいところです。
あとは、なんとか放射能が処理できれば…
個人的には、清純なる祈りが最も放射能に効力があるように思われますが。色即是空空即是色のような気がしています。
寂しい人間ゆえ、このような無記名での乱暴なコメントをお許しくださいm(_ _)m
若干、精神世界寄りでしょうか?
失礼します。
>個人的には、清純なる祈りが最も放射能に効力があるように思われますが
私もまったく同感です。祈りましょう。