【宮本常一との対話7】
「日本人には個性の確立がないといい、とくに農民がそれが強いというが、交易を主として発達した都市社会ならば自らの利益をまもるために強い自己主張も必要だっただろう。が、そのためには一方では人間が人間を警戒しなければならなかった。だからそこにいつも信と不信の葛藤が見られた。だが農民の生活の中にはまず信頼と融和が要求せられたのではなかったか。・・・農民の家には築土をめぐらしたものは少ないし、戸に錠のかかるものも少なかった。・・・
だが最近は農家でも鍵をかけて寝るようになって来たものが多い。人が信ぜられなくなって来たからである。人をうたがい、物をうたがうようになって来ると人は個性的になったという。」 宮本常一著作集3 「民俗随想 ふるさとの歴史」 p.263 初出は1963年。
これも考えさせられる文章だ。宮本は戦前の日本の田舎を、文字を知らない時代の人々の暮らしの痕跡を探して歩いていた。明治も20年代に入ってやっとほとんどの子どもが小学校に行くようになって、その年代からほとんどの人が読み書きができるようになった。それ以前に村の中で読み書きができたのは庄屋と僧侶ぐらいのものだった。書いたものに頼らないとすると、直接見聞することだけが情報源である。そこで「伝言ゲーム」でとんでもない話が伝わって行ったり、今となっては荒唐無稽なことを真面目に信じていたり、というコントのネタになるようなものが満載だった。基本的には人の言うことを信じてかからなければ生活が成り立たなかった。村の中では皆にとってそれが合理的なあり方なので、人を騙すようなことは少なく、したがって人を疑うような必要も少なかったものと思う。
私たちは小さい頃から個性的であれと育てられてきた。それが「人をうたがい、物をうたがうようになって来ると人は個性的になったという」ということであれば、本当にそれが望ましいことなのかと考え込まざるを得ない。
ひところ「自分さがし」というのが流行った。自分が「自分らしく」生きるためにはどうしたら良いのか、旅をしたりいろんな経験をしたりして追い求めるということだ。問題は「自分らしく」生きるとはどういうことかが分からないことだ。
そのモデルがメディアの中で個性的に活躍する有名人だったりする。確かに自分の才能を発揮して個性的な生き方をしているように見える。しかし、メディアに出てくる人などは全体から見ればごく一部であって、誰もがそうなれるわけではない。AKB48などはその間口をやや広げたわけだけれども、圧倒的多数の少女にとってそれは憧れにとどまる。最近ではネットで自由に発信できるようになったものの、インフルエンサーと呼ばれるような存在になれるのはこれまたごくごく一部である。たいていの発信は情報の洪水の中に埋もれてしまう。
「自分らしく生きる」ということは実は「個性的に生きる」ということではないのではないか。そうではなく、「信頼と融和」のネットワークの中に生きるということなのではないか。それならばあちこち探し回らなくても、今生きて暮らしている場で見出すことのできるものだ。さらに私はそれに人間関係の中だけではなく、自分が大きな自然のネットワークの一員であるという実感を持って生きるということを付け加えたい。そういう実感を得ることが都市では難しいとすれば、田舎に足繁く通ってみることをオススメしたい。
宮本が田舎をくまなく歩いたのは、おそらくそれがよそ者として「信頼と融和」のネットワークに入り込む、つまり自分らしく生きる宮本なりの生き方と思っていたのではないかと想像する。
最新の画像[もっと見る]
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
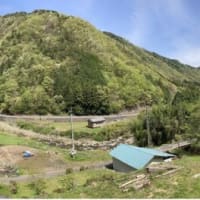 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
-
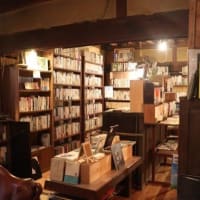 A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前
A Village retreat in Japan’s hidden heritage
4ヶ月前















