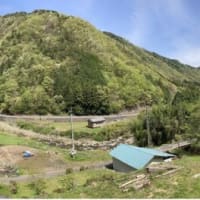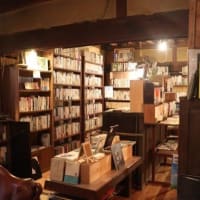愛知県岡崎市の幼稚園で食材に使われていた茨城県産干しシイタケから、1400Bq/kgの放射性セシウムが検出され、大々的に報道された。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120405/t10014248141000.html報道によれば、幼稚園では2kgを用いて530人分のうどんの具の一部としたという。一人あたりどれほどか計算してみると、1400Bq/kg×2kg/530人=5.3Bq/人。15kgの体重の子どもであれば、体内濃度として、5.3Bq/人÷15kg=0.4Bq/kgとなる。これ一回だけなら、子どもでもおとなでも体内に自然放射性物質であるカリウム40の放射能が70Bq/kg程度あるので、それと比べれば無視できる数字である。(それに対して、毎日摂取し続けると、その約100倍の放射能となるので、無視できなくなる。)
私が入手した情報では、この幼稚園の園長先生は、食材の放射能についてはかなり心配していて、産地をはっきりさせるなど努力されていたという。保護者の一人が、園長先生の了解を得て、気になる干しシイタケを名古屋市にある市民放射能測定センター(Cラボ)http://tokainet.wordpress.com/hsc/に測定を依頼し、その結果、放射能が高いということが分かり、保健所に届けた、というのが実際の経緯である。当初行政側は、園の名前を伏せて公表することを打診したそうだが、園長先生は、実名でOKと回答し、ご本人は保護者通信にこのことを報告するとのことだったという。園長先生が報道機関に発表されたコメントの全文を紹介しよう。
「放射線内部被曝から、被曝にもっとも弱い子どもたちを守りたいという思いで、給食食材の食品放射能分析を実施しました。3.14以来、食材業者と産地特定など細かいところまで注意してきましたので、結果については大変残念です。今回の干ししいたけは、一般に市販されているものであり、安全だと信頼して購入したものの一つでした。
私ども一園の問題でなく、このことを社会全体で受けとめることが大切だと思います。みんなで子どもを守るという立場で、五感で感知が出来ない放射能としっかり向きあっていただきたいと思います。これからも長く続くであろう放射能汚染と被曝を少しでも減らしていくための正しい情報を得るためにも、食品放射能分析は必要だと改めて感じています。」
私はたいへん立派な園長先生だと思う。組織のトップというのは、危機管理が第一の仕事である。その際に大切なのは、迅速な情報の公開と説明である。その責任をきちんと果たそうとされている。
今回の事例で分かったことは、政府の基準があっても、それを上回る放射能を示す食材が流通している可能性があるということ。一方で、これが大々的に報道されたということは、そういう事態は今ではごくまれになっているということでもある。今回の事態は、一度は子どもたちの口に入ってしまったけれども、保護者、幼稚園そして、市民放射能測定センターの連携によって、今後は防止できるという、よい事例と見なすことができる。地道であるが、このような成功事例をひとつひとつ積み重ねていくことが大切と思う。
また、もうひとつの観点からの理解を忘れないようにしたい。昨日、埼玉県の有機農家から聞いた話では、原木シイタケはもう収穫できないので山に放置しているという。そうすると、イノシシがやってきてそれを食べるのだという。人間の子どもの被曝は今回の事例のようにして守られるのであるが、イノシシのこども、ウリボウを守るすべはない。野生の生き物たちの内部被曝が進んでいるはずである。人間の一員として、本当に申し訳ないと思うし、被曝が生き物たちの病気につながらないよう、ただ祈るのみである。