「一首読み出でては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思い続けては秘密の真言を唱ふるに同じ」
白洲正子『西行』新潮文庫、1996年、p.333
西行の言葉。西行は、貴族の時代から武士の時代への過渡期に、天皇付の武士として権力の中枢にもアクセスできる立場を捨て、出家し、諸国を訪ねて気に入った場所には庵を編んでしばらく滞在し、行く先々で歌を詠み、生涯を終えた。
高野山に滞在して真言密教の修行をし、弘法大師の足跡を訪ね、修験道の修行も行った。非公認の私度僧であり、生涯旅坊主の質素な暮らしをした。それでも天皇が選ぶ勅撰和歌集に歌が入選すると名声は高くなり、行く先々で歓待されたものと思う。今で言えばノーベル文学賞作家がふらっと現れたようなものだ。
桜と月が好きでその姿に触れては多くの歌を詠んだ。恋の歌も多く、とても真面目な修行僧とは言えなかったわけだが、これは私度僧であれば普通であった。むしろすべての束縛や常識から離れて自由に生きるというライフスタイルが出家ということだったようだ。
こういう志向を数寄(すき)の道と言うとのこと。美しいものに徹底的に感嘆し何者にも囚われずシャレに生きる。一見耽美でやや軽薄なその外見と、仏道を深く探求する姿とは実は一枚のコインの裏表であったようで、西行にとってシャレた歌を一首詠むということは「一体の仏像を造る」に匹敵する、仏道を極めるための行為だった。
風になびく富士の煙の空に消えて ゆくへも知らぬわが思ひかな
晩年に富士山を見て詠んだこの歌を西行は生涯で最高のものと自ら認めていたという。当時富士山は噴煙をはいていたようで、その煙が空に消えるさまに、自分の存在のありようを重ねている。大乗仏教でいう「空」の境地であろうか。
シャレを極めて空に至る。西行、カッコいい。
















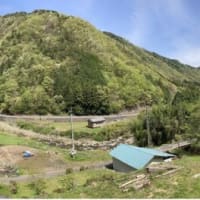


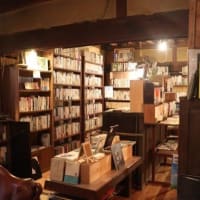






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます