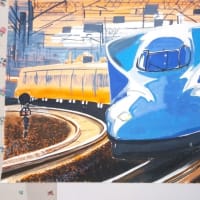「2月はさかなを描きま~す」私の発表に小さな声が耳に入りました。「さかな図鑑を持ってこよう」 「きっと、1階の熱帯魚のことだよね」
「きっと、1階の熱帯魚のことだよね」
 「きっと、1階の熱帯魚のことだよね」
「きっと、1階の熱帯魚のことだよね」
先生はそんなカンタン(?)な課題はおもしろくないと思います。みんながギョッ!と驚くような絵を期待しているのです。だからといってナポレオンフィッシュやマンボウは捕まえてくることができません。だから、、、、。これ以上はさかなを見てからのお楽しみ。

先生はみんなにいつも大きな声で叫んでいるよね。「描いている自分の絵を見るんじゃなくて、描こうとするモノをじっくりと観察しなさい!」さかなだって、じっくりと観察しなければ描けないよ。

話が脱線します。



スケッチ=見たままを描く 誤解を招く言葉ですね。ダ・ヴィンチ教室では観察しなさいと指導しています。「観て察する」まさに注意深く見て、深く考える作業です。つまり、さかなを見たまま描くことの前に、さかなと接し、何を感じ、どのように思うかが、子どもには大切なことです。何度もお話していますが、上手に描くことだけが目的ではありません。

小学2年生前後でそろそろ、さかなを記号イメージで描くことから次のステップに入ります。描こうとする対象物に興味を持つことを習慣づけたいと考えています。

魚の身になって考えれば、せっかく描いてもらうんだから、じっくり観察してほしいと思うんじゃないかな。耳はどこ?ひれはどこに付いているの?なんでこんな形のカラダなの?そんなことを観察して、魚のことを知ると、まるで生きているような、いきいきとした魚が描けると思うよ。

お刺身は好きですか?塩焼きは、干物はどうですか?
さかなのいのちを考えながら描くことで、いのちの大切さ、食べるときにも、いのちのありがたさ(食べられること)が分かってくれると嬉しいです。