
雛がタマゴからかえろうとするとき、内側から殻をつつく「啐」(そく)
親鳥は外側から優しくつつき返す「啄 」(たく)啐啄:調べてわかったことですが。そこには親から一方的につつくことはしないし、また親が殻を割る手伝いはしないという。双方の呼吸合致してこそが自発、自覚 の始まりの始まりだと思います。
この教室はカリキュラムの定期的計画などというものは持ち合わせていません。そんなのおかしいですよ。一方的な進め方なんて。ある意味で自由気まま、ほったらかしです。誤解されてはいけませんが同じ時間のクラスでも、各自バラバラなテーマに取り組んでいることは日常です。一年生も六年生も同じテーマに取り組んでいます。その差異はあまり問題ではありません。私からはそれぞれの自発に沿った、ちょこっとだけ高い要求をしています。「無理無理!できない!」の声は聞き流しています。(本当はできるのに、逃げているのはわかっているのに)一人ひとりの様子は細かく察知して、まずは個別に「ちょっかい」を出します。指導はそのあとにして。これが効くんです。
「なるほど!」と気付く子には、多くを説明せず、間違えそうになってでも、そのままに。また、反応が弱い子には、あの手この手、猫の手を借りてでも揺さぶりをかけます。あくまでも「ちょっかい」が大切なんです。その先を教えてしまっては、その子の自発、自覚の成長を邪魔する指導者として最悪の行為なんです。
先日、四年生のひとりが教室蔵書の中学美術1の教科書をジィーと見ていたので、やってみるか!と声をかけた。点描画はおもしろいぞ!と揺さぶりをかけた。その子の気付きに私もチャンスをもらい、久しぶりに筆を取ってみた。
自身がしたいと自発、自覚した時、少しのズレもなく、目の前に師が現れる。まさに私の師は子どもたち一人ひとりなんです。
三月、卒業生からもよく聞くのは「ヒゲ先生はひっつこい!」そのひっつこさが、その子の将来に活きると確信しているからに違いありません。この四月も多くの子との出会いが待ち遠しく、期待しています。かかってきなさい!












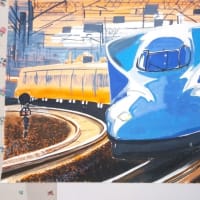












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます