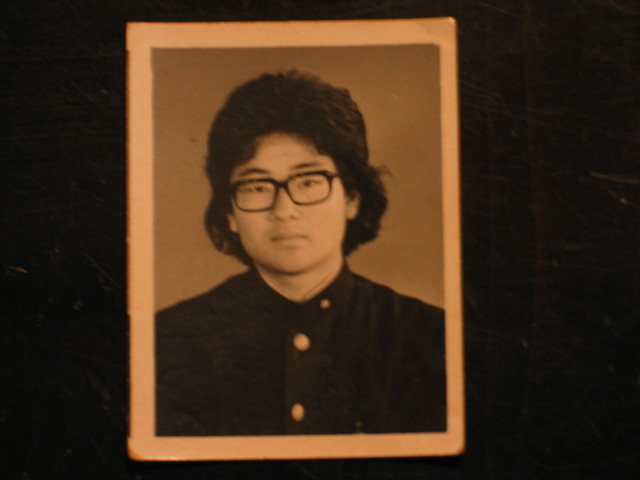生徒の持っている馬頭琴の竿が太過ぎて手に余るので、貸与していた内モンゴル自治区・呼和浩特の布和工房製の馬頭琴の、表板にひびが入った。ボディに向かって右側の、裏側からはバスバーで押し上げられ表側からは下駒の足で圧力が掛かった場所の中間だと思われたので、表からひびに膠を流し込むだけでは強度に不安があり、馴染みの西洋弦楽器の職人にお願いして、裏からパッチを当てて貰おうと思っていた

角度を変えて見ると、けっこう長〜いひびである。が、指で押しても、表板は凹まずひびも口を開けない

作業に使用出来るのは、ボディ上端の竿を抜いた穴からである。F 字穴からでは、バスバーが邪魔をするので・・・難しいだろう。ボディ内部に収まる竿の延長部の、真ん中辺りが意味も無く太くなっていた為竿を抜くのに難儀した。で、台付きの布ヤスリで、竿の抜き差しに支障の無いように削った。 F 字穴から覗いたボディの内部である。既に裏板を剥いだ状態なので太陽光が降り注いでいるので明るいが、ほぼ本来は暗闇で、 F 字穴から照明の当て方を工夫しても、バスバーの剥がれが発見出来るか?・・・判らない

引越しが一段落して精神的には余裕が生まれて、勉強がてら、裏蓋を開けて様子を見る事にした。厚めの塗装を切るのに、刃が余計な方向に動かぬ様に、ステンレスのテープを巻いてガードした。塗装の厚みを大型カッターで切って、膠を溶かす為にアイロンを当てて温めたら・・・塗装が泡立った。どんな種類の塗料を使っているのだろう? 続行すれば、裏板全面の塗装を塗り直しになってしまう。で、アサリゼロ(歯の厚み0.3ミリ)の鋸で裏板を切り取った。で、表板の裏側からひびを探したが・・・見つからないノギスでひびの位置を正確に測ったら、衝撃の事実が判明した。ひびの位置は・・・バスバーのど真ん中

バスバーの膠が上端部から剥がれ、バスバーだけが剥がれれば良かったものを、途中から膠がしっかりと接着していた為に、桐材の表板をバスバーが引き剥がしたの・・・だった。同様の惨状を、モンゴル国のバイガルジャブ親方の工房製の馬頭琴で見た事があった。バスバーの反りを変えて作り直して、剥がれてしまった表板の裏側に、薄板を貼って修理した事があった。まあ、今回は音の良い馬頭琴なので、あまり余計な事はしたく無いので、そのままタイトボンドで再接着する。竿を抜いた穴からでは、出来ない作業だと思う。幸いな事に手持ちの F型クランプで、ギリギリ圧着できるボディの厚みだったので・・・幸運

ほぼ雲の無い晴れ空、陽射しは強く無風で、気温5〜17℃。午後3時の気温16.1℃、湿度は47%
(2・137)36.5℃(78〜117)