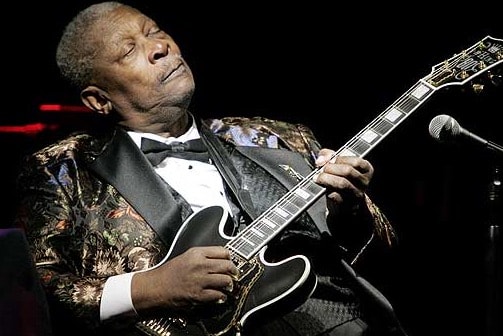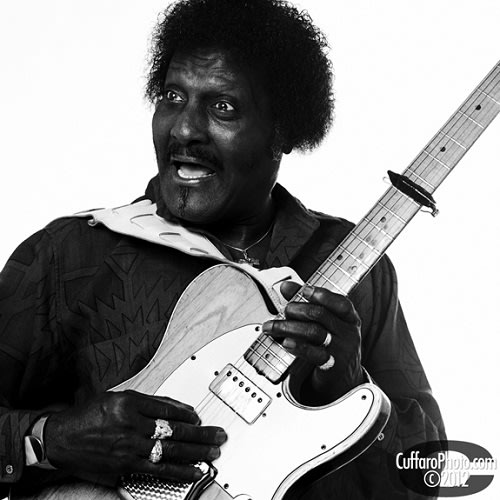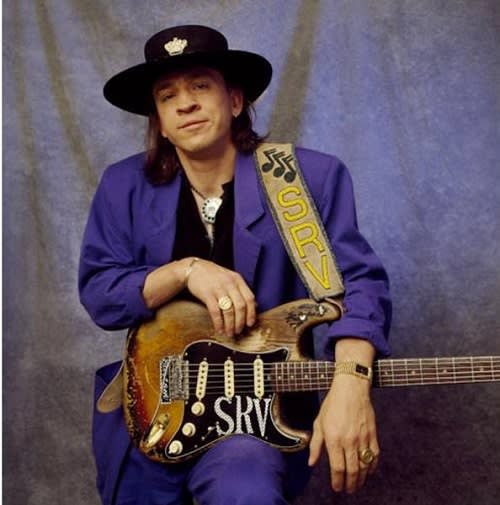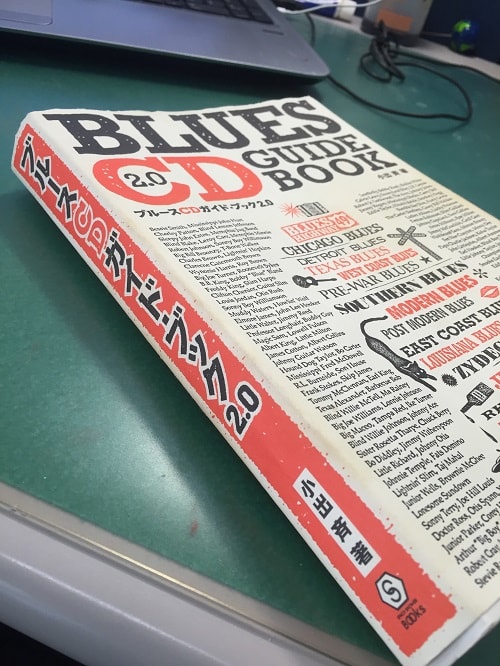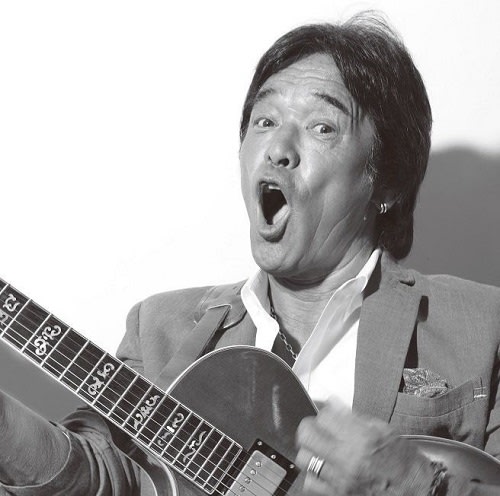なんだか、すさまじく寒いですけども、みなさまお元気ですか?
東京は雪が降ってないですが、他の地方は軒並み大雪!!
おいらの故郷の、広島でも大雪が降ったらしい。
広島で大雪なんて30年ぶりくらいらしくて、大騒ぎになってますなあ。
といっても、おいらの故郷は、広島は広島でも、島根に近い山間部なんで、雪なんて珍しくもなかったですが(笑)
そういえば、先週の土曜日の、VROOOM宅での練習プラス飲み会の時には、たまたまカポタストが必要なのに、無いという状況になりまして。
昔のブルースマンから学んだ、カポタストの作り方を披露したところ。
店長・VROOOM大絶賛(爆笑)
その時のことは、こちらの記事に書いてありますけども。
ちょっと捕捉しますと、皆さんご存知の通り、カポタストというのは、ギター演奏の時に使う小道具のこと。

こういうやつですね。
弦を押さえっぱなしにすることによって、指の押さえ方を変えずに、転調させることができる道具なわけです。
んで、それが無い時は、手近な棒2本と、ヒモがあれば簡単に作れるという技があるわけですよ。
おいらはそれを、冒頭の写真のブルースマンである、スリーピー・ジョン・エスティスから学んだわけですね。
このスリーピー・ジョン・エスティスというブルースマンは、いわゆる「再発見」されたアーティストというやつでして。
1930年代に活躍した後、忘れ去られてしまい、1970年代になって、カントリーブルースのブームが来て、再び脚光を浴びたわけです。
なもんで、再発見されたばかりの時は、そうとう貧乏だったらしく、カポタストなんか買えなかったわけで、
冒頭の写真のように、鉛筆をカポタストにしていたわけですよ。
それを見た時の衝撃はすごかったなあ。
そんで鉛筆でカポタストを作る方法を調べたことがあるんですわ。
普通は輪ゴムなんかで、きつくなるように、ぐるぐる巻きにするんですが。
輪ゴムがない時はヒモでくくって、ネックの裏側でもう一本の棒をヒモに差し込み、それをぐるぐる回すだけ。
するとヒモがキリキリとしまって、弦が押さえつけられます。
あとは、そのぐるぐる回した棒を、ヘッドの裏側のペグとかに引っかければ、完全に固定できますわ。
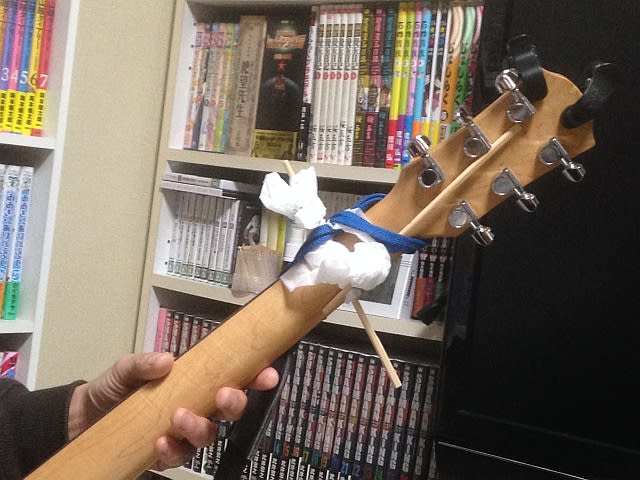
この写真がわかりやすいですね。
(ちなみに今回は、コンビニ袋をヒモとして使いました。)
もう1本の割りばしが、コンビニ袋をぐるぐる巻いたうえで、ヘッドの裏のペグに引っかかってますよね。
青いヒモはギターのストラップなので紛らわしいですけど気にしてはいけません(笑)
いやあ、こういう技術って、ブルースを聴いていなかったら、知る機会もなかったなあ。
「カポタストがなかったら諦める」
というのが、店長とVROOOMの共通の見解だったので、この方法を知っているギタリストは、相当少ないのかもしれん。
考えてみたら、おいらが使っているスライド・バーは市販されているものだけども。
昔のブルースマンは、瓶の先っぽとか、水道管の切れ端とか、場合によってはナイフなんかで演奏したわけで。
手近なものを利用して演奏する、彼らの姿勢からは学ばねばならんすね。
さて、それはともかくブルースマンへの道ですよっ!!
前回は、ブルースをうまく演奏するためには、歌えるようにならなくてはならない。
でもブルースはワンパターンだから、歌えるようになるのは簡単さ。
と説明したところまででしたな。
そう、ブルースは、基本的にはワンパターン!!
おんなじコード進行を、延々と繰り返すことが特徴なのです。
そのコード進行は、基本的には、以下のような12小節でできてます。

これは、ものすごく有名なパターンですよね。
でも、これだけだとまだ、その構成がわかりにくいっす。
次の図を見てください。
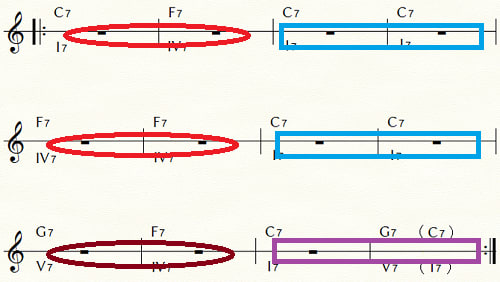
上の図に書き足しました。
左側の赤い丸(3回目のはわざと色を変えてあります)の部分が、歌です。
その部分はヴォーカルの声が入る部分ということですね。
3回目の丸の色を変えたのは、そこだけメロディが違うからです。
そう、逆に言えば、1回目と2回目は基本的に同じメロディになります。
右側の青い四角(これも3回目はわざと色を変えてあります)の部分が楽器の演奏です。
簡単に言うと「合いの手」と言っていいでしょう。
ブルースだと「レスポンス」と言ったりします。
そして3回目の「合いの手」だけは「ターン・アラウンド」と言います。
12小節の終わりを分かりやすくして、さらに次の12小節に続くということを宣言する、定型句みたいなものです。
そう、ブルースはこれの延々繰り返しなんですよ。
同じメロディを2回繰り返して、ちょっと違うメロディで3回目を歌って、ターン・アラウンド。
このワンパターンな流れが、頭の中に入っていることが必要なんですね。
裏を返せば、頭の中にこの流れが入っていさえすれば、ブルースは歌えるわけです!!
ブルースが歌えれば、良いギターソロも弾ける!!
こうつながってくるわけですねっ!!
そう、多くのギタリストがよくやる「ペンタ1発ソロ」からの脱却には、ここが第一歩なわけですよ。
以下次号じゃ!!