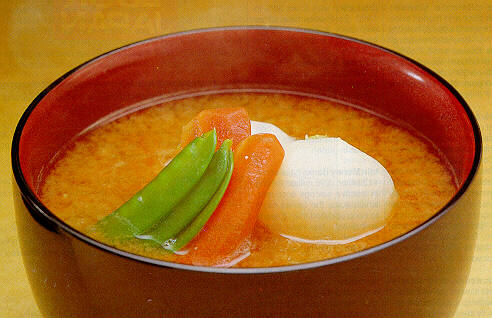パン作りをするようになって、もう2年以上が経っている。まだまだパンづくりの
道は遠く、私なんかベテランのパン職人さんやパン教室の講師さんから見たら、
ただのひよっ子だろう。もちろんそのとおりなので、それについては何も反論する
つもりはない。そのひよっ子なりに1つ感じていることがあるのだが、イーストって
やはりバカにできないということだ。
パンづくりに慣れてくると、天然酵母やサワー種、ルヴァンリキッドなどの、
イースト以外の酵母でパンを作りたくなってくる。私も授業で使っていたことも
あり、天然酵母を使うようになってからはずっとそればかりで作っていた時期が
あった。しかも天然酵母だけでは飽き足らず、サワー種やルヴァンリキッド、
酒粕をベースに起こした酒粕酵母まで自分で起こして使っていたこともあり、
いろんな酵母でのパン作りを楽しんだ。
天然酵母で焼いたパンの特徴は、ずっしりとしていてやや酸味が感じられると
いう点だ。これは気のせいではなく、酵母の発酵段階で乳酸菌と酢酸が発生
するので、それがパンの風味に添加されるために、そういう風味になる。
この酸は酵母の働きを弱めてしまう働きがあるために、パンを膨らませるための
ガスがイースト使用時に比べるとあまり発生しない。しかもパン生地に含まれる
グルテンは酸に弱いためにこの酸に分解されてしまい、結果として酵母の生成する
ガスが抜けてしまうために、イーストのパンよりも膨らまない、ずっしりとした
パンになる。これが、天然酵母で焼いたパンの一般的な特徴だ(ちなみに、この
酸がグルテンを分解する作用を応用して、天ぷらの生地に少し酢をまぜると、
サクサクの生地にすることができる)。
「天然酵母パン」と聞くと、なにやらオーガニックな響きがあるせいでふんわり
優しい味わいのパンを想像する人が多いかもしれないが、実際にはかなり好き
嫌いの分かれるパンだ。噛み応えは強めだし、上に書いたような独特の香りも
つくので、誰もが好きになれるパンとは限らない。それでも、パン好きには
受ける味わいであることは間違いないので、根強いファンがいるんだろう。
また、天然酵母はガスが発生しづらいという性質上、発酵に時間がかかるのだが、
それがパンの甘みを増すという効果もある。パンの甘みを最大限に引き出すには、
小麦粉の粒の芯にまで水分を浸透させる必要があるのだけど、それにはおよそ
12時間ほどかかる。天然酵母を使えば自動的に理想的な条件でパンを発酵させる
ことができるので、それもまた天然酵母で作ったパン独特の甘みといえるだろう。
ただしウイークポイントとして、天然酵母パンには独特の酸味と硬い食感がある。
これをなくして、小麦粉の味わいだけを強く出したければどうすればいいかと
いえば、イーストを使ってじっくりと発酵させればいい、ということになる。
でも普通にイーストを使って発酵させたら、夏なら1時間程度、冬でも2~3
時間もあれば発酵が完了してしまう。ではどうすればいいかというと、冷蔵庫で
発酵させればいいのだ。
イーストを使った生地が捏ねあがったら、生地をボウルに入れて上から生地全体を
覆うようにラップをかぶせ(乾燥を防ぐためなので、ぴっちりと包む必要はない)、
さらにボウルを覆うように濡れ布巾をかけて冷蔵庫に一晩寝かせておく。そんな
低温環境に生地を置いて発酵するのかと心配になるかもしれないが、実際のところ
何の問題もなく生地は発酵する。翌朝見てみると、見事に膨らんだパン生地が
できている。分割してベンチタイムをとり、そこから整形して二次発酵をすると、
またさらにしっかりと膨らんでくれる。発酵が終了して焼いてみると、これがまぁ
実においしいパンになっているから素晴らしいものだ。ふんわり、もっちり、
優しいお味のパンの出来上がり。しかも、なぜかイースト臭があまりしない、
というか感じられないくらいになっている(理由は不明)。
このやり方が、普通の日本人が好む味と食感のパンを作るのに理想的だという
ことがわかってからは、イーストばかり使うようになってしまった。典型的な
ハード系パンを作ろうとするなら、今でも天然酵母は必要だと思う。が、
そうでないのであればイーストを使った冷蔵発酵というのは一度考えてみても
いいと思う。あと、さらに逆手をとれば、天然酵母を起こす段階で発生する
乳酸と酢酸が天然酵母の特徴だというなら、最初から生地に酢とヨーグルトを
添加してイーストで焼いたって、結局は同じことになるのではないのかな?