
Information<Shihohkan Dance-Café>
-今日の独言- 奈良散策
昨日はポカポカ陽気に誘われて久しぶりに奈良へと出かけた。スコットランド国立美術館展を観るためだったのだが、会場の奈良県立美術館は平日だというのにかなりの人出だった。といっても大半は婦人客で、ちらほらと見かける男性はきまって初老の夫婦連れとおぼしきカップル。
総じて印象派前史というべき世界か、スコットランドの風景が微かな光と影のコントラストに深みを帯びる画面の数々、或いはどこまでも素朴な物腰に風土特有の憂愁を湛えたような精緻なタッチのリアルな人物像など、強烈な刺激からはほど遠いものの、鑑賞者を静謐な気分に包み込むように過ぎ行く時間は相応に貴重なものといえようか。
奈良公園を歩けばあちらこちらに鹿の姿、修学旅行とおぼしき中学生の人群れをいくつも見かける。足を伸ばして新薬師寺で十二神将を拝観、薄暗がりの堂内を因達羅からはじまり伐折羅までぐるりと一体々々と対したうえで、壁ぎわの椅子に腰かけて暫く。彼らそれぞれに率いる七千の眷属神、あわせて八万四千の大軍は地下深く長い眠りについたままか、蠢く気配すらなくひたすら静寂。と、此処にも引率の先生と修学旅行生たちのグループがやってきたが、さすがに彼ら、ずいぶんと神妙に女性堂守の解説に耳を傾けていた。
<歌詠みの世界-「清唱千首」塚本邦雄選より>
<春-51>
帰る雁いまはの心ありあけに月と花との名こそ惜しけれ 藤原良経
新古今集、春上、百首歌奉りし時。
邦雄曰く、正治2(1200)年8月、後鳥羽院初度百首の春二十首の内。帰雁へのなごりを、別れの悲しみを詠ったものは数知れぬが、月と花とが遜色を覚えるほどの美を認め、しかも月・影において讃えた例は稀だ。やわらかく弾み浮かぶ二句切れの妙、三つの美の渾然とした絵画的構成、壮年に入った良経の技巧の冴えは、おのずから品位を備えて陶然とさせる、と。
入りかたの月は霞の底にふけて帰りおくるる雁のひとつら
永福門院内侍
風雅集、春中、帰雁を。「ひとつら」は一列。
邦雄曰く、「月は霞の底にふけて」とは、そのまま優れた漢詩の一部分に似る。敢えて「帰りおくるる」と、盡きぬなごりを惜しみすぎたものらを、くっきりと描き上げたその才、尋常ではない。14世紀中葉の宮廷にあってその才を謳われ、80歳以上の高齢でなお活躍を続けたと伝えられる、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















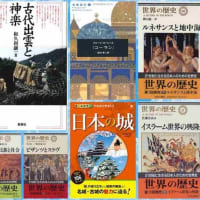




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます