
<芸能考-或は-芸談>-04
<達磨-だるま-歌>
塚本邦雄の「清唱千首」を参照していると「達磨歌」なる初めて眼にする呼称に何度か出くわしては悩まされていた。「達磨-だるま-歌」、いかにも揶揄したような滑稽味あふれた呼称だが、此方こそ意味不明、手も足も出ずダルマさん状態であった。
どうやら単純にいえば、奇を衒った手法を駆使して訳が分らぬ、解釈しようにも手も足も出ないような歌に対して「達磨歌」と揶揄蔑称したもの、ということらしい。
ところがよく調べていくと、この呼称問題の奥はけっこう深いようだ。
平安末期から鎌倉初期、終末観漂い暗い世相のなか新しい風が求められたひとつの時代の転換期である。宗教においても文芸においても新旧の交錯拮抗する時代でもあったのだ。
慈円や藤原良経、定家らがつどう九条家サロンの歌人たちは、先達古今集の歌風を刷新すべく新風を吹き込もうとした。具体的な技法の工夫としては、句切れの多用、語句の倒置や圧縮と飛躍、体言句の羅列など、従来からすれば新奇・奇矯な修辞法を駆使し、いわば事理に基づいた短歌的抒情、論理的な意味的結合の流れを断ち切って、体言句のもつ象徴的な喩・像の連合を一首の軸として歌の世界を構築しようとした。これら新しい歌風に対し、古今の伝統世界を是とする旧派歌人たちは、先述したように「達磨歌」と呼び嘲笑し蔑んだ。新風に対する否定的・批判的な論を展開した一方の雄に「方丈記」鴨長明がいる。長明は自著「無名抄」において「露さびて、風ふけて、心のおく、あはれのそこ、月のありあけ、風の夕暮、春の古里など、初めめづらしく詠める時こそあれ、ふたたびともなれば念もなき事、-略- 斯様のつらの歌は幽玄の境にはあらず、げに達磨とも是をぞいふべき」と記している。新風の「達磨歌」が、長明の言うように単なる言語の遊戯にしかすぎないなら、まさしく初めはめずらしく詠めても二度目となれば悪い意味でのマニエリスム以外のなにものでもないだろうが、彼の批判も些か一面的に過ぎたようである。
九条家サロンの歌人たちと意外に近しい位置に居た曹洞宗の開祖道元は自著「正法眼蔵」の山水経の段において「水は強弱にあらず、湿乾にあらず、動静にあらず、冷煖にあらず、有無にあらず、迷悟にあらざるなり。こりては金剛よりもかたし、たれかこれをやぶらん。融じては乳水よりもやはらかなり、たれかこれをやぶらん。-略- 人天の水をみるときのみの参学にあらず、水の水をみる参学あり、水の水を修証するゆへに。水の水を道著する参究あり、自己の自己に相逢する通路を現成せしむべし。他己の他己を参徹する活路を進退すべし、跳出すべし。」と説く。万物諸相の多様のうちに、それぞれ相通じ逢着する道があり、それらを実際に徹底して行き来したうえに、そこから跳び出すことこそ本来の参学だ、ということかと思えるが、最後の言葉「跳出すべし」とは、論理的な意味的結合の流れを断ち切って、その外部へと跳び出すこと即ち新しい世界像を獲得することであり、新風歌人たちの美学と大きく響きあっている。この仏法世界と歌の世界との共鳴は、世界と人との新しい関係の自覚であり、時代の変化に潜む要請でもあったのだろう。
この当時、「達磨」とは新しい時代の、新しい思想潮流のキーワードであったのだ。定家らの新風が同時代の人々に「達磨歌」と一方で揶揄されるように呼ばれ、他方で定家ら自身、これを逆手にとって新風の呼称として止揚し、自ら積極的に自己規定していくのも、時代の転換期の背景のうちに必然性として潜んでいたのである。
――参照サイト「院政期社会の言語構造を探る-達磨歌」
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。











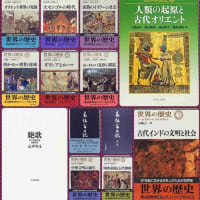
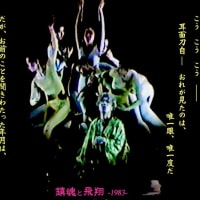
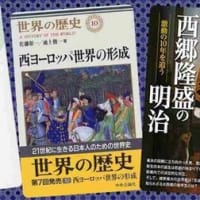
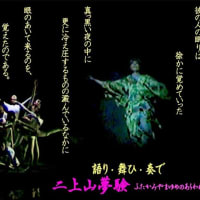
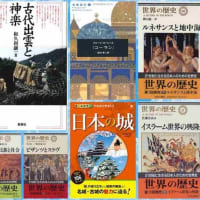
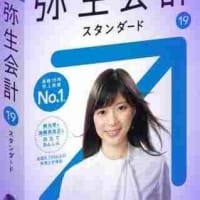
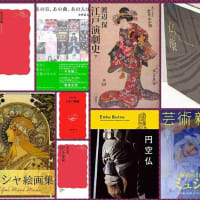
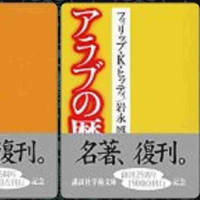
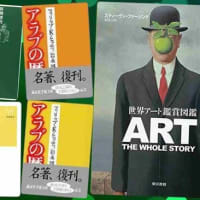
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます