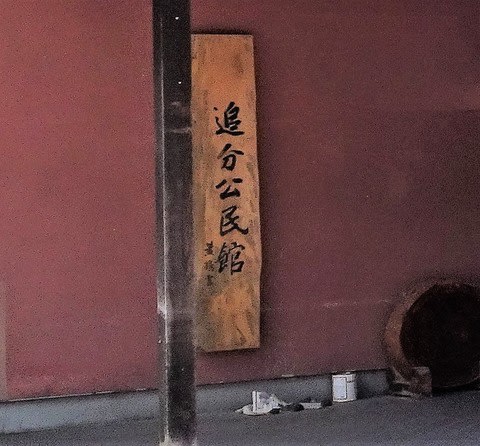堀 辰雄(1904-1953)は
明治37年東京に生まれ
昭和初期に活躍した作家。
大正12年 19歳の時に
師である室生犀星に連れられて
大正14年には滞在中に
芥川龍之介らとドライブで
追分を訪れて
静かなこの地が気に入り
毎年のように
この地を訪れるようになり
自然のなかで構想を練り
軽井沢を舞台とした数々の作品を残し
堀ほど軽井沢に
ゆかりの深い作家はいない。
旧軽井沢の別荘から
昭和19年 疎開と療養を兼ねて
この追分に定住している。
昭和26年には家を新築し
亡くなるまで1年10ヶ月
療養の日々を送り
昭和28年5月28日
この家で48歳の生涯を閉じた。
1993(平成5)年4月
堀 辰雄 終焉の地となった場所に
「堀辰雄文学記念館」が開館した。
代表作
ルウベンスの偽画(1927・S2年)
聖家族 (1930・S5年)
風立ちぬ (1936-1937・S11-12年)
菜穂子 (1941・S16年)
曠野 (1941・S16年)
大和路・信濃路(1943・S18年)