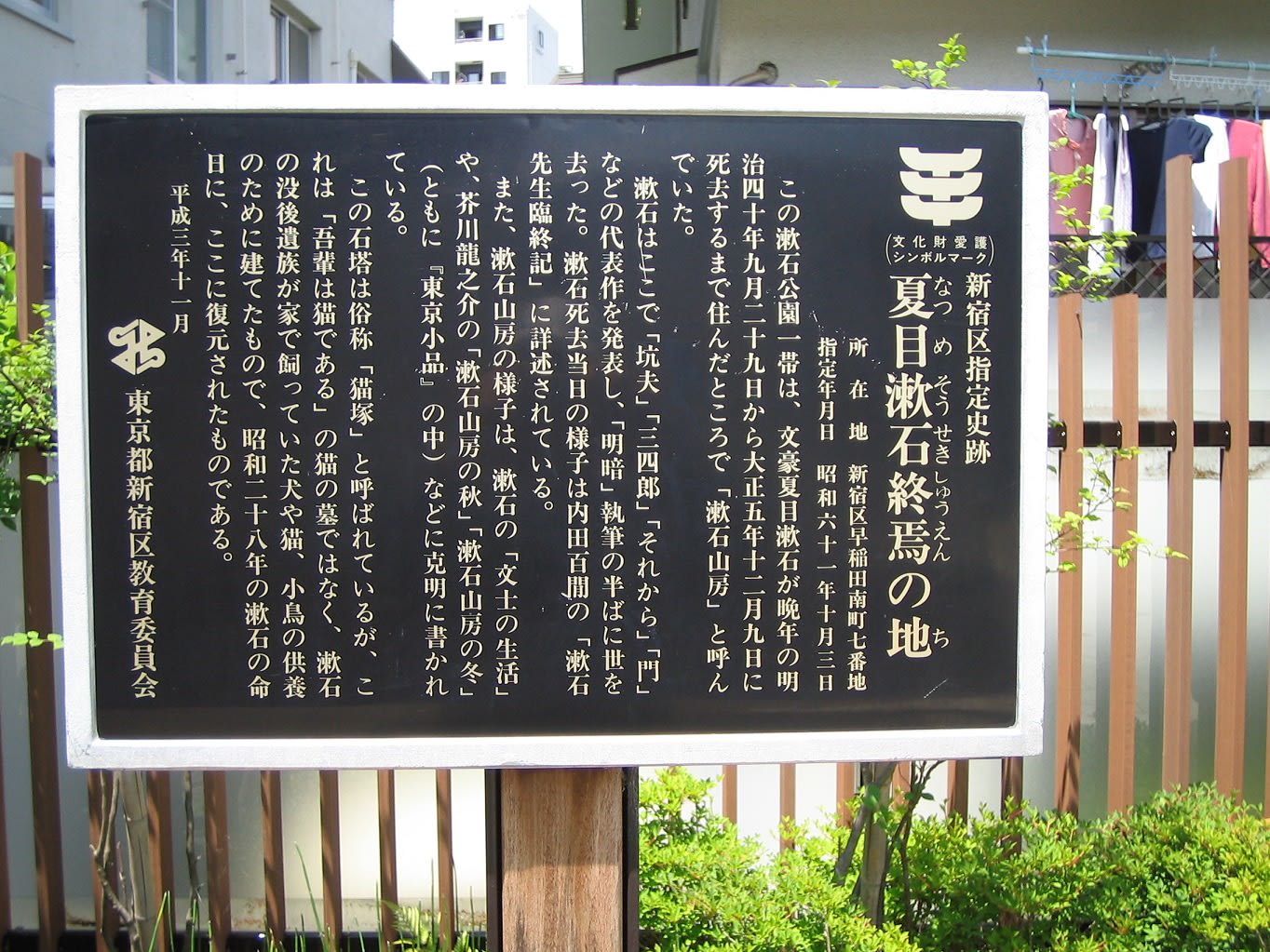1月19日 幕臣・政治家の
勝 海舟 が亡くなっている。
1823(文政6)年-1899(明治32)年 享年76歳
勝 海舟は 1823(文政6)年
本所(墨田区・両国公園内)で生まれ
1846(弘化4)年に 赤坂田町に引越するまで住んだ。
その間 蘭学を学び
1850(嘉永3)年に田町で蘭学塾を開く。
その後 ペリー来航により
幕府が広く意見を求めたことに
海舟の意見書が取り立てられる。

幕臣として活躍中
安政6年に氷川下(港区赤坂)に引っ越している。
この間 咸臨丸でアメリカへ
渡米中に桜田門外の変が起きている。
1862(文久2)年には
坂本龍馬は 刺殺しようと訪ねてきたが
逆に説得され 即 門下生となってしまった。
慶応4年には 西郷隆盛と
江戸城無血開城の談判をしている。
1868(明治元)年 徳川慶喜に
従って静岡へ移り住み
1872(明治5)年 再び東京に戻った。
明治政府にも重用され
参謀兼海軍卿・元老院議官など務め
伯爵となっている。
先日 坂本龍馬が暗殺される
5日前の手紙が発見され
その中に「新国家」なる言葉が記されていると
ニュースになっていたが
海舟を刺殺しようとした龍馬が
翻意し 弟子入りしてしまうほど
海舟の見識が のちの龍馬に影響を与え
その言葉になったのではと思うが・・・。